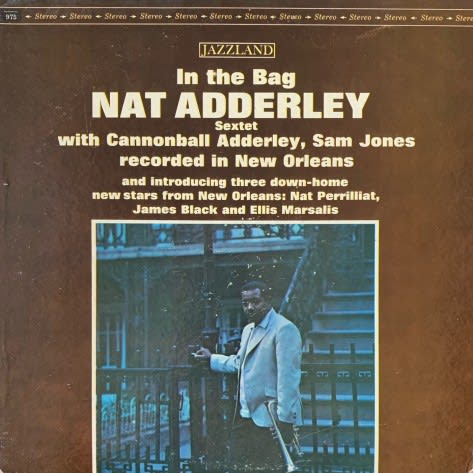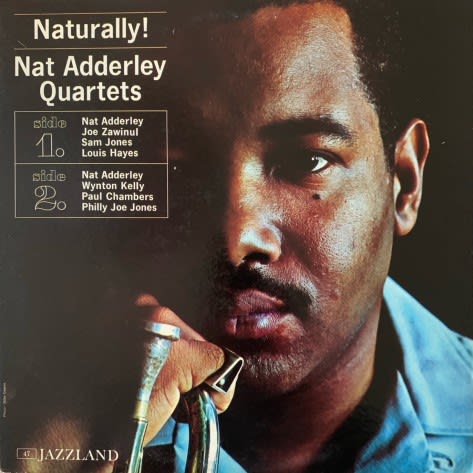Kenny Burrell / The Tender Gender ( 米 Cadet LPS 772 )
Argoレーベルは1965年にCadetと名前を変えているが、このアルバムは1966年4月にニューヨークで録音されている。RCA Studioで録音され、
レコードもRCAでプレスされたので品質がよく、音もいい。
リチャード・ワイアンズのピアノ・トリオをバックに歌いまくるバレルは、まるでワン・ホーン・カルテットのような雰囲気。ブルース・フィーリングが
ベースになっているけれど、時代の空気も流れ込んでいて、明るくポップなところもある。普段はガンガン鳴らすワイアンズのピアノも、ここでは
バレルのバッキングに徹していて、決してギターを邪魔しない。全体の纏まり感はとてもいい。
そんな中を流れるバレルのギターの音色がざっくりとした質感で素晴らしい。増幅されたフルアコの音色がギターの快楽を感じさせてくれる。
お約束の無伴奏ソロによるスタンダードも、いつものバレルらしい解釈。ギターっていいな、と思う。自作の楽曲が多く、そのどれもが聴かせる
メロディーを持ったいい曲ばかりなのも嬉しい。
同時代のジャズ・ギタリストたちの中では、最もオーソドックスな弾き方をするのがケニー・バレルだと思う。決して技巧に走らず、常に歌うことを
優先しているから、曲芸的バカテクを期待する向きには合わないかもしれないけれど、これがジャズ・ギターなのだ。管の入らない編成で聴くと、
全編に渡って彼の演奏を堪能できて、満足度が高い。
アーゴのヴァンガードでのライヴ盤、ファンタジーのヴァン・ゲルダー盤と並ぶ、バレルのギター3部作と呼びたい1枚。素晴らしい。