「ケインズが対象として考えている経済は、自分の力だけでは完全雇用を自動的に達することができず、放任すれば過少雇用の均衡状態に陥ってしまうような体質の経済であるから、かりに政策の処方を講ずれば完全雇用が達成維持できるとしても、そこでの調整メカニズムは自力で完全雇用を実現できるワルラス経済のそれとは、おのずから内在的性質を異にしているはずである。そこには完全雇用均衡の自動的な実現を妨げ、そうではない均衡に経済を落ち着かせてしまうような違った内在的メカニズムが働いているのではないだろうか。」
以上は、ケインズ学会編『ケインズは今なぜ必要が』に収録されている福岡正夫先生の講演の一部である。先生は卒寿を迎えなんとして、なお、こうした明晰な話をされているわけであり、筆者なんぞは、まだまだ洟垂れ小僧というところである。それでも、ケインズ経済学の核心は、先生がアローのサミュエルソンに対する批評を引きつつ明らかにされた「内在的メカニズム」にあることくらいは分かる。
………
素直に考えれば、「内在的メカニズム」を作動させるには、ワルラス体系における「利益を追求することで生じる力」とは別の、そして、それとは反対の向きとなる「未知の力」がいる。それなしには、いかに理論をこね繰り回そうとも、どうしても古典派的な経済学に類似したものになってしまう。ただ、それは、利益を捨てることに価値を見出すような行動になることを意味する。
経済学の基本的なコンセプトの一つは利益を最大化することだから、経済学の訓練を受けるほど、そんなものは存在しないように思えてくる。そうすると、「利益を最大化したいけれど、できない」というものを探し求めてしまう。それについて、古典派的な経済学者は、規制や雇用などの社会構造だと言うし、ケインズ的な経済学者は、限定合理性とか、不況を自己実現する悲観的な予想とかを挙げたりする。
前者はともかく、後者の場合、長期的に、あるいは、持続的に、利益を最大化できない状況を説明するには、それを支える「力」が必要になる。そうでなければ、ケインズの経済学は、長期的には、他愛もなく無用なものになる。なぜなら、「すぐに」利益を最大化できない理由を示し、「早めに」それらに到達するための処方箋を出しているだけの理論という位置づけになるからだ。
………
「利益を捨てることに価値を見出すような行動」と言われると、在り得ない気がするが、保険を扱っている者にとっては、日常のことである。火災保険は、期待値を計算するとマイナスであるが、好んで保険料を払ってくれる。その理由は、人生が短いからだ。火災のような稀でも大損害というリスクは、限られた人生では分散が利かない。逆に言えば、人生が無限なら、誰もが積立貯金をして、火災保険には入らない。
不況における経営者の投資行動も、これと同じである。低金利で低賃金にあるのだから、投資すべきところだが、上手く運ぶかは分からない。ならば、利益を得る機会を捨てる「保険料」を払い、人材や設備に投資する場合に生じる「大損害」を避ける。こうした行動は、不合理ではあるが、正当なものである。利益の最大化より、企業の生存性を優先することには価値がある。命あってのモノカネなのだ。
これを踏まえ、理屈を式の形にすると、『投資 = n/金利 -大損を回避する性向』となる。つまり、いかに金利を小さくし、収益性を上げて投資を刺激しようとしても、大損性のマイナス因子が強いと投資は出てこない。経営者は、需要の動向を見て、大損性を感じる。要は、売上が減りそうな状況では、怖くて投資はできないという、常識的な話である。
古典派的な経済学者は、大損性を無視するか、金利に織り込めるほど小さいと考えるから、ひたすら金利を下げろとなる。短期金利がゼロなら、長期金利もゼロに近づけ、量的質的な異次元緩和で解決できるとする。それで足りなければ、法人減税や投資補助金で収益性を追加すれば、投資が出るはずと考える。そして、問題なのは、長期金利を上げないよう、緊縮財政もやれとなることだ。
実際には、金利などで動かせる収益性より、大損を回避しようとする性向の方が遥かに強力だ。ウソだと思うなら、生身の経営者に「低利と減税と補助金を用意しますから、人材や設備に投資してください」と頼んでみたら良い。即座に「売上の見通しも立たんのに、そんな危ないことはできん」と返されるのがオチである。これが現実なのに、金融緩和と法人減税をするからと、消費増税で一気に需要を抜いたら、どうなるかは明らかだろう。
………
ケインズ的な経済学者は、「金融政策が効かない場合もあって、不況を脱するには需要が重要」と考えるから、現実に則している。しかし、金利が刺激する利益追求性を、大損回避性というマイナス因子の「力」が打ち消すというところまで、明瞭に認識しているわけではない。これが、アローを引いて福岡先生が指摘した「内在的メカニズム」を動かす、「未知」の原動力なのである。これを設定することで、説明は極めてシンプルになる。
ケインズの後継者は、IS-LM図式を用い、財市場と貨幣市場を分けて性質の違いを示したが、どちらも金利の関数であることに違いはない。IS曲線が垂直になり、LM曲線が水平になれば、金融政策は無効になることは分かっても、両曲線に少しでも角度があれば、幾ばくかは効果があることになるから、どこまでもやれば良いとなる。その意味で、金融政策は「万能」だ。ケインズ経済学の理論的苦しさは、ここにある。
その一方、ケインズは、さんざんリスクや不確実性に言及する。そうすると、これらと金利の関係が分からなくなってくる。それらの要因が金利で是正されるものなら、古典派的な経済学との差は程度の問題になる。反対に、是正されないとすると、金利の是正する力が加わっている以上、それを無効にしている逆向きの力が問われる。ケインズの後を継ぐ者がすべき仕事とは、アローの予想に従い、それを同定することだったはずで、それなしに古典派的な経済学を超えることは能わないのである。
………
福岡先生は、講演の中で、ケインズ体系の完成形として、いくつかの特徴を満たすことが必要だとしている。一つ目は、将来の不確実性、二つ目は、貨幣の流動性需要であるが、『投資 = n/金利 -大損を回避する性向』という枠組を作ると、不確実性が増せば、マイナスが増大するということで組み込めるし、それは同時に、投資せずに貨幣を持つことに逃げ込む行動だから、表裏一体のものだ。
三つ目に需要制約だが、大損性が金利の調整力を超えると、これが支配的になり、需要の増減にしたがって、投資がされることになる。したがって、先の枠組は、需要制約も表現している。実際、こういう動きは、日本で1994年から2006年まで観察されたものだ。なお、筆者は、企業の投資によって、所得と消費は決定されるという立場である。これは、日本の景気循環においては、投資が消費に先行していることで確かめられる。
四つ目と五つ目は、ケインズ体系での均衡だが、これは自己組織化臨界だと考えている。金利の調整力を大損性の力が上回ると、不合理の蓄積という新たな秩序が形成されていく。不合理という砂粒が山になっていくようなもので、積み上がる限界が、ある種の均衡となる。ただし、不安定なものであり、些細なことで、崩れては積み上がるを繰り返す。
実は、足元の日本経済が、ちょうど崩れたところである。不合理に投資を削り込んでいたため、アベノミクスによる多少の需要の好転で、内需企業も含め、収益が急伸した。オーバーシュートの揺り戻しである。このチャンスを活かし、大損性を癒しつつ、好循環へ導き、デフレの秩序を完全に崩すと、やがて、金利の効く範囲に入り、脱デフレとなる。残念ながら、政策は逆をするのだけれどね。以上、雑駁でお恥ずかしいが、こんな感じで、福岡先生の宿題は、返せるのかなと思う。
………
福岡先生は、講演の締めくくりで、ケインズ体系の均衡は、囚人のジレンマのようなナッシュ均衡ではないかと予想している。これは、まことに慧眼だと思う。そもそも、需要減少に不安を感じ、利益の機会を捨ててしまうのは、ミニマックス戦略のような、不合理さのある次善の策の行動である。これは、「ある経営者が超合理的であり、かつ、自分以外の経営者も超合理的と信じる」と仮定する背理法を使うと理解しやすい。
つまり、「目の前の売上減と金利の低下は、消費者がより多くの貯蓄と投資を望んでいるサインであろう。おそらく、他の経営者も同じく超合理的に、そう判断するに違いない。よって、自分はもちろん、他の経営者も投資して、経済が需要不足になることはない。したがって、成功は間違いない」という仮定だ。
しかし、こうした一分の隙もない論理は、「もしかして、他の経営者に愚鈍が多かったら、あるいは、安全のために後追い戦略で来られたら」と疑った瞬間に破綻する。なるほど、ほとんどの経営者が超合理的であったなら、金融緩和が効かないはずがなく、デフレになることもないという論理は正しい。ところが、それは、ゲーム理論から考えて、極めて脆く、簡単に破れが生じてしまう。そして、そのようにゲーム理論で「合理的」に予想したら、仮定は成り立たたなくなる。
普通の経営者は、売上減がマクロ要因なのか、製品の人気のせいかなんて、見分けがつかない。単に、売れ行きが落ちれば、生産能力を落とし、売れ行きが伸びれば、生産能力を加えるという、不完全だが実用的な戦略を採っているだけだ。収益は、需要と表裏一体の価格次第なので、普段は金利の動向を気にもとめない。現場は、そんなものであり、精緻な理論を知らなくても、やはり採られるのは、利益を最大化しない次善の策なのである。
………
ケインズ経済学は、完全雇用という政策目標に結び付けられていて、それが批判の種ともなった。それは、どうしても大き目の有効需要の追加を必要としてしまい、勢い余ってインフレを加速することにもなる。他方、不合理の原因を「大損性」と特定すれば、低水準であっても、底入れさえさせれば良いのだから、求められる財政出動は限定される。むろん、勢い良く底離れさせるには、多めが望ましいが、少なくとも、率先して抜くようなことさえしなければ良い。
日本経済が長期のデフレに陥ったのは、底離れのチャンスで、すかさず緊縮財政を取って、回復の芽を摘むことを繰り返してきたからである。それは、現下の局面で、またも実証されることだろう。これは、「金利の調整力は、需要への不安に勝る」という誤った理論に基づくものだが、実は、古典派的な経済学に立っても、「低金利においては、借り入れを増やすべし」という合理的行動を、政府にも認めれば、こうはならない。
ゲーム理論のミニマックス戦略の均衡を打破するには、需要に関する情報と信用が必要である。それを提供できるのは、企業のようにリスクを気にしなくて済む政府だけであり、プライス・リーダーシップならぬ、デマンド・リーダーシップを示せば良いということになる。結局、政府にだけは「金利に従うな」という不合理な行動を求める、理論の外の「思想」が不幸を招くのである。
以上は、ケインズ学会編『ケインズは今なぜ必要が』に収録されている福岡正夫先生の講演の一部である。先生は卒寿を迎えなんとして、なお、こうした明晰な話をされているわけであり、筆者なんぞは、まだまだ洟垂れ小僧というところである。それでも、ケインズ経済学の核心は、先生がアローのサミュエルソンに対する批評を引きつつ明らかにされた「内在的メカニズム」にあることくらいは分かる。
………
素直に考えれば、「内在的メカニズム」を作動させるには、ワルラス体系における「利益を追求することで生じる力」とは別の、そして、それとは反対の向きとなる「未知の力」がいる。それなしには、いかに理論をこね繰り回そうとも、どうしても古典派的な経済学に類似したものになってしまう。ただ、それは、利益を捨てることに価値を見出すような行動になることを意味する。
経済学の基本的なコンセプトの一つは利益を最大化することだから、経済学の訓練を受けるほど、そんなものは存在しないように思えてくる。そうすると、「利益を最大化したいけれど、できない」というものを探し求めてしまう。それについて、古典派的な経済学者は、規制や雇用などの社会構造だと言うし、ケインズ的な経済学者は、限定合理性とか、不況を自己実現する悲観的な予想とかを挙げたりする。
前者はともかく、後者の場合、長期的に、あるいは、持続的に、利益を最大化できない状況を説明するには、それを支える「力」が必要になる。そうでなければ、ケインズの経済学は、長期的には、他愛もなく無用なものになる。なぜなら、「すぐに」利益を最大化できない理由を示し、「早めに」それらに到達するための処方箋を出しているだけの理論という位置づけになるからだ。
………
「利益を捨てることに価値を見出すような行動」と言われると、在り得ない気がするが、保険を扱っている者にとっては、日常のことである。火災保険は、期待値を計算するとマイナスであるが、好んで保険料を払ってくれる。その理由は、人生が短いからだ。火災のような稀でも大損害というリスクは、限られた人生では分散が利かない。逆に言えば、人生が無限なら、誰もが積立貯金をして、火災保険には入らない。
不況における経営者の投資行動も、これと同じである。低金利で低賃金にあるのだから、投資すべきところだが、上手く運ぶかは分からない。ならば、利益を得る機会を捨てる「保険料」を払い、人材や設備に投資する場合に生じる「大損害」を避ける。こうした行動は、不合理ではあるが、正当なものである。利益の最大化より、企業の生存性を優先することには価値がある。命あってのモノカネなのだ。
これを踏まえ、理屈を式の形にすると、『投資 = n/金利 -大損を回避する性向』となる。つまり、いかに金利を小さくし、収益性を上げて投資を刺激しようとしても、大損性のマイナス因子が強いと投資は出てこない。経営者は、需要の動向を見て、大損性を感じる。要は、売上が減りそうな状況では、怖くて投資はできないという、常識的な話である。
古典派的な経済学者は、大損性を無視するか、金利に織り込めるほど小さいと考えるから、ひたすら金利を下げろとなる。短期金利がゼロなら、長期金利もゼロに近づけ、量的質的な異次元緩和で解決できるとする。それで足りなければ、法人減税や投資補助金で収益性を追加すれば、投資が出るはずと考える。そして、問題なのは、長期金利を上げないよう、緊縮財政もやれとなることだ。
実際には、金利などで動かせる収益性より、大損を回避しようとする性向の方が遥かに強力だ。ウソだと思うなら、生身の経営者に「低利と減税と補助金を用意しますから、人材や設備に投資してください」と頼んでみたら良い。即座に「売上の見通しも立たんのに、そんな危ないことはできん」と返されるのがオチである。これが現実なのに、金融緩和と法人減税をするからと、消費増税で一気に需要を抜いたら、どうなるかは明らかだろう。
………
ケインズ的な経済学者は、「金融政策が効かない場合もあって、不況を脱するには需要が重要」と考えるから、現実に則している。しかし、金利が刺激する利益追求性を、大損回避性というマイナス因子の「力」が打ち消すというところまで、明瞭に認識しているわけではない。これが、アローを引いて福岡先生が指摘した「内在的メカニズム」を動かす、「未知」の原動力なのである。これを設定することで、説明は極めてシンプルになる。
ケインズの後継者は、IS-LM図式を用い、財市場と貨幣市場を分けて性質の違いを示したが、どちらも金利の関数であることに違いはない。IS曲線が垂直になり、LM曲線が水平になれば、金融政策は無効になることは分かっても、両曲線に少しでも角度があれば、幾ばくかは効果があることになるから、どこまでもやれば良いとなる。その意味で、金融政策は「万能」だ。ケインズ経済学の理論的苦しさは、ここにある。
その一方、ケインズは、さんざんリスクや不確実性に言及する。そうすると、これらと金利の関係が分からなくなってくる。それらの要因が金利で是正されるものなら、古典派的な経済学との差は程度の問題になる。反対に、是正されないとすると、金利の是正する力が加わっている以上、それを無効にしている逆向きの力が問われる。ケインズの後を継ぐ者がすべき仕事とは、アローの予想に従い、それを同定することだったはずで、それなしに古典派的な経済学を超えることは能わないのである。
………
福岡先生は、講演の中で、ケインズ体系の完成形として、いくつかの特徴を満たすことが必要だとしている。一つ目は、将来の不確実性、二つ目は、貨幣の流動性需要であるが、『投資 = n/金利 -大損を回避する性向』という枠組を作ると、不確実性が増せば、マイナスが増大するということで組み込めるし、それは同時に、投資せずに貨幣を持つことに逃げ込む行動だから、表裏一体のものだ。
三つ目に需要制約だが、大損性が金利の調整力を超えると、これが支配的になり、需要の増減にしたがって、投資がされることになる。したがって、先の枠組は、需要制約も表現している。実際、こういう動きは、日本で1994年から2006年まで観察されたものだ。なお、筆者は、企業の投資によって、所得と消費は決定されるという立場である。これは、日本の景気循環においては、投資が消費に先行していることで確かめられる。
四つ目と五つ目は、ケインズ体系での均衡だが、これは自己組織化臨界だと考えている。金利の調整力を大損性の力が上回ると、不合理の蓄積という新たな秩序が形成されていく。不合理という砂粒が山になっていくようなもので、積み上がる限界が、ある種の均衡となる。ただし、不安定なものであり、些細なことで、崩れては積み上がるを繰り返す。
実は、足元の日本経済が、ちょうど崩れたところである。不合理に投資を削り込んでいたため、アベノミクスによる多少の需要の好転で、内需企業も含め、収益が急伸した。オーバーシュートの揺り戻しである。このチャンスを活かし、大損性を癒しつつ、好循環へ導き、デフレの秩序を完全に崩すと、やがて、金利の効く範囲に入り、脱デフレとなる。残念ながら、政策は逆をするのだけれどね。以上、雑駁でお恥ずかしいが、こんな感じで、福岡先生の宿題は、返せるのかなと思う。
………
福岡先生は、講演の締めくくりで、ケインズ体系の均衡は、囚人のジレンマのようなナッシュ均衡ではないかと予想している。これは、まことに慧眼だと思う。そもそも、需要減少に不安を感じ、利益の機会を捨ててしまうのは、ミニマックス戦略のような、不合理さのある次善の策の行動である。これは、「ある経営者が超合理的であり、かつ、自分以外の経営者も超合理的と信じる」と仮定する背理法を使うと理解しやすい。
つまり、「目の前の売上減と金利の低下は、消費者がより多くの貯蓄と投資を望んでいるサインであろう。おそらく、他の経営者も同じく超合理的に、そう判断するに違いない。よって、自分はもちろん、他の経営者も投資して、経済が需要不足になることはない。したがって、成功は間違いない」という仮定だ。
しかし、こうした一分の隙もない論理は、「もしかして、他の経営者に愚鈍が多かったら、あるいは、安全のために後追い戦略で来られたら」と疑った瞬間に破綻する。なるほど、ほとんどの経営者が超合理的であったなら、金融緩和が効かないはずがなく、デフレになることもないという論理は正しい。ところが、それは、ゲーム理論から考えて、極めて脆く、簡単に破れが生じてしまう。そして、そのようにゲーム理論で「合理的」に予想したら、仮定は成り立たたなくなる。
普通の経営者は、売上減がマクロ要因なのか、製品の人気のせいかなんて、見分けがつかない。単に、売れ行きが落ちれば、生産能力を落とし、売れ行きが伸びれば、生産能力を加えるという、不完全だが実用的な戦略を採っているだけだ。収益は、需要と表裏一体の価格次第なので、普段は金利の動向を気にもとめない。現場は、そんなものであり、精緻な理論を知らなくても、やはり採られるのは、利益を最大化しない次善の策なのである。
………
ケインズ経済学は、完全雇用という政策目標に結び付けられていて、それが批判の種ともなった。それは、どうしても大き目の有効需要の追加を必要としてしまい、勢い余ってインフレを加速することにもなる。他方、不合理の原因を「大損性」と特定すれば、低水準であっても、底入れさえさせれば良いのだから、求められる財政出動は限定される。むろん、勢い良く底離れさせるには、多めが望ましいが、少なくとも、率先して抜くようなことさえしなければ良い。
日本経済が長期のデフレに陥ったのは、底離れのチャンスで、すかさず緊縮財政を取って、回復の芽を摘むことを繰り返してきたからである。それは、現下の局面で、またも実証されることだろう。これは、「金利の調整力は、需要への不安に勝る」という誤った理論に基づくものだが、実は、古典派的な経済学に立っても、「低金利においては、借り入れを増やすべし」という合理的行動を、政府にも認めれば、こうはならない。
ゲーム理論のミニマックス戦略の均衡を打破するには、需要に関する情報と信用が必要である。それを提供できるのは、企業のようにリスクを気にしなくて済む政府だけであり、プライス・リーダーシップならぬ、デマンド・リーダーシップを示せば良いということになる。結局、政府にだけは「金利に従うな」という不合理な行動を求める、理論の外の「思想」が不幸を招くのである。


















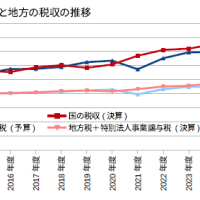





ちなみに、
『投資 = n/金利 -大損を回避する性向』
のご提案については、拙著第4章4節の177~183ページ当たりで、提案しているのも、おおむね同様の観点です。
そこでは、従来の「収益最大化原理」に、「リスク・不確実性最小化原理」を追加すべきと述べています。
これを式の形で表しますと、次のように、ご提案の観点とおおむね一致しています。
投資 = n/金利 - 大損を回避する性向
投資 = 収益最大化要因 ± リスク・不確実性最小化要因
なお、拙著では、経済環境の変化によって、要因の影響力が変化すると考えています。例えば、バブル期には(多くの経済主体が強気になるため)右辺第2項は平均的に重視されなくなりますが、逆に重い不況でリスク・不確実性が高まると(例えば、取引先の倒産などで不時の資金需要があるときに、銀行が融資をしてくれないかもしれない・・)第2項が重視されるようになります。第2項は、景気に対してプロシクリック(景気変動を強める方向)に働くと思われます。