「問題を見つけることは、半分を解決したも同じだ」と言われる。困った状態にあっても、何が問題か分からないことは多いし、分ったつもりで的外れなことをしたりもする。的外れなことをして、問題をこじらせるくらいなら、適当な問題を設定し、余計なことを避ける方がマシかもしれない。社会保障制度改革国民会議における年金への提言には、そんな印象がある。
………
昨日の日経によれば、会議の提言には年金支給開始年齢の引き上げが盛り込まれるようである。支給開始年齢については、65歳とする既定の計画が完成するのは、男性で2025年、女性で2030年である。更なる引き上げは、常識的には、その後だろうから、かなり先のことになる。むろん、制度改正は早めに行って、「年金の出ない期間」における雇用確保の準備するという意義もあるわけだが。
一般の方は、年金の出ない期間が生じるかねないことに不安を覚えるかもしれないが、支給年齢引上げの際は、併せて、65歳からの繰上げ支給を受ける選択肢も用意されるはずだ。繰上げ支給を受ければ、給付月額は低くなるものの、生涯受けるトータル額には損がないよう設計がなされるだろう。そういう意味で、あまり心配する必要はない。
ポイントは、今の基準で見て年金の給付水準が下がることだ。例えば、年金の水準がどの程度かを現役時代の所得との比率で示す「所得代替率」は、モデル年金において50%とされているが、これを割り込むことになろう。おそらく、「67歳」支給開始の場合は50%が維持されるといった説明に転換されると思われる。
この50%基準だが、2004年の年金改正で、現役世代の負担力に合わせて給付水準を低下させる「マクロ経済スライド」が導入されるとともに、際限ない低下を恐れる政治の要請によって設けられたものだ。筆者は、年金制度を持続可能なものにするため、50%基準にこだわるべきでないと考えるので、そうした転換も構わないのではないか。
………
今日の日経の社説は年金・医療と財政だったが、相変わらずだね。この数年の国民会議などにおける議論の進展や経済状況の変化を取り入れるべきだと思う。経済界の主張を代弁し、企業の社会保障負担の軽減をひたすら主張するのが正しいとは思えない。今一度、「国民生活の基礎たる経済の発展を期す」という社是を思い起こすべきだろう。
日本の言論は、それぞれが立場を主張し、争議の上に正解が見出せるほどの厚みがない。力のある者ほど、国民生活という公共的観点を共有せねばなるまい。年金制度については、50%基準を抱える矛盾さえ解けば、持続可能性に問題はなく、根本改革は無要である。年金積立金の運用利率4.1%は高めにしても、アベノミクスが多大な利益をもたらしたことで、現実味が変わってきた。また、最重要の出生率が想定を上回っていることも欠かせない。
積立方式への転換は、数理的に無意味なことが証明されているのだから、もはや論じるに値しない。最低保障年金も、現在の事実上の保障である3.3万円で十分であって、税方式化による企業の保険料負担軽減の材料にすべく持ち出すのは、もうやめるべきである。無年金や低年金の問題は、減免措置の申請漏れを減らす工夫や、失業・病気・出産の期間による年金額の低下の補完といった、地に足が着いた主張をすべきだろう。
もちろん、痛みが伴っても必要な改革もある。高齢者医療の窓口負担については、本コラムは70歳に到達した者から順次2割負担にすべしと提案した。厚労省の事務方もそうした腹案を持っていたようだが、選挙を前に実現せずじまいだ。公平論を掲げるのみならず、円滑に移行できる案を推して、世論を導くことも必要と考える。また、高齢者だから、年金所得だからと、課税を優遇することは正すべきであろう。
………
昨日は5年に一度の就業構造基本調査が大きく報じられた。5年前と比較して、すべての年齢階層で男性の有業率が下がり、週間就業時間も減っているのを見ると、日本経済の低迷が人口問題による宿命とは異なるものだと分かる。パートなどの非正規やニート率の増加は報道のとおりだ。日本経済は持てる力を発揮できていない。
ついでに、興味を引く数字としては、夫の所得が1000万円を超えると、妻のパート就業率が下がるというものがあった。高所得者は妻もフルタイムということかもしれない。こういう世帯は老後も年金リッチとなる。雇用の非正規化は年金での格差ももたらす。高齢者にかかる税制改革の必要性は、こうしたところにもうかがえる。
社会保障の持続可能性は、制度より経済の問題である。デフレという異常事態から脱すれば、雇用の改善により、保険料収入は増大し、出生率も上昇する。金利と物価が上がれば、積立金収入は向上し、マクロ経済スライドの作動で給付が節約される。本当の問題は、非正規の人たちの負担と給付をどう改善し、格差を是正するかである。残念ながら、日本の政党に社会保障制度の改革案を求めても難しい。新聞の役割は、経済状況を的確に追いながら、具体的な改善策を政治に問うことではなかろうか。
(昨日の日経)
働く女性は20~30代の7割、非正規2000万人突破・就業構造基本調査。年金開始の引き上げ明記へ・国民会議。中国資金供給の伸び鈍化。ゲーム激変・教科書がヒット。大機・外貨の足りないニッポン。
(今日の日経)
脱デフレ産みの苦しみ。新規上場が復調、アジア最多。社説・年金医療と財政どう立て直すのか。子育て・雇用掛け声先行。株高でバブル世代動く。消費増税は景気に配慮を・浜田氏。経済史・人口1億人突破。
※日本は新事業が出にくい国と言われたりもするが、景気が回復すればこんなものである。※保育40万人は相当の数字と思うがね。※株高より円安ではないか、海外旅行をやめて、国内でブランドのお買い物である。資産効果を意識しすぎだ。※このシリーズは今一つだが、今回は佳作。ただ当時は人口増は豊かさへの足枷と思われていたがね。
………
昨日の日経によれば、会議の提言には年金支給開始年齢の引き上げが盛り込まれるようである。支給開始年齢については、65歳とする既定の計画が完成するのは、男性で2025年、女性で2030年である。更なる引き上げは、常識的には、その後だろうから、かなり先のことになる。むろん、制度改正は早めに行って、「年金の出ない期間」における雇用確保の準備するという意義もあるわけだが。
一般の方は、年金の出ない期間が生じるかねないことに不安を覚えるかもしれないが、支給年齢引上げの際は、併せて、65歳からの繰上げ支給を受ける選択肢も用意されるはずだ。繰上げ支給を受ければ、給付月額は低くなるものの、生涯受けるトータル額には損がないよう設計がなされるだろう。そういう意味で、あまり心配する必要はない。
ポイントは、今の基準で見て年金の給付水準が下がることだ。例えば、年金の水準がどの程度かを現役時代の所得との比率で示す「所得代替率」は、モデル年金において50%とされているが、これを割り込むことになろう。おそらく、「67歳」支給開始の場合は50%が維持されるといった説明に転換されると思われる。
この50%基準だが、2004年の年金改正で、現役世代の負担力に合わせて給付水準を低下させる「マクロ経済スライド」が導入されるとともに、際限ない低下を恐れる政治の要請によって設けられたものだ。筆者は、年金制度を持続可能なものにするため、50%基準にこだわるべきでないと考えるので、そうした転換も構わないのではないか。
………
今日の日経の社説は年金・医療と財政だったが、相変わらずだね。この数年の国民会議などにおける議論の進展や経済状況の変化を取り入れるべきだと思う。経済界の主張を代弁し、企業の社会保障負担の軽減をひたすら主張するのが正しいとは思えない。今一度、「国民生活の基礎たる経済の発展を期す」という社是を思い起こすべきだろう。
日本の言論は、それぞれが立場を主張し、争議の上に正解が見出せるほどの厚みがない。力のある者ほど、国民生活という公共的観点を共有せねばなるまい。年金制度については、50%基準を抱える矛盾さえ解けば、持続可能性に問題はなく、根本改革は無要である。年金積立金の運用利率4.1%は高めにしても、アベノミクスが多大な利益をもたらしたことで、現実味が変わってきた。また、最重要の出生率が想定を上回っていることも欠かせない。
積立方式への転換は、数理的に無意味なことが証明されているのだから、もはや論じるに値しない。最低保障年金も、現在の事実上の保障である3.3万円で十分であって、税方式化による企業の保険料負担軽減の材料にすべく持ち出すのは、もうやめるべきである。無年金や低年金の問題は、減免措置の申請漏れを減らす工夫や、失業・病気・出産の期間による年金額の低下の補完といった、地に足が着いた主張をすべきだろう。
もちろん、痛みが伴っても必要な改革もある。高齢者医療の窓口負担については、本コラムは70歳に到達した者から順次2割負担にすべしと提案した。厚労省の事務方もそうした腹案を持っていたようだが、選挙を前に実現せずじまいだ。公平論を掲げるのみならず、円滑に移行できる案を推して、世論を導くことも必要と考える。また、高齢者だから、年金所得だからと、課税を優遇することは正すべきであろう。
………
昨日は5年に一度の就業構造基本調査が大きく報じられた。5年前と比較して、すべての年齢階層で男性の有業率が下がり、週間就業時間も減っているのを見ると、日本経済の低迷が人口問題による宿命とは異なるものだと分かる。パートなどの非正規やニート率の増加は報道のとおりだ。日本経済は持てる力を発揮できていない。
ついでに、興味を引く数字としては、夫の所得が1000万円を超えると、妻のパート就業率が下がるというものがあった。高所得者は妻もフルタイムということかもしれない。こういう世帯は老後も年金リッチとなる。雇用の非正規化は年金での格差ももたらす。高齢者にかかる税制改革の必要性は、こうしたところにもうかがえる。
社会保障の持続可能性は、制度より経済の問題である。デフレという異常事態から脱すれば、雇用の改善により、保険料収入は増大し、出生率も上昇する。金利と物価が上がれば、積立金収入は向上し、マクロ経済スライドの作動で給付が節約される。本当の問題は、非正規の人たちの負担と給付をどう改善し、格差を是正するかである。残念ながら、日本の政党に社会保障制度の改革案を求めても難しい。新聞の役割は、経済状況を的確に追いながら、具体的な改善策を政治に問うことではなかろうか。
(昨日の日経)
働く女性は20~30代の7割、非正規2000万人突破・就業構造基本調査。年金開始の引き上げ明記へ・国民会議。中国資金供給の伸び鈍化。ゲーム激変・教科書がヒット。大機・外貨の足りないニッポン。
(今日の日経)
脱デフレ産みの苦しみ。新規上場が復調、アジア最多。社説・年金医療と財政どう立て直すのか。子育て・雇用掛け声先行。株高でバブル世代動く。消費増税は景気に配慮を・浜田氏。経済史・人口1億人突破。
※日本は新事業が出にくい国と言われたりもするが、景気が回復すればこんなものである。※保育40万人は相当の数字と思うがね。※株高より円安ではないか、海外旅行をやめて、国内でブランドのお買い物である。資産効果を意識しすぎだ。※このシリーズは今一つだが、今回は佳作。ただ当時は人口増は豊かさへの足枷と思われていたがね。



















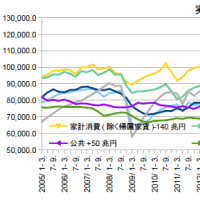





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます