経済学を学び始めた遥か昔、「常識で分かることを数式化するだけで、何がおもしろいんだ」と思ったものである。しかし、ケインズは違った。「個々が正しいことをしても、総体としては不合理な結果になる」という合成の誤謬にはシビれたね。常識を超える発見をしてこその科学だろうと。ただ、同時に、文学的には素晴らしいにしても、論理に何か引っかかるものも感じた。
21世紀の今となっては、ケインズが何を間違えていたかは明らかだ。個々がしていたのは、正しいことではなく、わずかに間違ったことだったのである。わすかな不合理でも、それが組織化される傾向があれば、大きな秩序を作り出してしまう。もはや、このような物理現象は理工学では常識となっているのだから、デフレやインフレについても、同じ観点で理解すべきだろう。
現在の経済学は、マクロのミクロ的基礎付けと言って、個々の完全な合理性に拘り、総体的な現象を、むしろ見え難いものにしてしまった。ケインズの主張を正常進化させていれば良かったものをと惜しまれる。むろん、経済学も多様であり、「反主流派」の行動経済学では、個々がどのように行動するかを実験で明らかにして、不合理な行動の存在を実証して来てもいる。
………
行動経済学のこうしたアプローチは、科学において実証が何より大切なことからすれば、正しいものだと考える。課題としては、主流派とは逆に、いかに論理付け、整理して、簡潔な理解へ到達するかであろう。それが適用範囲を広げることにもなる。その基本的な手法は、ヒトの心理に立脚するものなのだから、「変わりやすい地球環境の中で、人類が生き残ってくるのに有利な戦略の表れ」として整理するのが自然な流れだとは思う。
例えば、利得より損害を強く回避しようとするのは、より多く食糧をせしめるより、危険を避けて命と体を守る方が子孫を残す可能性を高められたことの表れかもしれない。現代において、利益最大化よりも会社の存続可能性を確保しようという傾向は、太古からの人類の戦略の適用例のようにも見える。
ただし、それは変えられないものではないことに注意が必要だ。脂肪分を積極的に摂取しておくという、人類が子孫を残す上で有利であったに違いない戦略は、飽食の現代では、必ずしも有利とは言えない。健康と、そして、モテるためには、ダイエットも必要だ。25万年の来歴によって、性(さが)というまでに形成された戦略を、今日では、意思の力で修正しなければならなくなっている。
ためにする議論に聞こえるかもしれないが、現在の経済学の主流派の立場からすれば、心理に基づく行動は、理性で変わり得るものだ。実際、行動ファイナンスの研究の中で見つけられたアノマリーが、認識されたことによって、消えてしまった例もある。したがって、戦略は、長期的には進化し、利益最大化をもたらすだろうと言えなくもない。
………
また、行動経済学のマクロ経済への適用については、カーネマンも認めるように、実験で得られたのは瞬間的判断での反応であり、そのまま使えるのかという問題もある。期待値の低い選択肢を選んでしまう反応を示したからといって、長期的には、選択が繰り返されることで反応が変化したり、期待値の計算による判断が持ち込まれることだって考えられる。
マクロ経済では、設備投資の判断は、繰り返されるものだし、直感に頼らなければならないものでもない。繰り返しや理性の導入をもってしても、なお不合理な選択をし続けるという、強力な論拠が必要だ。それには、不合理な判断を生む戦略が進化の過程で形成されてきたというだけでなく、戦略の原因を掘り下げる必要がある。
その点について、「どうすれば経済学」は、リスクを分散させられない制約があれば、不合理な行動は続くとし、その制約とは、試行回数の確保に必要な時間であり、人生が限られる以上、克服は無理としている。これを、文学的に「人は死せる存在であるがゆえに不合理」と表現しているわけだ。いわば、行動経済学が実証した反応の原因を突き詰め、マクロ経済の理解に活かせるよう発展させているのである。
道具立ては、至ってシンプルである。統計学の用語で言えば、分散が大きい場合、期待値は大数の法則が働かないと、「意味がない」と言っているに過ぎない。1億分の1の確率で1億円の損害が出るリスクと、10万分の1の確率で10万円の損害が出るリスクと、どちらかを選ばねばならない場合、どちらも期待値は-1円で同じだとしても、後者が選ばれるはずだ。これは直感的にも分かるだろう。
………
主流派の経済学の合理性に対する重大な批判は、アレのパラドックスに始まる。アレは、全体として期待値が高いにも関わらず、その中に、まれでも得られるものがまったく実現しない可能性が含まれると、主観的な評価が期待値より大きく低下するという「反例」を示した。行動経済学は、こうした現象を体系的に説明するものであり、カーネマンの「確率ウェート関数」は、0~1の確率の両端近くで、評価が期待値から大きくズレることを実証している。
こうした反応の原因は何か。そうする効用を人間が持っていることは確かめられたわけだが、原因は必ずしも明らかではない。これを、「大数の法則が働かない試行回数の制約による分散の大きさ」として、原因を特定するのが「どうすれば経済学」となる。原因が時間制約と分かれば、マクロ経済に行動経済学を適用する際には、時間制約が存在するのか、長期的に自然解消される性質のものかを調べれば良いことになる。
調査するまでもないような気もするが、ここから先は実証の問題である。筆者の経験からすると、経営者は一定の期間に成績を求められるし、それは時代を経ても変わっていない。逆に、長期的な視点で研究開発を支持して成果に到達した経営者が褒められたり、オーナー経営者が果敢にリスクを取って大成功を収めたことが賞されたりするのだから、これらは、大方の経営者にとって容易に成し得る業ではないということだろう。
しかも、設備投資の判断においては、一回ごとの試行が独立しているとは言い難い。不況は何年か続くものなので、積極策で失敗した後、更に積極策を続けて成功で埋め合わせるというのは、余りに危険だ。個別性の少ないマクロ経済予測ですら、来年は今年と同じとするナイーブ予測の成績が良かったりする有様だ。おそらく、正のフィードバックが働くことがリスクに抗することを、より危険にしているのだろう。
………
こうした時間制約の観点で眺めてみると、主流派の経済学が理解に苦しみ、行動経済学が新しい解釈に努めているものが整理されてくる。もちろん、全部が片付くわけではないが、簡潔なものとなり、適用範囲を広げることになる。以下では、理解を深めるために、いくつかを取り上げて説明してみよう。
まずは、損害保険と宝くじである。どちらも、期待値の観点では、払った分より、見返りが随分と少ない「マイナスの商品」である。そうでなければ、胴元も保険業も成り立たない。従って、現在の経済学が想定するような合理的な人は買わないはずで、短期的にはともかく、長期的には衰退し、不合理が解消されなければおかしいことになる。
ところが、現実には、宝くじは15世紀半ばにはオランダで行われていた記録があり、海上保険は14世紀のイタリアで営まれていたとされる。してみると、現在の経済学が主張する合理性の発揮には、500年以上かかる場合もあるようだ。それからすれば、15年デフレが続いているくらいで、文句を言ってはいけないのかもしれない。もし、「果報は寝て待て」、「待てば海路の日和あり」が正しいなら、デフレへの対応は、実に他愛ないものになる。
しかも、現在の経済学では、不合理を解釈するのに、損害保険はリスク回避的な人が買い、宝くじはリスク愛好的な人が買うとする。つまり、損害の不安を払拭する効用や、賞金を当てる夢を見る効用の代価としてお金を払っていると見る。そうすると、世の中には、両方を買う人は珍しくないわけで、そういう人は、リスク回避的あり、かつ、リスク愛好的であるという矛盾した性格を兼ね備えることになる。何ともマズい解釈をしているわけだ。
………
この矛盾も、時間制約が共通の原因になっていると考えれば、頭を悩ませることもない。それぞれ別の効用を持ち出したりするから、かえって分らなくなる。このことを明瞭に理解するには、反対の「人生が無限の場合」に、宝くじや損害保険に対して、どう行動するかを考えてみると早い。
もし、人生が永遠なら、宝くじを買い続けていれば、積み重なった代金は、いずれは一等の賞金を上回るようになる。それならば、買わずに積み立て貯金にでもしておけば良い。そちらの方が一等の賞金を当てるより早く、その額に到達するだろう。損害保険も同じだ。人生が永遠なら、火災に会っても、その後、保険料に見合う額を積み立てていけば、損害額を超える日が来る。
つまり、人生が永遠の者にとっては、宝くじも損害保険も無意味なのだ。逆に言えば、人生が限られていることが期待値に従わない行動に意味を持たせている。好みの問題ではない。多くの人は、若い時に冒険を好み、老いてからは保守的になるが、これは、好みが変わるのではなく、持ち時間が減るためだ。持ち時間がある場合に限り、リスクを分散させられ、期待値に頼れるようになるのである。
………
もう一つ、極端な例を示そう。数学者のD・べルヌーイによるサンクトペテルブルクのパラドックスというものだ。これは、コイン投げで、裏が出続けると、賞金が2倍、4倍と倍々で増えていくゲームであり、この期待値を計算すると無限大となる。それにもかかわらず、このゲームに参加したいと思う人はいないという矛盾である。
普通の人は、最初の賞金を2円として、10回連続で裏を出しても1024円と考え、有利なゲームではないと判断する。実は、統計学的には、期待値は無限大であっても、それに近づくには無限にコインを投げなければならないことが知られている。例えば、20回連続で裏を出して100万円を当てるには、約100万回コインを投げなければならないが、それには、毎分1回、1日8時間、土日休みなしで、6年かかる。
ベルヌーイのパラドックスについて、現在の経済学は、金額が大きくなるほど効用が低下するからと解釈しているが、効用を持ち出さなくても、こういう性質の無限大は、人生に限りのある者には、とても手に負えるものではない。このように、時間制約を考慮せずに、期待値に従って合理的に行動すると考えるのは、現実を見誤ることになるのだ。
………
さて、長くなった。ケインズの天才的なアイデアは、行動経済学が実証した人の不合理性と結びついて、マクロ経済の動きを論理的に説明できるようになるだろう。それを橋渡しするのが「時間制約」である。もっとも、「時間制約」と格好をつけたところで、「分散が大きいと期待値に頼れない」という統計量の扱い方の基本的な話ではある。
結局、難しいのは、利益最大化への拘りや、効用による従来の解釈のしがらみから自由になることだと思う。正直、理工系の人からすると、なぜ、筆者がこんなに長々と学説の位置付けを説明しなければならないか、疑問に思えるかもしれない。まあ、これは、解脱のための説法みたいなものかもしれない。分ってしまえば、何ということはないのだ。
消費増税は、そのための苦行なのだろう。失敗を目の前にしたとき、企業の利益最大化のために、これほど金融緩和や法人減税をしたのに、なぜ設備投資は出て来ないのかと、ひとしきり嘆いた後は、需要を抜いてリスクを与えてはダメなのだという、無垢の人なら素直に受け入れることを、従来の経済学の信者も悟ってほしい。そこで悟りを開けず、「超」異次元緩和だの、「超」法人減税だのを求めるといった、救われないことに走ってはいかんよ。
※次回は、成長に関して見ていこうかな。
21世紀の今となっては、ケインズが何を間違えていたかは明らかだ。個々がしていたのは、正しいことではなく、わずかに間違ったことだったのである。わすかな不合理でも、それが組織化される傾向があれば、大きな秩序を作り出してしまう。もはや、このような物理現象は理工学では常識となっているのだから、デフレやインフレについても、同じ観点で理解すべきだろう。
現在の経済学は、マクロのミクロ的基礎付けと言って、個々の完全な合理性に拘り、総体的な現象を、むしろ見え難いものにしてしまった。ケインズの主張を正常進化させていれば良かったものをと惜しまれる。むろん、経済学も多様であり、「反主流派」の行動経済学では、個々がどのように行動するかを実験で明らかにして、不合理な行動の存在を実証して来てもいる。
………
行動経済学のこうしたアプローチは、科学において実証が何より大切なことからすれば、正しいものだと考える。課題としては、主流派とは逆に、いかに論理付け、整理して、簡潔な理解へ到達するかであろう。それが適用範囲を広げることにもなる。その基本的な手法は、ヒトの心理に立脚するものなのだから、「変わりやすい地球環境の中で、人類が生き残ってくるのに有利な戦略の表れ」として整理するのが自然な流れだとは思う。
例えば、利得より損害を強く回避しようとするのは、より多く食糧をせしめるより、危険を避けて命と体を守る方が子孫を残す可能性を高められたことの表れかもしれない。現代において、利益最大化よりも会社の存続可能性を確保しようという傾向は、太古からの人類の戦略の適用例のようにも見える。
ただし、それは変えられないものではないことに注意が必要だ。脂肪分を積極的に摂取しておくという、人類が子孫を残す上で有利であったに違いない戦略は、飽食の現代では、必ずしも有利とは言えない。健康と、そして、モテるためには、ダイエットも必要だ。25万年の来歴によって、性(さが)というまでに形成された戦略を、今日では、意思の力で修正しなければならなくなっている。
ためにする議論に聞こえるかもしれないが、現在の経済学の主流派の立場からすれば、心理に基づく行動は、理性で変わり得るものだ。実際、行動ファイナンスの研究の中で見つけられたアノマリーが、認識されたことによって、消えてしまった例もある。したがって、戦略は、長期的には進化し、利益最大化をもたらすだろうと言えなくもない。
………
また、行動経済学のマクロ経済への適用については、カーネマンも認めるように、実験で得られたのは瞬間的判断での反応であり、そのまま使えるのかという問題もある。期待値の低い選択肢を選んでしまう反応を示したからといって、長期的には、選択が繰り返されることで反応が変化したり、期待値の計算による判断が持ち込まれることだって考えられる。
マクロ経済では、設備投資の判断は、繰り返されるものだし、直感に頼らなければならないものでもない。繰り返しや理性の導入をもってしても、なお不合理な選択をし続けるという、強力な論拠が必要だ。それには、不合理な判断を生む戦略が進化の過程で形成されてきたというだけでなく、戦略の原因を掘り下げる必要がある。
その点について、「どうすれば経済学」は、リスクを分散させられない制約があれば、不合理な行動は続くとし、その制約とは、試行回数の確保に必要な時間であり、人生が限られる以上、克服は無理としている。これを、文学的に「人は死せる存在であるがゆえに不合理」と表現しているわけだ。いわば、行動経済学が実証した反応の原因を突き詰め、マクロ経済の理解に活かせるよう発展させているのである。
道具立ては、至ってシンプルである。統計学の用語で言えば、分散が大きい場合、期待値は大数の法則が働かないと、「意味がない」と言っているに過ぎない。1億分の1の確率で1億円の損害が出るリスクと、10万分の1の確率で10万円の損害が出るリスクと、どちらかを選ばねばならない場合、どちらも期待値は-1円で同じだとしても、後者が選ばれるはずだ。これは直感的にも分かるだろう。
………
主流派の経済学の合理性に対する重大な批判は、アレのパラドックスに始まる。アレは、全体として期待値が高いにも関わらず、その中に、まれでも得られるものがまったく実現しない可能性が含まれると、主観的な評価が期待値より大きく低下するという「反例」を示した。行動経済学は、こうした現象を体系的に説明するものであり、カーネマンの「確率ウェート関数」は、0~1の確率の両端近くで、評価が期待値から大きくズレることを実証している。
こうした反応の原因は何か。そうする効用を人間が持っていることは確かめられたわけだが、原因は必ずしも明らかではない。これを、「大数の法則が働かない試行回数の制約による分散の大きさ」として、原因を特定するのが「どうすれば経済学」となる。原因が時間制約と分かれば、マクロ経済に行動経済学を適用する際には、時間制約が存在するのか、長期的に自然解消される性質のものかを調べれば良いことになる。
調査するまでもないような気もするが、ここから先は実証の問題である。筆者の経験からすると、経営者は一定の期間に成績を求められるし、それは時代を経ても変わっていない。逆に、長期的な視点で研究開発を支持して成果に到達した経営者が褒められたり、オーナー経営者が果敢にリスクを取って大成功を収めたことが賞されたりするのだから、これらは、大方の経営者にとって容易に成し得る業ではないということだろう。
しかも、設備投資の判断においては、一回ごとの試行が独立しているとは言い難い。不況は何年か続くものなので、積極策で失敗した後、更に積極策を続けて成功で埋め合わせるというのは、余りに危険だ。個別性の少ないマクロ経済予測ですら、来年は今年と同じとするナイーブ予測の成績が良かったりする有様だ。おそらく、正のフィードバックが働くことがリスクに抗することを、より危険にしているのだろう。
………
こうした時間制約の観点で眺めてみると、主流派の経済学が理解に苦しみ、行動経済学が新しい解釈に努めているものが整理されてくる。もちろん、全部が片付くわけではないが、簡潔なものとなり、適用範囲を広げることになる。以下では、理解を深めるために、いくつかを取り上げて説明してみよう。
まずは、損害保険と宝くじである。どちらも、期待値の観点では、払った分より、見返りが随分と少ない「マイナスの商品」である。そうでなければ、胴元も保険業も成り立たない。従って、現在の経済学が想定するような合理的な人は買わないはずで、短期的にはともかく、長期的には衰退し、不合理が解消されなければおかしいことになる。
ところが、現実には、宝くじは15世紀半ばにはオランダで行われていた記録があり、海上保険は14世紀のイタリアで営まれていたとされる。してみると、現在の経済学が主張する合理性の発揮には、500年以上かかる場合もあるようだ。それからすれば、15年デフレが続いているくらいで、文句を言ってはいけないのかもしれない。もし、「果報は寝て待て」、「待てば海路の日和あり」が正しいなら、デフレへの対応は、実に他愛ないものになる。
しかも、現在の経済学では、不合理を解釈するのに、損害保険はリスク回避的な人が買い、宝くじはリスク愛好的な人が買うとする。つまり、損害の不安を払拭する効用や、賞金を当てる夢を見る効用の代価としてお金を払っていると見る。そうすると、世の中には、両方を買う人は珍しくないわけで、そういう人は、リスク回避的あり、かつ、リスク愛好的であるという矛盾した性格を兼ね備えることになる。何ともマズい解釈をしているわけだ。
………
この矛盾も、時間制約が共通の原因になっていると考えれば、頭を悩ませることもない。それぞれ別の効用を持ち出したりするから、かえって分らなくなる。このことを明瞭に理解するには、反対の「人生が無限の場合」に、宝くじや損害保険に対して、どう行動するかを考えてみると早い。
もし、人生が永遠なら、宝くじを買い続けていれば、積み重なった代金は、いずれは一等の賞金を上回るようになる。それならば、買わずに積み立て貯金にでもしておけば良い。そちらの方が一等の賞金を当てるより早く、その額に到達するだろう。損害保険も同じだ。人生が永遠なら、火災に会っても、その後、保険料に見合う額を積み立てていけば、損害額を超える日が来る。
つまり、人生が永遠の者にとっては、宝くじも損害保険も無意味なのだ。逆に言えば、人生が限られていることが期待値に従わない行動に意味を持たせている。好みの問題ではない。多くの人は、若い時に冒険を好み、老いてからは保守的になるが、これは、好みが変わるのではなく、持ち時間が減るためだ。持ち時間がある場合に限り、リスクを分散させられ、期待値に頼れるようになるのである。
………
もう一つ、極端な例を示そう。数学者のD・べルヌーイによるサンクトペテルブルクのパラドックスというものだ。これは、コイン投げで、裏が出続けると、賞金が2倍、4倍と倍々で増えていくゲームであり、この期待値を計算すると無限大となる。それにもかかわらず、このゲームに参加したいと思う人はいないという矛盾である。
普通の人は、最初の賞金を2円として、10回連続で裏を出しても1024円と考え、有利なゲームではないと判断する。実は、統計学的には、期待値は無限大であっても、それに近づくには無限にコインを投げなければならないことが知られている。例えば、20回連続で裏を出して100万円を当てるには、約100万回コインを投げなければならないが、それには、毎分1回、1日8時間、土日休みなしで、6年かかる。
ベルヌーイのパラドックスについて、現在の経済学は、金額が大きくなるほど効用が低下するからと解釈しているが、効用を持ち出さなくても、こういう性質の無限大は、人生に限りのある者には、とても手に負えるものではない。このように、時間制約を考慮せずに、期待値に従って合理的に行動すると考えるのは、現実を見誤ることになるのだ。
………
さて、長くなった。ケインズの天才的なアイデアは、行動経済学が実証した人の不合理性と結びついて、マクロ経済の動きを論理的に説明できるようになるだろう。それを橋渡しするのが「時間制約」である。もっとも、「時間制約」と格好をつけたところで、「分散が大きいと期待値に頼れない」という統計量の扱い方の基本的な話ではある。
結局、難しいのは、利益最大化への拘りや、効用による従来の解釈のしがらみから自由になることだと思う。正直、理工系の人からすると、なぜ、筆者がこんなに長々と学説の位置付けを説明しなければならないか、疑問に思えるかもしれない。まあ、これは、解脱のための説法みたいなものかもしれない。分ってしまえば、何ということはないのだ。
消費増税は、そのための苦行なのだろう。失敗を目の前にしたとき、企業の利益最大化のために、これほど金融緩和や法人減税をしたのに、なぜ設備投資は出て来ないのかと、ひとしきり嘆いた後は、需要を抜いてリスクを与えてはダメなのだという、無垢の人なら素直に受け入れることを、従来の経済学の信者も悟ってほしい。そこで悟りを開けず、「超」異次元緩和だの、「超」法人減税だのを求めるといった、救われないことに走ってはいかんよ。
※次回は、成長に関して見ていこうかな。


















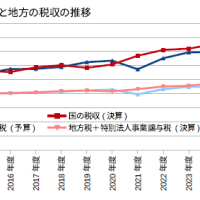





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます