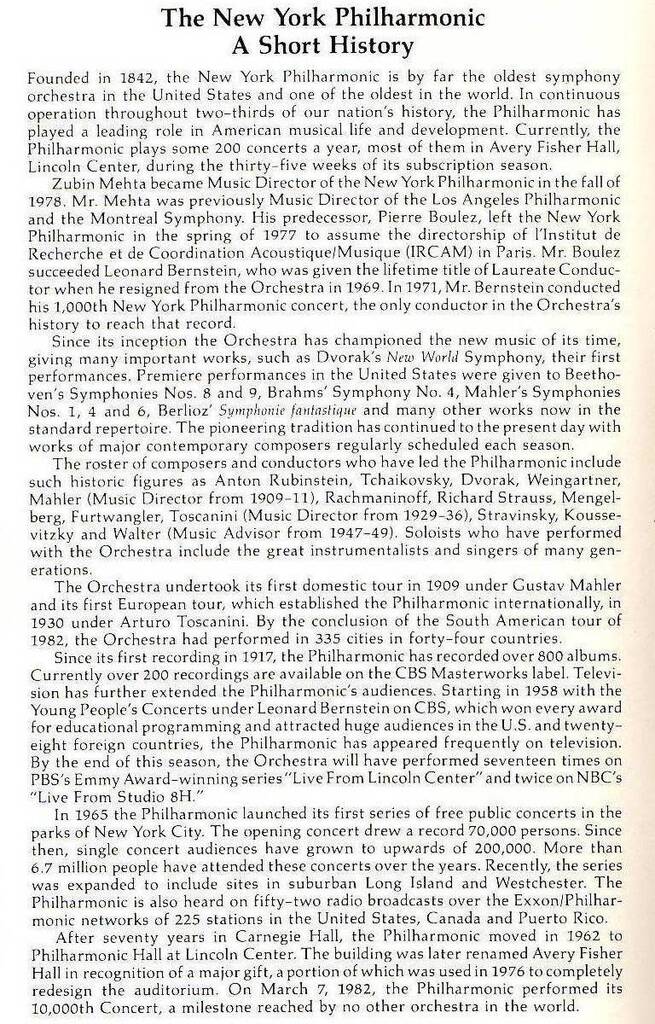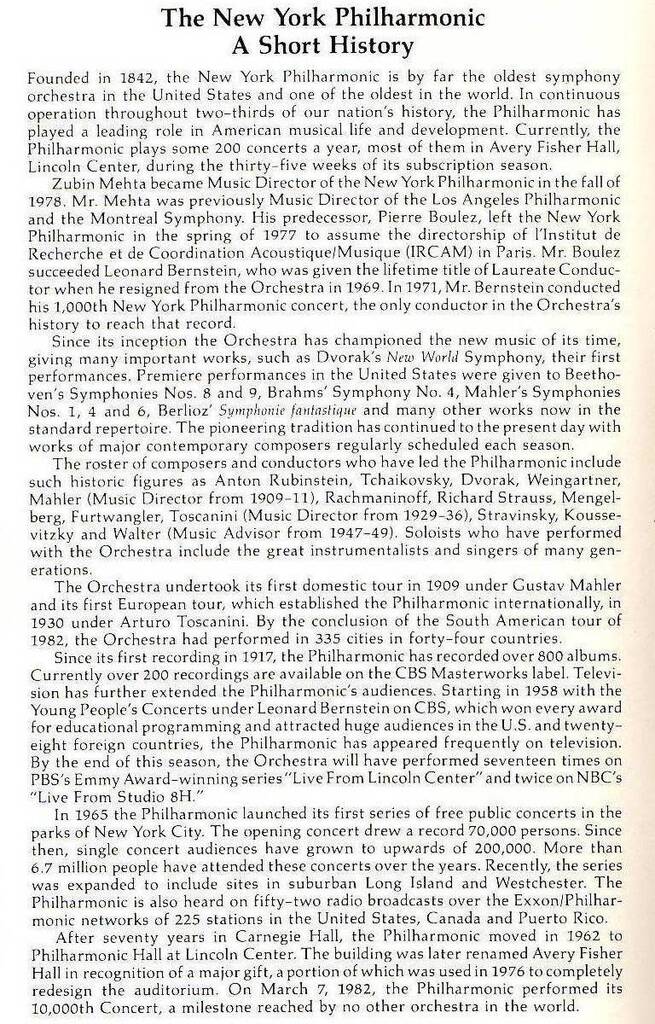前回までのブログでニューヨーク・フィルハーモニックの1983-1984シーズン・オープニング・コンサートのことを書きました。
ということは、またこのシーズンもはじまりです。
オープニング・コンサートは単発公演ですが、翌日からはいつものように週4回の公演となります。
1983年9月15日(木)8:00pm 第10268回
1983年9月16日(金)2:00pm 第10269回
1983年9月17日(土)8:00pm 第10270回
1983年9月20日(火)7:30pm 第10271回 出席
エイヴリー・フィッシャー・ホール
ウィリアム・シューマン 交響曲第10番アメリカン・ミューズ
ベートーヴェン/交響曲第3番 エロイカ
ラファエル・クーベリック 指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック
●
週4回というのは、こんな感じ。
木曜日8:00pm
金曜日2:00pm
土曜日8:00pm
火曜日7:30pm
これが、ほぼ毎週繰り返されます。
同じ曲を4回演奏しなければならないが、いつまでもそのフレッシュさを感じさせてくれるのも指揮者の技量なのだろう。
河童のシーズンチケットは4回目のものなので9月20日の公演ということになる。
その4回目の演奏はどうだったの?
●
エロイカ第1楽章再現部における楽員の音楽への、のり。
本当に乗りにのった素晴らしい演奏であった。ラファエル・クーベリックとともに。
クーベリックの容姿とくに左手の動きは全くフルトヴェングラーそのものである。まさにドイツ音楽、フルトヴェングラーの精神的後継者ともいえるクーベリックの指揮によるエロイカを聴いたといえる。
第1楽章再現部における溢れ出るような音楽、流れ出るような音楽。生を感じさせる。本当に素晴らしく即興性にあふれた生きた音楽であった。
最初の二つの強打から始まった音楽はもうすでにその時点で生き生きしていた。第1主題とその背後で小刻みに震える弦の生き生きした表現。この時点でただひたすら快調。言葉ではあらわせない。とにかく聴いてくれと言いたい。
そしてこの第1主題の快調なテンポが第2主題に移った時の急激なテンポの変化。こんな落差のあるエロイカなんて、第1主題と第2主題のテンポの差がこんなに大きい演奏なんて、ほかにあっただろうか。フルトヴェングラーの第2主題はもっとおそいかもしれないが、第1主題は第2主題に限りなく近くおそい。
いずれにしろ、このように極端に第1主題と第2主題のテンポが異なるのに何故、音楽はひたすら流れるのであろうか。
クーベリックにはこのように前進する音楽はよく合っているのではないか。アウフタクトよりもどちらかというと、欲しいその音に対して非常な力点があり、特別に強烈なアタックがその音にのしかかっているわけではないが、みんなその音に集中するため、ひたすら前進する力強さを感じる。そして、のってくるとその左手がフルトヴェングラー的としかいいようのない動きとなる。
この第1楽章は本当に素晴らしい演奏でした。出だしからホルンはフォルテシモは全て破裂音であり、それは第4楽章の例のコーダまで全く変わらず、本当に迫力がありドイツのいたるところにある馬に乗った中世騎士のような勇壮な姿が目前に浮かんでくる。このニューヨーク・フィル相手に、というか、へんなきらびやかさと軽さがまるで感じられないのがまたよい。
それは次の第2楽章のしっとりとした音楽にもよくあらわれてた。指揮者がかわると音楽ばかりではなく音そのものまで変化する。
この暗くて迫力に満ちた音楽性。これをきいて瞬時に思い出すのは、同じくクーベリックがベルリン・フィルを指揮した録音。ここには暗く流れる音楽がある。ここでどうしてもフルトヴェングラーとの音楽の違いを感じないわけにはいかない。
フルトヴェングラーはもっとテンポがおそく、ひとつひとつの音をかみしめながら歩いている。彼の場合、歩いていると言ったほうがふさわしい。従って第2主題が現れた時や、中間部など前と変わらないテンポであり、その音色の持つ劇的なものの変化で聴衆を魅了する。このようなことを考えるとき、フルトヴェングラーは全く葬送行進曲にふさわしい音楽作りをしていたといえる。
クーベリックはその点ちょっと異なっていて言葉ではうまく表せないが、一言で言うとフルトヴェングラー風の悲劇性を感じさせない。どちらかというとアンサンブルのあやの方に興味がいく。ついドヴォルザークのような音楽と歌を感じてしまう。
この感触は言葉ではうまく言い表せないが別の例をひきだすと、バルビローリ/ベルリン・フィルによるあのマーラーの9番の第1楽章を聴くとき、実にすばらしい音楽に浸れる幸せは感じさせてくれるが、これがクーベリックで聴くとその上に何か非常に現代的なものに近づこうとするマーラーの姿が明晰に浮かんでくる。例は良くないかもしれないがとにかくこの葬送行進曲を聴いているとこのようなことを強く感じる。実演でなお一層その感を深くしたのだから、あながち今まで考えていたことがそんなに間違っているようなこととも思えない。クーベリックの音楽はレコードで聴く場合とはそんなに極端な差異はなく、逆に自分で感じていた認識を深める方向に持っていってくれる。従ってこれがマーラーなどのように、より大胆な表現が許容されるような音楽にいたるにつれて、さらに説得力を持つのはよくわかる。
大胆さの持つ説得力。これは一つ間違うと表面的なものに終わってしまう場合がえてしてあるものなのだが、そのような演奏では大局的に曲をみた場合、不自然な造形を持つものなのだ。彼の場合にはそのようなことはないので、局部的なはったりではなく、全体に与えるその一部分の必然性をいやがおうでも感じてしまう。
第3楽章で強く思うのは、あの第1楽章と同じようにアウフタクトよりも、ひたすら次の小節の一拍目にかかる音の集中力。弦などは次のリズムに移る前の小節などは不揃いになり音が濁ったりするのだが、これは彼らが出来ないからなのではない。それならばなぜ次の小節からかくのごとき集中力のあるまるでトーンクラスターのような音楽が発生するのか。ホルンの強奏はあいかわらず音を全て割って吹いている。オーケストラ全体の上にひたすらさんぜんと光り輝いている。ものすごい迫力だ。
第4楽章の流れるような変奏曲。まるで第1楽章の再現部から続いてでもいたかのように。ここにきて我々はただひたすらこの二拍子の変奏曲の音のあやに身を任せていればよいのです。手をちょっと下げ気味にしてひたすら二拍子を振る姿。あのような単純さがしばしば深い感動をもたらす。それにのりにのったニューヨーク・フィルに対しても拍手を惜しんではいけない。俗に言われているあまりよい意味ではないアメリカ的なもの、それがここには全くない。ここにあるのはひたすら力点に向かうその集中力だけなのです。このような姿はやっぱり美しいものだと思う。集中力の持つ美しさ。それを引き出すクーベリック。実にすばらしい。
そして最後のゆっくりした変奏曲。ここで音楽は少し休み、そしてあいかわらずホルンは素晴らしく光り輝き、そのままコーダへと移る。ここは完全にホルンの独壇場。何かに取りつかれた迫力。ド迫力。そしてほかのすべての楽器が、それにまとわりつくように前進するその姿。本当にエロイカにふさわしい音楽である。
.
さて、最初に演奏されたウィリアム・シューマンのシンフォニー。
とにかく初めて聴く曲。予備知識‘ゼロ’。
しかしその構成といい長さといい全く現代にアピールする曲だと思う。現代という時代音楽において、その歴史的価値を判断することほどばかげていることはないと思う。素朴に、与えられた曲について考えてみることだ。
第1楽章は、なぜかマーラーの交響曲第8番の第1楽章を思い出してしまった。まるでなにかの前奏曲のようなひたすら明るく輝く音楽。たまに異常に澄んだハーモニーが出てくるのも印象的であった。とにかく対位法的なものが明晰でそれぞれの楽器が異なったメロディーをかなでる姿は味わい深い。これだけの大編成でこれだけはっきりした音楽を作ることができるということは、やっぱり何かうったえかけるものを素直に感じとるべきだろう。第1ヴァイオリンは1プルトが多くて、これはこの曲についてだけかなと思ったら、次のエロイカでもそのままであった。
曲全体は3楽章形式のようなのだが、第3楽章の最初はスケルツォみたいな雰囲気であり、実質4楽章形式である。その第4楽章にあたる最後の部分は光り輝くオーケストラが対位法的な説得力をもって迫ってくる。
シンフォニーにおいてこの4楽章形式はひたすら崩れる必要はないと感じる。メロディーは、ハーモニーは失ったかもしれない。しかしこの形式がまだ続いているというのは興味深い。
最後に、ニューヨーク在住のウィリアム・シューマンがステージに現れて拍手にこたえていた。
●
以上、全く稚拙な文章だが、妙にリアルだ。その時そう感じたのだろう。などと他人事みたいなことをいってもしょうがない。
なお、この4回定期は、WQXRでオンエアーされた。
WQXR
1984年1月8日(日) 3:05pm
このときはエアチェックをしていなかった。
どこでどうさまよっていたのだろう。
真冬なので、週末のチャリジョギングはしていないはずだし。
別の河童日記をひらくのは別の機会だ。。
おわり