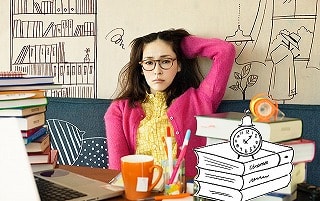『カノジョは嘘を愛しすぎてる』をヒューマントラストシネマ渋谷で見ました。
(1)友人の紹介で見に行ったのですが、映画館が女子高生であふれていたのには驚きました。でも、原作がベストセラー漫画(青木琴美作)で、映画の主人公を人気の佐藤健が演じ、ヒロイン役がオーディションで選ばれた女子高生なのですから当然かもしれません。
本作の冒頭では、渋谷にあるビルの屋上にいる主人公・アキ(佐藤健)のところに、ヘリコプターが空から舞い降りてきて、中から大人気のバンドCRUDE PLAY(通称クリプレ)の4人が出てきます。

中の一人が、「リーダーを迎えに来た」と言うと、アキは「ヘリで来るなよ、タクシーでよかった」と答えます。そして、バンドのベーシスト・シンヤ(窪田正孝)が、「僕はここで。先にパーティー会場に行っている。後は、昔の4人で楽しんで」といってその場を離れます。残った4人は、「アルバムV3達成!」とシャンパンで乾杯します。
この場面は、アキがどういった位置にいるのかを暗に示しています。すなわち、アキは、クリプレの影のリーダー的な存在であり、またシンヤを除くメンバーと昔は仲良しだったようなのです(注1)。

ただ、冒頭のシーンの最後に、「あの頃の僕は大体が不機嫌だった。しかし、その理由ははっきりわからなかった」というアキの音声が被って、タイトルクレジットが流れます。
続いて、アキは音楽スタジオでキーボードに向かいますが、「何も持っていなかった頃より、僕は空っぽだ。本当に欲しかったものを何一つ持っていないからかもしれない」と彼の喋る音声が流れます。
そして、自分の部屋に戻ると、そこには恋人の茉莉(相武紗季)がベッドにいて、「できた?あたしの曲」と尋ねるので、アキは「もう高樹(音楽プロデューサー:反町隆史)のゴーストはやらないって言ったよね」、「モウこれ以上は無理だ。高樹とお前が寝ているところを想像すると、頭が狂いそうになる」、「鍵は置いていって」と答えて部屋を飛び出してしまいます。
そんなアキが、自分の部屋のソバの隅田川の川べりで手すりに持たれながら鼻歌を口ずさんでいると、青果店の娘で高校生のリコ(大原櫻子)が、押してきた自転車を倒してしまい、荷台にあった箱から果物や野菜が転がり落ちてしまいます。

それを拾ってあげるアキが、唐突に「一目惚れって信じますか?」と尋ねると、リコは、「信じます。だって、一目惚れしちゃった。今の鼻歌に鳥肌が立った。名前を教えてください」と答えます。 それに対してアキは、なぜか「シンヤ」と嘘を答えてしまうのです(注2)。

そんな出会いからアキとリコとのラブストーリーが始まるわけですが、はたして二人は上手くゴールに到達できるのでしょうか、………?
本作では、酷く屈折した心の持ち主の主人公と、純真そのもののヒロインとの組み合わせが物語の展開をなかなか面白くしています。さらに、その背景として渋谷とウォーターフロント周辺というのもよくマッチしています。最近のラブストーリーとしてはまずまずの出来栄えだと思いました(注3)。
(2)アキとリコとが初めて出会うまでの経緯などは実に手際よく描かれていて感心します。
飛躍の多い展開も見られるところ(注4)、本作は台詞の多い(歌の少ない)ミュージカルではないかと思えば、それらに一々突っ込まずに楽しく見ることが出来そうです。
でも、最後のアキとリコによる「ちっぽけな愛のうた」で大きく盛り上がるのですから(注5)、その後のシーンやエンドロール後のおまけシーンはなくもがなという感じがするところです。
もう一つ残念だったのは、クリプレの演奏のTV録画収録風景をリコたちが見るときに、彼らが実際には演奏していないこと(あるいはCDで聞く演奏とだいぶ違うな)に気がついて、おかしいな、自分たちもああなるのかな、嫌だなと思うシーンがあれば、その後違った展開になるかもしれないと思える点です(注6)。
とはいえ、本作に登場するクリプレや「MUSH&Co.」(リコとその仲間の2人)のように、ライブ活動をするバンドがスタジオ・ミュージシャンにまるきり依存してしまうのかどうか、よくわからないところです(注7)。
(3)渡まち子氏は、「人気俳優の佐藤健と、オーディションで選ばれたシンデレラ・ガールの大原櫻子の相性がよく、3回登場するキス・シーンは原作ファンならずともうっとりするはず。加えて、大原櫻子のびやかな歌声と素朴な笑顔が大きな魅力だ」として55点をつけています。
ただ、柳下毅一郎氏は、「例によってセリフですべて心情を説明する副音声映画であるうえに、物語も別に起伏がないので本当につまらない。俳優は平凡。演奏は口パク。単純につまらない」と酷評しています(注8)。
とはいえ、例えば、柳下氏は、「ゴージャスな美形ばっかり出てくる少女漫画の映画化にしてはびっくりするほど高級感がない下町人情話が展開する」と述べていますが、確かにヒロインは「青果店」の娘(柳下氏は「八百屋の娘」としていますが)ながら、「下町人情話」に特有の人の良い一族郎党とか近所の八つぁん熊さんなどは一切登場しないのですから、ちょっと言い過ぎではないかと思いますが。
(注1)さらに主人公・アキは、時間が空くと隅田川の川べりで、ラジコンヘリを飛ばすのが趣味でもあります。リコとの初めての出会いの前にもラジコンヘリを飛ばしていましたが、酷く苛ついて墜落させ、壊してしまいます。
(注2)このシーンの最後には、「付き合い始めたあの頃は、これっぽっちも好きじゃなかった」とか、「全部嘘。でも、彼女は僕のことを正直な人と言うんだ」といったアキの音声が流れます。
(注3)佐藤健は、最近では、『リアル~完全なる首長竜の日~』を見ました。
なお、佐藤健は、これまた青春音楽映画である『BECK』に出演していて、同作でもギターを弾くものの、むしろ「天才的な歌手」であることが前面に出され、さらにまたラブストーリー絡みでもありませんから、本作と比較しても仕方がないでしょう〔ただ、本作の主人公アキは「天才サウンドクリエーター」とされ、また、音楽プロデューサー・高樹はリコについて「天才を見つけちゃった」と言ったりして(同じ言葉を、高樹は茉莉にも以前言ったことがあるようです)、両作で「天才」という言葉が大安売りとなっています。音楽畑では「天才」があちこちでみかけられるようです!〕。
(注4)なにしろ、例えば、アキがリコと出会うのと時を同じくして、高樹が、川べりで歌うリコの歌声を聴いて、すぐにデビューさせようとするのですから!
その上、リコとその仲間2人とのバンド「MUSH&Co.」のプロデューサーにシンヤが名乗りを上げるのです。
(注5)アキは、茉莉の言う条件を飲んでリコと別れることにしたのですから、さらにはリコがシンヤの曲を歌っている姿を見て感じるところ(リコは、もう蛹からかえったアゲハチョウのように一人で飛び立てる)があったのですから、最後の「ちっぽけな愛のうた」は2人の別れの最終仕上げであって(♪……/手のひらに掴んだ夢を/今は追い続けていこう/一人でもきっと越えてゆける/……♪)、それ以降の展開は考えられないのではないでしょうか?たとえアキがロンドンから戻ってきてリコを再度愛するようになるにしても、それは別の物語でしょう。
(注6)「MUSH&Co.」のデビュー・ライブ演奏をリコとその仲間がすっぽかして、リコはアキと一緒にロンドンに旅立つというのはどうでしょう(でも、これだと茉莉との約束をアキは破ってしまうことになってしまい、またリコの独り立ちもご破算になってしまいますが)。
(注7)クリプレがスタジオで練習をしている時に高樹が現れたので、メンバーが「今度の曲は自分たちで演奏してみたい」と言うと、高樹は「冗談言うな。誰が素人の演奏に金など払うか。だが、練習するのは悪くない。弾くふりがうまくなるからな」と言い放ちます。
これに対してメンバーは怒り狂いますが、リーダーのシュン(三浦翔平)は、「クソみたいな演奏しか出来ない俺達が悪いんだ」と宥めます(なお、クリプレの場合に問題となるのは、後から加わったベーシストのシンヤはプロですから、ドラマーのテッペイと、ギタリストのカオルでしょう)。
とはいえ、CDやTV等では、スタジオ・ミュージシャンを使った演奏で済ますことが出来ますから、問題はライブ演奏ではないかと思われます。
「MUSH&Co.」の場合、高樹から「デビュー決定、おめでとう」と言われて、仲間の一人が「自分たちは演奏を始めて少ししか経っていない」と言うと、高樹は「演奏なんか出来なくても関係ない。後ろでプロがやってくれる」と答えます。
実際にも「MUSH&Co.」のデビュー・ライブ演奏では、仲間の2人の他に、バックに2人ほどスタジオ・ミュージシャンが立っています。
ただ、何人もギタリストがステージに立っていてもそれほどおかしくないかもしれませんが、ドラムスの場合、ライブではどうするのでしょうか?
現実の話として、下手くそな演奏しか出来ないバンドがメジャー・デビューすることはそんなに多くないのではとも思えるのですが。
(注8)つまらないことながら、クリプレや「MUSH&Co.」が広い意味で「口パク」であることは映画の中で言われていることですから、ことさら非難するに値しないと思われますが(元々、映画における演奏シーンが「口パク」ではなくリアルなものだとは、一般に思われていないのではないでしょうか)。
★★★☆☆
象のロケット:カノジョは嘘を愛しすぎてる
(1)友人の紹介で見に行ったのですが、映画館が女子高生であふれていたのには驚きました。でも、原作がベストセラー漫画(青木琴美作)で、映画の主人公を人気の佐藤健が演じ、ヒロイン役がオーディションで選ばれた女子高生なのですから当然かもしれません。
本作の冒頭では、渋谷にあるビルの屋上にいる主人公・アキ(佐藤健)のところに、ヘリコプターが空から舞い降りてきて、中から大人気のバンドCRUDE PLAY(通称クリプレ)の4人が出てきます。

中の一人が、「リーダーを迎えに来た」と言うと、アキは「ヘリで来るなよ、タクシーでよかった」と答えます。そして、バンドのベーシスト・シンヤ(窪田正孝)が、「僕はここで。先にパーティー会場に行っている。後は、昔の4人で楽しんで」といってその場を離れます。残った4人は、「アルバムV3達成!」とシャンパンで乾杯します。
この場面は、アキがどういった位置にいるのかを暗に示しています。すなわち、アキは、クリプレの影のリーダー的な存在であり、またシンヤを除くメンバーと昔は仲良しだったようなのです(注1)。

ただ、冒頭のシーンの最後に、「あの頃の僕は大体が不機嫌だった。しかし、その理由ははっきりわからなかった」というアキの音声が被って、タイトルクレジットが流れます。
続いて、アキは音楽スタジオでキーボードに向かいますが、「何も持っていなかった頃より、僕は空っぽだ。本当に欲しかったものを何一つ持っていないからかもしれない」と彼の喋る音声が流れます。
そして、自分の部屋に戻ると、そこには恋人の茉莉(相武紗季)がベッドにいて、「できた?あたしの曲」と尋ねるので、アキは「もう高樹(音楽プロデューサー:反町隆史)のゴーストはやらないって言ったよね」、「モウこれ以上は無理だ。高樹とお前が寝ているところを想像すると、頭が狂いそうになる」、「鍵は置いていって」と答えて部屋を飛び出してしまいます。
そんなアキが、自分の部屋のソバの隅田川の川べりで手すりに持たれながら鼻歌を口ずさんでいると、青果店の娘で高校生のリコ(大原櫻子)が、押してきた自転車を倒してしまい、荷台にあった箱から果物や野菜が転がり落ちてしまいます。

それを拾ってあげるアキが、唐突に「一目惚れって信じますか?」と尋ねると、リコは、「信じます。だって、一目惚れしちゃった。今の鼻歌に鳥肌が立った。名前を教えてください」と答えます。 それに対してアキは、なぜか「シンヤ」と嘘を答えてしまうのです(注2)。

そんな出会いからアキとリコとのラブストーリーが始まるわけですが、はたして二人は上手くゴールに到達できるのでしょうか、………?
本作では、酷く屈折した心の持ち主の主人公と、純真そのもののヒロインとの組み合わせが物語の展開をなかなか面白くしています。さらに、その背景として渋谷とウォーターフロント周辺というのもよくマッチしています。最近のラブストーリーとしてはまずまずの出来栄えだと思いました(注3)。
(2)アキとリコとが初めて出会うまでの経緯などは実に手際よく描かれていて感心します。
飛躍の多い展開も見られるところ(注4)、本作は台詞の多い(歌の少ない)ミュージカルではないかと思えば、それらに一々突っ込まずに楽しく見ることが出来そうです。
でも、最後のアキとリコによる「ちっぽけな愛のうた」で大きく盛り上がるのですから(注5)、その後のシーンやエンドロール後のおまけシーンはなくもがなという感じがするところです。
もう一つ残念だったのは、クリプレの演奏のTV録画収録風景をリコたちが見るときに、彼らが実際には演奏していないこと(あるいはCDで聞く演奏とだいぶ違うな)に気がついて、おかしいな、自分たちもああなるのかな、嫌だなと思うシーンがあれば、その後違った展開になるかもしれないと思える点です(注6)。
とはいえ、本作に登場するクリプレや「MUSH&Co.」(リコとその仲間の2人)のように、ライブ活動をするバンドがスタジオ・ミュージシャンにまるきり依存してしまうのかどうか、よくわからないところです(注7)。
(3)渡まち子氏は、「人気俳優の佐藤健と、オーディションで選ばれたシンデレラ・ガールの大原櫻子の相性がよく、3回登場するキス・シーンは原作ファンならずともうっとりするはず。加えて、大原櫻子のびやかな歌声と素朴な笑顔が大きな魅力だ」として55点をつけています。
ただ、柳下毅一郎氏は、「例によってセリフですべて心情を説明する副音声映画であるうえに、物語も別に起伏がないので本当につまらない。俳優は平凡。演奏は口パク。単純につまらない」と酷評しています(注8)。
とはいえ、例えば、柳下氏は、「ゴージャスな美形ばっかり出てくる少女漫画の映画化にしてはびっくりするほど高級感がない下町人情話が展開する」と述べていますが、確かにヒロインは「青果店」の娘(柳下氏は「八百屋の娘」としていますが)ながら、「下町人情話」に特有の人の良い一族郎党とか近所の八つぁん熊さんなどは一切登場しないのですから、ちょっと言い過ぎではないかと思いますが。
(注1)さらに主人公・アキは、時間が空くと隅田川の川べりで、ラジコンヘリを飛ばすのが趣味でもあります。リコとの初めての出会いの前にもラジコンヘリを飛ばしていましたが、酷く苛ついて墜落させ、壊してしまいます。
(注2)このシーンの最後には、「付き合い始めたあの頃は、これっぽっちも好きじゃなかった」とか、「全部嘘。でも、彼女は僕のことを正直な人と言うんだ」といったアキの音声が流れます。
(注3)佐藤健は、最近では、『リアル~完全なる首長竜の日~』を見ました。
なお、佐藤健は、これまた青春音楽映画である『BECK』に出演していて、同作でもギターを弾くものの、むしろ「天才的な歌手」であることが前面に出され、さらにまたラブストーリー絡みでもありませんから、本作と比較しても仕方がないでしょう〔ただ、本作の主人公アキは「天才サウンドクリエーター」とされ、また、音楽プロデューサー・高樹はリコについて「天才を見つけちゃった」と言ったりして(同じ言葉を、高樹は茉莉にも以前言ったことがあるようです)、両作で「天才」という言葉が大安売りとなっています。音楽畑では「天才」があちこちでみかけられるようです!〕。
(注4)なにしろ、例えば、アキがリコと出会うのと時を同じくして、高樹が、川べりで歌うリコの歌声を聴いて、すぐにデビューさせようとするのですから!
その上、リコとその仲間2人とのバンド「MUSH&Co.」のプロデューサーにシンヤが名乗りを上げるのです。
(注5)アキは、茉莉の言う条件を飲んでリコと別れることにしたのですから、さらにはリコがシンヤの曲を歌っている姿を見て感じるところ(リコは、もう蛹からかえったアゲハチョウのように一人で飛び立てる)があったのですから、最後の「ちっぽけな愛のうた」は2人の別れの最終仕上げであって(♪……/手のひらに掴んだ夢を/今は追い続けていこう/一人でもきっと越えてゆける/……♪)、それ以降の展開は考えられないのではないでしょうか?たとえアキがロンドンから戻ってきてリコを再度愛するようになるにしても、それは別の物語でしょう。
(注6)「MUSH&Co.」のデビュー・ライブ演奏をリコとその仲間がすっぽかして、リコはアキと一緒にロンドンに旅立つというのはどうでしょう(でも、これだと茉莉との約束をアキは破ってしまうことになってしまい、またリコの独り立ちもご破算になってしまいますが)。
(注7)クリプレがスタジオで練習をしている時に高樹が現れたので、メンバーが「今度の曲は自分たちで演奏してみたい」と言うと、高樹は「冗談言うな。誰が素人の演奏に金など払うか。だが、練習するのは悪くない。弾くふりがうまくなるからな」と言い放ちます。
これに対してメンバーは怒り狂いますが、リーダーのシュン(三浦翔平)は、「クソみたいな演奏しか出来ない俺達が悪いんだ」と宥めます(なお、クリプレの場合に問題となるのは、後から加わったベーシストのシンヤはプロですから、ドラマーのテッペイと、ギタリストのカオルでしょう)。
とはいえ、CDやTV等では、スタジオ・ミュージシャンを使った演奏で済ますことが出来ますから、問題はライブ演奏ではないかと思われます。
「MUSH&Co.」の場合、高樹から「デビュー決定、おめでとう」と言われて、仲間の一人が「自分たちは演奏を始めて少ししか経っていない」と言うと、高樹は「演奏なんか出来なくても関係ない。後ろでプロがやってくれる」と答えます。
実際にも「MUSH&Co.」のデビュー・ライブ演奏では、仲間の2人の他に、バックに2人ほどスタジオ・ミュージシャンが立っています。
ただ、何人もギタリストがステージに立っていてもそれほどおかしくないかもしれませんが、ドラムスの場合、ライブではどうするのでしょうか?
現実の話として、下手くそな演奏しか出来ないバンドがメジャー・デビューすることはそんなに多くないのではとも思えるのですが。
(注8)つまらないことながら、クリプレや「MUSH&Co.」が広い意味で「口パク」であることは映画の中で言われていることですから、ことさら非難するに値しないと思われますが(元々、映画における演奏シーンが「口パク」ではなくリアルなものだとは、一般に思われていないのではないでしょうか)。
★★★☆☆
象のロケット:カノジョは嘘を愛しすぎてる