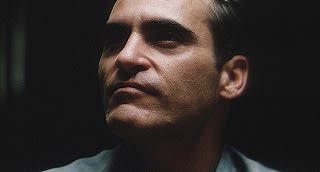『セデック・バレ』を吉祥寺のバウスシアターで見ました。
(1)本作は、台湾で大ヒットしている作品であり、それも戦前の台湾を扱ったものと聞いて、あるいは以前見て大変感動した台湾映画『非情城市』(1989年)のような雰囲気を持っているのかなと期待して、映画館に出かけました(注1)。
舞台は、昭和初期の台湾の山岳地帯の一つの地区。
1895年(明治28年)の下関条約によって統治することとなった日本は、台湾原住民(戦前は「高砂族」といわれていました)の抵抗を排除して、急速に台湾での支配を確立していきます。
ただ、昭和初期になると、それまでの統治実績に自信があったのでしょうか(注2)、日本側は、自分たちを防護することにそれほど重きを置いていないように見受けられます(注3)。
他方、原住民の方では、貧困などから日本に対する恨みがかなり積み重なっていました(注3)。
きっかけは、日本人警察官と原住民の若者との乱闘騒ぎ。それを引き金として、原住民による反乱が勃発します。

具体的に本作で取り上げられるのは、満州事変の前年に当たる1930年10月に起きた霧社事件。
台湾原住民の一つであるセデック族のおよそ300人が、頭目(注4)の一人モーナに率いられて立ち上がり、日本人の警察官のいる駐在所を襲撃したあと、運動会のために学校の校庭に集まっていた日本人約140名を虐殺したのです。

映画の第1部「太陽旗」では、1895年に日本が統治するために乗り込んできたときから決起の日までが描かれ、第2部「虹の橋」では、彼らが3,000名近くに増強された日本の警察と軍隊によって鎮圧されるまでが描かれます。
本作を見ると、遠くは、アメリカにおけるインディアンと騎兵隊の戦いなどに連想がいきますし、近くは、この間のアルジェリア人質事件など様々な事件が思い起こされるところです。
でも、そんな現実的な面よりも、モーナ達決起したセデック人が守ろうとしたのがあくまでも自分たちの「狩り場」であり、勇者として死んで「虹の橋」を渡って祖先の仲間に入ろうとセデックの人たちが望んだという点に(注5)、クマネズミは歴史ロマンを感じました。
とはいえ、何しろ2部作の合計で4時間半以上かかる長尺で、いろいろ興味を惹くものが画面に登場してこないと相当の忍耐が必要になるわけながら、とどのつまりは日本による台湾統治期に起きた原住民による反乱を描くだけですから(注6)、全体として酷く単調な感じになってしまいます(注7)。
(2)勿論、本作に、日本による戦前の植民地政策の問題点を感じる見方もあるでしょう。
例えば、映画評論家の山根貞男氏は、4月19日付朝日新聞に掲載された「原住民の目に映る愚行」と題する映画評において、次のように述べています。
「アジアの映画人が結集した大作といえよう。その映画的な力のもと、画面には、大自然の豊かさ、原住民のおおらかさ、彼らの文化の素晴らしさが充満するが、それだけに、戦いの残酷さは際立つ。ことに後半、山岳地帯を走り回って勇壮に戦う原住民が、大砲はおろか空爆や毒ガスまで用いた日本軍に追い詰められ、女性たちが集団自決に至るくだりは、戦争という人間の愚行を生々しく描」いている。
「それにしても、我々日本人には痛い映画である。アクション映画の面白さを満喫するからこそ、そう感じる。後半、日本の巡査になり日本名を名乗る若い原住民2人が、戦う両方の側に引き裂かれて苦悩する。その姿は我々に通じるといえば、いい気なものだとセデック族の戦士に罵倒されようか。現代史に根ざしたそんな活劇である」。
「原住民の目に映る愚行」というタイトルとか(注8)、「我々日本人には痛い映画である」や、「セデック族の戦士に罵倒されよう」といった文章からは、戦前の日本統治に対する山根氏の強い反省の念がうかがえるところです。
しかしながら、本作で描かれる霧社事件は、既に80年以上も昔の出来事です。歴史的な事実として、もっと客観的に見た方がいいのではないかな、と思われます。
さらに、この映画を制作した魏(ウェイ・ダーション)監督も、「「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった」などと述べているように、特定のイデオロギーに立って映画を撮ったわけではないように考えられます(注9)。
そこで、この点についてクマネズミは、次のフリー・ジャーナリストの福島香織氏の見解に、まだしも同感します(注10)。
同氏は、『日経ビジネス』オンラインの2011年10月5日の記事で、次のように述べています。
「自分の目で前後編を見た上で言えば「セデック・バレ」は抗日事件を題材にしながらも反日映画ではなかったと思う。誤解を恐れずに言えば、むしろ親日映画かもしれない。さらに言えば、ひょっとすると反中華映画かもしれない」。
「映画の最初の「霧社事件を改変している」と字幕で説明しているように、歴史の真実を訴える映画でも、歴史を解説する映画ではないだろう。また、戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画でもなさそうだ」(注)。
「この映画が親日映画ではないか、と感じるのは、原住民の抗日事件を描きながら、靖国神社や武士道に象徴される日本人の感性を台湾人が理解していることをそこはかとなく表現しているからだ」。
要すれば、本作は抗日事件を題材にしながらも戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画ではない、ということでしょう。
クマネズミもそう思いましたが、でもさらに言えば、福島氏のように、「抗日」「反日」「親日」「反中華」といった言葉をことさら持ち出すこともないのではないか、と思いました。
いうまでもなく、本作には日本軍や日本人警察官が登場し(注11)、かなり蔑んだ態度をセデック族の人々に対してとったりしますが、原住民の領域に乗り込んでくる外国人部隊がどこでもとった態度の範囲を出ていないように見受けられます。
他方で、モーナ―が決起を決断するに際しては、森の奥にある滝の前で、日本軍討伐隊との戦いで死んだはずの父親の姿を見、父が「お前はセデック・バレ(真の人)だ」と言うのを聞き、最後に一緒に歌を歌う様子が描かれます(注12)。
また、実際には、日本軍戦死者は22人とごくわずかだったにもかかわらず、本作では、モーナたちに機関銃をいくつか奪われたりして、相当の数の日本兵が殺されます。
こんなところからも、本作は、虐げられてきた民族が武器をとって反逆の狼煙を上げながらも結局は打ち負かされてしまうというファンタジックな歴史ロマンの一作ではないかと思えたところです(注13)。
(注1)台湾映画はあまり見ておりませんが、本作を制作した魏監督の『海角七号/君想う、国境の南』とか、さらに『モンガに散る』を見ています。
また、台湾を舞台とする映画としては、邦画『トロッコ』が印象的でした。なお、同作に登場するのと似たトロッコが、本作では、日本軍の兵員や武器の輸送に使われています!
(注2)例えば、本作でもちらっと映し出されますが、「蕃童教育所」における日本語教育。「お父さん」「お母さん」などを黒板に大書して、原住民児童に繰り返し言わせています。
『日本語教育と近代日本』(多仁安代著、岩田書院)によれば、台湾原住民に対する「日本語教育は、本島人(漢族系台湾人)より成果が上がっていたというのが定説になっている」ようです(同書P.104)。
なお、同書によれば、「蕃童教育所」は警察が所管するもので、「警察官が執務のかたわら日本語や礼法を教えたのが始まりらしい」とのこと(「修業年限は4年で、教科目は修身・国語・算術・図書・唱歌・体操など」)。 また、台湾人に対する日本語教育の機関としては、もう一つ総督府学務部所管の「国語伝習所」があったようです。
(注3)各地に設けられた警察組織の中にも、セデック族を取り込んでいたりします。映画では二人描かれますが(花岡一郎と花岡二郎:ただし、兄弟ではありません)、花岡一郎は師範学校を卒業しています。二人とも、日本の取締当局と反乱を起こしたセデック族との間に立たされて悩み、結局は自決してしまいます。
なお、上記「注2」にあるように、彼らは「蕃童教育所」で教鞭もとっています。
また、花岡二郎の妻の役には、母親が台湾原住民のビビアン・スーが扮しています。
(注3)映画で描かれているのは、例えば、森林伐採に携わる原住民に支払われる賃金の低さ。
(注4)セデック族は10以上の(社)に別れていて、霧社事件で決起したのは6社。モーナは、そのうちのマヘボ社の頭目。
(注5)劇場用パンフレットに掲載の「STORY」には、セデック族の信じていることとして、「先祖から受け継いだ狩り場」において「鍛錬をし、顔に刺青を入れることによって真のセデック族になってこそ、死後は祖先のいる虹の橋を渡ることができる」とあります。
(注6)幻想的なシーンを取り入れたり、歌と踊りの場面が挿入されたり、ある程度の変化は付けられているのですが。
(注7)2時間半に短縮されたインターナショナル版の方がクマネズミには良かったのかもしれません。
(注8)尤も、タイトルと評論の中身(「戦争という人間の愚行」との得ているに過ぎません)とがズレている感じですが。
(注9)「映画「セデック・バレ」を製作した目的は?」との質問に対して、魏監督は、「歴史を語ることで恨みを解きたいと考えた。歴史とは本来、非常に難解で、遺憾なことも多い。映画を通じて歴史を理解し、その時代の見方に立って、当時の人々の環境や立場を考えてほしいと思う。理解して初めて和解がある。霧社事件では、先住民族と日本人が文化と信仰の違いから誤解が生まれ、衝突した。衝突の原点に戻らなければ原因は分からない。「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった。物事は善悪だけでは判断できない。日本側も先住民族側も完璧であるはずがなく、複雑な要素が絡み合う。「日本を好きか嫌いか」という簡単な質問では答えられない複雑な気持ちを分かってほしい」などと答えています〔2011年10月20日(木)付『毎日新聞』掲載―このサイトの記事に再録されています〕。
(注10)また、このサイトの記事でも、次のように述べられています。
「中国大陸でよくある“愛国的”な視点では、決してない。もちろん、過去の日本の所業を無批判に受け入れているのでもない。セデック族の生活と昔ながらの考え方を、まずは「人としての誇りの問題」としてとらえているが、「現代社会では、とても受け入れられない伝統」ということも、よく分かる。歴史の流れの過程で発生した悲劇を、数々な残虐な出来事を含めて冷徹な視点で描写した作品だ」。
(注11)日本人の警察官役として安藤政信や木村祐一が、日本側の最高司令官として河原さぶが出演しています。

また、『海角七号』似出演していた田中千絵が、安藤政信扮する日本人警察官の妻の役で出演しています。
(注12)歌い終わると、モーナの父親は、滝壺の中に消えていきます。
(注13)それでも、立ち上がったセデック族の若者が、戦いの不利を悟って次々と自死する様には(その妻たちも、足手まといにならないようにと自死します)、かなり違和感を覚えました(生きて戦うことよりも死んで先祖の列に加わることの方に意義を感じているようなのです)。
尤も、日本側の最高司令官も、本作のラストの方で、セデック族の戦い方について「我々が百年前に失った武士道の精神を見たのか?」と訝しがるくらいですから、その時よりさらに80年以上も経過してしまった現在、分かろうとしても無理なのかもしれません。
★★★☆☆
象のロケット:セデック・バレ第一部、第二部
(1)本作は、台湾で大ヒットしている作品であり、それも戦前の台湾を扱ったものと聞いて、あるいは以前見て大変感動した台湾映画『非情城市』(1989年)のような雰囲気を持っているのかなと期待して、映画館に出かけました(注1)。
舞台は、昭和初期の台湾の山岳地帯の一つの地区。
1895年(明治28年)の下関条約によって統治することとなった日本は、台湾原住民(戦前は「高砂族」といわれていました)の抵抗を排除して、急速に台湾での支配を確立していきます。
ただ、昭和初期になると、それまでの統治実績に自信があったのでしょうか(注2)、日本側は、自分たちを防護することにそれほど重きを置いていないように見受けられます(注3)。
他方、原住民の方では、貧困などから日本に対する恨みがかなり積み重なっていました(注3)。
きっかけは、日本人警察官と原住民の若者との乱闘騒ぎ。それを引き金として、原住民による反乱が勃発します。

具体的に本作で取り上げられるのは、満州事変の前年に当たる1930年10月に起きた霧社事件。
台湾原住民の一つであるセデック族のおよそ300人が、頭目(注4)の一人モーナに率いられて立ち上がり、日本人の警察官のいる駐在所を襲撃したあと、運動会のために学校の校庭に集まっていた日本人約140名を虐殺したのです。

映画の第1部「太陽旗」では、1895年に日本が統治するために乗り込んできたときから決起の日までが描かれ、第2部「虹の橋」では、彼らが3,000名近くに増強された日本の警察と軍隊によって鎮圧されるまでが描かれます。
本作を見ると、遠くは、アメリカにおけるインディアンと騎兵隊の戦いなどに連想がいきますし、近くは、この間のアルジェリア人質事件など様々な事件が思い起こされるところです。
でも、そんな現実的な面よりも、モーナ達決起したセデック人が守ろうとしたのがあくまでも自分たちの「狩り場」であり、勇者として死んで「虹の橋」を渡って祖先の仲間に入ろうとセデックの人たちが望んだという点に(注5)、クマネズミは歴史ロマンを感じました。
とはいえ、何しろ2部作の合計で4時間半以上かかる長尺で、いろいろ興味を惹くものが画面に登場してこないと相当の忍耐が必要になるわけながら、とどのつまりは日本による台湾統治期に起きた原住民による反乱を描くだけですから(注6)、全体として酷く単調な感じになってしまいます(注7)。
(2)勿論、本作に、日本による戦前の植民地政策の問題点を感じる見方もあるでしょう。
例えば、映画評論家の山根貞男氏は、4月19日付朝日新聞に掲載された「原住民の目に映る愚行」と題する映画評において、次のように述べています。
「アジアの映画人が結集した大作といえよう。その映画的な力のもと、画面には、大自然の豊かさ、原住民のおおらかさ、彼らの文化の素晴らしさが充満するが、それだけに、戦いの残酷さは際立つ。ことに後半、山岳地帯を走り回って勇壮に戦う原住民が、大砲はおろか空爆や毒ガスまで用いた日本軍に追い詰められ、女性たちが集団自決に至るくだりは、戦争という人間の愚行を生々しく描」いている。
「それにしても、我々日本人には痛い映画である。アクション映画の面白さを満喫するからこそ、そう感じる。後半、日本の巡査になり日本名を名乗る若い原住民2人が、戦う両方の側に引き裂かれて苦悩する。その姿は我々に通じるといえば、いい気なものだとセデック族の戦士に罵倒されようか。現代史に根ざしたそんな活劇である」。
「原住民の目に映る愚行」というタイトルとか(注8)、「我々日本人には痛い映画である」や、「セデック族の戦士に罵倒されよう」といった文章からは、戦前の日本統治に対する山根氏の強い反省の念がうかがえるところです。
しかしながら、本作で描かれる霧社事件は、既に80年以上も昔の出来事です。歴史的な事実として、もっと客観的に見た方がいいのではないかな、と思われます。
さらに、この映画を制作した魏(ウェイ・ダーション)監督も、「「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった」などと述べているように、特定のイデオロギーに立って映画を撮ったわけではないように考えられます(注9)。
そこで、この点についてクマネズミは、次のフリー・ジャーナリストの福島香織氏の見解に、まだしも同感します(注10)。
同氏は、『日経ビジネス』オンラインの2011年10月5日の記事で、次のように述べています。
「自分の目で前後編を見た上で言えば「セデック・バレ」は抗日事件を題材にしながらも反日映画ではなかったと思う。誤解を恐れずに言えば、むしろ親日映画かもしれない。さらに言えば、ひょっとすると反中華映画かもしれない」。
「映画の最初の「霧社事件を改変している」と字幕で説明しているように、歴史の真実を訴える映画でも、歴史を解説する映画ではないだろう。また、戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画でもなさそうだ」(注)。
「この映画が親日映画ではないか、と感じるのは、原住民の抗日事件を描きながら、靖国神社や武士道に象徴される日本人の感性を台湾人が理解していることをそこはかとなく表現しているからだ」。
要すれば、本作は抗日事件を題材にしながらも戦争の非人道性や日本統治時代の過ちの批判をメーンテーマにした映画ではない、ということでしょう。
クマネズミもそう思いましたが、でもさらに言えば、福島氏のように、「抗日」「反日」「親日」「反中華」といった言葉をことさら持ち出すこともないのではないか、と思いました。
いうまでもなく、本作には日本軍や日本人警察官が登場し(注11)、かなり蔑んだ態度をセデック族の人々に対してとったりしますが、原住民の領域に乗り込んでくる外国人部隊がどこでもとった態度の範囲を出ていないように見受けられます。
他方で、モーナ―が決起を決断するに際しては、森の奥にある滝の前で、日本軍討伐隊との戦いで死んだはずの父親の姿を見、父が「お前はセデック・バレ(真の人)だ」と言うのを聞き、最後に一緒に歌を歌う様子が描かれます(注12)。
また、実際には、日本軍戦死者は22人とごくわずかだったにもかかわらず、本作では、モーナたちに機関銃をいくつか奪われたりして、相当の数の日本兵が殺されます。
こんなところからも、本作は、虐げられてきた民族が武器をとって反逆の狼煙を上げながらも結局は打ち負かされてしまうというファンタジックな歴史ロマンの一作ではないかと思えたところです(注13)。
(注1)台湾映画はあまり見ておりませんが、本作を制作した魏監督の『海角七号/君想う、国境の南』とか、さらに『モンガに散る』を見ています。
また、台湾を舞台とする映画としては、邦画『トロッコ』が印象的でした。なお、同作に登場するのと似たトロッコが、本作では、日本軍の兵員や武器の輸送に使われています!
(注2)例えば、本作でもちらっと映し出されますが、「蕃童教育所」における日本語教育。「お父さん」「お母さん」などを黒板に大書して、原住民児童に繰り返し言わせています。
『日本語教育と近代日本』(多仁安代著、岩田書院)によれば、台湾原住民に対する「日本語教育は、本島人(漢族系台湾人)より成果が上がっていたというのが定説になっている」ようです(同書P.104)。
なお、同書によれば、「蕃童教育所」は警察が所管するもので、「警察官が執務のかたわら日本語や礼法を教えたのが始まりらしい」とのこと(「修業年限は4年で、教科目は修身・国語・算術・図書・唱歌・体操など」)。 また、台湾人に対する日本語教育の機関としては、もう一つ総督府学務部所管の「国語伝習所」があったようです。
(注3)各地に設けられた警察組織の中にも、セデック族を取り込んでいたりします。映画では二人描かれますが(花岡一郎と花岡二郎:ただし、兄弟ではありません)、花岡一郎は師範学校を卒業しています。二人とも、日本の取締当局と反乱を起こしたセデック族との間に立たされて悩み、結局は自決してしまいます。
なお、上記「注2」にあるように、彼らは「蕃童教育所」で教鞭もとっています。
また、花岡二郎の妻の役には、母親が台湾原住民のビビアン・スーが扮しています。
(注3)映画で描かれているのは、例えば、森林伐採に携わる原住民に支払われる賃金の低さ。
(注4)セデック族は10以上の(社)に別れていて、霧社事件で決起したのは6社。モーナは、そのうちのマヘボ社の頭目。
(注5)劇場用パンフレットに掲載の「STORY」には、セデック族の信じていることとして、「先祖から受け継いだ狩り場」において「鍛錬をし、顔に刺青を入れることによって真のセデック族になってこそ、死後は祖先のいる虹の橋を渡ることができる」とあります。
(注6)幻想的なシーンを取り入れたり、歌と踊りの場面が挿入されたり、ある程度の変化は付けられているのですが。
(注7)2時間半に短縮されたインターナショナル版の方がクマネズミには良かったのかもしれません。
(注8)尤も、タイトルと評論の中身(「戦争という人間の愚行」との得ているに過ぎません)とがズレている感じですが。
(注9)「映画「セデック・バレ」を製作した目的は?」との質問に対して、魏監督は、「歴史を語ることで恨みを解きたいと考えた。歴史とは本来、非常に難解で、遺憾なことも多い。映画を通じて歴史を理解し、その時代の見方に立って、当時の人々の環境や立場を考えてほしいと思う。理解して初めて和解がある。霧社事件では、先住民族と日本人が文化と信仰の違いから誤解が生まれ、衝突した。衝突の原点に戻らなければ原因は分からない。「これは時代が作り出した過ちだ」と言えるようにしたかった。物事は善悪だけでは判断できない。日本側も先住民族側も完璧であるはずがなく、複雑な要素が絡み合う。「日本を好きか嫌いか」という簡単な質問では答えられない複雑な気持ちを分かってほしい」などと答えています〔2011年10月20日(木)付『毎日新聞』掲載―このサイトの記事に再録されています〕。
(注10)また、このサイトの記事でも、次のように述べられています。
「中国大陸でよくある“愛国的”な視点では、決してない。もちろん、過去の日本の所業を無批判に受け入れているのでもない。セデック族の生活と昔ながらの考え方を、まずは「人としての誇りの問題」としてとらえているが、「現代社会では、とても受け入れられない伝統」ということも、よく分かる。歴史の流れの過程で発生した悲劇を、数々な残虐な出来事を含めて冷徹な視点で描写した作品だ」。
(注11)日本人の警察官役として安藤政信や木村祐一が、日本側の最高司令官として河原さぶが出演しています。

また、『海角七号』似出演していた田中千絵が、安藤政信扮する日本人警察官の妻の役で出演しています。
(注12)歌い終わると、モーナの父親は、滝壺の中に消えていきます。
(注13)それでも、立ち上がったセデック族の若者が、戦いの不利を悟って次々と自死する様には(その妻たちも、足手まといにならないようにと自死します)、かなり違和感を覚えました(生きて戦うことよりも死んで先祖の列に加わることの方に意義を感じているようなのです)。
尤も、日本側の最高司令官も、本作のラストの方で、セデック族の戦い方について「我々が百年前に失った武士道の精神を見たのか?」と訝しがるくらいですから、その時よりさらに80年以上も経過してしまった現在、分かろうとしても無理なのかもしれません。
★★★☆☆
象のロケット:セデック・バレ第一部、第二部