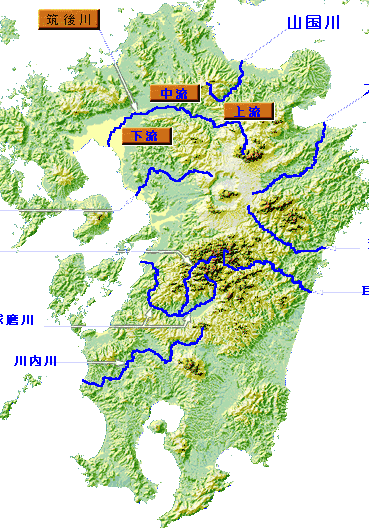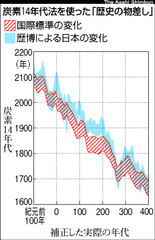せっかくシャネルの映画を見たのですから、少しはファッションについて勉強してみようと思い立ち、京都造形芸術大学准教授・成実弘至氏による『20世紀ファッションの文化史―時代をつくった10人』(2007.11)の第3章「ガブリエル・シャネル モダニズム、身体、機械」を開いてみました。
としたところ、驚いたことにまず次のように述べられています。
シャネルが「デザイナーとしてなにを達成したかを見きわめるのはそう簡単ではな」く、例えば「シャネルはパリモードにおいてはじめて成功した女性として語られることがあるが、これは事実ではな」いのであって、また「シャネルはスポーツウエアやテーラードスーツを女性ファッションに取り入れたとされるが、これも彼女の専売特許ではない」。
結局のところ、「ヴァレリー・スティールによると、シャネルのデザインは1920年代のほかのデザイナーとくらべて大きな相違はなかった」ようなのです。
ではシャネルのどこが凄かったのでしょうか?
著者は次のように述べています。
「なによりシャネルの偉大さは20世紀女性にふさわしい人生をみずから生き、ひとつの模範解答を示したことにある。…シャネル最大の作品はまず彼女自身であり、その存在が神話化したのもゆえなきことではなかった」。
「斬新なデザインは女性たちの憧れとなるカリスマがまとうことで流行となる。シャネルは現代を生きる若い女性であり、新しいファッションにふさわしい魅力的な容姿と個性的な雰囲気をもっていた。実は、これこそがほかの女性ドレスメーカーにはなく、彼女だけがもっていたものである」。
なるほど。映画「ココ・シャネル」を見た今では、本書で述べられている見解は十分に納得出来ます。
実際の具体的なデザインについてはどうでしょうか?
例えば、「小さな黒いドレス」について、「このスタイルにはモダニズムの精神が明確に表現されていた」として、「装飾を極限まで削ぎ落としたデザイン」と「身体を機械としてとらえるような発想」というポイントを挙げます。
そして、著者は、同時代のル・コルビュジェの建築美学との関連性について、「コルビュジェが「住むための機械」としての住宅を提唱したとするなら、シャネルのドレスは「着るための機械」というイメージをアピールしたといえるだろう」とまで述べています。
こうした分析を踏まえて、著者は結論的に次のように述べます。
「シャネルはモダニズムの精神のもとに女性身体をひとつのスタイルに統合した。彼女の才能は独創的なものをつくりだすというより、時代の息吹を感じ文化のさまざまな要素を自在に編集することで、新たな価値観を生みだすことにあった」。
なお、本書は、昨年1月13日の朝日新聞書評で取り上げられました。
冒頭で、評者の建築史家・橋爪紳也は、「著者は、これまでの服飾文化史に挑戦状を叩き付ける。ポワレ、シャネル、ディオール、ヴィヴィアン・ウエストウッド、川久保玲(コム・デ・ギャルソン)など著名な10人のファッションデザイナーの足跡を紹介する。その視点と語り口が従来の人物評とは根本的に違うのだ」と本書の特色を明らかにした後、末尾で、「教科書的な服飾様式史や、著名なデザイナーたちの単なる成功談の類に飽きた人に、まず本書を薦めたい。これほど生き生きとした服飾産業と近代の社会システムとをめぐる物語は、これまで読んだことがない」と大変な賛辞を送っています。
としたところ、驚いたことにまず次のように述べられています。
シャネルが「デザイナーとしてなにを達成したかを見きわめるのはそう簡単ではな」く、例えば「シャネルはパリモードにおいてはじめて成功した女性として語られることがあるが、これは事実ではな」いのであって、また「シャネルはスポーツウエアやテーラードスーツを女性ファッションに取り入れたとされるが、これも彼女の専売特許ではない」。
結局のところ、「ヴァレリー・スティールによると、シャネルのデザインは1920年代のほかのデザイナーとくらべて大きな相違はなかった」ようなのです。
ではシャネルのどこが凄かったのでしょうか?
著者は次のように述べています。
「なによりシャネルの偉大さは20世紀女性にふさわしい人生をみずから生き、ひとつの模範解答を示したことにある。…シャネル最大の作品はまず彼女自身であり、その存在が神話化したのもゆえなきことではなかった」。
「斬新なデザインは女性たちの憧れとなるカリスマがまとうことで流行となる。シャネルは現代を生きる若い女性であり、新しいファッションにふさわしい魅力的な容姿と個性的な雰囲気をもっていた。実は、これこそがほかの女性ドレスメーカーにはなく、彼女だけがもっていたものである」。
なるほど。映画「ココ・シャネル」を見た今では、本書で述べられている見解は十分に納得出来ます。
実際の具体的なデザインについてはどうでしょうか?
例えば、「小さな黒いドレス」について、「このスタイルにはモダニズムの精神が明確に表現されていた」として、「装飾を極限まで削ぎ落としたデザイン」と「身体を機械としてとらえるような発想」というポイントを挙げます。
そして、著者は、同時代のル・コルビュジェの建築美学との関連性について、「コルビュジェが「住むための機械」としての住宅を提唱したとするなら、シャネルのドレスは「着るための機械」というイメージをアピールしたといえるだろう」とまで述べています。
こうした分析を踏まえて、著者は結論的に次のように述べます。
「シャネルはモダニズムの精神のもとに女性身体をひとつのスタイルに統合した。彼女の才能は独創的なものをつくりだすというより、時代の息吹を感じ文化のさまざまな要素を自在に編集することで、新たな価値観を生みだすことにあった」。
なお、本書は、昨年1月13日の朝日新聞書評で取り上げられました。
冒頭で、評者の建築史家・橋爪紳也は、「著者は、これまでの服飾文化史に挑戦状を叩き付ける。ポワレ、シャネル、ディオール、ヴィヴィアン・ウエストウッド、川久保玲(コム・デ・ギャルソン)など著名な10人のファッションデザイナーの足跡を紹介する。その視点と語り口が従来の人物評とは根本的に違うのだ」と本書の特色を明らかにした後、末尾で、「教科書的な服飾様式史や、著名なデザイナーたちの単なる成功談の類に飽きた人に、まず本書を薦めたい。これほど生き生きとした服飾産業と近代の社会システムとをめぐる物語は、これまで読んだことがない」と大変な賛辞を送っています。