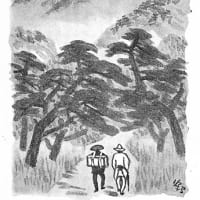日本近代文学の森へ (25) 岩野泡鳴『泡鳴五部作(2)毒薬を飲む女』その1

2018.6.28
女房の千代子が怒鳴り込んできて修羅場となったので、義雄はお鳥を、大工の家の二階に移し、自分もそこへ通っていくようになったのだが、千代子は、陰陽術に凝って、お鳥を呪ったり、占いで新しい居場所を突き止めようとしたりしている。その占いが、どうもあたっている節がある、てなところから『毒藥を飮む女』は始まる。初出では、この冒頭のあたりは、『発展』の最後の部分だったらしいから、話は地続きである。
「おい、あの婆アさんが靈感を得て來たやうだぜ。」
「れいかんツて──?」
「云つて見りやア、まア、神さまのお告げを感づく力、さ。」
「そんな阿呆らしいことツて、ない。」
「けれど、ね、さうでも云はなけりやア、お前達のやうな者にやア分らない。──どうせ、神なんて、耶蘇教で云ふやうな存在としてはあるものぢやアない。從つて、神のお告げなどもないのだから、さう云つたところで、人間がその奧ぶかいところに持つてる一種の不思議な力だ。」
「そんなものがあるものか?」
「ないとも限らない──ぢやア、ね、お前は原田の家族にでもここにゐることをしやべつたのか?」
「あたい、しやべりやせん──云うてもえいおもたけれど、自分のうちへ知れたら困るとおもつて。」
「でも、あいつは、もう、知つてるぞ、森のある近所と云ふだけのことは。」
「森なら、どこにでもある。」
「さうだ、ねえ」と受けて、義雄はそれ以上の心配はお鳥に語らなかつた。無論、千代子が或形式を以つて實際お鳥を呪ひ殺さうとしてゐるらしいことも、お鳥には知らしてない。たださへ神經家であるのに、その上神經を惱ましめると、面倒が殖えるばかりだと思つてゐるからだ。
が、お鳥も段々薄氣味が惡くなつたと見え、日の經つに從つて、義雄の話を忘れるどころかありありと思ひ出すやうになつたかして、つひにはまた引ツ越しをしようと云ひ出した。もし知られると、今までにでも、云はないでいい人にまで目かけだとか、恩知らずだとか、呪ひ殺してやるだとか云つてゐるあいつのことだから、わざと近所隣りへいろんな面倒臭いことをしやべり立てるだらうからと云ふのである。
然し、この頃お鳥はおもいかぜを引いてとこに這入つてゐた。近所の醫者を呼んで毎日見て貰ふと、非常に神經のつよい婦人だから、並み以上の熱を持ち、それがまた並み以上に引き去らないのだと説明した。その上、牛込の病院に行けないので、一方の痛みも亦大變ぶり返して來た。
かの女は氣が氣でなくなつたと見え、獨りでもがいて、義雄にも聽えるやうに、
「何て因果な身になつたんだらう」と三疊の部屋で寢込みながら、忍び泣きに泣いた。おもての方の廣い、然し向う側の森から投げる蔭をかぶつた室──六疊──には、憲兵が三人で自炊する樣になつてゐた。
千代子は藁人形を作って、お鳥を呪い殺そうとしているらしい。恐ろしい。
お鳥は、重い風邪をひき、しかも淋病の痛みもぶり返す。義雄のほうも、甲府で痛めた耳の具合がよくなく、その上、持病の痔が悪化して痛くてたまらない。義雄は「病気の問屋」だ。
そんなとき、「龍土会」の忘年会があった。この「龍土会」というのは、「おもに自然主義派と云はれる文學者連を中心としての會合で、大抵毎月一囘晩餐の例會を開くことになつてゐる」と説明されているが、これは実在したもので、詳しくは以下のとおり。
明治時代の文学者の集会名。東京麻布竜土町(港区六本木七丁目)にあったフランス料理店竜土軒(現在は同区西麻布一丁目に移転)で会合をもつようになった明治三十七年(一九〇四)十一月以後この名が決まったが、会そのものは、三十年代前半に柳田国男が牛込加賀町の自宅に文学仲間を招いて文学談を楽しんだのがはじまり。柳田邸を離れて諸処の料亭を会場にするように発展したのは三十五年以後で、原則的には月例で、会員は特定しなかった。参会者は柳田国男・国木田独歩・田山花袋・島崎藤村・蒲原有明・岩野泡鳴・徳田秋声・正宗白鳥など自然主義系の作家が多かったが、小栗風葉・川上眉山なども参加し、ジャーナリスト・画家なども集まるようになり、次第に社交場化したので、初期の仲間は柳田国男を中心に四十年二月から別に研究会としてのイプセン会を派生させることになった。以後断続、大正二年(一九一三)三月二十一日柳橋の柳光亭で行われた島崎藤村渡仏送別会が事実上最後で、その後は復活の試みも成功せず、自然主義運動の母胎として終った。
(「国史大辞典」和田謹吾執筆)
引用はしないが、この「龍土会」の様子が、ここでは生き生きと描かれていて実に興味深い。
田島秋夢(徳田秋声)(注)、田邊独歩(国木田独歩)、花村(田山花袋)、藤庵(島崎藤村)などはすぐに分かるが、何度も出てくる「麹町の詩人」って誰なんだろうと思っていたら、「国史大辞典」で、ああ、蒲原有明かあと分かった。蒲原有明と「自然主義」の作家との交流は意外だった。文学史の授業だけじゃ、分からないことがいっぱいあるね。
「病気の問屋」だった泡鳴にしてみれば、健康に恵まれた田山花袋がよほど羨ましかったらしく、こんな記述がある。
そして、花村の耳も鼻も目も内臟も、どこもかも健全で、而も巖乘(がんじよう)な體格が何よりも羨ましくなつたと同時に、獨歩の死んだ時、茅ヶ崎へ集まつた席で、義雄は自分が花村に向つて、君は僕等すべての死んだあと始末をして、誰れよりもあとで死ぬ人だと云つたことを思ひ出した。
現に、独歩は明治41年に36歳で没し、泡鳴は大正9年に47歳で没しているが、花袋は昭和5年に58歳で没している。それでも長生きとはいえないけれど、泡鳴の「予言」も少しはあたっているわけだ。「少しは」というのは、蒲原有明は昭和27年に77歳で没し、島崎藤村は、昭和18年に71歳で没し、徳田秋声は昭和18年に71歳で没しているからだ。(ここを調べて書きながら、スゴイ発見をしたぞ。藤村と秋声は、生まれた年も、死んだ年もまったく同じだ!)また、そこにいたかどうかしらないが、正宗白鳥に至っては昭和37年に83歳で没している。しぶとい人だ。
人の生き死になんて、分からないものだ。同窓会で旧友と会うたびに、誰が最後まで残るかなあなんて話題になるが、そんなこと誰にもわかりはしない。先に逝こうが後に残ろうが、結局は、みんないなくなる。いなくなって、それっきりなのか、それとも、どこかで「再会」するのか、それも分からない。「再会」できればそれにこしたことはないけれど、果たして話題が持つかなあと思うと、めんどくさい気もするし、まあ、人生って、よく分からない。
(注)この記述は間違いでした。「田島秋夢」のモデルは、「正宗白鳥」です。(2018.6.29記)