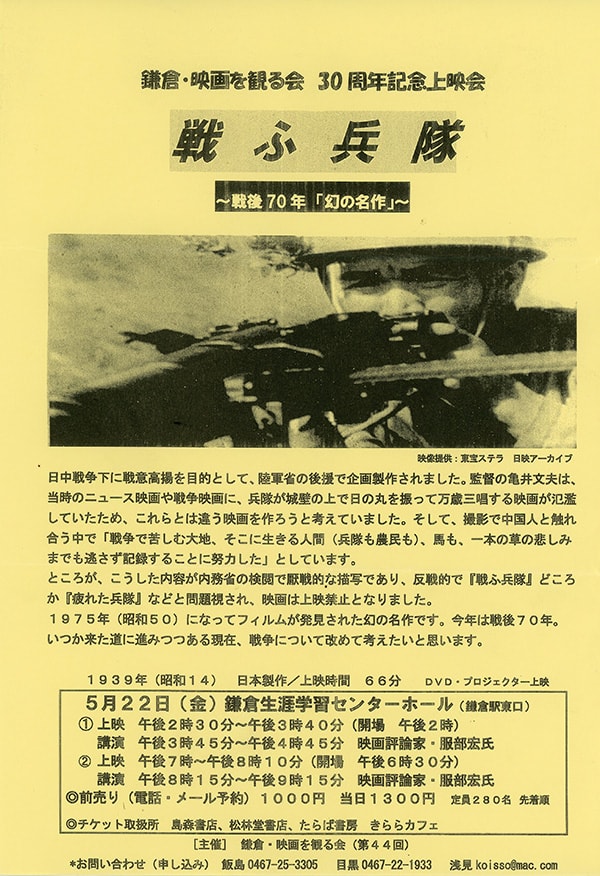祝優勝照ノ富士初々しさは宝である
画仙紙ハガキ
●
今日の、照ノ富士関の優勝を祝して。
そして、優勝インタビューを聞いて。

祝優勝照ノ富士初々しさは宝である
画仙紙ハガキ
●
今日の、照ノ富士関の優勝を祝して。
そして、優勝インタビューを聞いて。
【劇評】劇団キンダースペース「全俳優によるモノドラマ」──成熟した「モノドラマ」
2015.5.24
「モノドラマ」というのは、原田一樹が創始した演劇のひとつのジャンルである。このことについて、原田は、2004年、熊本県立劇場企画公演オンステージシアター「モノドラマ」の第二回目の公演を前にして、当時館長の故川本雄三氏と行った対談の中でこう語っている。(対談の中の発言をまとめてあります。)
実は、「モノドラマ」を作る5、6年前に初めて一人芝居というものを観たんです。一人芝居は一人の俳優が一つの役を演じることが中心で、見終わった後に、私は、演じるだけではなく、もっと「俳優が空間を創っていく」ような形はないかと考えました。(……)役を演じることが主眼ではなく、舞台には一人しかいないけれど、例えば椅子があったら、そこに、別の人物が座っているように見える、あるいは、何もない舞台が異なる部屋や外の空間になったり、というようなことですね。これは、とても俳優の力量が問われるのですけれど。(……)俳優は、演じて説明するのではなく、観客の想像力をかきたてる瞬間を創ることができるかどうか、ですね。演劇ならではの表現を求めて観客は劇場に足を運んでくれます。「何もないそこに何かが見える」という感覚を、舞台を通じて共有できるといいですね。(……)つまり、あるシーンで、その俳優が見つめている何もない空間の何もない一点を、観客も全員見ているというのが理想です。まあ、ほとんどの観客は、俳優を見てしまうものですが。ともかく、俳優一人が多数の人物を演じ、ひとつの文学世界を空間に創り上げる形の演劇を、一人芝居や朗読劇、リーディングとは別のものとしたいという思いから「モノドラマ」と名付けました。
つまり「モノドラマ」を定義すれば、「俳優一人が多数の人物を演じ、ひとつの文学世界を空間に創り上げる形の演劇」ということになる。その点で、「モノドラマ」は「講談」や「落語」に似ていると原田は言う。「上手い噺家は、瞬間の動きで一つの空気を作り出す。」そして「場のリアリティ」を創造するのだと言う。
「講談」や「落語」との相違は、俳優が一人という点では同じだが、俳優が舞台を自由に動きまわり、簡単な舞台装置、照明、音楽、効果音などが使われるという点が違うといえば分かりやすいだろう。(「落語」でも、かつては、簡単な舞台装置を使い、音曲なども加えて演じる形も行われましたが、今では、あまりみかけません。)
更に、川本氏の「『モノドラマ』では、日本の近代文学作品を取り上げていますね。」という質問に対してはこう答えている。
外国の作品も取り上げてみましたが、どうもしっくりこなかったのです。翻訳にもよると思いますが。モノドラマとして成立するものを求めた結果、近代というものと向き合った作家の作品がやっぱり腑に落ちる。なぜかと思うと、やはりこれらの作品は、時代の中で揺れている。俳優が演じてみると、そこに主人公の不安とか、葛藤といったものが空間に表われてくる。そこに魅力を感じます。
ここまでくれば、キンダースペースの「モノドラマ」が、いかなるものであるかの概要は理解できよう。
とはいえ、実際に見てみないことには、なかなかその感じはつかみにくい。ぼくが最初に「モノドラマ」を見たのは、2009年の「オダサク×ダザイ」あたりだったかと思うのだが(もっと前かもしれない)、正直、かなりとまどったのを覚えている。何人もの役を演じ分けるのは、落語でおなじみだが、いわば「地の文」のところを、セリフ(会話)と同じ立ち位置で語ったり、二人のセリフを落語のように「上下を切る」ことなく言うなど、新しい試みが、すっと入ってこなかったのだ。それならいっそ「朗読」でいいのではないか、と思ったような気もする。
けれども、それは、原田のいう「何もないそこに何かが見える」という想像力の働かせ方に、観客としてのぼくが慣れていなくて、「俳優をみてしまう」結果だったのだと、今なら思うわけである。もちろん、始めてまもない「モノドラマ」そのものの演出・演技の未成熟ということもあったのかもしれないが。
さて、あれから、およそ6年ほど経ち、それ以後の「モノドラマ」をたぶん欠かさず見てきて、今回の、「全俳優によるモノドラマ」6本を見たわけだが、その6本すべてが、完成度が高く、充実していて、それよりなにより、見ていて楽しくてならなかった。「モノドラマ」の手法が、脚本・演出・演技のすべてにわたって、成熟した感があった。それに観客としてのぼくの成熟もあったのかもしれない。
今回は、5月21日のBプログラム、太宰治『吉野山』(平野雄一郎)、宮本輝『火』(古木杏子)、直木三十五『相馬の仇討』(深町麻子)、そしてAプログラム、有島武郎『一房の葡萄』(小林もと果)、岡本綺堂『指輪一つ』(森下高志)、向田邦子『大根の月』(榊原奈緒子)の順番で見た。
どれをとっても、鮮やかに情景が目の前に広がり、原田のいう「ひとつの文学空間」が見事に舞台上に現出した。
『吉野山』は、寒さと飢えに震える出家のみじめさと心の葛藤を平野が好演。「ウソツキ!」と舞台正面にむかって小さく叫ぶ平野の演技には、観客からも思わず笑いが。平野は、太宰の世間に対する屈折した抗議をユーモアも交えて見事に演じた。坊主の周囲の意地悪い村人たちの表情までもが、生き生きと舞台に浮かぶさまは、まさに「モノドラマ」の真骨頂だ。
『火』は、非常に深みのあるドラマに仕上がっていた。古木の胸の奥にこまかい振動をおこすような低い声による語りに、人間の心に巣くうどうしようもない欲望や衝動が舞台のうえのあやしくうごめいた。暗く静かな舞台空間を直線的に断ち切る赤い照明にするどく光る古木の目も印象的。これも「モノドラマ」の魅力のひとつだ。
『相馬の仇討』は、講談の語り口と、歌舞伎のような切れのある体の動きに、深町の持ち前のシブサとヒョウキンさが加わり、エンタテイメントとしても十分に通用する独特の世界を作り出していた。葬式の立て札(?)のような登場人物を墨書した立て札を人物に見立てて、それを縦横に扱うという演出も今までにないアイデアで面白かったし、深町の柔軟な演技力にうなった。
『一房の葡萄』は、お恥ずかしい次第だが、この6本の中では、ただひとつ読んだことがある作品。(ほんとに読書量が足りない)おなじみの話だが、こうして「モノドラマ」になって、小林の落ち着いた成熟した語りに耳傾け、その姿に見入っていると、美しい紫色の葡萄が、真っ白い先生の手のうえに、ほんとうに「見えた」。そして、横浜の青い海も。有島武郎の透明な文学世界にしばし酔わせてもらった。
『指輪一つ』は、一種の怪談。関東大震災による東京の混乱、それを旅の途中で知る「私」の困惑。そして偶然の出会いが、信じられない結末へと導いていく展開を、森下は淡々と、しかも緊張感をもって、演じきった。「そんなことはありえない」はずの「奇跡」だが、そこに人間の罪と、救いの両方を見せてくれた。ここにも「みえないもの」が現出したのだ。
『大根の月』。向田邦子の穏やかな語り口が、そのまま榊原に乗り移ったような熱演。大根の月、それは、大根を薄く切ろうとして失敗し、昼の半月のようになったというエピソードによるのだが、「事件」へと向かうスリリングな展開に観客を引き込んでいく演技は見事。日常がはらむ恐ろしさと、そしてたぶん希望。胸しめつけられる思いで見た。
こうして、それぞれの舞台を思い返していると、傑出した演出と、熟練の演技とに今更ながら感嘆するばかりだが、それと同時に、それを可能にした数々の日本近代文学・現代文学(ふつう、「近代文学」は、明治から昭和の太平洋戦争までの文学、「現代文学」は、太平洋戦争以後の文学のことを指します。)の力も改めて思いしらされる。
原田がいうように、日本の近・現代文学は、「時代の中で揺れ」、「主人公」は「不安・葛藤」を抱え込んでいる。それらの作品がこのような形で舞台化されることで、かれらの「文学」が更新される。そのことの幸いをぼくらは噛みしめなくてはならないし、改めてキンダースペースに感謝しなければならない。


【映画評】「戦ふ兵隊」──言葉は無力だ
2015.5.24
ドキュメンタリー映画『戦ふ兵隊』を見た。「鎌倉・映画を観る会」が30周年記念上映会として、上映したものだ。会場の鎌倉生涯学習センターホールは、定員286人だが、満席。大半は高齢者だったのが、残念といえば残念だが、ぼくが行ったのは午後2時半の回だから仕方ないだろう。午後7時の回はどうだったのだろうか。こういう映画を高齢者が見るのと、若者が見るのとではまったく意味が違ってくると思うのだが。
そのチラシには、次のような解説がある。
日中戦争下に戦意高揚を目的として、陸軍省の後援で企画製作されました。監督の亀井文夫は、当時のニュース映画や戦争映画に、兵隊が城壁の上で日の丸を振って万歳三唱する映画が氾濫していたため、これらとは違う映画を作ろうと考えていました。そして、撮影で中国人と触れ合う中で「戦争で苦しむ大地、そこに生きる人間(兵隊も農民も)、馬も、一本の草の悲しみまでも逃さず記録することに努力した」としています。ところが、こうした内容が内務省の検閲で厭戦的な描写であり、反戦的で『戦ふ兵隊』どころか『疲れた兵隊』などと問題視され、映画は上映禁止となりました。1975 年(昭和50)になってフィルムが発見された幻の名作です。今年は戦後70 年。いつか来た道に進みつつある現在、戦争について改めて考えたいと思います。
上演時間は66分。DVD・プロジェクターによる上映である。当然鮮明な映像ではない。同時録音によるため、人のしゃべっている内容もよく聞き取れない。音楽も音質は悪い。それなのに、ぼくがまず驚いたのは、映像の「美しさ」だった。軍馬や戦車が走るシーンでは、ジョン・フォードの『駅馬車』を思い出したし、ロバが映し出されると、ロベール・ブレッソンの『バルタザールどこへ行く』を思い出した。家を焼かれた中国人のオジイサンの顔が画面いっぱいにアップになると、なぜか『戦艦ポチョムキン』が頭に浮かんだ。前線司令部の一室の隅に固定されたカメラが、延々と隊長(?)と部下のやりとりをワンカットで写し続けるシーンでは小津映画を、そして侯孝賢(ホウ・シャオシェン)を思い出した。
この映画には、ありとあらゆる映画を喚起させる何か、があった。そう思ったのは、映画が持つ力だったのだろうか、それともぼくの勝手な想像だったのだろうか。
いずれにしても、この映画が、あらゆる映像的なテクニックを駆使して、万感の思いを込めた映画だということは確かなことだ。
ドキュメンタリー映画は、現実を写すわけだが、もちろん、現実のどこをどう写すかによって、まるでちがった「現実」がそこに現れる。
たとえば、軍隊の行軍。カメラは、ただ隊列を組んでひたすら中国の奥地へと歩く兵隊を写す。そして、そこにザクザクザクと重く響く軍靴の音。このとき、またもや、ぼくの頭の中には想像の世界がひろがって、あの萩原朔太郎の詩『軍隊』の、「ざつく、ざつく、ざつく、ざつく」がなりひびいた。そうだ、ぼくは、朔太郎のこの詩で、軍靴の音を聞いたけど、実際の音としては、聞いたことがなかったのだ。神宮外苑の学徒動員の映像は何度も目にしているが、こんなに生々しい軍靴の音は、初めて耳にした。朔太郎は、詩の中でこんなふうに軍隊の行進を描く。
お この重壓する
おほきなまつ黒の集團
浪の押しかへしてくるやうに
重油の濁つた流れの中を
熱した銃身の列が通る
無數の疲れた顏が通る。
ざつく、ざつく、ざつく、ざつく
お一、二、お一、二。
暗澹とした空の下を
重たい鋼鐵の機械が通る
無數の擴大した瞳孔ひとみが通る
それらの瞳孔ひとみは熱にひらいて
黄色い風景の恐怖のかげに
空しく力なく彷徨する。
疲勞し
困憊し
幻惑する。
お一、二、お一、二
歩調取れえ!
「反戦詩人」でもない、むしろ晩年は「日本浪漫派」に属した(だからといって、そのことが即好戦的だったことを意味するわけでもないだろうが)朔太郎だが、日本の街中を更新する軍隊を見て、すでに、この中国の大地を進む軍隊の「疲労困憊」を見ていたのだ。なんという想像力だろう。まるで、この朔太郎の「言葉」は、「戦ふ兵隊」のナレーションのようではないか。
この映画には、ナレーションはない。あるのは、ときどき現れる字幕である。字幕といっても、映像の下に出るアレではなく、無声映画の、あの画面一杯に文字だけ写される「字幕」(専門的には何と言うのだろうか)である。(この字幕の書き文字のおもしろさも印象に残った。)
映画の最後の方に、破壊された漢口の街の建物の入り口階段で「休息」する兵隊の姿を写す前に、字幕は、「兵士はこの偉業を成し遂げたことに大きな安らぎを感じているのです」といったようなことを語る。字幕の「言葉」をきちんと覚えてはいないが、どの字幕も、兵士の勇気をたたえ、この天皇陛下のために行われている戦争の素晴らしさを語る。けれども、その「言葉」を、「映像」がそして「音」が、片っ端から見事に裏切っていく。銀行の入り口の階段に腰を下ろし、横たわる兵士の姿からは、「天皇のために戦い、そして成し遂げた」ことへの満足感などまったく伝わってこない。そこにあるのは、ただただ虚脱感と疲労困憊である。
当日配られたパンフレットには、野田真吉のこんな批評が掲載されていた。
「戦ふ兵隊」のなかで私がもっとも心をうたれたシーンは長い苦難にみちた進軍のすえ、多数の戦死者をだしながら、やっと漢口に辿りついた兵隊たちが街の中心地にある塩業銀行の石の階段や前の広場に、疲れ果てた身体を、抱きかかえている銃身にささえられ、腰おいて休息しているシーンである。彼らは群がりよるハエを払う気力さえもない。銀行前広場の一角には軍楽隊が士気を鼓舞するかのようにスッペの「軽騎兵」の曲を奏楽している。生き残った兵隊たちはただひと時の眠りしか求めていないようである。彼等は眼を閉じたまま。身動き一つしない。ハエが胡麻をふりかけたように兵隊たちの疲れた服にまといついている。疲れきった兵隊たちの顔をはいまわっている。呼吸をしているのさえわからない石像のような兵隊たち。私はこの「戦ふ兵隊」のラストシーンほど、深い人間的感動を表現した戦争映画のシーンをいまだしらない。(野田真吉「日本ドキュメンタリー映画全史」現代教養文庫)
この銀行の前のシーンがラストシーンとはなっていないが、野田は、実に細かく書いてくれている。
映像が、そして音が、すべてを語っている。その中で、「言葉」は、どんなに「きれい事」を連ねても、まったく無力である。その無力を知ったとき、時の政府は、この映画を「上映禁止」としたのだ。その「敏感さ」を讃えてもいいくらいなものだ。もちろん「敏感さ」といってもたいしたものじゃない。誰だって分かるテイのものなのだが。
言葉は無力である。言葉は裏切るものである。かのハムレットも「言葉、言葉、言葉」と言っていたではないか。それがどういう文脈だったか忘れたが、「言葉はすばらしい」という意味ではなかったはずだ。「言葉なら何とでも言える」というのも、言葉への不信を表明する「言葉」だ。
けれども、「われわれはただ言葉だけによって、人間なのだし、またつながっているのである。」(モンテーニュ)ということも事実なのだ。とすれば、誰が間違っているかは明白だろう。そういう嘘っぱちの字幕を入れなければこの映画を作ることすらできなかった状況、そしてそこまでしても結局は上映禁止に追い込まれてしまった状況、そういう状況を作り出した人間、彼らが間違っていたのだなどということは今更言うまでもないことだ。
それでも、それほどまでに絶望的な戦時下の状況にあって、これだけ誠実な映画を作ろうとした人たちがいたことは何という救いだろうか。ひるがえって現今の日本の状況は、ひょっとしたら、この時よりも悪いのではないかとさえ思われる。言葉はどこまでも軽くなり、現実を裏切り、捏造し、隠蔽しつづけている。映像が裏切ろうとするほどの手ごたえもない「軽い言葉」。こういう世の中にあって、言葉を使って表現をする人間は、どうしたらいいのだろうか。ほんとうの言語表現は、まずは絶望するところからしか生まれてこないような気がしている。絶望して、言葉もない、というところからしか、ほんとうの言葉は生まれないのかもしれない。その可能性を探る人たちを、いまのぼくは、探るしかない。できることなら、ぼく自身がそういう言葉を探らねばならないのだろうが、ぼくは、悲しいことに、あまりにも非力すぎる。