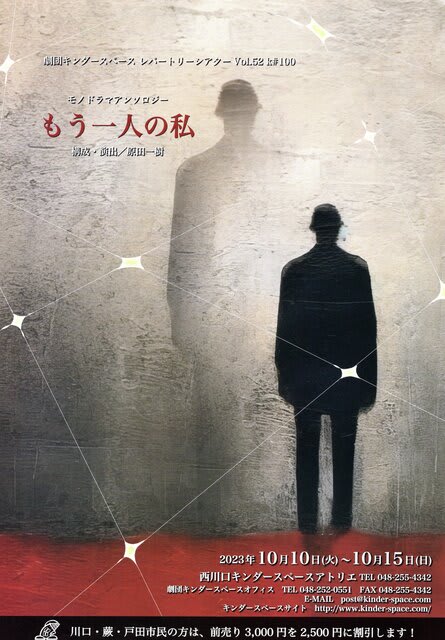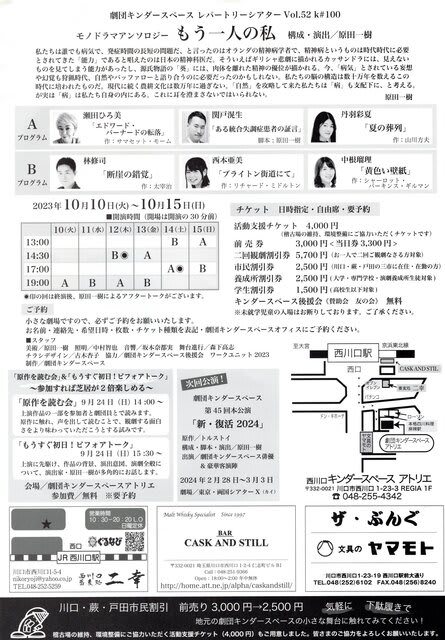木洩れ日抄 110 お財布忘れて

2024.9.24
やっと涼しくなったので、今日こそはと思って、鎌倉へ出かけた。カメラは何にするか、レンズはどれを使うかといろいろ考えたが、まだ早いとは思うけど、英勝寺のヒガンバナの様子でも見てこようかと思って、上大岡から地下鉄で戸塚まで、それからJRで鎌倉へ、といういつものコース。
ところが、地下鉄車内で、ふとカバンの中に財布が入っていないことに気づいた。ポケットを探ったら10円出てきたけど、現金が10円しかないとなると、英勝寺の拝観料が払えない。英勝寺は小さな尼寺で、入口に尼さんがいて拝観料を払うのだが。PayPayなど見た記憶がない。やっぱり現金のみだろう。ああ、どうしよう、尼さんに頼んで今度来たときには倍払いますから何とか入れてくださいと頼もうか、なんかOKしてくれそうな気もするけど、あまりにカッコ悪いしなあ、と、あれこれ考えた。
たぶん、円覚寺なら、受付も大きいから、PayPayとかSuicaとかが使えるかもしれないけど、北鎌倉となると、どうしたって、浄智寺には行きたい。しかし浄智寺の受付も、PayPayやっている雰囲気じゃないから、現金だけだろうなあ。ああ、どこかに500円玉でも落ちてないかなあなどと思っているうち、まあ、スマホで電車には乗れるから、とりあえず、江ノ電に乗って、海でも撮ろうと決めた。
江ノ電は、そんなに混雑してなかったので、稲村ヶ崎あたりまで行ってみようかと思ったけど、雲が多いので、海もイマイチな感じがして、そうだ、あんまり好きじゃないけど長谷寺なら、商業主義的で、自動チケット売り場もあるから、Suicaあたりで決済できるはずだと思って、久しぶりに長谷で降りた。さすがに、インバウンド人気で、人通りも多い。歩いているうちに、そうだ、長谷寺に行く前に、ぼくの好きな光則寺によっていこう。たしか、あそこは拝観料が無料だったはずだと思って、そっちに向かった。
しかし、光則寺は、受付はないけど、山門の下に賽銭箱のようなものが置いてあり、「入場料」(ってとこがおもしろいね。長谷寺に比べると商売っ気ゼロ。)100円を入れてくださいと張り紙があった。そうだった。何度も来ているのに忘れてた。でも、ここでは知人主催で、落語会もやったことあるし、住職とも多少面識がある。こんど来たとき、倍払おうということにして、入った。ここの庭は、雑然としているところがいい。英勝寺と似ている。
あちこち写真を撮っているうちに、そうだ、この寺には、元同僚(この方が、ここでの落語会を主催したのだ。)の息子さんのお墓があるんだった。お彼岸だし、お参りして行こうと思った。お寺の裏に広がる墓地は結構広く、息子さんのお墓は前にもお参りしたことがあるのに、探すのに苦労したけど、なんとかお参りをすますことができた。
お参りをおえて、庭においてある大きな石に座って、コンビニのおにぎり食べながら、しみじみと元同僚の息子さんを偲んだ。なくなったのは、15年も前。ずいぶんと時が経ったものだ。財布を忘れたのも、結局ここへ来るためだったのかもしれないと、ふと思った。
長谷寺は、Suicaで支払えたけど(400円)、やっぱり、おもしろくなかった。光則寺や英勝寺の趣がなく、観光の寺だ。観音像は立派だけど、境内にオシャレなレストランなんかいらない。
長谷寺を出るとき、江ノ電でも撮りながら帰ろうと思って、それまで使っていた50mmf1.2のレンズを外して、ズームレンズにかえようとしたら、ズームレンズの片方の(フィルターつける方じゃない方)の、レンズキャップが外れない。どんな力を入れても外れない。こんなことは初めてだったが、ま、しょうがない。もうメンドクサイから写真は今日はおしまいということにして、長谷駅に行ったら、ホームで、何人ものジイサンが一眼レフを構えて電車が入ってくるのを待っている。黄色い線は越えてないけど、なんか、身を乗り出した彼らの姿が、いい年してみっともなく感じて、江ノ電なんか、いいかげんにしておいたほうがいいなあと思いつつ、帰途についた。キャップが外れなかったのも、江ノ電なんかやめておけということだったのかもしれない。
ちなみに、外れないキャップをどうにかしてもらえないかと、帰りがけに、ヨドバシに寄ったら、売り場のオニイサンが、思い切り力を入れてもやっぱりはずれない。おかしいなあ、こんなの初めてですよ。これ以上力を入れると、レンズを壊してしまう可能性がありますから、修理に出されたほうがいいと思いますよというので、修理のカウンターに持っていったら(と書いたけど、実際には、修理に出すにもヨドバシのポイントカードがあったほうがいいから、忘れてきた財布をとりに家にもどってからまたヨドバシにいった。メンドクサイことである。)、そこのオニイサンもうんうんやっていたけど、ダメですね、じゃあ、修理に出しましょうといいながら、もう一度、ちょっとキャップに触ったら「あ、とれた!」っていうので、びっくりした。ぜんぜん力を入れてないのにみごとに外れた。そうか、力を入れすぎたから外れなかったのかと思ったけど、不思議なことである。
まあ、なんだかんだと、近頃は、何をやるにしても思い通りにはいかない。若いころの倍の手数がかかる。こうやっているうちにも、どんどんと年を取っていくのである。