
クリスマスプレゼントにもらった±0の懐中電灯torch。LEDランプの寿命は10万時間だから、およそ11年間光りつづける。(でも電池寿命は一日もたない23時間)
今日すずきせんせいに年内最後の修論エスキスの時間をとっていただいた。今まではエスキスと言いつつコンペの報告とか就活の報告とかがメインになってしまっていたので、修論の話だけをしたのは久しぶり、というより初めてかもしれない。
もともと僕は大学に入ったら建築史をやろうと思っていたはずなのに、いろんなめぐりあわせで予期していなかった建築生活を送ることになり(もちろんそのおかげで大変充実した大学生活だったが)、結果的に大学院では建築史研究室に入ったものの、自分は建築史院生らしくないことを求められているという思いもあり、「らしくないこと」を意識的にしてきたつもりだったけど、それが「こみやまくんは歴史をやるつもりがないらしい」と先生を嘆かせることとなり、僕のやってきたことを先生も面白がって認めてくれてるとは思うけれど、仮にも歴史系に所属した学生としては少し後悔もある。だから最後は歴史研らしく終わって恩返ししたいのだ。
----------------------------------------
title 19世紀英国の建築状況における「軽い建築」の受容過程について
0 建築の軽さを考えることについて 「君は自分の建物の重量を知っているかい」
1 「軽い建築」 軽快で、軽量で、(そして軽薄な?)
1-1 建築がふたたびモノへと回帰する
1-2 「羽ばたく飛行機」と「蛮王のための宮殿」
2 初期鉄骨造建築をめぐる19世紀英国の建築状況
2-1 技術者と建築家それぞれの職能組織
2-2 19世紀の建築思潮
2-3 イギリスの社会情勢と世界戦略
3 鉄と鉄骨造の歴史
3-1 <精錬法の変遷> 鋳鉄から錬鉄、そして鋼へ
3-2 <使用法の変遷> 補助材から構造材、そして表現材へ
3-3 <接合部の変遷> リベットから溶接、高力ボルトへ
3-4 <中心地の変遷> イギリスからアメリカへ
4 建築に鉄が導入されていった背景
4-1 鉄の導入を推進した人物たちの出自
4-2 梁断面の変遷にみる建築部材の軽量化および効率化
4-3 耐火性向上を意図した木骨組みから鉄骨組みへの架け替え
4-4 生産・加工・運搬・施工
(4-5 機械設備の導入との関係)
5 建築の軽快さ(または軽薄さ)について
5-1 鉄骨造建築をめぐる論説の整理とその技術史的考察
5-2 「重量法則」という視点
5-3 結果としての、非物質化とエフェメラリゼーションの萌芽
6 建築の技術と歴史 その直線的ではない進歩についての仮説
7 参考とした文献
----------------------------------------
ペヴスナーが近代建築運動の三つの源流として19世紀の鉄骨造建築・アールヌーヴォー・アーツアンドクラフトを挙げているのには、始めはなるほどと思ったけど、だんだん違和感をもつようになった。それぞれ対概念だったはずのものがドイツ工作連盟でひとつになるという歴史観には、どこか直線的なものを感じる。それぞれの共通項をくくりだして止揚しているからには、そこからこぼれ落ちた部分があるわけで、それが19世紀鉄骨造に関しては、材料や構法といったフィジカルな部分なのだと思う。むしろ現代はそうした側面、モノとしての建築という側面が重要視されているわけで、そこを拾い上げることがひいては、なぜハイテックはイギリスで誕生したのかということの説明にもなるのではないかと思う。直線上にのらない「クルドサック的技術」にもその時代なりのハイテク性はあったはずだ。だから僕の修論の裏テーマは、「建築の技術と歴史 その直線的ではない進歩について」。
この部分について先生に「そうなんだよ!」と共感してもらえたのでよかった。
エスキスの最後に先生は、「君がまとまった量の文章を書くのはこれが最後だろうから、君がこの先10年間拠って立てるような論文にしなさい。全部が同じ密度じゃなくてもいいから、今君が興味を持っている論点で、とにかくいっぱい書いておきなさい」と。「これが最後だろうから」という部分は寂しいし不本意だけれど、この先10年間僕の足元を照らせるようなものにはしたい。難波研→鈴木研(→松村研?)という変遷と、これから自分が進もうと思っている道を、照らしてくれるたいまつに。
















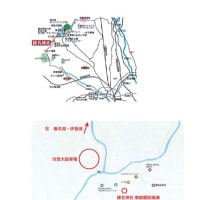
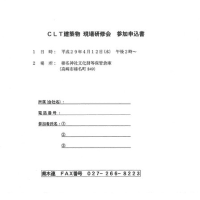
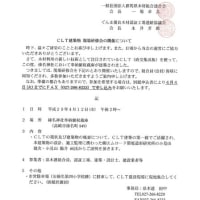







そこはかとなく卒論との連続性も匂わせております。副査、ぜひよろしくお願いいたします。がんばります。