雍正帝の兄弟らの行く末を確認しておこうと思ったら、
あまりにも人数が多く、えらい長丁場になってしまいました。。。。
最後は、康熙帝の江南女趣味ばかりを追いかける羽目にも・・・・。
それはともかくとして、
もう一度、まとめてみると、
康熙帝の皇子35人中、成人したのは20人。
その中で雍正帝の在位期間中、五人が幽閉されたまま。
さらに二人は獄中死した--。
しかも常にスパイを放ち、あちこちの動きをつかもうと
注意を怠らなかった・・・。
墓の中の康熙帝が、自分の子供たちのこのような状況を知ったら、どう思うだろうか・・・・。
とても顔向けできたものではない。
雍正帝自身もその状況を決して楽しんではおらず、
最も哀しんでいたのは、本人なのではないか、とさえ感じる。
--だから100里も離れた遥か彼方の地に自分の墓を作ると言い出したのだ、という説がある。
当初、候補に挙がっていた東陵の土地について、大臣らが
「九鳳朝陽山は、風水の条件に不備がある上、土壌に砂が多く、陵墓に適していない」
と上奏したのは、最初から皇帝の胸の内を察した臣下らが、気持ちを代弁するが如く上奏したのか。
そして雍正帝も「わが意を得たり」とばかりに採用したのか--。
それともほかに何か考えがあったのだろうか・・・。
陵墓を離れた場所に二つ設けることは、維持費の面で見ても、余計な経費がかかる。
それぞれに一つずつ陵墓の管理のための専門の行政機関をおき、常駐組織を置かねばならないのだから・・・。
国のすべてのことについて、無駄や矛盾をなくし、効率化を進めようとした雍正帝らしくないやり方ともいえる。

泰陵
雍正帝の命を受け、怡親王・允祥と大臣らが、その意向に沿って北京の西南方向で調査を進めた。
--怡親王・允祥といえば、第十三皇子。
雍正帝に最もかわいがられた弟。
雍正朝の勲功第一として、世襲親王である鉄帽子王に加えられ、
清朝九番目の鉄帽子王家となった人。
そんな風に弟の一人が、場所選定事業に関わっていたのですな。
しかし北京の周辺をめくら滅法に探し回れというのではなく、
「西南方向」と一応、方角は決められていたよう。
そうして最終的に決まった今の西陵のある易県には、
もう一つ、重要な要素がある。
--古来より重要な関所の一つだった紫荊関(しけいかん)の麓だということだ。
雍正帝の西陵の場所選びには、戦略上の大きな狙いがあったのではないか、と
いう説も最近は出ているという。

泰陵
排水システム
西陵は紫荊関の麓、山中から出てきてすぐの平野部に広がる。
北京は、北に燕山山脈が東西に横たわり、
西には、太行山脈が南北に連なって、山西との境となっている。
北から北京に抜けるため、燕山山脈の山中の最も重要な関所が「居庸関(八達嶺)」。
西側から北京に抜けようと思うと、太行山脈の山中の最も重要な関所が「紫荊関」である。
さらにその少し南側にあるのが、同じく太行山脈の山中の「倒馬関」。
この三関が、北京の「内三関」と呼ばれる。
このように紫荊関は古来より戦略の要所となっており、
ここが破られると、もう北京までは丸裸。
だだっ広い平野が続くので、北京まで馬で一気に駆け抜け、落とされてしまう。
紫荊関が破られれば、もう北京を破られるのも時間の問題となる。
北京界隈が燕と呼ばれた遥か昔より、戦いの勝敗を決める重要拠点となってきた。
「山西」、「山東」の「山」とは、太行山脈を指すが、
その山中には、古来より「古太行八径」と呼ばれる山中を抜ける八本の道があった。
紫荊関は、その七本目「蒲陰径」上にある。
紫荊関の重要性は、
「居庸関が破られても、北京が破られた例は十中三しかないが、
紫荊関が破られて、そのまま北京城まで破られた例は十中七。」
と言われるほどだという。
明末清初の著名な思想家・顧炎武は、『天下郡国利病書』の中で、
「居庸関は吾が背なり、紫荊関は吾が喉なり」
と言った。

下手な手書きの地図で恐縮。
自分なりに相関図をまとめてみた(笑)。
・・・・今、過去記事を見返していたら、
カテゴリー『河北・蔚県と暖泉』シリーズにも、相関地図があることを発見。
暖泉1・「蔚県800城」の一つ
そのほかにも、紫荊関を超えた西側にある宿場町・城塞都市として発展した
『河北・蔚県と暖泉』シリーズも合わせて読んでみてくださいー。
シリーズ第一話・蔚県1・宦官王振の故郷
この記事からずっと上に順番に遡って見てくださいー。
紫荊関は元々、春秋戦国時代の燕の時代から万里の頂上の一環として作られた関所である。
燕の下都の西北の守りの壁となった。
秦・漢代の名は「上谷関」、後漢では「五阮関」、
宋・金代は「金坡関」と呼ばれた。
元代以後は「紫荊関」の名で通る。
現存する紫荊関とその周辺の万里の長城は、
明代を通じて何度も補強・増強を繰り返された末の偉容である。
周辺の頂上の見張り台は330台、
紫荊関は「九門九関」、2000人近い兵士が城中していた。

泰陵
北京という都市は、もともと草原地帯と農耕地帯の境界線にあり、
農耕民族が騎馬民族から生活を守るための最前線の城塞として築かれ、発展してきた。
そのため戦火が絶えることはなく、古来より記録に残るだけでも
紫荊関で起こった戦役は140回ほどもある。
その中の代表的なものをいくつか挙げよう。
後漢の洪武帝時代・建武21年(西暦45年)、烏桓(うがん)と匈奴、鮮卑族の連合軍が侵入。
今では匈奴はモンゴル族の祖先、鮮卑もトルコ系といわれるが、
どうもこの頃は、モンゴル系もトルコ系も皆、顔はツングース、言語もアルタイ語で
あまり分化していなかったようなので、とりあえずは北方のアルタイ系の諸民族、っていうくくりでいい感じですな。
代郡(現在の山西省代県)から東の地域では、特に烏桓の被害がひどく、
「民がことごとく逃亡し、国境は人っ子一人みかけることもなし」
という悲惨な状況になったという。
名将・馬援(ばえん)が指揮を執り、紫荊関で烏桓の撃退に成功した。

泰陵
満州語、モンゴル語、漢字での表記が見える。
「世宗憲皇帝之陵」。
またもう少し後の時代には、次のような例もある。
金朝の大安元年(1209、南宋の嘉慶2年)、モンゴルのチンギス・ハーンは、居庸関を北から攻めたが、
金朝がこれを固く守り、破ることができなかった。
そこでモンゴル軍は、一部の兵力を割き、
西側から回り込んで、紫荊関を攻撃、金軍を破って
易州、啄(さんずい)州(たくしゅう、易州の東、三国志の桃園の契りで有名な地)の二州を占領、
そこから中都(今の北京)を攻め落とし、ついでに居庸関も挟み撃ちにして攻め落とした。
さらに返す刃で大軍を率いて紫荊関を西に出ると、山西の太原、代州も攻め落とした・・・・。
これで北京周辺を完全制圧したのである。
もう一つ、明代の有名な土木の戦役がある。
明の正統14年(1449)、オイラト・モンゴルのエセン・ハーンが
土木で明王朝の皇帝(英宗、正統帝)を捕虜にするという前代未聞の事件(土木の変)が起きた。
エセン・ハーンは勢いに乗り、そのまま人質の皇帝を連れて大軍を率いて南下、
万里の長城のすぐそばまで迫った。
しかし居庸関を攻めてみたものの、守りが固くてなかなか攻め落とせない。
そこで同じようにまた西側に回り込んで紫荊関を攻め、明側が敗れた。
オイラトの大軍は、そのまま駆けに駆けてあっという間に
良郷(北京の郊外・房山。今では地下鉄も伸びている。つまりは北京城のすぐ目の前)
まで迫った。
明の兵部尚書・于謙は、紫荊関まで自らも軍を指揮して出征、
エセンの弟ボーロを殺し、ようやくオイラト軍を撃退させて、辛くも北京を守り抜いた。

泰陵
ぽちっと押してくださると、励みになります!

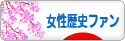
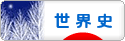
あまりにも人数が多く、えらい長丁場になってしまいました。。。。
最後は、康熙帝の江南女趣味ばかりを追いかける羽目にも・・・・。
それはともかくとして、
もう一度、まとめてみると、
康熙帝の皇子35人中、成人したのは20人。
その中で雍正帝の在位期間中、五人が幽閉されたまま。
さらに二人は獄中死した--。
しかも常にスパイを放ち、あちこちの動きをつかもうと
注意を怠らなかった・・・。
墓の中の康熙帝が、自分の子供たちのこのような状況を知ったら、どう思うだろうか・・・・。
とても顔向けできたものではない。
雍正帝自身もその状況を決して楽しんではおらず、
最も哀しんでいたのは、本人なのではないか、とさえ感じる。
--だから100里も離れた遥か彼方の地に自分の墓を作ると言い出したのだ、という説がある。
当初、候補に挙がっていた東陵の土地について、大臣らが
「九鳳朝陽山は、風水の条件に不備がある上、土壌に砂が多く、陵墓に適していない」
と上奏したのは、最初から皇帝の胸の内を察した臣下らが、気持ちを代弁するが如く上奏したのか。
そして雍正帝も「わが意を得たり」とばかりに採用したのか--。
それともほかに何か考えがあったのだろうか・・・。
陵墓を離れた場所に二つ設けることは、維持費の面で見ても、余計な経費がかかる。
それぞれに一つずつ陵墓の管理のための専門の行政機関をおき、常駐組織を置かねばならないのだから・・・。
国のすべてのことについて、無駄や矛盾をなくし、効率化を進めようとした雍正帝らしくないやり方ともいえる。

泰陵
雍正帝の命を受け、怡親王・允祥と大臣らが、その意向に沿って北京の西南方向で調査を進めた。
--怡親王・允祥といえば、第十三皇子。
雍正帝に最もかわいがられた弟。
雍正朝の勲功第一として、世襲親王である鉄帽子王に加えられ、
清朝九番目の鉄帽子王家となった人。
そんな風に弟の一人が、場所選定事業に関わっていたのですな。
しかし北京の周辺をめくら滅法に探し回れというのではなく、
「西南方向」と一応、方角は決められていたよう。
そうして最終的に決まった今の西陵のある易県には、
もう一つ、重要な要素がある。
--古来より重要な関所の一つだった紫荊関(しけいかん)の麓だということだ。
雍正帝の西陵の場所選びには、戦略上の大きな狙いがあったのではないか、と
いう説も最近は出ているという。

泰陵
排水システム
西陵は紫荊関の麓、山中から出てきてすぐの平野部に広がる。
北京は、北に燕山山脈が東西に横たわり、
西には、太行山脈が南北に連なって、山西との境となっている。
北から北京に抜けるため、燕山山脈の山中の最も重要な関所が「居庸関(八達嶺)」。
西側から北京に抜けようと思うと、太行山脈の山中の最も重要な関所が「紫荊関」である。
さらにその少し南側にあるのが、同じく太行山脈の山中の「倒馬関」。
この三関が、北京の「内三関」と呼ばれる。
このように紫荊関は古来より戦略の要所となっており、
ここが破られると、もう北京までは丸裸。
だだっ広い平野が続くので、北京まで馬で一気に駆け抜け、落とされてしまう。
紫荊関が破られれば、もう北京を破られるのも時間の問題となる。
北京界隈が燕と呼ばれた遥か昔より、戦いの勝敗を決める重要拠点となってきた。
「山西」、「山東」の「山」とは、太行山脈を指すが、
その山中には、古来より「古太行八径」と呼ばれる山中を抜ける八本の道があった。
紫荊関は、その七本目「蒲陰径」上にある。
紫荊関の重要性は、
「居庸関が破られても、北京が破られた例は十中三しかないが、
紫荊関が破られて、そのまま北京城まで破られた例は十中七。」
と言われるほどだという。
明末清初の著名な思想家・顧炎武は、『天下郡国利病書』の中で、
「居庸関は吾が背なり、紫荊関は吾が喉なり」
と言った。

下手な手書きの地図で恐縮。
自分なりに相関図をまとめてみた(笑)。
・・・・今、過去記事を見返していたら、
カテゴリー『河北・蔚県と暖泉』シリーズにも、相関地図があることを発見。
暖泉1・「蔚県800城」の一つ
そのほかにも、紫荊関を超えた西側にある宿場町・城塞都市として発展した
『河北・蔚県と暖泉』シリーズも合わせて読んでみてくださいー。
シリーズ第一話・蔚県1・宦官王振の故郷
この記事からずっと上に順番に遡って見てくださいー。
紫荊関は元々、春秋戦国時代の燕の時代から万里の頂上の一環として作られた関所である。
燕の下都の西北の守りの壁となった。
秦・漢代の名は「上谷関」、後漢では「五阮関」、
宋・金代は「金坡関」と呼ばれた。
元代以後は「紫荊関」の名で通る。
現存する紫荊関とその周辺の万里の長城は、
明代を通じて何度も補強・増強を繰り返された末の偉容である。
周辺の頂上の見張り台は330台、
紫荊関は「九門九関」、2000人近い兵士が城中していた。

泰陵
北京という都市は、もともと草原地帯と農耕地帯の境界線にあり、
農耕民族が騎馬民族から生活を守るための最前線の城塞として築かれ、発展してきた。
そのため戦火が絶えることはなく、古来より記録に残るだけでも
紫荊関で起こった戦役は140回ほどもある。
その中の代表的なものをいくつか挙げよう。
後漢の洪武帝時代・建武21年(西暦45年)、烏桓(うがん)と匈奴、鮮卑族の連合軍が侵入。
今では匈奴はモンゴル族の祖先、鮮卑もトルコ系といわれるが、
どうもこの頃は、モンゴル系もトルコ系も皆、顔はツングース、言語もアルタイ語で
あまり分化していなかったようなので、とりあえずは北方のアルタイ系の諸民族、っていうくくりでいい感じですな。
代郡(現在の山西省代県)から東の地域では、特に烏桓の被害がひどく、
「民がことごとく逃亡し、国境は人っ子一人みかけることもなし」
という悲惨な状況になったという。
名将・馬援(ばえん)が指揮を執り、紫荊関で烏桓の撃退に成功した。

泰陵
満州語、モンゴル語、漢字での表記が見える。
「世宗憲皇帝之陵」。
またもう少し後の時代には、次のような例もある。
金朝の大安元年(1209、南宋の嘉慶2年)、モンゴルのチンギス・ハーンは、居庸関を北から攻めたが、
金朝がこれを固く守り、破ることができなかった。
そこでモンゴル軍は、一部の兵力を割き、
西側から回り込んで、紫荊関を攻撃、金軍を破って
易州、啄(さんずい)州(たくしゅう、易州の東、三国志の桃園の契りで有名な地)の二州を占領、
そこから中都(今の北京)を攻め落とし、ついでに居庸関も挟み撃ちにして攻め落とした。
さらに返す刃で大軍を率いて紫荊関を西に出ると、山西の太原、代州も攻め落とした・・・・。
これで北京周辺を完全制圧したのである。
もう一つ、明代の有名な土木の戦役がある。
明の正統14年(1449)、オイラト・モンゴルのエセン・ハーンが
土木で明王朝の皇帝(英宗、正統帝)を捕虜にするという前代未聞の事件(土木の変)が起きた。
エセン・ハーンは勢いに乗り、そのまま人質の皇帝を連れて大軍を率いて南下、
万里の長城のすぐそばまで迫った。
しかし居庸関を攻めてみたものの、守りが固くてなかなか攻め落とせない。
そこで同じようにまた西側に回り込んで紫荊関を攻め、明側が敗れた。
オイラトの大軍は、そのまま駆けに駆けてあっという間に
良郷(北京の郊外・房山。今では地下鉄も伸びている。つまりは北京城のすぐ目の前)
まで迫った。
明の兵部尚書・于謙は、紫荊関まで自らも軍を指揮して出征、
エセンの弟ボーロを殺し、ようやくオイラト軍を撃退させて、辛くも北京を守り抜いた。

泰陵
ぽちっと押してくださると、励みになります!


















