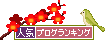楡林、東山関帝廟。
あいやー。出たー。
最近はやりのアニメチックな狛犬。
どこぞの美術大学卒業のアーティストに作らせたら、
小さいころから、ディズニーや日本のアニメを見て育った世代。
審美眼がそれに汚染されているというわけだ。

この狛犬は、この10年以内に新しく作られたものに違いない。
どちらかというと、ディズニー顔?? ライオンキング系??
まあ。訪れる側も現代の審美眼なわけだから、観賞用としてはいいでしょうけど。
子供が背中に這い登る用に作られたんでしょうし。
信仰のためなら何でもありじゃ。

陝西というのは、関帝信仰がさかんなところらしい。
古くから中国では、「県県有文廟、村村有武廟(県ごろに文廟なり、村ごとに武廟あり」)というのだそうだが、
文廟は、孔子を祀る廟。科挙を目指す文人やそれに受かってきた官僚らの崇拝対象であり、文明的な「礼」の象徴である。
これは庶民が自発的に建てるというよりは、庶民に文明的になってほしいと教化するお上側による
トップダウン方式の押しつけ的な形に近いだろう。
これに対して、「村村有武廟(つまりは関帝廟)」のほうは、
星の数ほどある村村に政府がお金を出して建てることはあまりなく、
人々が信仰のために自分で建てたものが多い。

写真: 楡林東山関帝廟にある石碑。
関帝廟は、いうまでもなく、三国志にも登場する劉備玄徳の弟分・関羽を祭った廟である。
私は関羽信仰というのは、
政府を頼らない庶民同士の相互補助システムの道徳的な支柱なのではないか、と感じている。
それがなぜ陝西において、盛んなのか、ということについては、
後程、考証したいと思う。
関羽が象徴するものは、仲間のために命がけで戦う勇気。
一旦見込んだ友人、主人は決して裏切らず、曹操にほれ込まれ、どんなに優遇されても決してなびかず、
劉備玄徳の元に帰ってきたぶれない魂。
それが養老年金制度とも社会保険制度とも無縁な大部分の人々の相互保障に必要な「道徳観」なのではないだろうか。
国に税金を払い、それを国が再分配するという年金や社会保険のシステムが
すべての人に行きわたっていないのは、
近代社会が成立するまで、どの国でも同じだが、
日本の封建社会は、どちらかというと、「国」「藩」の単位が小さかったために、
「お上」が近く、目が行き届きやすく、それがめんどうを見た。
だからつながりは「上下」である。
これに対して中国は、中央集権の時代が千年以上も続いてきたから事情が違う。
「お上」はあまりにも遠く、首都にいる。
地元の一番偉い人は、科挙に合格した秀才が中央から派遣されてくるが、
「原籍回避」原則のために、絶対によそ者しか配属されてこず、しかも数年で変わる。
そこで相互補助の役割は主に「宗族」が担ってきた。
同じ姓でつながる父系を中心とした血縁集団の中で、互いのめんどうをみてきたわけである。
福建の「土楼」に暮らす人々などは、そういう「宗族」集団で、
原始社会主義のような暮らしをしているわけだ。
何百人もの人が、宗族のもつ土地をいっしょに耕し、老人も女も子供もいっしょにそれを分け合って食う。
しかしよその土地に何か商売をしに行ったり、役人となって官界で生きていったり、
そういう「宗族」から離れて生きていかなければならない、大きな距離を移動する人、
よそ者ばかりが集まる都会では、そこに「友情」が補助的な役割として入ってきた、ということではないだろうか。
現代の中国では、すでに「宗族」のシステムは、ほとんど崩壊してしまっている。
もちろん、田舎にいけば、まだ残っているところもある。
私のお世話になっている中国人社長は、自分が事業に成功した今、
甥らをアメリカに留学させたり、いとこの嫁の弟を社員に雇ったりしている。
これも一つの「宗族」システムといえるのではないだろうか。
前から思っていることだが、中国における「友達」の意味は、日本とはまったく重みが違う。
中国の「友達」とは、相互補助システムの仲間、という意味だ。
つまりは「収穫」も含めて、ある程度は分け合うような考えがある。
だから友人同士の借金は当たり前。
前述のドラマ「北京愛情故事」でも、貧乏な鳳凰男が、病院の支払ができず、友人を呼びつけて支払いをさせる場面が出てくる。
貧乏な彼にそれを返すことができないのは、承知の上の「出世払い」である。
それを現金で返す場合もあれば、
「心」で返す場合もあるし、「体」で返す場合もあるし、「人脈」で返す場合もある。
「心」で返すとは、たとえば悩み事をたくさん聞いてくれる、会いたい時にいつでもかけつけてくれる、
必要としている答えを出してくれる、自分とはレベルが違うくらい頭がいいのに、友達と認めてくれる、
もしくは違う土地にいて、現地でのさまざまな便宜を図ってくれるといったことだ。
これも後述のように「機会平等」でない社会なので、「地元」以外で用事をこなすには、必須となる。
「体」で返すのは、各種雑用を頼まれてくれるということ。
引っ越しの手伝い、自分が仕事でいけない時に女房子供老人のコンパニオンになってくれる、
仕事の使いっぱしりをしてくれる、といったこと。
「人脈」は、そのままだが、社会学でいう世界の「低信用社会」の一つである中国では、「機会」はまったく「均等」ではない。
だから人脈の価値が、高信用社会よりはるかに高い。
そういうものを持っていれば、お金がなくても人に価値を認められる。
そういう人間としてのすべての「カード」を互いに照らし合わせ、
自分のカードと交換する価値がある、と見込んだ相手同士が
「友達」ということになる。
もちろん精神的なキャパの小さい、年齢の若いころに交わした友情の方が、
「分母」が小さい分だけ、簡単に「分子」もデカくなりやすいから、
幼馴染、同級生というだけで、生涯の「交換」になりやすいことは、いうまでもない。
大人になってからは、「マントウを分けてくれた」ことが、「友情」の得点にはならなくても
小さいころのその行為が、一生の「友情」につながるといった。。。。
関羽というのは、そういう「友情」として、互いに自分の「カード」を出し合う、と決め合った相手に
自分の「カード」を最大限に、惜しみなく出す、「義」という徳の高い存在として
中国人には、とらえられているのではないだろうか。
北方中国(私のカテゴリーでは、黄河以北)で、特に男同士で最も重視される要素が「義」だろう。
「友情」は、互いのカードを出し合う、と決めた了解なのに、
人のカードだけ最大限にもらっておきながら、自分のカードは、けちけちと出さない、
それが最も忌み嫌われる。
出した成果が少なくとも、それが本人の「分母」に比べ、
どれだけ大きな「分子」であるか、ということが、尊ばれる。
収入が月500元しかない人の400元のカンパは、月5000元の人の1000元より周りから評価が高い。
北京で周囲の夫婦を見てて、よくある典型的なパターンは、こういうものが多い。
つまり奥さんは給料は低くても、首になりにくい、福利厚生の厚い、公務員かそれに準ずる仕事につき、
家族が日常的に暮らせる程度の生活費は稼いでくる。
だんなは普段はぶらぶらしていて、何をしているのかよくわからないが、
周りから「義」に厚い、と評価してもらうために、せっせと点数アップのために活動にいそしんでいる。
手を貸してくれ、といわれれば、飛んでいき、酒につきあって相手のうっ憤に共感を示し、
自分たちのグループに足りない「人脈」を新たに開発して、周囲に貢献する、といったことである。
そうすると、いざ大きな出費があった時には、あちこちに借金をしてまわっても
集まるお金が大きくなる、ということである。
男の価値は、普段の「日銭」を稼ぐことよりも、
いざという時にかき集められる資金の大きさで決まる、ということだ。
ちょこちょこと日銭を稼いできても、
家族が大きな危機に見舞われた時に金をかき集められない男の方が軽蔑されるのである。
ちなみに女に求められる「徳」は、「慈祥」(慈悲深い)ということだろうか。
家族のために世話を焼くことである。これは日本も同じだろうが、かなり範囲が広い。
子供の世話、双方4人の老人の世話、だんな、子供たちの友人の世話。
男性が目を細めて話をする女というのは、たとえば、友人のお母さんが自分の分までセーターを編んでくれた、などというものもあり、びっくりすることがある。
いわゆる「ねね」タイプですかな。
秀吉の部下らの三度の飯のほかにも、ふんどしまで洗っていたという。。。
ああいう系ですかね。
以前にも書いたかもしれないが、
それだけ日常生活の中に「いざという時」に友人から借金をかき集めないといけないような状況が起こりうる。
・不測のけが、病気: 会社勤めしている本人以外に医療保険がないことが多い。
配偶者、こども、公務員ではなかった親、無職の親戚などなど。
医療保険をかけていても、適応されない範囲も多い。
・不測の事故・失態: 交通事故で相手にけがをさせた、妙ないいがかりをつけられた。
法的な疑惑をかけられて拘留された場合、釈放運動、保釈金の支払いなど。
・不動産の支払い: 定職を持っていない人は、銀行から住宅ローンを組むことはむずかしい。
また2軒目、勤務先以外の土地でもだめ。所有権が曖昧な、農村の土地もだめ。
何かと制限が多い上、速攻でお金がいることが多いので、時間差で借りなければならないことも多い。
日本のように「自己破産」という制度はない。
「自己破産」は、社会的な信用の失墜により、日常生活の不便、名誉失墜をもたらすからこそ成立するが、
こちらでは、「社会的な信用の失墜」がなくてもそういう不便はすべてすでに起こっている。
しかもよその土地に逃げてしまえば、過去は知られないで済む可能性が高い。
こちらの人に言わせてみれば、
「破産を宣言したら、すべてがチャラになるなんて、そんな天国のような制度があれば、
全員が借りるだけ借りて、さっさと宣言するだろう」てなもんである。
高利貸しもあるが、私のイメージでは、多くの場合、「地縁」や「宗族」による抑制力の利く相手にしか貸さない。
大都会のようにあまりにも雑多になりすぎた社会であれば、それさえも通用しなくなる。
よく耳にするのは、ひどく田舎な、閉鎖的な社会での高利貸しだ。
そういう土地柄では、親戚、地元で軽蔑されること、名誉を奪われることを何よりも恐れる。
だから高利貸しもお金を貸すのである。
故郷から夜逃げしても、残された親、兄弟、親戚を借金取りやくざがいじめ続けると、
良心にさいなまれて、大抵は取り立てることができる。
・・・という風に見ていくと、
陝西に関帝廟が多いというのは、納得いくのである。
生産能力の脆弱な、農業地帯の最北端ぎりぎりの土地に生きる人々にとって、
他人の助けを必要としなければならないことは、豊かな土地より多かったのではないだろうか。
乾燥と寒冷のダブルパンチの環境では、ちょっとの気候変動でもすぐに不作になる。
不作の年には食べるものも足りなくなり、
少ない収穫を取り合うということは、権力者からの搾取もきつくなるし、命にかかわってくる。
またモンゴルとの最前線にいるということは、
すべての庶民が武力で自らを自衛しなければならない場面と隣り合わせに生きていること意味し、
戦いに強く、勇敢だった関羽を崇拝するのもうなずける。
彼らがさらされているのは、モンゴル側のゲリラ的な襲来であるため、
必要なのは、大軍の作戦・指揮に優れている諸葛孔明や岳飛のような武将ではなく、
一人で戦う能力が最大限に強い武人だろう。
これは結局、私が日常的に接している北京の人々の価値観にも共通することのような気がする。
北京は首都であり、都会なのだが、実は生産するものはあまりなく、工場も農場も少ない。
長江デルタ(上海、南京、杭州、蘇州など)や珠江デルタ(広州、深せん、東完など)周辺の工場地帯のように、
能力如何に関係なく、とりあえず誰でも働くことのできる職場というのは、そんなに多くはない。
実は中国の北方人は、「南方人はケチ」、「南方人は薄情」、「南方人は義理に厚くない」と、悪口をいう。
つまりはどちらかというと、「友情」の概念は、日本人に近いのだ。
「働かない人は、怠け者だから」、「自分に必要なお金も普段から確保できないのは、計画性がない」という、
日本人に近い価値観を持っている。
それが可能なのは、単純労働の働き口が最低でも随時確保できる社会構造になっているからだ。
農民であっても、南方なら気候が温暖なため、2月過ぎから11月まで、1年のうち9か月以上、
へたすると、もっと作物はとれる。
菜っ葉くらいなら、いつでも畑に生えているわけで、飢える可能性は低い。
それに対して、北方は生産性が低く、結局工業についても同じことがいえる。
だから「義」が、南方よりも社会的に重視されるようになるということではないのだろうか。
陝西の関羽信仰が他地方に比べ、なぜ盛んなのか、ということについて、論証を重ねてきた。
では、具体的にどう盛んだったかというと。
まず中国全体で関羽信仰が「バージョンアップ」したのは、明代以後といわれる。
明代以前までの関羽は、「王」の尊称で呼ばれたが、明代以降は「帝」に昇格。
庶民の信仰もあるが、政府も率先して推進していった。
洪武二十七年(1394)、南京で勅令で関廟を建立。
建文三年(1401)、朱棣(永楽帝)は、帝位を簒奪する戦いを起こす際、 関公の「お告げ」があったと称した。
こうなると、帝位についた後は、大々的な関公信仰となったことは、いうまでもない。
正徳四年(1509)、すべての関廟を「忠武廟」と改名するよう勅令を出す。
万暦二十二年(1594)、関羽を「帝」に封じ、「英烈廟」と改名。
どうやらこれを見ていると、関羽の「忠」が、為政者には喜ばしく映ったらしい。
楡林の関帝廟は、石を投げれば当たるほどあり、数も定かではなかったという。
万里の長城の陝西部分は、東は府谷(黄河の東側)から西は定辺(黄河の西側)に至るまで、
沿途に36ヶ所の要塞都市が作られたが、ほとんどすべてに関帝廟があった。
最前線がそうなら、州、県城内、その周辺は、さらに関帝廟あり。
どうやらお上にも都合よく、庶民にも愛される要素が高かった凝縮の結果が、
ここまで盛んな信仰となったということらしい。
*********************************
写真: 楡林東山関帝廟。扁額。下の方に小さく関羽の木彫りが。

楡林、東山関帝廟の境内。


本殿の後ろにあつ建物。

職員の人たちの事務エリアでしょうか。
ついに東山関帝廟から出てきてしまいた。
それでもしばらく関羽話は、つづきまっす。

ばあさまとそのわんころ。
楡林、東側の城壁に貼り付くように建っている民家にて。
楡林城の東側に開けられた口。
ここは昔、城門があった場所ではないので、ただ切り開いてあるだけだ。

東側の城壁は、山の斜面を利用したものなので、西に下っていくと、ひたすら下り坂。

石畳みの街並みが続き、ノスタルジック。。


楡林は、まさに「小北京」。
古い北方建築の街並みが、色濃く残る町だ。

どの門構えにも風情があり、ついつい釣られて、何度もシャッターを切ってしまう。

春節直後なので、貼り換えたばかりの春聯がまぶしい。