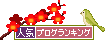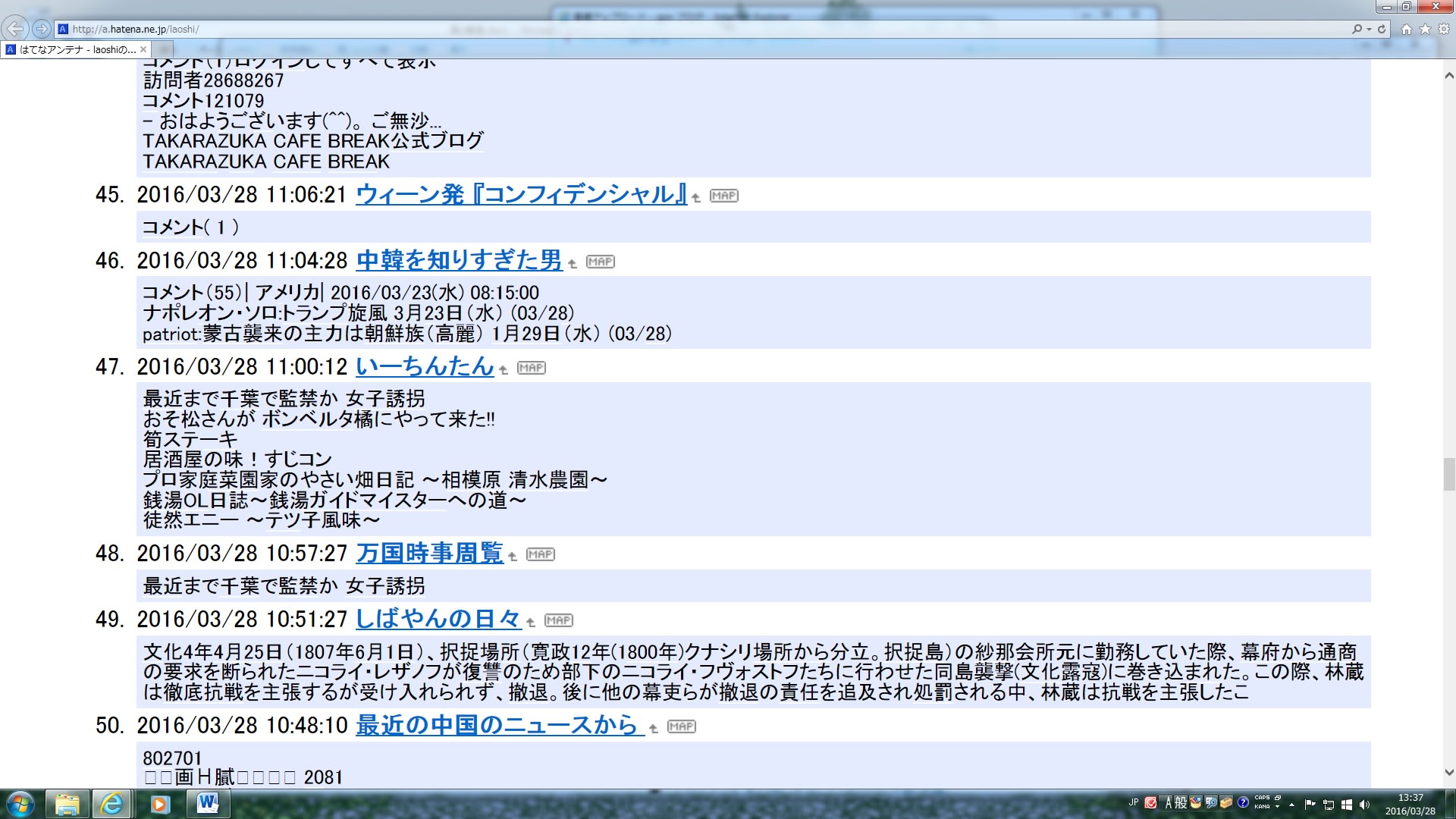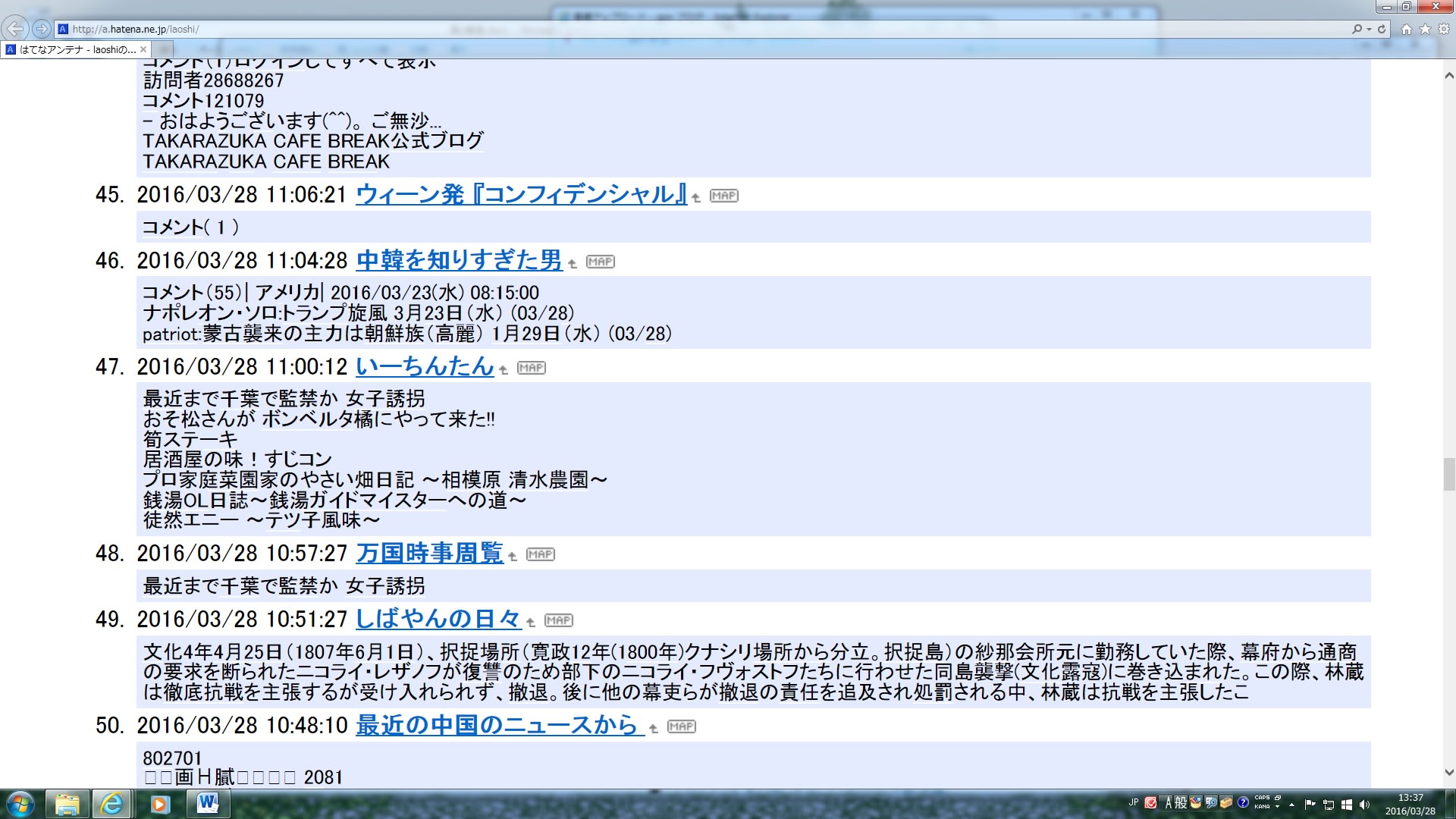雲南の旅を少し休憩し、雑談風に少しつぶやきを。
先日投稿した『麗江・ログ湖9、広州の良識ある市民に感謝』に関する問答を振り返りつつ、思ったことがあった。
それは広州の子供たちが、学校で仕込まれているはんにち教育にも関わらず、良識ある行動をとってくれたことは、
日本のアニメや漫画の貢献が大きいのではないか、ということである。
昨今の海外への影響力を考えると、その点は、想像に難くない。
つまりは荒唐無稽こうにちドラマと日本産アニメ漫画の「ソフト・パワー」対決で、
日本に軍配が上がったということの象徴的な出来事なのではないか、と。
それは別に日本人の方が中国人よりも優れているとか、そういうことではなくて、歪んだせいじ体制の元では、
歪んだ動機の元で、歪んだ作品しか作られず、それが人の心を打たない、ということである。
子供の脳は正直だから、イデオロギーで物を考えず、素直によいものに心を委ねる。
ところでそんな日本のアニメ漫画のソフトパワーの威力を実感し、自らもあやかりたいと思ったのか、
こちらでは過去10年あたりで、せいふが成長戦略として大々的に国産アニメ漫画の制作を支援してきた。
莫大な資金を投入するわ、税制優遇政策を打ち出すわ。。。
その成果が、この数年ようやく国産ブランドとして、一定の影響力をもつようになってきた『喜羊2と灰太郎』などからも認められよう。
日本のアニメ漫画といえば、韓国や台湾は、80-90年代にはかつて、日本のアニメ作画の制作基地としても、日本のアニメにかかわってきた。
当初は安い労働力を背景に、下請けをしていたが、その人材の中から国産作品を描く人たちも出てきたということだが、
影響力のある作品が育ったという話があまり聞こえてこないのは、なぜだろうか。
そもそもアニメや漫画というのは、膨大な作業量が一瞬のうちに流れて行ってしまう、
まことに割に合わない作業の連続なわけである。
仕事量のわりに、見返りとなる経済効果が薄く、関係者全員にあふれるほどの経済的な恩恵が確実に約束されるというものではない。
つまりは、飯のタネになるには、あまりにも酔狂な産業なのだ。
私が小さいころ、周囲にアニメや漫画にかかわりたいという同級生はたくさんいたが、
とにかく皆が言い合っていたのは、「大変な世界らしい」ということだった。
有名になった作者ならともかく、最初は下積みで弟子として、死なない程度の薄給で、ほとんどただ働きで寝る暇の与えられず、何年もこき使われるらしい、と。
それでも好きで好きで、とにかく関わっていたい、という酔狂な人間が後を絶たず、
日本では人材には事欠かなかったからこそ、ここまで層の厚い産業に育ってきたわけである。
いきなり天才・宮崎駿監督が登場したのではなく、そこに至るまでの重厚な人材群と産業体制があり、
それにかかわる多くの人たちが、労働に見合わない経済的見返りでも喜んで働いてきた、という世にも珍しい世界だと思う。
その「好きだからこそ、飼い殺しでもいいから関わっていたい」を前提にしなければ、発展できないからこそ、
ほかの国がいくらマネしようと思ってもそうそう簡単にできないのではないだろうか。
もちろん今どきは、そんなことはないだろうが、それは昭和の時代の重厚な基礎があったからこそであり、そこまでたどりつく前に他国では産業として、成立するまでいかない。
東アジアの若者--、韓国にしても台湾にしても香港にしても中国にしても、
少しでも給料が高いと聞けば、少々のはったりをかましてでも、自分をバンバン売り込んでさっさと転職していってしまう。
そんな彼らが、薄給で「好きだからいいの」と、何年もアニメ漫画を描くなどということは、ほとんど想像もつかない。
それがかの地域、国々で国産アニメ漫画があまり育たない理由なのではないだろうか。
アメリカは、その労働力の問題を克服するために、CGに走り、なんとか採算を取る方向に走っているが、
日本アニメ漫画の手描きの味わいを維持することが、如何に容易ならざることか、ということである。
もちろんそこには、日本的な土壌である、社会主義的な保障体制、一億総中流の社会、という世界にも珍しい社会体制だからこそ成立するというところもあるのかもしれない。
こちらの人たちの世知辛さが日本の比ではないことを見ていても、つくづくそう感じることが多い。
だから中国せいふは、おんぶにだっこでお上がすべてをめんどう見る、という形で産業を興そうとしてきたわけである。
そうでもしなければ、民間の自然発生的な動きにより、市場原理だけでとても成立し得る産業ではないのだ。