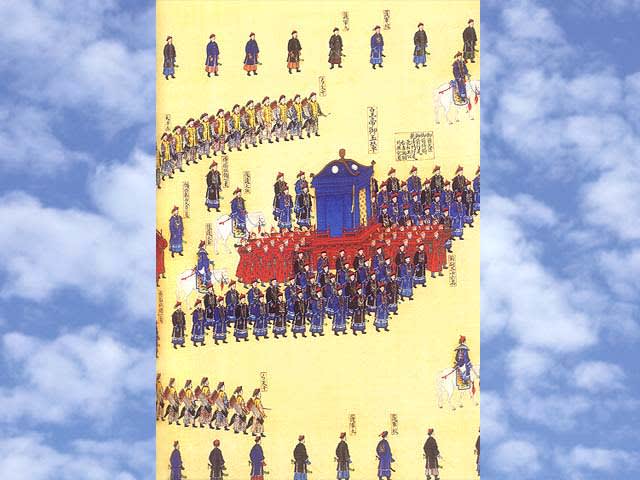清代の随筆集《郎潜紀聞》(陳康祺)に轎(かご)に関わるこんなエピソードが紹介されている。
乾隆帝が軍機章京の呉熊光を気に入り、いきなり軍機大臣に大抜擢しようとした。
軍機処は雍正年間以後、政治の中心となった小さな部屋。
通常は6-7人いた軍機大臣が交替で当直して控え、全国の行政に関わる政策の草案を作り、皇帝に相談しつつ決めていた。
つまり国事は、6-7人の軍機大臣が政策を皇帝に提案し、皇帝がそれに同意する形ですべて決められており、
国の中枢、官僚として出世する最終ゴールと言ってもよく、
通常は六部の尚書などを歴任してきたり、今でも兼任している高官が就任した。
一方、軍機章京は、軍機処の事務処理をする実務部隊、体力仕事なので、通常は若い駆け出しの官僚が担っていた。
そんな駆け出しがいきなり抜擢されたのだから、
「ごぼう抜き人事」もいいところなのだが、乾隆帝はよくこういう人事をやっている(笑)。
これに反対したのが、当時の軍機大臣の領班(筆頭)だった和[王申](ヘシェン)。
元々は自分も「ごぼう抜き人事」で乾隆帝に大抜擢されたのだが、
呉は自分とライバル関係にあった阿桂(アグイ)に近いために、面白くなかったのである。
呉の軍機大臣への任命に反対する理由として和[王申]が挙げたのが、
「呉熊光は家が貧しく、轎を用意できないのではないか。」
ということだった。
軍事章京というのは専門職ではなく、あくまでも兼職であり、
すべての章京には正式なほかの官職があり、章京の任務はおまけ、という建前になっている。
呉熊光のその本職の方の官職は、通政司参議、官位は五品でしかない。
これは章京としては、ごくまともな地位であり、
それくらいの年齢と立ち位置の、馬力のある若手が下仕事に精を出したわけである。
当初、和[王申](ヘシェン)が呉熊光の軍機大臣への任命に反対した理由は、
呉熊光の官位は五品でしかないため、ほかの軍機大臣とつり合いが取れない、というものだった。
ご最もな理由である。
ほかの軍機大臣らは皆、大学士、尚書、侍郎などの一品か二品くらいはある高官が務めているのだから。
ごぼう抜き人事の代表格と言われていた自分でさえ、さすがにそこまで脈略ない人事ではなかった。
乾隆帝に見初められてから、まずは乾清門の御前侍衛から始め、副都統を兼任。
次に正藍旗副都統になり、それから戸部侍郎に任命され、その次がようやく軍機大臣である。
その期間が確かに短かったとはいえ、一応は段階を踏ませたわけである。
しかしそれから40年ほど月日が流れており、この呉熊光の抜擢は
乾隆帝の最晩年の話なので、80代のじいさま、かなり耄碌していたことも考慮に入れる必要がある。
実際、乾隆帝の最晩年の認知症の症状も記録されている。
それは本文とは関係ないので、どうでもいいことなのだが。。。
和[王申](ヘシェン)に呉熊光の官位が低すぎると言われた乾隆帝は、
即座に「三品まで上げろ」といい、官位を上げてしまった。
皇帝様のご執心に、次に和[王申](ヘシェン)が用意した言い訳が、
「呉熊光は家が貧しく、轎(かご)を用意できないのではないか。」
ということだったのである。
「轎(かご)が用意できないのではないか」という言葉から、
いくつかわかることがある。
1、京師(北京)勤務の高官は、出勤に轎(かご)に乗って行くのが慣例だったこと。
2、轎を用意し、維持し続ける経費が、ひどく高かったこと。
3、官三位に昇級しても、それが用意できないくらい高価だったこと。
4、それでもすべての京官が轎で出仕していたということは、
どこかしらからそのお金を工面していたこと。
5、逆に言えば、官僚としての給料以外にどこかから工面して来ないと、
体面さえ保てない仕組みになっていたこと。
ひとりの人間を担いで長距離を移動するわけだから、
最低でも前後に二人ずつ、四人の轎夫(かごふ)を雇わねばならず、
衙門(役所)への通勤の行き帰りのほか、外出して社交の場に顔を出す時も、
轎で出かけていくことが、身分の証になっただろうから、午後や夜も使うことがあったのだろう。
そうなると、パートタイムというわけにも行かず、最低でも4人、多いと8人の人間を一気に雇い入れ、
常に養い続ける必要がある。
それは確かに官僚ひとりの俸禄では、苦しかったに違いない。
しかしそれでもほかに収入があることを前提に、社交界が成り立っていたということになる。
ちなみにこの後、乾隆帝は「轎が」とごねる和[王申](ヘシェン)を黙らせるために
呉熊光に銀千両を褒美として出し、轎の支度金とさせたという。
再び白塔寺

数年前の写真ですが、お化粧直しをしていました。

ぽちっと、押していただけると、
励みになります!