何やら、高齢化・過疎化で全国的に中山間地の田が減っているとのこと。「田にしても山にしても、個人のものなら個人で管理すべき」との意見も聞くけど、条件の悪い中山間地で、人口が減り、高齢化が極限まで進んでいる状況で、はっきりいって管理は無理。
これを全て保全しようとした場合、仮に兼業農家なら、平日は都市部で働き、週末も農作業に追われてしまう。時間、費用をかけてまで田舎を守ろうという人は、ごく稀だろう。
一方で、田の荒廃によって、様々な影響があると聞いている。
盆のこと。「昔は家ごとに青大将(蛇)がおったが、最近は見んくなった」という話をした。ふと思ったのが、今と昔では、田の状況が違うためではないか、と。
田が少ないということは、そこに棲むカエルや多くの生物の数も減ってしまうということ。生態系が崩れるということだろう。
田が荒れる直接の被害は、イノシシとか猿が家の近くまで来てしまうことじゃないか。雑草により隠れ蓑ができ、いくらでも歩き回ることができる。不要になった田に樹木を植えた場合、見通しが悪くなり、猿の自由空間も広がるというもの。うちの親父が「集落内には木を植えるべきではない」との自論を展開しているのも頷ける。
また、最近の局地的豪雨も関連があるのでは、という話を聞いた。これまで山がじっくりと雨を吸い、ゆっくりと下流に流していたサイクルが、農地や山林の荒廃によって崩れているとのこと。局地的豪雨に限らず、人工の針葉樹林の影響で、山に保水力がなくなっているのは現実。
とは言っても、今の時代に、大型機械は入らない、車も横付けできない、水を当てるのも大変な条件の悪い棚田を作り続けるのは大変なこと。普段「水」の恩恵を受けている下流の都市部の方々に、その水を守るための上流の自然環境保全にも目を向けていただきたいものです。











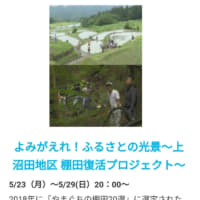









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます