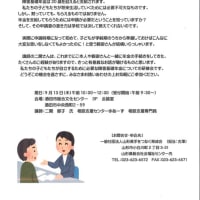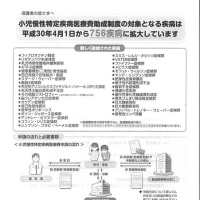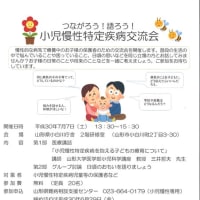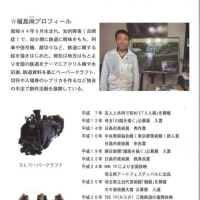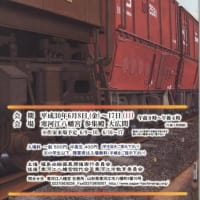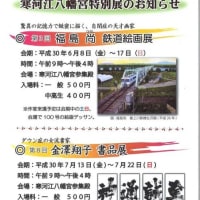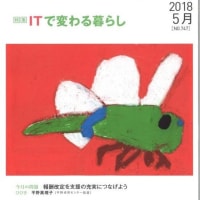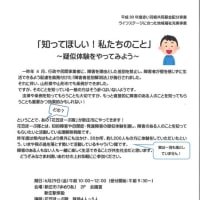知的障害者の「意思決定支援」の考え方や課題について整理した、いい論文を見つけた。
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第19回目。
「意思決定支援」が定着するためにも、「成年後見制度」の利用促進が求められている。
そのことについて、次に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
2.成年後見制度と意思決定支援
障害者権利条約12条によっても、
また改正障害者基本法23条によっても、
成年後見制度の見直しが求められる。
障害者総合支援法等の附則により
「障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方」の検討は急務である。
成年後見類型審判が全審判数の85%に達するなど、
現状は深刻である。
その際、国際育成会連盟「意思決定支援制度の主要要素」が参考になろう。
【引用終わり】
*****************************************************
国際育成会連盟「意思決定支援制度の主要要素」は、本ブログの
「国際育成会連盟で採択された「意思決定支援制度の主要要素」」
2012年11月19日を参照してほしい。
http://blog.goo.ne.jp/y-ikuseikai/e/c19544aa231694796acc6f9fc3276814
以下のような内容である。
① セルフ・アドボカシーの促進・支援。
② 一般的な市民向けの制度の利用。
③ 後見制度を意思決定支援制度に段階的に置き換える。
④ 意思決定支援制度の登録支援者は、支援ネットワークの強化に努める。
⑤ 支援される障害者が支援者を選ぶこと。
⑥ 意思疎通バリアを取り除くようにすること。
⑦ 本人と支援者との間の問題を回避し解決する手段を作ること。
⑧ 支援ニーズの高い人ほど保護を手厚くすること。
「意思決定支援」が、制度上うまく普及するには以上が機能することである。
こうしたことにそって、法整備に努力してもらわなければならない。
でも、法整備を待たなくてもやれることは多い。
上記の主要要素にある「意思決定支援」の趣旨を踏まえた支援者側の対応が求められている。
(ケー)
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第19回目。
「意思決定支援」が定着するためにも、「成年後見制度」の利用促進が求められている。
そのことについて、次に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
2.成年後見制度と意思決定支援
障害者権利条約12条によっても、
また改正障害者基本法23条によっても、
成年後見制度の見直しが求められる。
障害者総合支援法等の附則により
「障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方」の検討は急務である。
成年後見類型審判が全審判数の85%に達するなど、
現状は深刻である。
その際、国際育成会連盟「意思決定支援制度の主要要素」が参考になろう。
【引用終わり】
*****************************************************
国際育成会連盟「意思決定支援制度の主要要素」は、本ブログの
「国際育成会連盟で採択された「意思決定支援制度の主要要素」」
2012年11月19日を参照してほしい。
http://blog.goo.ne.jp/y-ikuseikai/e/c19544aa231694796acc6f9fc3276814
以下のような内容である。
① セルフ・アドボカシーの促進・支援。
② 一般的な市民向けの制度の利用。
③ 後見制度を意思決定支援制度に段階的に置き換える。
④ 意思決定支援制度の登録支援者は、支援ネットワークの強化に努める。
⑤ 支援される障害者が支援者を選ぶこと。
⑥ 意思疎通バリアを取り除くようにすること。
⑦ 本人と支援者との間の問題を回避し解決する手段を作ること。
⑧ 支援ニーズの高い人ほど保護を手厚くすること。
「意思決定支援」が、制度上うまく普及するには以上が機能することである。
こうしたことにそって、法整備に努力してもらわなければならない。
でも、法整備を待たなくてもやれることは多い。
上記の主要要素にある「意思決定支援」の趣旨を踏まえた支援者側の対応が求められている。
(ケー)