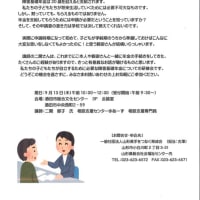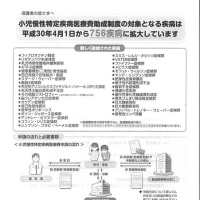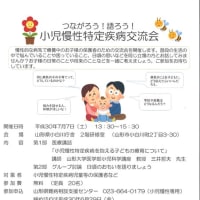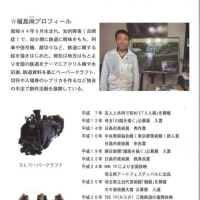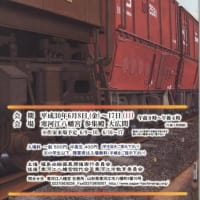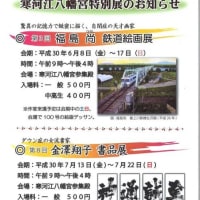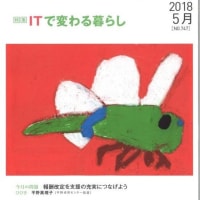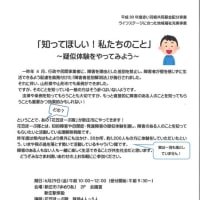知的障害者の「意思決定支援」の考え方や課題について整理した、いい論文を見つけた。
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第25回目。
知的障がい者の「意思決定支援」にかかわる課題は山積している。
知的障害の定義も法律上未整備である。
こうした課題について整理し、その解決に向けての取り組みが必要である。
そうした内容が、次に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
6.意思決定支援についての諸課題
◯ 我が国の法律では「知的障害」の法的定義がない。
国際的には、IQに基づくIDC-10と、
発症年齢や生活適応を加味したAAIDDの定義があるが、
それらの動向を見守りつつ、
知的障害者福祉法において「知的障害」を定義する必要がある。
また「療育手帳」制度については、
手帳制度全般の在り方を含めて検討すべきである。
◯ 現在「知的障害者福祉法」において
「措置」による福祉サービス利用の制度が残されているが、
「意思決定支援」に留意しつつ、その運用について検討すべきである。
◯ 改正障害者基本法には29条「司法手続きにおける配慮等」が新たに加えられた。
刑事事件・民事事件等の対象や当事者等となった場合の知的障害者等に対する「意思決定支援」も重要である。
◯ 以上思いつくままに列挙したが、
この他にも、児童期の家庭生活や学校教育、
男女交際や結婚・子育て、
医療受診、
精神保健福祉法の保護者制度と入院時同意など、
意思決定支援に関して検討すべき課題は多く、今後の議論に期待したい。
【引用終わり】
*****************************************************
知的障がい者に対して、適切な「意思決定支援」がなされるよう法律を整備する必要がある。
そうしたことによって社会的にも「意思決定支援」に関する理解が進み、機運も高まる。
知的障がい者の権利擁護を一歩も二歩も進めることになる。
「意思決定支援」は内容的にも多岐にわたる。
あらゆる場面で必要である。
育成会運動にとって、「意思決定支援」推進は大きな課題である。
(ケー)
その論文は、柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)である。
その論稿を、分割してずっと紹介している。
その第25回目。
知的障がい者の「意思決定支援」にかかわる課題は山積している。
知的障害の定義も法律上未整備である。
こうした課題について整理し、その解決に向けての取り組みが必要である。
そうした内容が、次に述べられている。
*************************************************
【引用始め】
柴田洋弥著「知的障害者等の意思決定支援について」(2012-07-16)
「発達障害研究」第34巻3号掲載予定http://homepage2.nifty.com/hiroya/isiketteisien.html より
Ⅳ.意思決定支援についての課題
6.意思決定支援についての諸課題
◯ 我が国の法律では「知的障害」の法的定義がない。
国際的には、IQに基づくIDC-10と、
発症年齢や生活適応を加味したAAIDDの定義があるが、
それらの動向を見守りつつ、
知的障害者福祉法において「知的障害」を定義する必要がある。
また「療育手帳」制度については、
手帳制度全般の在り方を含めて検討すべきである。
◯ 現在「知的障害者福祉法」において
「措置」による福祉サービス利用の制度が残されているが、
「意思決定支援」に留意しつつ、その運用について検討すべきである。
◯ 改正障害者基本法には29条「司法手続きにおける配慮等」が新たに加えられた。
刑事事件・民事事件等の対象や当事者等となった場合の知的障害者等に対する「意思決定支援」も重要である。
◯ 以上思いつくままに列挙したが、
この他にも、児童期の家庭生活や学校教育、
男女交際や結婚・子育て、
医療受診、
精神保健福祉法の保護者制度と入院時同意など、
意思決定支援に関して検討すべき課題は多く、今後の議論に期待したい。
【引用終わり】
*****************************************************
知的障がい者に対して、適切な「意思決定支援」がなされるよう法律を整備する必要がある。
そうしたことによって社会的にも「意思決定支援」に関する理解が進み、機運も高まる。
知的障がい者の権利擁護を一歩も二歩も進めることになる。
「意思決定支援」は内容的にも多岐にわたる。
あらゆる場面で必要である。
育成会運動にとって、「意思決定支援」推進は大きな課題である。
(ケー)