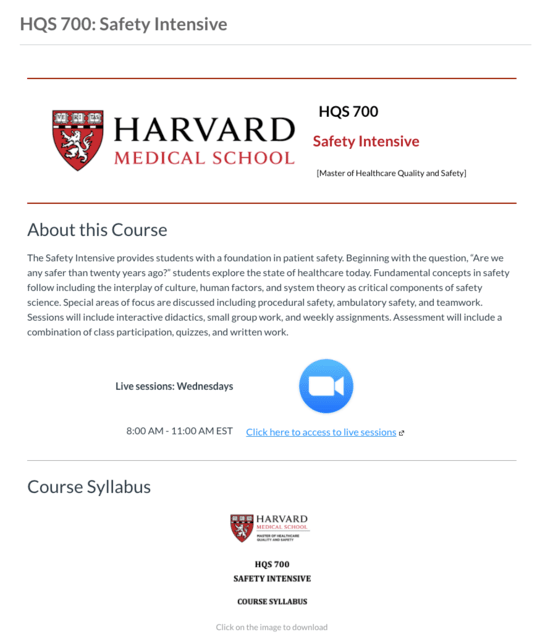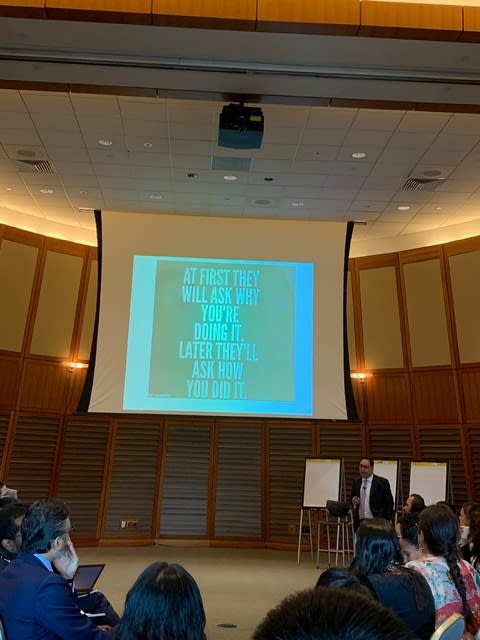みなさんこんにちわ。
強烈な、勉強量がありすでに医師国家試験の時の緊張感をいい意味で超えています。
けどアラフォーなのにこんなにがっつり学ぶことができるということはとてもいいことだと
思って、いずれもっともっと日本でHealthcare Quality improvementとPatient Safetyを学問的に、教育的に、実践的に広げたいと思って教科書を作ろうかなぁと考えました。なので、僕が勉強してOut putとしての知識の整理にブログを用いて記載していきます。基本的に僕がこの分野の内容を書いている場合は、残念ながら誰かに伝えたいというメッセージではなくて、あくまで自分のためと、わかりやすい教科書作成のためになりますので、少し難しい表現などもあるかもしれないです。
もし少しでも興味がある方は、MHQSはこんな感じのこと勉強していて、こんなことしているんだなぁというノリで無視してもらえればOKです。そもそも、今まで日本人では始めてのことなので未知数ですから。
(OUT PUT 大全集という本でもおっしゃってた通りの方法で、全く僕も同じようにOut put大事にしてきた人間なので)
Introduction to Patient Safety
1-1 Learning objectives
- Describe how specific patient stories of harm have shaped the safety movement.
- List the key milestones in the history of patient safety over the last 25 years.
- Describe whether care is safer today than 25 years ago
具体的な患者の被害体験談がSafety movementをどのように形成してきたか説明できる。
過去25年間の患者の安全の歴史の中で、重要なマイルストーンを列挙できる。
25年前よりも今日の方が安全かどうかを説明できる。
1-2 Learning objectives
- Reflect on a patient’s journey
- Analyze the role of different health providers in patients experience related to safety
患者体験のReflection行う
安全性に関連した患者体験における別の医療提供者としての役割を分析する
1-3 Learning objectives
- Define adverse events, near misses, and medical errors and describe their impact on healthcare.
- Name key areas of the continued risk of harm in today’s environment.
- List and differentiate between different types of unsafe acts.
- Define key concepts in patient safety including different types of errors
- Analyze James Reason's organizational model of accidents.
医療における有害事象、ニアミス、医療過誤を定義でき、それらが医療に与える影響を説明できる。
今日の環境における継続的な危害のリスクの主要な領域を挙げる。
異なるタイプの安全でない行為を列挙し、区別する。
さまざまなタイプのエラーを含む、患者の安全性における重要な概念を定義する。
【James Reasonの事故組織モデル】を分析する。
期限は1週間:これに対して僕がやるべきこと、
論文22本、患者体験6Case、On demand Video7本、Essay 1つ、Discussion forumでの議論1日。Quiz 24問
なんとなくこれで大きな教科書が1Weekで終わる感じ?!が、頑張るしかない。
深く刻んだこと
"To learn only from one’s own mistakes would be a slow and painful process and unnecessarily costly to one’s patients. Experiences need to be pooled so that doctors may also learn from the errors of others. This requires a willingness to admit one has erred and to discuss the factors that may have been responsible. It calls for a critical attitude to one’s own work and that of others. No species of fallibility is more important or less understood than fallibility in medical practice.
The physician’s propensity for damaging error is widely denied, perhaps because it is so intensely feared… Physicians and surgeons often flinch from even identifying error in clinical practice, let alone recording it, presumably because they themselves hold… that error arises either from their or their colleagues’ ignorance or ineptitude. But errors need to recorded and analysed if we are to discover why they occurred and how they could have been prevented." (McIntyre and Popper, 1983: p. 1919)
*疑問:なぜ医療安全の研究と医療の質の研究者の傾向性が違うのか?ここに書かれている。
Whereas practitioners of quality improvement in healthcare tended to look to industrial process improvement as their model, patient safety researchers and practitioners have looked to high-risk industries, such as aviation, chemical and nuclear industries, which have an explicit focus on safety usually reinforced by a powerful external regulator.) Vincent, Charles. Patient Safety (p.21). Wiley. Kindle 版.
いずれも、産業や工業、航空交通などのエラーから医療の本質的なエラーに対するサロゲート研究になっていたことが伺える。
The Harvard Medical Practice Study (HMPS), still the most famous study in the field of patient safety, was originally established to assess the number of potentially compensable cases in New York State, not primarily as a study of the quality and safety of care (Hiatt et al., 1989). However, its major legacy has been to reveal the scale of harm to patients. The study found that patients were unintentionally harmed by treatment in almost 4% of admissions in New York, and about 1% of patients were seriously harmed (e.g. resulting in death or permanent disability) (Brennan et al., 1991; Leape et al., 1991) Vincent, Charles. Patient Safety (p.25). Wiley. Kindle 版.
*伝説的な研究、課題論文にもなっている。NY州の入院患者の約4%が意図しない有害事象があり、1%死亡ないし後遺症に至る有害事象があったとことになる。
何が重要か?それは、医療安全研究の基盤となった
1)カルテレビューの基盤的手法の確立
2)Adverse evenet 医療により有害性を得た、また入院長期化や後遺症などの事 、Negligence(過失や怠慢):プロ集団の医師中で標準的な解釈や手法を下回る行為や知識、態度も。
3)世界で初めて入院時の有害事象について調べた大規模調査30121人のカルテレビュー結果:全入院患者のAE:3.7%、そのうちPermanent disability:2.6%, 13.6%: deathという衝撃的な数字であった。これにより、米国で年間入院患者の98609人が有害事象に遭遇していると見積もられ、これが結果的にTo err is Humanに繋がる。あのNewhouse 教授も若い頃に研究に参加している。
Betsey Lehmabの症例(1994):400mg/m2 over 4days、世界的名門であるHarvard 関連病院:Dana Farber Cancer Institute で起きたが抗癌剤投薬ミスで、全米に衝撃。この結果、Dana Farberは世界的な医療安全の病院へ転換していった。ITサポート、薬剤ダブルチェック、委員会の設立、指導者の責任と指導方法、患者家族の透明性の増加などが一気に進む引き金になった。(感想は、同級生12名でよってたかって、議論をする。自分の意見を提出するとそれがアップされて、同級生から同意と不同意と建設的な議論に発展する、自動的に学びては学ぶという画期的な手法でした)
To err is Human
- To err is human: principal recommendations of the IOM report Congress should create a Centre for Patient Safety.
- A nationwide mandatory reporting system should be established.
- The development of voluntary reporting should be encouraged.
- Congress should pass legislation to extend peer review protection to patient safety data.
- Performance standards and expectations for healthcare organizations and healthcare professional should focus greater attention on patient safety.
- The Food and Drug Administration should increase attention to the safe use of drugs in both the pre- and post-marketing processes.
- Healthcare organizations and the professionals affiliated with them should make continually improved patient safety a declared and serious aim, by establishing patient safety programmes with defined executive responsibility.
- Healthcare organizations should implement proven medication safety practices.
- (FROM KOHN, CORRIGAN AND DONALDSON, 1999)
Vincent, Charles. Patient Safety (p.26). Wiley. Kindle 版.
To Err is Humanのコアメッセージ
The IOM’s Four-Part Message
The IOM committee sought what could be learned from other disciplines and applied in health care by clinical and administrative leadership. It described actions that health care professionals can take now in their own institutions, whether they are new trainees, experienced clinical leaders, or instructors. The major thrust of the report was a four-part plan, intended to create financial and regulatory incentives to create a safer health care system and a systematic way to integrate safety into the process of care (the focus of this chapter). The four parts of the IOM recommendations are described below:
♦ Part 1: National Center for Patient Safety – The IOM recommended the creation of a National Center for Patient Safety in the U.S. Department of Health and Human Services’s Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), because health care is a decade or more behind other high-risk industries in its attention to ensuring basic safety, establishing national safety goals, tracking progress in meeting them, and investing in research to learn more about preventing mistakes. This center would also serve as a clearinghouse and source of effective practices that would be shared broadly.
♦ Part 2: Mandatory and Voluntary Reporting Systems – To learn about medical care associated with serious injury or death and to prevent future occurrences, the IOM recommended establishing a nationwide, mandatory public reporting system, where Federal legislation would protect the confidentiality of certain information (e.g., medical mistakes that have no serious consequences). The intent was to encourage the growth of voluntary, confidential reporting systems so that practitioners and health care organizations could learn about and correct problems before serious harm occurs.
♦ Part 3: Role of Consumers, Professionals, and Accreditation Groups – The IOM believed that fundamental change would require pressure and incentives from many directions, including public and private purchasers of health care insurance, regulators (including the Food and Drug Administration), and licensing and certifying groups. A direct result was the announcement of new standards on safety from the Joint Commission and a report, Safe Practices for Better Health Care. A Consensus Report, by the National Quality Forum.10
♦ Part 4: Building a Culture of Safety – The IOM urged health care organizations to create an environment in which safety becomes a top priority. This report stressed the need for leadership by executives and clinicians and for accountability for patient safety by boards of trustees. In particular, it urged that safety principles known in other industries be adopted, such as designing jobs and working conditions for safety; standardizing and simplifying equipment, supplies and processes; and avoiding reliance on memory. The report stressed medication safety in part because medication errors are so frequent11 and in part because a number of evidenced-based practices were already known and needed wider adoption. Though at the time of publication, the levels of evidence for each category varied, the members of the committee believed that all were important places to begin to improve safety.
**Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Chapter 3 An Overview of To Err is Human: Re-emphasizing the Message of Patient Safetyより
**To err is humanの何が重要か?:Committee of Quality of Health Care in Ameriaの設立。44000-98000が年間Medical Errorに遭遇していると発表。その入院における費用の損失は17-29億ドルと見積もった。しかし、目に見えないコストとして、患者側からの信頼の損失、両方の満足度の低下、社会的損失は測定できていない。メディアが発表前に発表してしまい、一部意図としない方向へ、情報の一人歩きも。
という事で、随分とTo err is Humanで進んできたがこの段階でまとめると問題点はこうなる
意識が高くなり、Patient safety の概念が浸透した、爆発的に理解が進んだ、BUT 有害事象の発生率は未だ高く、有効な介入手法やスキルは思った以上に少なく、理想以上に信頼できるものではなく(エビデンスも乏しい:これはSafety Cultureのところでまた議論する)、入院患者を対象にした理解が多く(外来、ERなどは少ない)、罹患率ではなく死亡率にばかり研究される。
がある。
そこで誕生したのが、The National Patient Safety FoundationからFree from Harm (To err is human から15年の報告書)より未来への指針の発表である。基本的8つの提案書からなっている。個人レベルで理解しておきたいのは、1、3、7
Recommendations:
1. Ensure that leaders establish and sustain a safety culture リーダとSafety culutreの維持
2. Create centralized and coordinated oversight of patient safety PSを集約した中央組織の作成
3. Create a common set of safety metrics that reflect meaningful outcomes 意味のあるアウトカムを反映する共通の評価基準の作成
4. Increase funding for research in patient safety and implementation science 研究の促進・資金・現場への応用
5. Address safety across the entire care continuum 横断的連続性を持った包括的なSafetyケア
6. Support the health care workforce 医療者へのサポート
7. Partner with patients and families for the safest care 患者や家族との協力
8. Ensure that technology is safe and optimized to improve patient safety 向上させるために、技術の安全性を確認と最適化
In health care, a strong safety culture is one in which health care professionals and leaders are held accountable for unprofessional conduct yet not punished for human mistakes; errors are identified and mitigated before they harm patients, and strong feedback loops enable frontline staff to learn from previous errors and alter care processes to prevent recurrences.
医療において、強力な安全文化とは、医療従事者やリーダーが、人為的なミスに対して罰せられることなく、非生産的な行為に対して責任を負うこと、エラーが患者に危害を加える前に特定され、軽減されること、そして、強力なフィードバックループにより、現場のスタッフが過去のエラーから学び、ケアプロセスを変更して再発を防ぐことができる.
The role of effective leaders is to establish a safety culture by defining the goals and values of the organization—health care leaders must clearly and relentlessly communicate that safe care is a primary, non-negotiable goal.
効果的なリーダーの役割は、組織の目標と価値観を定義することで安全文化を確立することであり、リーダーはSafety Careが第一の、譲れない目標であることを明確に、そして執拗に伝えなければならない。
*The IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events: AEの指標の
航空業界や工業等の他業種・産業との安全性という観点は類似していると言われている。医療安全の研究の代わりに研究対象とされて非常に発展してきた。類似点はよく参考にされるが、実は相違点は言及されることは少ない。
まとめ(David Gaba 2000)ブログ著者作成
|
|
医療
|
他産業
|
|
明確な統制構造の整備・使用機器の統一、使用方法の標準化
|
分業・分散・企業多数あり、標準化されない
|
使用機器の統一、使用方法の標準化あり
|
|
業務手順両方の標準化
|
医療者の業務は標準化されにくい。Hand on する必要がある業務が多すぎる。医師ごとに対応が異なる
|
標準化されている。Ex)パイロットは誰でも概ねOKなレベル: equivalent actors.
|
|
業務訓練・準備・技能の習得
|
医学部で学ぶ。しかし高度かつ複雑なプロセス、現場の手法や手順をOn the jobで学び続ける必要がある。
|
就業前訓練を極めて重要視し、勤務開始前に十分に安全なレベルまでトレーニングされることが多い。パイロット等
|
|
規制
|
規制が臨床業務に影響を与えることはあまりない
|
規制が厳格であり業務に強く反映される
|
Adverse Event の分類 *Patient Safety Primer Last Updated: September 2019 Patient Safety 101
- Preventable adverse events: those due to error or failure to apply an accepted strategy for prevention 予防可能な有害事象:予防のための一般に認められた戦略の誤りまたは不適用に起因する有害事象
- Ameliorable adverse events: events that, while not preventable, could have been less harmful if care had been different;
緩和可能な有害事象:予防可能ではないが、ケアが違っていれば有害性が低くなる可能性があった事象。
- Adverse events due to negligence: those due to care that falls below the standards expected of clinicians in the community. 過失による有害事象:地域社会の臨床医に期待される基準を下回るケアに起因する事象。
患者に有害性を与えなかった他の2つの分類 Two other terms are used to describe hazards to patients that do not result in harm:
Near miss: an unsafe situation that is indistinguishable from a preventable adverse event except for the outcome. A patient is exposed to a hazardous situation but does not experience harm (either through luck or early detection). ニアミス:結果を除いて、予防可能な有害事象と区別がつかない危険な状況。患者が危険な状況にさらされているにもかかわらず、(運が良かったか早期発見によって)危害が発生しなかった場合。
Error: a broader term referring to any act of commission (doing something wrong) or omission (failing to do the right thing) that exposes エラー:より広義の用語で、患者を危険にさらすような作為(何か間違ったことをした)または省略(正しいことをしなかった)の行為を指す。**特に学問的に難しくするのは、ある行為がErrorであったと判明・判断できのは必ず現象が起きてからのみである。そのために、hindishigt である。
James Reason の貢献:
1) 目に見える失敗であるactive failureと隠れた要因であるlatent conditionを言及
2) System approachの開発:大事故は個人の理由のみで起きることはなく、その背景や根底にある複数の小さなエラーの積み重ねがあることが多い。スイスチーズモデルの提唱に繋がる。個人が犯したエラーは、欠陥のあるシステム、つまりチーズの穴によって悲惨な結果をもたらす。個々の臨床医の責任を免除するものではないことに注意!! つまり、自分が思うに、これまでの日本のシステムエラーの言及に止まる内容のみでは、バランス感覚がとても大事であるが個人レベルでの診断プロセスの誤りに言及できないことが明らか。本意としては、免罪符ではなく、個人レベルでのHand onがある医療では、エラーが起きても安全であるように修復できる適切な環境を個人に置くことがより大事。
Slip (実行の失敗): 目的は正しいが行為が誤っていて発生したエラー
Lapse (失念): は短期的な記憶違い、物忘れ、勘違いなどのCognition biasも入るかも、それが実行すればSlip
Mistake (計画の失敗):意図的あるいは意図とせず実施する計画的(やろうと思ってやった)失敗