2013年7月25日(木)
楠木正成は、前衛の城として下赤阪城を、本城として上赤阪城を持っていた。
千早城は赤坂城の詰めの城として、その背後の金剛山中腹の山上に築いた。
楠木正成は金剛山一帯に点々と要塞を築きその総指揮所として千早城を活用し、
下赤坂城、上赤坂城、千早城の3城で鎌倉幕府軍と対峙した。
千早城は堅牢な山城で、正成が藁人形などによる奇策を用いて籠城戦を戦いぬき、
最終的に幕府軍を撤退させる事に成功した事で有名である。
最初は千早城の前衛の城とされる「下赤坂城」へ向かった。
前日、道の駅「ちはやあかさか」を訪れた際に、下赤坂城の前を通ったので難なく行くことができた。

下赤坂城への道は千早赤坂村立中学校への登校路となっている。

校舎手前右側にグラウンドがあり、サッカー部の朝練が始まるところだった。

グラウンドの直ぐ上が中学校であるが、この先は行き止まり???

中学校の玄関は右側にあった。

左は体育館のようだ。

この先は校内で行き止まりかと思ったら、玄関と体育館の間は村道とのこと。
狭いながらも車も通れるようになっていると聞いて一安心。

玄関と体育館の間を抜け、左折して右上を見上げると下赤坂城址の碑が見えた。

小高い土盛の上に碑が建てられてある以外には特に何も見当たらない。
碑の前に説明板があるだけで、以下のように紹介されている。
標高185.7m、比高61.4m。
金剛山地から延びる丘陵の自然地形を利用して築城された中世山城である。
この城は鎌倉時代後半から南北朝時代にかけて活躍した楠木正成(1294?~1336)によって
築城されたと云われている。(以下略)

昭和九年(1934)3月に楠木城跡(上赤坂城跡)、千早城跡とともに国の史跡に指定されている。
この地はむしろ棚田の方が有名のようだ。
平成11年、農林水産省により「日本の棚田百選」に認定されている。

目の前に棚田風景が広がる。
毎年田植え直後や稲刈りの時期になると大勢の観光客が押し寄せるそうである。

下赤坂城を後にして、次に向かったのは詰の城「千早城」である。
千早城は、鎌倉時代末期より南北朝時代に存在した楠木正成の城である。
千早城は楠木正成が元弘二年(1332)金剛山腹に築いた山城で、
四方を絶壁に囲まれ要塞堅固を誇ったといわれる連郭式山城である。
別名金剛山城、楠木詰城と呼ばれている。
昭和九年(1934)3月に赤坂城跡(下赤坂城跡)、楠木城跡(上赤坂城跡)とともに国の史跡に指定されている。
前日、千早赤坂村の郷土資料館を訪れた際に、
100名城スタンプは「まつまさ」という店にあることを教えて貰っていたのが参考になった。
「まつまさ」への入口は、金剛山登山口バス停の150mほど手前にあった。
細い坂道になっているので、聞いていなかったらきっと見落としていたことだろう。

「まつまさ」には駐車場(有料600円)が整備されており、ここを利用するのが便利という情報も得ていた。
金剛山への登山道がすぐ前のため、登山者もこの駐車場をよく利用するようだ。

駐車場に車を停めて、「まつまさ」でスタンプを押し、
8時44分、登城(登山)開始である。

金剛山・楠木神社への登山道は直ぐに始まる。
バス停に近いもう一つの登山道は五百数十段の急な石段が続くため、こちらの登山道を利用する人の方が多いらしい。
最初からやや急な上りが続く。

荷物など余分な物を持たない軽装な姿でどんどん先へ行ってしまう人が目に付く。
とてもそのスピードには付いていけない。
聞くところによると、金剛山には2千回以上も登っている人がいるそうだから凄い。

日頃から運動不足のかみさんにはこの程度の坂道でも相当に堪えるようだ。

8分ほど進むと脇水が出るところがあった。
ここから先は水が無いので、ここで給水をするよう注意書があった。

お茶は持参しているので心配ないが、試しにかみさんが手で掬って一口、『冷たくて美味しいっ!』
自分も飲んでみたが美味かった。
ここの水を汲んで行きたかったが、ペットボトルも持ってなかったので、諦めた。

水飲み場の正面が千早神社(千早城)への登り口になっていた。

案内図によると、こちらは神社への裏参道となっている。

一段と急な山道が続く。

道の脇には荷物を運ぶレールが取り付けられている。
山頂裏手にある山の家用モノレールである。

10分ほど上ると、三の丸跡と思しき場所に出た。
右(写真)は四の丸広場跡へと通じている。
左が三の丸跡・二の丸跡・千早神社(千早城本丸)へと続く。
事前調査によるとこの辺りが堀切になっているようだが、その形跡は確認できなかった。
今から700年近くも前のことだから、地形が変わってしまっていても不思議ではない。

最初に左手の千早神社(千早城本丸)へ向かうことにした。
なだらかな石段が続く。

最初の石段を上ったところに社務所があった。
三の丸跡と思われる。

社務所の横に千早城址の碑が建てられていた。

碑の向かい側に小さな社があった。
千早神社の分神であろうか。

社務所の先の石段を上ると・・・

鳥居の先に、千早神社が見える。
二の丸跡である。

千早神社
説明板には以下のように案内されている。
千早城本丸跡に、もと八幡大菩薩を祀って千早城の鎮守として、創建する。
後に楠木正成郷・正行朝臣・久子刀首を合祀して神社と称する。
後に楠木正成、正行を祀り「楠社」と称した。

明治七年(1874)、社殿が再建され、明治十二年(1879)に社名を「千早神社」に変更した。

ここから先(裏山)は、神社と一体で神聖な場所ということで、立入を遠慮願いたいとあるが・・・

山頂(673m)には別の道があるのではと思い込み、いったん裏参道分岐方面へ戻って別の道を進んでみることにした。
千早神社を少し下ると、金剛山への登山道があった。

数分進むと、コンクリート造りの古びた建物が目に入った。
茶宴台広場とのことで、休憩場所と思われるが、何とも寂しい雰囲気が漂う。
ちょうど千早神社の裏手になる場所だ。

茶宴台広場から先は金剛山へと通じるようなので、ここから先は止めておこう。
この茶宴台広場からも千早城山頂(673m)は見えないし、ここにも立入禁止の看板が立っていた。
結局本丸跡には上ることが許されていないようで、仕方なく諦めることにした。

千早神社入口近くまで戻り左手を見ると、二手に分かれている道があった。
建物が見える。

少し進むと家があった。
「大阪府立存道館」と書かれている。
純粋な道義心を体得する鍛練の場という意味だそうである。

その一段下には別の家があった。「千早山の家」である。
どちらも閉館しており、千早城とは特に関係のない建物のようだ。

四の丸広場跡へ向かう。

四の丸広場跡には千早神社の鳥居が建てられている。

四の丸広場跡
千早城址の中で最も広く、平坦な場所である。

茶屋らしき建物が数軒あるが、今は全て閉店されていた。

広場の中央に千早城址と書かれた看板と藁人形が飾られていた。
「太平記」に、南北朝時代に楠木正成が鎌倉幕府の大軍と戦い、藁人形に甲冑を着せるなどして
互角に応戦したことが記されていることから、作られたものであろう。

最終的に千早城は落城するが、籠城して鎌倉幕府軍と対峙して戦っている最中に、
関東において挙兵した新田義貞が、手薄となった鎌倉を攻め、鎌倉幕府は滅亡することとなった。
鎌倉幕府が滅亡するのは100日戦争(千早城の戦い)が終了した12日後のことであった。
他には特に見所も無さそうなので、四の丸広場跡を後にして、五百数十段の石段を下ることにした。

石段(表参道)は曲がりくねっていて、段差があるため、歩き易いとは言い難い。

こういった石段は、上りより下りの方が足に負担がかかる。
上りの方が楽である。

しばらく石段を下ると千早神社の鳥居が見えてきた。

下り始めて15分ほどで、鳥居に到着した。

鳥居の下に最後の急な石段があった。
手摺りに掴まらないと不安を感じるほどの角度である。

千早神社への登山口には藁人形が置かれていた。

千早城のことについての文化庁の説明板(省略)がある。

金剛山登山口バス停を見たところ。
金剛山ロープウェイはこのバス停よりさらに2Kmほど先になる。

スタート地点の「まつまさ」駐車場に戻ったのは、10時25分。
ちょうど2時間の軽いハイキングであった。
金剛山登山道入り口には、山の脇水が流れっ放しになっていた。
自由に汲んでも良いそうだ。
汗をかいた後の乾いた喉にはありがたい。

「まつまさ」の向かいで、自家製豆腐を販売していた。
この水は豆腐作りには欠かせないのだ。
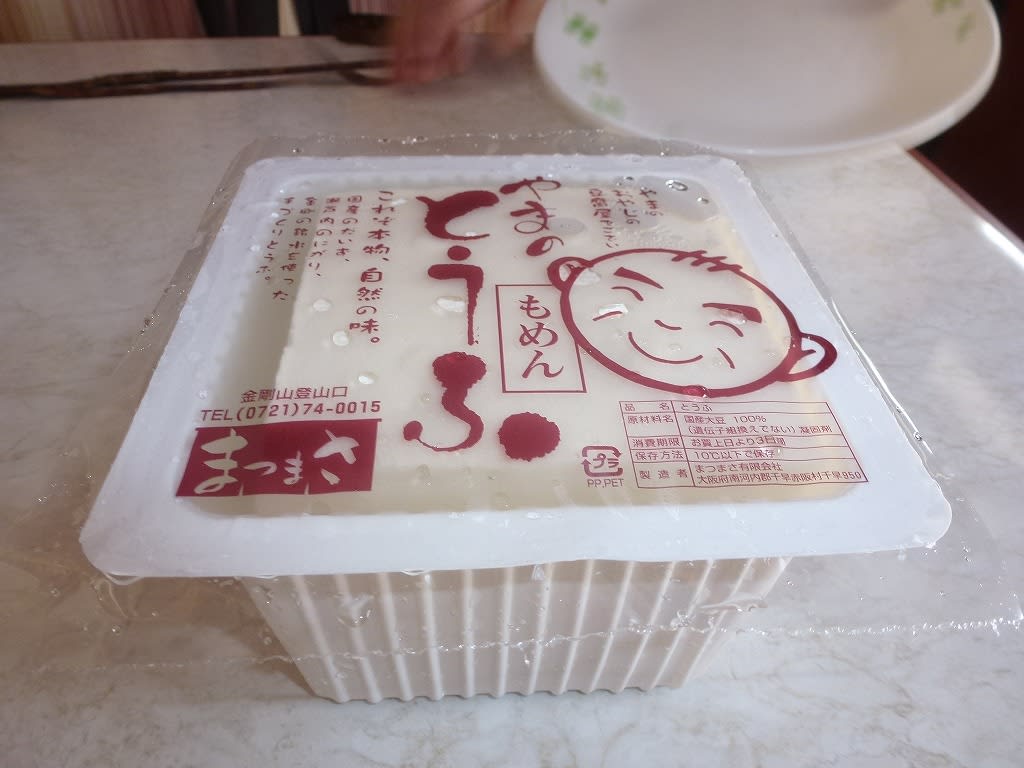
早速車の中で食べてみた。
普通の倍はあろうかという大きな木綿豆腐だったが、ペロリと平らげてしまった。
冷たくて実に美味しかった。

この後、本城と位置づけられている上赤坂城跡(楠木城跡)に向かった。
やっとの思いで探し当てた楠木城址であるが、道が極端に狭く、
車が途中で立ち往生しそうになったことと、かみさんの悲鳴にも負けて、登城を断念して引き返した。
上赤坂城(楠木城)の代わりと言っては変だが、ここは南公誕生の地碑で我慢しておこう。
前日、道の駅「ちはやあかさか」を訪問した際に、郷土資料館前に南公誕生地の碑があった。
この碑を目当てに訪問した訳ではないので本当に偶然のことである。

説明には次のように書かれている。
楠木正成は永仁二年(1294)この地に誕生したと伝えられている。
文禄年間に増田長盛が豊臣秀吉の命を受け、土檀を築き、建武以後楠木邸にあった、
百日紅を移植したという記録が残っている。

この日はまだ時間も早かったので、次の目的地である「高取城」を目指すことにした。
奈良県高取町を目指して車を走らせた。
ウマさんの「日本100名城巡り」の目次(日付順)に戻る。
ウマさんの「日本100名城巡り」の目次(お城順)に戻る。
楠木正成は、前衛の城として下赤阪城を、本城として上赤阪城を持っていた。
千早城は赤坂城の詰めの城として、その背後の金剛山中腹の山上に築いた。
楠木正成は金剛山一帯に点々と要塞を築きその総指揮所として千早城を活用し、
下赤坂城、上赤坂城、千早城の3城で鎌倉幕府軍と対峙した。
千早城は堅牢な山城で、正成が藁人形などによる奇策を用いて籠城戦を戦いぬき、
最終的に幕府軍を撤退させる事に成功した事で有名である。
最初は千早城の前衛の城とされる「下赤坂城」へ向かった。
前日、道の駅「ちはやあかさか」を訪れた際に、下赤坂城の前を通ったので難なく行くことができた。

下赤坂城への道は千早赤坂村立中学校への登校路となっている。

校舎手前右側にグラウンドがあり、サッカー部の朝練が始まるところだった。

グラウンドの直ぐ上が中学校であるが、この先は行き止まり???

中学校の玄関は右側にあった。

左は体育館のようだ。

この先は校内で行き止まりかと思ったら、玄関と体育館の間は村道とのこと。
狭いながらも車も通れるようになっていると聞いて一安心。

玄関と体育館の間を抜け、左折して右上を見上げると下赤坂城址の碑が見えた。

小高い土盛の上に碑が建てられてある以外には特に何も見当たらない。
碑の前に説明板があるだけで、以下のように紹介されている。
標高185.7m、比高61.4m。
金剛山地から延びる丘陵の自然地形を利用して築城された中世山城である。
この城は鎌倉時代後半から南北朝時代にかけて活躍した楠木正成(1294?~1336)によって
築城されたと云われている。(以下略)

昭和九年(1934)3月に楠木城跡(上赤坂城跡)、千早城跡とともに国の史跡に指定されている。
この地はむしろ棚田の方が有名のようだ。
平成11年、農林水産省により「日本の棚田百選」に認定されている。

目の前に棚田風景が広がる。
毎年田植え直後や稲刈りの時期になると大勢の観光客が押し寄せるそうである。

下赤坂城を後にして、次に向かったのは詰の城「千早城」である。
千早城は、鎌倉時代末期より南北朝時代に存在した楠木正成の城である。
千早城は楠木正成が元弘二年(1332)金剛山腹に築いた山城で、
四方を絶壁に囲まれ要塞堅固を誇ったといわれる連郭式山城である。
別名金剛山城、楠木詰城と呼ばれている。
昭和九年(1934)3月に赤坂城跡(下赤坂城跡)、楠木城跡(上赤坂城跡)とともに国の史跡に指定されている。
前日、千早赤坂村の郷土資料館を訪れた際に、
100名城スタンプは「まつまさ」という店にあることを教えて貰っていたのが参考になった。
「まつまさ」への入口は、金剛山登山口バス停の150mほど手前にあった。
細い坂道になっているので、聞いていなかったらきっと見落としていたことだろう。

「まつまさ」には駐車場(有料600円)が整備されており、ここを利用するのが便利という情報も得ていた。
金剛山への登山道がすぐ前のため、登山者もこの駐車場をよく利用するようだ。

駐車場に車を停めて、「まつまさ」でスタンプを押し、
8時44分、登城(登山)開始である。

金剛山・楠木神社への登山道は直ぐに始まる。
バス停に近いもう一つの登山道は五百数十段の急な石段が続くため、こちらの登山道を利用する人の方が多いらしい。
最初からやや急な上りが続く。

荷物など余分な物を持たない軽装な姿でどんどん先へ行ってしまう人が目に付く。
とてもそのスピードには付いていけない。
聞くところによると、金剛山には2千回以上も登っている人がいるそうだから凄い。

日頃から運動不足のかみさんにはこの程度の坂道でも相当に堪えるようだ。

8分ほど進むと脇水が出るところがあった。
ここから先は水が無いので、ここで給水をするよう注意書があった。

お茶は持参しているので心配ないが、試しにかみさんが手で掬って一口、『冷たくて美味しいっ!』
自分も飲んでみたが美味かった。
ここの水を汲んで行きたかったが、ペットボトルも持ってなかったので、諦めた。

水飲み場の正面が千早神社(千早城)への登り口になっていた。

案内図によると、こちらは神社への裏参道となっている。

一段と急な山道が続く。

道の脇には荷物を運ぶレールが取り付けられている。
山頂裏手にある山の家用モノレールである。

10分ほど上ると、三の丸跡と思しき場所に出た。
右(写真)は四の丸広場跡へと通じている。
左が三の丸跡・二の丸跡・千早神社(千早城本丸)へと続く。
事前調査によるとこの辺りが堀切になっているようだが、その形跡は確認できなかった。
今から700年近くも前のことだから、地形が変わってしまっていても不思議ではない。

最初に左手の千早神社(千早城本丸)へ向かうことにした。
なだらかな石段が続く。

最初の石段を上ったところに社務所があった。
三の丸跡と思われる。

社務所の横に千早城址の碑が建てられていた。

碑の向かい側に小さな社があった。
千早神社の分神であろうか。

社務所の先の石段を上ると・・・

鳥居の先に、千早神社が見える。
二の丸跡である。

千早神社
説明板には以下のように案内されている。
千早城本丸跡に、もと八幡大菩薩を祀って千早城の鎮守として、創建する。
後に楠木正成郷・正行朝臣・久子刀首を合祀して神社と称する。
後に楠木正成、正行を祀り「楠社」と称した。

明治七年(1874)、社殿が再建され、明治十二年(1879)に社名を「千早神社」に変更した。

ここから先(裏山)は、神社と一体で神聖な場所ということで、立入を遠慮願いたいとあるが・・・

山頂(673m)には別の道があるのではと思い込み、いったん裏参道分岐方面へ戻って別の道を進んでみることにした。
千早神社を少し下ると、金剛山への登山道があった。

数分進むと、コンクリート造りの古びた建物が目に入った。
茶宴台広場とのことで、休憩場所と思われるが、何とも寂しい雰囲気が漂う。
ちょうど千早神社の裏手になる場所だ。

茶宴台広場から先は金剛山へと通じるようなので、ここから先は止めておこう。
この茶宴台広場からも千早城山頂(673m)は見えないし、ここにも立入禁止の看板が立っていた。
結局本丸跡には上ることが許されていないようで、仕方なく諦めることにした。

千早神社入口近くまで戻り左手を見ると、二手に分かれている道があった。
建物が見える。

少し進むと家があった。
「大阪府立存道館」と書かれている。
純粋な道義心を体得する鍛練の場という意味だそうである。

その一段下には別の家があった。「千早山の家」である。
どちらも閉館しており、千早城とは特に関係のない建物のようだ。

四の丸広場跡へ向かう。

四の丸広場跡には千早神社の鳥居が建てられている。

四の丸広場跡
千早城址の中で最も広く、平坦な場所である。

茶屋らしき建物が数軒あるが、今は全て閉店されていた。

広場の中央に千早城址と書かれた看板と藁人形が飾られていた。
「太平記」に、南北朝時代に楠木正成が鎌倉幕府の大軍と戦い、藁人形に甲冑を着せるなどして
互角に応戦したことが記されていることから、作られたものであろう。

最終的に千早城は落城するが、籠城して鎌倉幕府軍と対峙して戦っている最中に、
関東において挙兵した新田義貞が、手薄となった鎌倉を攻め、鎌倉幕府は滅亡することとなった。
鎌倉幕府が滅亡するのは100日戦争(千早城の戦い)が終了した12日後のことであった。
他には特に見所も無さそうなので、四の丸広場跡を後にして、五百数十段の石段を下ることにした。

石段(表参道)は曲がりくねっていて、段差があるため、歩き易いとは言い難い。

こういった石段は、上りより下りの方が足に負担がかかる。
上りの方が楽である。

しばらく石段を下ると千早神社の鳥居が見えてきた。

下り始めて15分ほどで、鳥居に到着した。

鳥居の下に最後の急な石段があった。
手摺りに掴まらないと不安を感じるほどの角度である。

千早神社への登山口には藁人形が置かれていた。

千早城のことについての文化庁の説明板(省略)がある。

金剛山登山口バス停を見たところ。
金剛山ロープウェイはこのバス停よりさらに2Kmほど先になる。

スタート地点の「まつまさ」駐車場に戻ったのは、10時25分。
ちょうど2時間の軽いハイキングであった。
金剛山登山道入り口には、山の脇水が流れっ放しになっていた。
自由に汲んでも良いそうだ。
汗をかいた後の乾いた喉にはありがたい。

「まつまさ」の向かいで、自家製豆腐を販売していた。
この水は豆腐作りには欠かせないのだ。
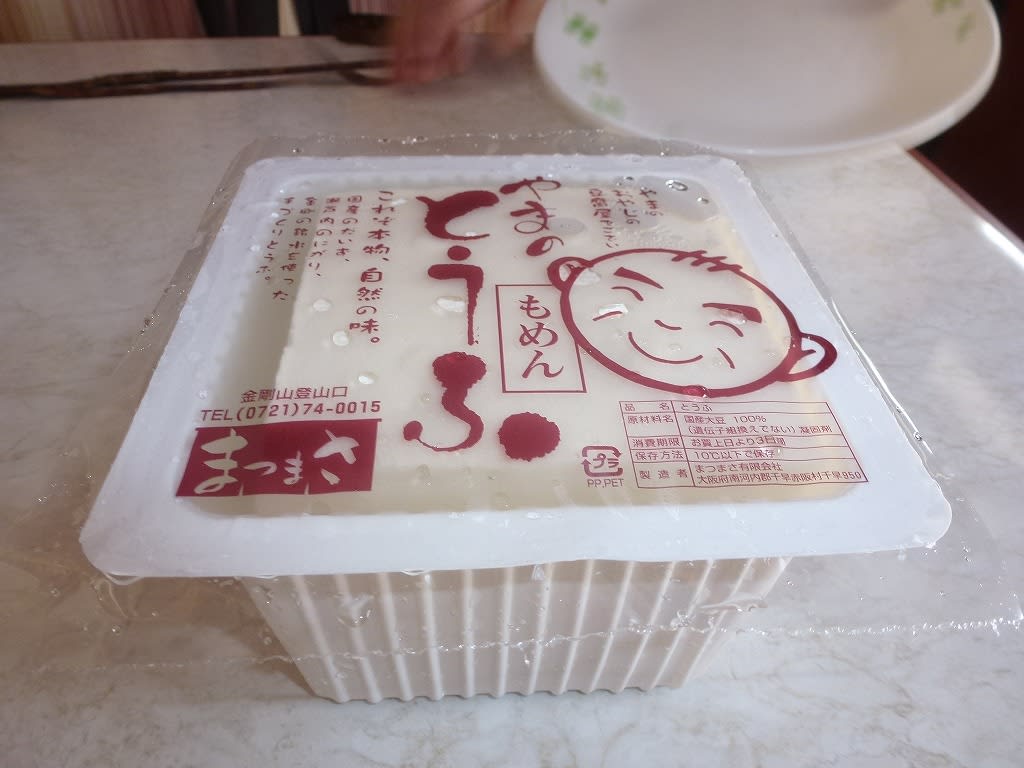
早速車の中で食べてみた。
普通の倍はあろうかという大きな木綿豆腐だったが、ペロリと平らげてしまった。
冷たくて実に美味しかった。

この後、本城と位置づけられている上赤坂城跡(楠木城跡)に向かった。
やっとの思いで探し当てた楠木城址であるが、道が極端に狭く、
車が途中で立ち往生しそうになったことと、かみさんの悲鳴にも負けて、登城を断念して引き返した。
上赤坂城(楠木城)の代わりと言っては変だが、ここは南公誕生の地碑で我慢しておこう。
前日、道の駅「ちはやあかさか」を訪問した際に、郷土資料館前に南公誕生地の碑があった。
この碑を目当てに訪問した訳ではないので本当に偶然のことである。

説明には次のように書かれている。
楠木正成は永仁二年(1294)この地に誕生したと伝えられている。
文禄年間に増田長盛が豊臣秀吉の命を受け、土檀を築き、建武以後楠木邸にあった、
百日紅を移植したという記録が残っている。

この日はまだ時間も早かったので、次の目的地である「高取城」を目指すことにした。
奈良県高取町を目指して車を走らせた。
ウマさんの「日本100名城巡り」の目次(日付順)に戻る。
ウマさんの「日本100名城巡り」の目次(お城順)に戻る。

























