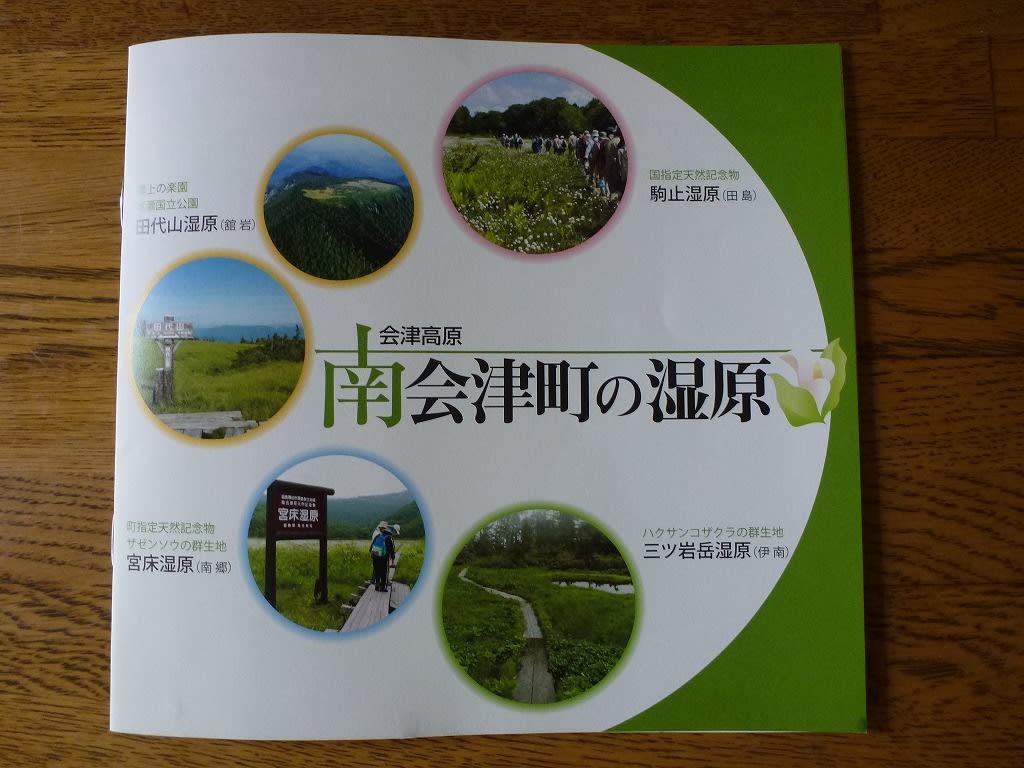2012年6月6日(水)
常南トラベル(株)が主催する日帰りバスの旅「八方が原ハイキング」に参加した。
所属する「健康ウォーキング同好会」からは、会長以下有志の9名が参加した。
常南交通本社(谷田部)から大型バスに乗り込んだ。
バスはほぼ満席に近い状態であったが、この後、下館からの乗客のため、294号線へ。

バスに乗り込むと直ぐに朝食の弁当が配られた。
ハムと焼きそばが半分づつ入っているパンだ。ソーセージと小さなトマトが付いている。
どこかのコンビニでも見かけたようなメニューである。
朝食にはおにぎりの方が良いのでは、と自分は思う。

バスは快調に294号線を北上していたが、下妻の125号線手前付近で全く進まなくなった。
事故による渋滞に巻き込まれてしまった。

う回させられた道は後ろも前もご覧のような状況である。

40分以上も遅れて常総線下館駅で最後の乗客を乗せると、直ぐに道の駅「にのみや」で最初の休憩だ。

北関東道真岡ICで昼食弁当を積み込み、東北道へ。

上河内SAで2度目の休憩だ。

上河内SAに到着した時には降っていなかったが、小休止している間に小雨が降り出した。
台風3号の影響で、雨の領域も次第に北上している感じである。

添乗員から手作りのハイキングコース図が配られ、コースの説明を受ける。
「小間々駐車場」から「大間々駐車場」まで皆と一緒に歩き、そこからはいくつかのコースがあるので、
各自自分に適した好きなコースを歩く、ということである。

10時36分、ようやくこの日のゴールとなる八方が原の「山の家たかはら」(学校平駐車場)へ到着し、最後の休憩。
常南交通本社を出発して既に4時間を経過していた。
始発の石岡ロードパークから乗車した人は5時間半もの長旅となった。

ここで、昼食の弁当を受け取り、

準備体操だ。
常南交通のバスハイクにはこれまで10回参加しているが、バス添乗員の号令による準備体操は初めてである。

この後、バスでスタート地点の「小間々駐車場」へ移動。
10時55分、ようやく出発だ。
あいにくこの頃から心配された雨が降り出した。予報より少し早い。

数分遅れて「健康ウォーキング同好会」9名も一団の後を追った。
「健康ウォーキング同好会」がしんがりを務める形となった。

大間々駐車場までは、「大間々自然歩道」を歩く。
自然歩道の入口は、山ツツジの木々に覆われている。
道標がないと見落としかねない。

山ツツジのトンネルを過ぎると、新緑の林が続く。

緩やかな上りの道であるが、レインコートを被っているので、『暑い!』
フードで頭を覆っているので、なおさらである。
直ぐに汗が噴き出てきた。

我々より若干年配と思われる一団とすれ違った。
大間々駐車場をスタートとする下るだけのコースなのだそうだ。

林を抜けると、やや明るい場所に出た。

レンゲツツジはまだ蕾の状態である。
見頃は今週末から来週始め頃だろうか?

山ツツジは既に満開状態、既に満開を過ぎている木も多数見られる。

こちらは、トウゴクミツバツツジ?
ファンの間では、「小間々の女王」と呼ばれるそうだが、その数は少ない。

大間々駐車場が見えてきた。

見頃のレンゲツツジには1週間ほど早かった。
A子さんによると、昨年5月中旬に訪れた時には一面のレンゲツツジだったそうだ。
それで今回も参加したそうであるが、花の時期を見極めるのは難しい。

11時35分、大間々駐車場に到着。

コースの確認をして・・・

「ミツモチ山」目指して出発!

右の「見晴しコース」「青空コース」を進む。
左は「やしおコース」で戻りのコースとして歩くことにした。

この頃になって雨が上がり、時折り陽が差すことも。
『良かったわねぇ』
(傘を差している人もいるが、雨は降っていない)

「シロヤシオ」がところどころに咲いている。
「アカヤシオ」は5月下旬には既に終わっているとのこと。
同じツツジの仲間なのに開花時期は大きく異なるのだ。

「シロヤシオ」は、愛子様のお印として一躍有名になった、そうである。
お花の好きな皇太子ご夫婦が、「純白の花のような純真な心を持った子供に育って欲しい」
との願いをお印に込めたといわれている、とのこと。

右は「見晴しコース」、急な上りが続く、との説明があった道である。
(添乗員によると、こちらのコースを選んだ人はいなかったそうである)
我々は左の「青空コース」を進む。

『緩やかで歩き易いコースが良いゎ』

蕾だけのツツジ(種類は不明)も見られる。
満開になった時が楽しみな蕾の状態である。

『雨が上がって良かったわねぇ』
『ついてるねぇ』

突然視界が開けて、高原山一帯の中岳(1728m)と釈迦ケ岳(1795m)が。
あいにく釈迦ケ岳の頂上付近は雲がかかっている。

殆ど平坦な道が続く。
やや物足りない、という気がしないではない。

これはまた物騒な立て看板だ。
狩猟の人には、くれぐれも気を付けて欲しいものである。

見事な「シロヤシオ」(ゴヨウツツジ)である。

ところどころに咲いている「山ツツジ」に見惚れる。

『なんてきれいなんでしょっ』

12時25分、ミツモチ山(1,248m)の展望台下に到着。
案内板によると、この辺り一帯を”ミツモチ”(かつては三ツ持)と云うそうである。

昼食の前に展望台へ上ってみることに。

数十mも上がると、小さな展望台があった。

雨は上がったばかりで、展望台からの眺望はもう一つ、といったところ。
しかし、高原を吹き抜ける爽やかな風が気持ち良い。

ベンチに戻り、とにかく弁当だ。
真岡鉄道の駅弁”野立御膳”とある。

これは、なかなかの弁当ではないか。
山菜炊き込みご飯に鳥の唐揚げ、鮪の角煮、串だんご、かまぼこ、かんぴょう・竹の子・ごぼうの煮物
などなどが詰まった贅沢な弁当である。酒のつまみにも合いそうだ。

『美味しいっ!』
『今まで食べた中で一番じゃないかしら?』
ご飯はボリュームがあり、女性には多すぎるのでは? と思ったが、皆さんきれいに平らげてしまった。
気になる値段であるが、ネットで調べたら、お手ごろな700円とあった。
真岡を訪れる機会があれば、買い求めたいものである。

気が付くと「やしおコース」から上ってきた人たちも弁当を広げていた。
距離は同じだが「やしおコース」の方が若干時間がかかるとの説明があったが、その通りだ。

戻りは「やしおコース」である。大間々駐車場まで2.6Kmとある。
展望台前の道標に従って進む。

背の低い熊笹が生い茂っている中を進む。

しばらく下りが続く。

13時15分、大丸(おおまる)を通過。
大間々駐車場まで1.6Kmだ。

かなりな下りである。
『逆コースだったら、結構大変だったわねぇ』
『戻りのコースにして良かったねぇ』
同感である。
(歩きながら動いている人を撮るのでブレてしまう。見苦しい点は御容赦願いたい)

ブナやミズナラなどの林が続く。

イラモミの古木
案内によると、イラモミは秩父や丹沢、東海地方に分布しているほか、
この高原山にとび離れて分布している、とのこと。

ミズナラの大木

大きなシダの群生なども見られる。
ここが標高1,200mあることを忘れさせる景色ではある。

一息入れよう。
『お茶が美味しいっ』

林の中は薄暗くなり、次第にガスって来た。また雨が降り出してきた。
林の中のため、雨を少しばかりだが凌いでくれるのはありがたい。

「やしおコース」は下りばかりではない。
今度は上りである。

15分ほどの上りを一気に進むと、「青空コース」との分岐点に出た。
ほどなく、大間々駐車場である。

ゴールまでには少し時間に余裕があったので、大間々駐車場の外周歩道を歩くことに。
昨年見事なツツジのトンネルがあった、というI会長の記憶にすがることにした。
大間々自然歩道を小間々駐車場へ数百mほど進むと、

外周歩道らしき小さな小径があった。
小径へ入ると、山ツツジのトンネルが現れた。
I会長の記憶は正しかっことが証明されたのだ。
『これは、本当に見事だねぇ』

ひと際大きなツツジの木はまさに満開の状態であった。
『これで何とか八方が原に来たという格好が付いたねぇ』

外周歩道を抜けると、小間々駐車場と大間々駐車場を結ぶ道路に出た。
そのまま道路を小間々駐車場に向かうことにした。

雨上がりのため、新緑の緑が一層際立っている。目に沁みるようだ。
『気分爽快ってこのことよね~』

新緑に混じってポツリと咲いている山ツツジの朱色が一段と映える。

舗装された道路を20分ほど歩き、小間々駐車場へ到着した。
ここからまた、大間々自然歩道を歩くことにした。

ゴールの「学校平駐車場」は朝方進んだ方とは反対側の道を進むことになる。

鮮やかな山ツツジのトンネルが続く。

途中で軽く小休止して、

林の中を進む。

時折り、緑の中に山ツツジの朱に出遭う。
何とも言えないコントラストである。

20分ほど大間々自然歩道を下ると、学校平駐車場に到着した。

山の駅「たかはら」で注文したコーヒーは一味違った味がした。
15時20分、バスは次の目的地「かんぽの宿栃木喜連川温泉」へ向かった。

約1時間で「かんぽの宿栃木喜連川温泉」に到着。

「かんぽの宿栃木喜連川温泉」には10年前に日帰り入浴で一度訪れている。
その時は「日帰り館」だったと記憶しているが、今は「宿泊館」での入浴に変わっていた。

汗はとっくに引いてしまっていたが、ひと風呂浴びて汗を流すことに。

館内の食堂でくつろぐ人たちもいるなか、我々は一足先に一層のくつろぎを求めてバスへ向かった。

『かんぱ~いっ!』

風呂上がりに冷えたビールは格別である。
この味を味わうために道の駅「たかひら」で水分補給を我慢していた人も。
17時20分、満足の笑顔で溢れたバスは、静かに「かんぽの宿喜連川温泉」を後にした。

帰りのバスは、高速道ではなく、一路294号線で茨城を目指した。
18時30分、道の駅「にのみや」で最期の休憩。

車窓から筑波山が見えた。
(ピンボケなのは、決してアルコールのせいではない、と思っている)

『今日は、大変お疲れ様でしたっ!』
朝方の事故渋滞が最後まで影響したのか、自宅に着いたときには既に20時を廻っていた。
この日の天気は”午後から雨”の予報だったが、途中から日差しも差してきたのは幸いだった。
”雨の中での弁当”も覚悟していただけに、日差しの中での弁当は正直言って助かった。
蕾のレンゲツツジや盛りを過ぎたシロヤシオに何となく物足りなさを感じていたが、
最後に大間々外周歩道で見事な山ツツジのトンネルに出遭ったことで、金を払った分の元は取れた、と思っている。
昨年参加したI会長の経験・記憶が生かされた、ということである。
ミツモチ山の高原で食べた弁当は、今までで最高の味であった。
これからも常南交通社が主催するいくつかのハイキングへ参加する予定だが、
どのような昼食弁当が出るのか、大いに楽しみである。
今後もこの日の弁当級が提供されるのを期待したい。
”ウマさんの気ままなバスハイキングの目次”に戻る。
常南トラベル(株)が主催する日帰りバスの旅「八方が原ハイキング」に参加した。
所属する「健康ウォーキング同好会」からは、会長以下有志の9名が参加した。
常南交通本社(谷田部)から大型バスに乗り込んだ。
バスはほぼ満席に近い状態であったが、この後、下館からの乗客のため、294号線へ。

バスに乗り込むと直ぐに朝食の弁当が配られた。
ハムと焼きそばが半分づつ入っているパンだ。ソーセージと小さなトマトが付いている。
どこかのコンビニでも見かけたようなメニューである。
朝食にはおにぎりの方が良いのでは、と自分は思う。

バスは快調に294号線を北上していたが、下妻の125号線手前付近で全く進まなくなった。
事故による渋滞に巻き込まれてしまった。

う回させられた道は後ろも前もご覧のような状況である。

40分以上も遅れて常総線下館駅で最後の乗客を乗せると、直ぐに道の駅「にのみや」で最初の休憩だ。

北関東道真岡ICで昼食弁当を積み込み、東北道へ。

上河内SAで2度目の休憩だ。

上河内SAに到着した時には降っていなかったが、小休止している間に小雨が降り出した。
台風3号の影響で、雨の領域も次第に北上している感じである。

添乗員から手作りのハイキングコース図が配られ、コースの説明を受ける。
「小間々駐車場」から「大間々駐車場」まで皆と一緒に歩き、そこからはいくつかのコースがあるので、
各自自分に適した好きなコースを歩く、ということである。

10時36分、ようやくこの日のゴールとなる八方が原の「山の家たかはら」(学校平駐車場)へ到着し、最後の休憩。
常南交通本社を出発して既に4時間を経過していた。
始発の石岡ロードパークから乗車した人は5時間半もの長旅となった。

ここで、昼食の弁当を受け取り、

準備体操だ。
常南交通のバスハイクにはこれまで10回参加しているが、バス添乗員の号令による準備体操は初めてである。

この後、バスでスタート地点の「小間々駐車場」へ移動。
10時55分、ようやく出発だ。
あいにくこの頃から心配された雨が降り出した。予報より少し早い。

数分遅れて「健康ウォーキング同好会」9名も一団の後を追った。
「健康ウォーキング同好会」がしんがりを務める形となった。

大間々駐車場までは、「大間々自然歩道」を歩く。
自然歩道の入口は、山ツツジの木々に覆われている。
道標がないと見落としかねない。

山ツツジのトンネルを過ぎると、新緑の林が続く。

緩やかな上りの道であるが、レインコートを被っているので、『暑い!』
フードで頭を覆っているので、なおさらである。
直ぐに汗が噴き出てきた。

我々より若干年配と思われる一団とすれ違った。
大間々駐車場をスタートとする下るだけのコースなのだそうだ。

林を抜けると、やや明るい場所に出た。

レンゲツツジはまだ蕾の状態である。
見頃は今週末から来週始め頃だろうか?

山ツツジは既に満開状態、既に満開を過ぎている木も多数見られる。

こちらは、トウゴクミツバツツジ?
ファンの間では、「小間々の女王」と呼ばれるそうだが、その数は少ない。

大間々駐車場が見えてきた。

見頃のレンゲツツジには1週間ほど早かった。
A子さんによると、昨年5月中旬に訪れた時には一面のレンゲツツジだったそうだ。
それで今回も参加したそうであるが、花の時期を見極めるのは難しい。

11時35分、大間々駐車場に到着。

コースの確認をして・・・

「ミツモチ山」目指して出発!

右の「見晴しコース」「青空コース」を進む。
左は「やしおコース」で戻りのコースとして歩くことにした。

この頃になって雨が上がり、時折り陽が差すことも。
『良かったわねぇ』
(傘を差している人もいるが、雨は降っていない)

「シロヤシオ」がところどころに咲いている。
「アカヤシオ」は5月下旬には既に終わっているとのこと。
同じツツジの仲間なのに開花時期は大きく異なるのだ。

「シロヤシオ」は、愛子様のお印として一躍有名になった、そうである。
お花の好きな皇太子ご夫婦が、「純白の花のような純真な心を持った子供に育って欲しい」
との願いをお印に込めたといわれている、とのこと。

右は「見晴しコース」、急な上りが続く、との説明があった道である。
(添乗員によると、こちらのコースを選んだ人はいなかったそうである)
我々は左の「青空コース」を進む。

『緩やかで歩き易いコースが良いゎ』

蕾だけのツツジ(種類は不明)も見られる。
満開になった時が楽しみな蕾の状態である。

『雨が上がって良かったわねぇ』
『ついてるねぇ』

突然視界が開けて、高原山一帯の中岳(1728m)と釈迦ケ岳(1795m)が。
あいにく釈迦ケ岳の頂上付近は雲がかかっている。

殆ど平坦な道が続く。
やや物足りない、という気がしないではない。

これはまた物騒な立て看板だ。
狩猟の人には、くれぐれも気を付けて欲しいものである。

見事な「シロヤシオ」(ゴヨウツツジ)である。

ところどころに咲いている「山ツツジ」に見惚れる。

『なんてきれいなんでしょっ』

12時25分、ミツモチ山(1,248m)の展望台下に到着。
案内板によると、この辺り一帯を”ミツモチ”(かつては三ツ持)と云うそうである。

昼食の前に展望台へ上ってみることに。

数十mも上がると、小さな展望台があった。

雨は上がったばかりで、展望台からの眺望はもう一つ、といったところ。
しかし、高原を吹き抜ける爽やかな風が気持ち良い。

ベンチに戻り、とにかく弁当だ。
真岡鉄道の駅弁”野立御膳”とある。

これは、なかなかの弁当ではないか。
山菜炊き込みご飯に鳥の唐揚げ、鮪の角煮、串だんご、かまぼこ、かんぴょう・竹の子・ごぼうの煮物
などなどが詰まった贅沢な弁当である。酒のつまみにも合いそうだ。

『美味しいっ!』
『今まで食べた中で一番じゃないかしら?』
ご飯はボリュームがあり、女性には多すぎるのでは? と思ったが、皆さんきれいに平らげてしまった。
気になる値段であるが、ネットで調べたら、お手ごろな700円とあった。
真岡を訪れる機会があれば、買い求めたいものである。

気が付くと「やしおコース」から上ってきた人たちも弁当を広げていた。
距離は同じだが「やしおコース」の方が若干時間がかかるとの説明があったが、その通りだ。

戻りは「やしおコース」である。大間々駐車場まで2.6Kmとある。
展望台前の道標に従って進む。

背の低い熊笹が生い茂っている中を進む。

しばらく下りが続く。

13時15分、大丸(おおまる)を通過。
大間々駐車場まで1.6Kmだ。

かなりな下りである。
『逆コースだったら、結構大変だったわねぇ』
『戻りのコースにして良かったねぇ』
同感である。
(歩きながら動いている人を撮るのでブレてしまう。見苦しい点は御容赦願いたい)

ブナやミズナラなどの林が続く。

イラモミの古木
案内によると、イラモミは秩父や丹沢、東海地方に分布しているほか、
この高原山にとび離れて分布している、とのこと。

ミズナラの大木

大きなシダの群生なども見られる。
ここが標高1,200mあることを忘れさせる景色ではある。

一息入れよう。
『お茶が美味しいっ』

林の中は薄暗くなり、次第にガスって来た。また雨が降り出してきた。
林の中のため、雨を少しばかりだが凌いでくれるのはありがたい。

「やしおコース」は下りばかりではない。
今度は上りである。

15分ほどの上りを一気に進むと、「青空コース」との分岐点に出た。
ほどなく、大間々駐車場である。

ゴールまでには少し時間に余裕があったので、大間々駐車場の外周歩道を歩くことに。
昨年見事なツツジのトンネルがあった、というI会長の記憶にすがることにした。
大間々自然歩道を小間々駐車場へ数百mほど進むと、

外周歩道らしき小さな小径があった。
小径へ入ると、山ツツジのトンネルが現れた。
I会長の記憶は正しかっことが証明されたのだ。
『これは、本当に見事だねぇ』

ひと際大きなツツジの木はまさに満開の状態であった。
『これで何とか八方が原に来たという格好が付いたねぇ』

外周歩道を抜けると、小間々駐車場と大間々駐車場を結ぶ道路に出た。
そのまま道路を小間々駐車場に向かうことにした。

雨上がりのため、新緑の緑が一層際立っている。目に沁みるようだ。
『気分爽快ってこのことよね~』

新緑に混じってポツリと咲いている山ツツジの朱色が一段と映える。

舗装された道路を20分ほど歩き、小間々駐車場へ到着した。
ここからまた、大間々自然歩道を歩くことにした。

ゴールの「学校平駐車場」は朝方進んだ方とは反対側の道を進むことになる。

鮮やかな山ツツジのトンネルが続く。

途中で軽く小休止して、

林の中を進む。

時折り、緑の中に山ツツジの朱に出遭う。
何とも言えないコントラストである。

20分ほど大間々自然歩道を下ると、学校平駐車場に到着した。

山の駅「たかはら」で注文したコーヒーは一味違った味がした。
15時20分、バスは次の目的地「かんぽの宿栃木喜連川温泉」へ向かった。

約1時間で「かんぽの宿栃木喜連川温泉」に到着。

「かんぽの宿栃木喜連川温泉」には10年前に日帰り入浴で一度訪れている。
その時は「日帰り館」だったと記憶しているが、今は「宿泊館」での入浴に変わっていた。

汗はとっくに引いてしまっていたが、ひと風呂浴びて汗を流すことに。

館内の食堂でくつろぐ人たちもいるなか、我々は一足先に一層のくつろぎを求めてバスへ向かった。

『かんぱ~いっ!』

風呂上がりに冷えたビールは格別である。
この味を味わうために道の駅「たかひら」で水分補給を我慢していた人も。
17時20分、満足の笑顔で溢れたバスは、静かに「かんぽの宿喜連川温泉」を後にした。

帰りのバスは、高速道ではなく、一路294号線で茨城を目指した。
18時30分、道の駅「にのみや」で最期の休憩。

車窓から筑波山が見えた。
(ピンボケなのは、決してアルコールのせいではない、と思っている)

『今日は、大変お疲れ様でしたっ!』
朝方の事故渋滞が最後まで影響したのか、自宅に着いたときには既に20時を廻っていた。
この日の天気は”午後から雨”の予報だったが、途中から日差しも差してきたのは幸いだった。
”雨の中での弁当”も覚悟していただけに、日差しの中での弁当は正直言って助かった。
蕾のレンゲツツジや盛りを過ぎたシロヤシオに何となく物足りなさを感じていたが、
最後に大間々外周歩道で見事な山ツツジのトンネルに出遭ったことで、金を払った分の元は取れた、と思っている。
昨年参加したI会長の経験・記憶が生かされた、ということである。
ミツモチ山の高原で食べた弁当は、今までで最高の味であった。
これからも常南交通社が主催するいくつかのハイキングへ参加する予定だが、
どのような昼食弁当が出るのか、大いに楽しみである。
今後もこの日の弁当級が提供されるのを期待したい。
”ウマさんの気ままなバスハイキングの目次”に戻る。