「故郷と歴史」 対談:平成7年7月
司会・構成:土居 善胤
- お話:
- 日本近代史研究家 玉江 彦太郎氏
- 聞き手:
- 福岡シティ銀行 常務取締役 別府 正之
※役職および会社名につきましては、原則として発行当時のままとさせていただいております。
司会
一枚のこの写真から、お話をうかがいましょう。この写真は今日の主人公末松謙澄(すえまつけんちょう)が数え歳二十四・五歳のときですね。
玉江
明治十一年か十二年に、ロンドンの英国公使館で上野景範公使をかこんでの写真です。
官途について三・四年目。時の実力者の※伊藤博文に目をかけられて、一等書記官見習で渡英したばかりですね。
別府
一人一人が新生日本を背負っている面(つら)がまえがいい。明治日本の夜明けを感じさせる風が吹いていますね。見ていて飽きない。
それぞれに、後年は活躍を。
玉江
大臣や公使、日銀総裁や実業界と活躍していますね。
司会
明治維新の薩摩長州の人たちの事はよく知っていても、地元出身で活躍した人たちの事はあまり知らない。今日の末松謙澄はその典型でしょう。
※伊藤博文
(天保十二1841~明治四十二1909)幼名俊輔。長州出身。公爵。松下村塾に学び維新に活躍。憲法制定に参与。首相、組閣四度。枢密院議長。貴族院議長に歴任。日清戦争講和全権大使。ハルピン駅で暗殺された。
一流のひと

玉江
慶応二年、徳川幕府の第二次長州征伐のとき、小倉藩は長州の奇兵隊に攻めこまれて城を焼いて京都(みやこ)・田川郡方面に敗退しますね。俗に御変動と呼ばれる丙寅の役(へいいんのえき)ですが、かつての幕府だから維新になってどうしても分が悪い。
その中から、末松謙澄は躍り出ている。新政府に入って一流の外交官となり、ロンドン時代に世界最初の『源氏物語』の英訳出版をして、いまも読みつがれている。政治家となり、最初の文学博士となり、逓信・内務大臣を歴任して伊藤博文の知恵袋となる。
国の興亡をかけた日露戦争では、英国で日本支持の世論を高め、その功績で子爵に列せられている。
小倉藩の出身では、陸軍に奥保鞏(おくやすかた)元帥(弘化三1846~昭和五1930)が出ていますね。この二人が歴史にのこる活躍をした巨きな人物です。謙澄が編纂した『防長回天史』は毛利藩の維新史をこえて、広く維新正史としての評価が高まっています。そして四度総理大臣になる伊藤博文の次女・生子(いくこ)の婿にもなっている。

上野景範公使(前列中央)。
富田鉄之助(後の日銀総裁、前列右端)
末松謙澄(後列右端)。
別府
まことに壮観ですね。ではその末松謙澄の出生から。
玉江
今から百四十年前の安政二年に、豊前国京都郡前田村(現、福岡県行橋市)の大庄屋、末松七右衛門(房澄)と母伸子の四男として生まれています。男女五人ずつの十人兄弟でした。
幼名を千松、線松とも言います。のちに謙一郎、さらに謙澄とあらため、「のりずみ」のつもりが皆が「けんちょう」と呼ぶので、サインもK.Suyematsuに。号は青萍(せいひょう)、青い水草の意です。父の七右衛門は臥雲の号を持つ歌人でした。
別府
幼時から学問尊重の家風の中に育ったのですね。大庄屋の坊ちゃんで、大事にされて…。
玉江
でも幼いときから鼻っ柱が強かったようですね。頭を剃「そ」られるのが大嫌い、それで寝ているときに剃ったら、癇癪をおこしては生「は」やしてかえせと周りを困らせたようです。
別府
勉強のほうは。
玉江
十一歳のとき村上仏山という漢学者の塾、水哉園(すいさいえん)に入門しています。同年、二十四人の入門者がおり、筑前筑後、遠くは肥後あたりからも来ていたほどですから、仏山は名声が聞こえた大先生だったのです。
別府
そして漢詩がまた絶品とか。
玉江
仏山先生の影響が大きいのですね。御変動のどさくさで家が暴民に焼き打ちにあって、一家離散になる。
そのとき仏山先生が線松少年を自分の家に引きとり、戦乱のおさまるまで7カ月間親身の面倒を見てくれる。この間の感化は大きかったでしょうね。
別府
数えの十二歳の頃ですね。人物をつくるのは、幼少期の試練が大切なのかなあ(笑)。
父臥雲の国学、仏山の漢学、上京しての洋学と、やはり時代が必要とする人物は、時代が育てるんですね。
生涯の友高橋是清
司会
謙澄が青雲の志を抱いて上京したのは明治四年、十七歳のときですね。
玉江
大庄屋も焼き打ちにあって、四男坊主の上京までは、とても手がまわらなかったでしょうね。後年「学ブニ常師ナク、居スルニ定マル処ナシ。落魄シテ都門ニ過スコト数年」と述懐しています。
上京して開明派の漢学者として知られた大槻盤渓(おおつきばんけい)(享和元1801~明治十1877)や、洋学者の近藤真琴(天保二1831~明治一九1886)の※攻玉社(こうぎょくしゃ)の塾にも通い土佐出身の顯官、佐々木高行(後侯爵)の書生になっている。これから運命の出会いが始まるのです。
※攻玉社
攻玉社は近藤真琴が、外国の石(洋学)を砥石にして玉(大和魂)を攻「みが」くということで塾名とした。福澤諭吉の慶応義塾、中村正直の同人社と並んで明治の三塾の一つ。海洋学の専門塾で、日清、日露戦を指揮した将星たちは攻玉社出身が多い。
別府
興味津々ですね。
玉江
明治新政府は、西洋に追いつくことが一番と、たいへんな高給で外人教師を招聘(しょうへい)していました。その一人がアメリカ宣教師フルベッキです。
開成学校(のち大学南校→東京帝国大学)の教師で、教育、法律、行政に献策。岩倉遣外使節派遣、徴兵令、学制制定への貢献が大きかった人です。
この人のところに、のちの日銀総裁、総理大臣の高橋是清(たかはしこれきよ)がいたのですね。佐々木の令嬢静衛(しずえ)がフルベッキの娘さんに英語を習いにくる。そのお伴が謙澄で、高橋が話しかけて懇意になった。
その頃、東京師範学校が設立され、官費学生を募集しました。謙澄はその難関をパスするのですが、是清が君は広い天地で活躍する人だ、先生でしばられるなと辞めさすのです。
それから、謙澄は漢学、是清は英語の交換授業を始めるのです。レッスンは最初からパレーの万国史だったそうで、すごいものです。
別府
明治の若者の意気溌刺(はつらつ)さが感じられる風景ですね。
玉江
高橋是清は後年、その風貌からダルマ蔵相と親しまれますが、昭和十一年の二・二六事件で陸軍若手将校の凶弾にたおれます。謙澄より一歳上で、ともに十八・九歳の出会いです。
ところが師範中退で佐々木夫人がおかんむり。官費のいい学校に受かったのに、辞めるような我儘者は世話できない…と。それで高橋のところに転がりこむのです。
別府
それでは交換授業は成果があったでしょうね(笑)。
玉江
そのときに謙澄は退学記念写真を浅草の写真館で撮っているから意気軒昴たるものですね(笑)。
※攻玉社
攻玉社は近藤真琴が、外国の石(洋学)を砥石にして玉(大和魂)を攻「みが」くということで塾名とした。福澤諭吉の慶応義塾、中村正直の同人社と並んで明治の三塾の一つ。海洋学の専門塾で、日清、日露戦を指揮した将星たちは攻玉社出身が多い。
「この御仁は」と伊藤博文

伊藤博文
別府
それはそれで生計の方は(笑)。
玉江
そこで二人の着想がいい。明治開化で次々と新聞が発刊されているが、外国事情をのせている新聞がない。フルベッキ先生の所には英米の新聞がたくさん来る。特にロンドンの絵入新聞は面白い。あれを翻訳して売り込めば商売になると。
これは名案だと売り込みにまわったが次々と断られて、やっと岸田吟香(きしだぎんこう)の東京日日新聞が買ってくれた。甫喜山景雄(ほきやま)という人が君等は一カ月いくらで暮らせるのかときくので、五十円だと答えたら月々五十円をくれたそうで、愉快ですね。
その縁で明治七年に東京日日新聞の日報社に入社するのです。高橋も文部省の役人になっていて彼の芝の家に同居し激論を交わす。それがペンネーム笹波萍二の社説となったのです。
別府
田舎出の若者が自力で道を拓いた。ほっとしますね(笑)。
玉江
それが数えの二十歳ですからね。
ところがすぐに福地源一郎(桜痴)が主筆として入社するのです。福地は長崎の人で、幕府の外国方に出仕して遣外使節に随行し、新政府の岩倉遣外使節にも同行している。明治を代表する言論人です。
謙澄はあんな大物がきたのでは、自分の前途がないから、辞めようと言いだす。是清は「大物が入れば師事すればいい。それだけ君の前途がひらける」と激励するのです。
別府
もつべきはよき友ですね(笑)。
玉江
福地は紙面一新をはかって、社説欄を設け、二十歳の謙澄を執筆者に抜擢する。「笹波萍二」の誕生です。
そして彼の書いた*「元老院批判」「教務省廃止論」などが、ときの権力者伊藤博文や、山縣有朋(やまがたありとも)の目を引くのです。
別府
明治という若い時代のたぎりを感じますね。
玉江
入社早々の頃でしょうが、東京日日の首脳の回顧では、ハイカラ謙澄は弁当に牛乳をかけて食べていたそうで、不思議な事を思ったそうです。
福地は、謙澄をつれて銀座へよく食事に出かけていました。あるとき、官員馬車がとまり、先生と声がかゝる。声の主は伊藤博文で、二言三言。そして「この御仁(ごじん)は」ときく。
福地が豊前出身で論説の末松謙澄と紹介。伊藤は笹波萍二の論説に関心をもっていたし、隣国豊前人に親しみを覚えて「遊びに来られよ」と誘うのです。
別府
決定的な運命の出会いですね。その博文もまだ、三十五・六歳ですね。
玉江
博文は訪問した謙澄を歓待して、ストックホルムで買ってきた「ローマ史論」を記念にくれる。それから山縣有朋ともつながるんです。
別府
長州出身の二人は、自分たちが攻めこんで、城の焼滅、幼主をかついでの敗退となった、小倉藩への償いの気持ちも…。
玉江
あったかもしれませんね。
山縣有朋とも「給料を倍出すから俺の所へ来い」「福地への恩義があるから、それはできない」。そうした問答があってさらに目をかけられたそうです。
別府
そのふれあいから謙澄が官途につくのですね。
玉江
明治八年十二月二十八日の事で新聞人笹波萍二の活躍はわずかに二年でした。
そしてすぐに江華島問題解決のため、黒田清隆全権を補佐する井上馨に随行して渡韓し、修交条約の起草に加わります。二十一歳、出仕して翌日の渡韓です。驚きますね。
謙澄の記によればこのとき、井上が近々英国へ派遣されるので「足下同行の意アルヤ。アラバ随行セシメン」と言う。謙澄は「小子洋行ノ志此ニ年アリ。閣下モシ随行ヲ許セバ豈(あに)之ヲ辞センヤ」と随行を頼むのですね。
ところが、なしの礫(つぶて)で、井上は外の人間を連れて行く。約束違反だと面白くないのでたてつくが、いくら鼻っ柱の強い謙澄でも相手が、伊藤博文の盟友井上では歯がたたない。(笑)。
- ※山縣有朋
(天保九1838~大正十一1922)長州出身、前名狂介。陸軍元帥、公爵。松下村塾に学び、維新に活躍。徴兵令を制定。内相、首相を歴任。日清・日露で功をたて、後に枢密院議長。元老として権力をふるった。 - ※井上馨
(天保六1835~大正四1925)通称聞多「もんた」。侯爵。長州出身。維新に活躍。外相、農相、内相、蔵相を歴任。後年元老。
西南の役へ
別府
それから明治十年の西南役ですね。
玉江
征討総督本営付を命じられる。山縣有朋の引き抜きですね。有朋の幕下に入った謙澄は得意の健筆をふるいます。
城山にこもった西郷さんへあてた山縣有朋の降伏勧告状は情理を尽くした一世の名文ですが、謙澄の筆になるとも言われています。
司会
このあたり、司馬遼太郎さんの名作『翔ぶが如く』でも圧巻で、〈「辱知生(じょくちせい)山縣有朋、頓首(とんしゅ)再拝、謹デ西郷隆盛君ノ幕下ニ啓ス。有朋ガ君ト相識(し)ルヤ、茲(ここ)ニ年アリ。君ノ心事ヲ知ルヤ蓋(けだ)シ又深シ」という文章ではじまっている。
格調はかならずしも卑(ひ)くなく、後年、冷酷と老獪(ろうかい)をもっておそれられた人物とおなじ人間が書いたかとさえ疑われる。山縣は年まさに四十であった。多少の若さを残し、多少の感傷とみずみずしさを残しつつ、暮夜、幕営の灯のもとで、西郷を想う気持の昂(たかぶ)りを懸命に抑えつつ書いている光景が、目にうかぶようである。〉(文藝春秋刊)とありますね。
玉江
勧告文を続けましょうか。「窃(ひそ)カニ有朋ガ見ル所ヲ以テスレバ、今日ノ事タル、勢ノ不得已(やむをえざる)ニ由(よ)ルナリ。君ノ素志ニ非ルナリ。有朋能(よ)ク之ヲ知ル。」(略)
「君が人生ノ毀誉(きよ)ヲ度外ニ措(お)キ復(ま)タ天下後世ノ議論ヲ顧ミザル而巳(のみ)。嗚呼(ああ)君ノ心事タル寔(まこと)ニ悲シカラズヤ。有朋、コトニ君ヲ知ル深キガ故ニ君ガタメニ悲シムコトマタ切ナリ。」(略)「ソレ一国の壮士ヲ率イテヨク天下ノ大軍ニ抗シ劇戦数旬百敗撓(たゆ)マザルモノ既ニ以テ君ガ威名ノ実ヲ天下ニ示スニ足レリ」(略)
「願ハクバ、君早ク自ラ図(はか)リテ一ハコノ挙ノ君ガ素志ニアラザルヲ明ニシ、一ハ両軍ノ死傷ヲ明日ニ救フ計ヲナセ。(略)故旧ノ情有朋切ニコレヲ君ニ翼望(きぼう)セザルヲ得ズ。書ニ対シテ涕涙(ているい)ノ如ク、イワムト欲スルコトヲモ悉(ことごとく)スアタワズ。君幸二少シク有朋ガ情懐ノ苦ヲ察セヨ。涙ヲ揮(ふる)ウテ之(これ)ヲ草ス。書、意を悉(つく)サズ。頓首再拝」とあります。
司馬さんによれば、「山縣はこの手紙をさきに人吉の段階で書き、それを多少あらたに筆を加えたらしい」とあります。
有朋は歌人、散文家としても出色の人でしょう。そして周辺に謙澄が補佐していた。一幅の絵がうかびますね。
ロンドン八年















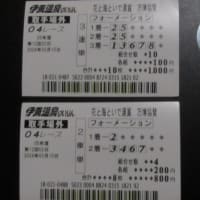
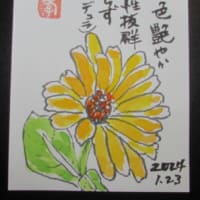









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます