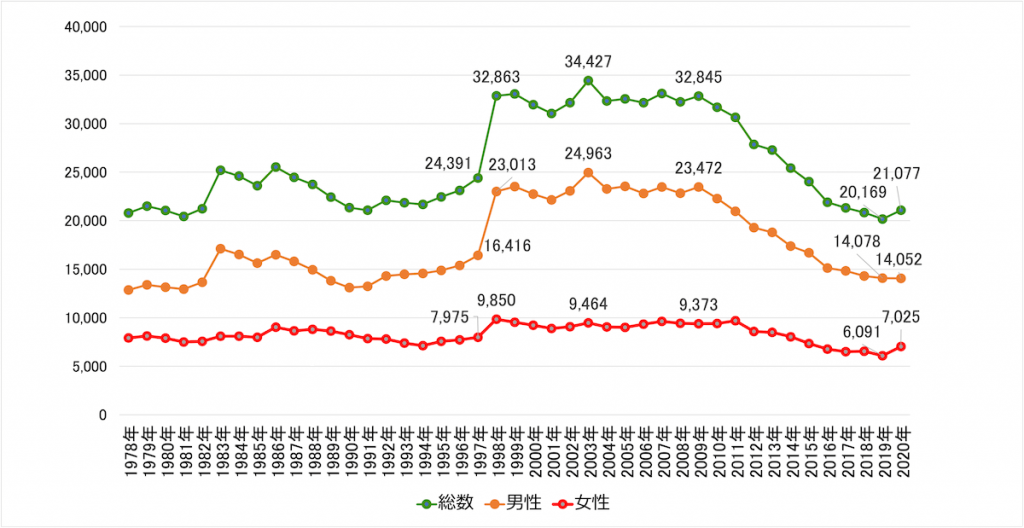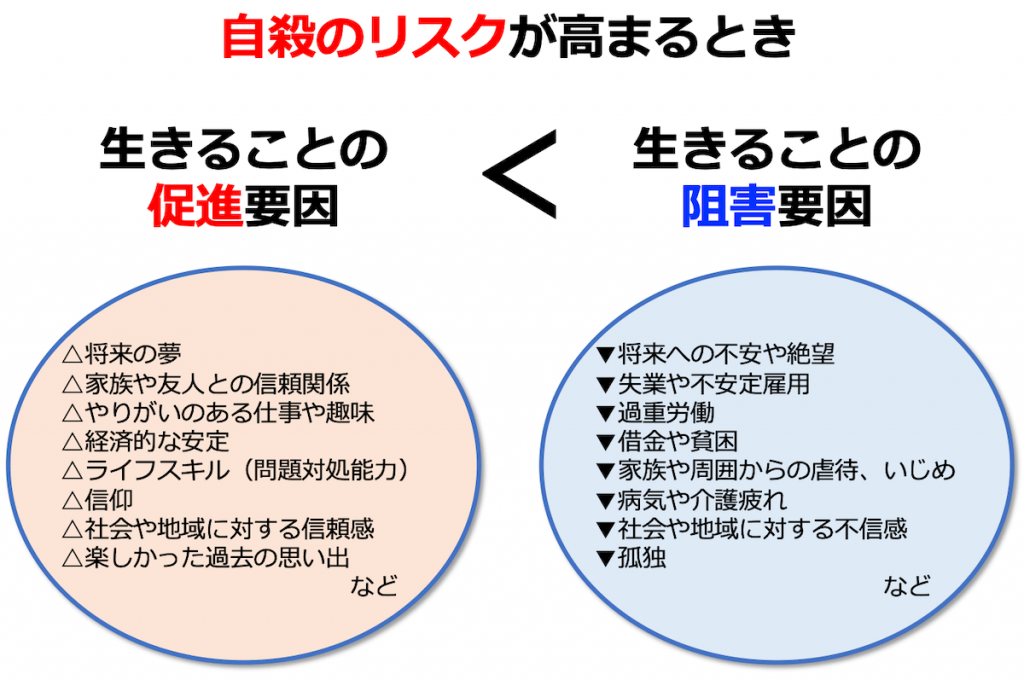一人一人が「主体性」をもって、健全な民主主義を取り戻すためには、何が必要でしょうか?
財政学者で東京大学名誉教授 神野直彦さん
そのキーワードとして「教育」が挙げられるます。
人間を手段化するためではなく、一人一人の「人間的能力を開花させる教育」こそが、日本を根底から創り直す最も確かな道です。
日本が「民主主義の危機」に陥った原因の一つに一つに、「中間層の衰退」があります。
日本社会では、貧困層が広がる一方で、ごく一部の富裕層が圧倒的な富を手にするという、極端な不均衡な構造が形成されつつあります。
こうした社会では、民主主義が健全に機能しなくなります。
歴史的に見ても、民主主義は安定した中間層の存在が前提に成立してきました。
互いの利益が調整され、公共の意思が成り立つのもは、共通の土壌があってこそです。
新自由主義では市場経済のもたらす格差は、積極的に肯定されます。
所得の格差は「その人の能力」を反映しているから公平である―と。
それはつまり、「あなたが貧しいのは、あなたの能力が足りないからだ」と言っているのと同じです。
日本ではこれまで、できるだけ職務を単純化し、賃金を抑制することで国際競争力を高めようとしました。
それにより非正規従業員は増え、ますます所得格差が広がったのです。
新自由主義は、この考え方を正当化するため、学校教育にも「競争原理」を浸透させていきました。
子どもたちにテストの点で競わせ、貧しくなりたくなければ、成績を良くして、偏差値の高い大学に入って、給料の良い会社に就職して・・・という幻想を教え続けたました。
市場における効率性を優先するあまり、人間を「魂を持った存在」としてでなく、「使えるか・使えないか」という有用性で評価するようになってしまった。
もちろん、成長する上で「競争」も大切な要素です。
しかし、そればかりが過度に強調され、「「協力すること」の価値を教える機会が減ったことに問題があるのです。
また、「この問題」には「こう答える」と機械のようにインプットして、それを再現することが、学校教育の評価軸になってきました。
「なぜそうなるのか」「それについて、どう思うか」よりも「何年に何が起きたか」と言った事実の断片ばかりを丸暗記させられてきたのです。
かつて、経済学者の正村公宏先生は小・中学校教育における最も重要な目的は「みずから社会を構成する主体となる力を身につけさせること」と指摘しました。
しかし、新自由主義的な暗記型の詰め込み教育では、そのような主体性が育つわけがありません。
人間を「機械化」していくのですから「主体性」が失われいくのは当然です。
「経済の父」と謳われたアダム・スミスもまた、教育は「職業に就くための手段」としてよりも、「受けること自体」に意味があると強調しています。
政府が教育を提供する意義は、生産性が分業化され、労働が単純化することによって生じた社会の亀裂を解消し、社会統合を実現してところにあると考えていたのです。
「教育」の語源であるラテン語の「エデュカチオ」には「引き出す」という意味があります。
教育は本来、単に知識を詰め込んでいくものではなく、「その人らしさ」を引き出し営みです。
東大名誉教授の折原浩先生は、教育の手法を「盆栽型」と「栽培型」に分け、対比されました。
盆栽型は、子どもを<型にはめる>教育です。
盆栽の枝を、曲がりたくない方向に針金で矯正するように、子どもの個性や可能性を無視して基本的訓練だけを徹底し、一定の型に押し込めていく手法です。
一方、栽培型は、子どもが伸びたい方向を重んじ、サポートする教育です。
あらかじめ決められた<理想像>に従って育てるのではなく、その子の関心や好奇心を内面から引き出すよに行われる手法です。
経済学者で東大名誉教授だった宇沢弘文先生もまた、教育は「人間として成長することをたすけるもの」として、「栽培型」の教育観に立っていました。
宇沢先生が人間を生産要素に過ぎないとみなす人的資本論を、きわめて非人間的、反社会的だと痛烈に批判されました。
アメリカの哲学者ジョン・デューイの教育哲学を継承する宇沢先生は、学校教育における「社会的統合の原則」を強調されていました。
教育において最も重要なのは、異なる背景をもつ子どもたちが、学校という同じ空間に集い、共に学び、遊ぶ中で、<同じ仲間なんだ>という意識を育んでいくことである―と。
<共に生きる感覚>を養うことこそが、学校教育の目的であるということです。
競争原理を植え付けようとする新自由主義は、まさに真逆のことをしているわけです。
学校教育は「協働的」「互恵的」な学びを重視し、拡充する必要があります。
その上で、学校教育が基軸となって、社会全体の教育的機能をもつ、つまり、誰もが何度でも学び直せる「学びの社会」を創りあげていくことが重要です。
学びの社会の柱には「シティズンシップ教育」—市民として積極的に社会に参加し、責任ある行動を取るための知識や能力を育む教育―を据えることが大切です。
スウェーデンでは社会全体で「教育の場」を創りだしています。
地域の人々が主体的に参加する学びび場として「学習サークル」が開かれ、語学、音楽、文学などを自主的に学び、政治や社会、生活について話す機会が生まれている。
社会と生活と学びが分かちがたく結ばれているのです。
このようなサークルは民主的な方法で運営されており、地域に根差した学習の営みが民主主義を支えています。
人間は本来、「学びの人」であり、仲間と学び合いながら「自己変革」を遂げる主体です。
「学びたい」という内発的な意欲を丁寧に引き出していくような環境が今、求められています。
せっかく、民主的なシステムがあっても、形骸化したり、皆が不幸になっていく方向に流されたりしては何の意味もありません。
「学びの社会」を創るということは、「人間が人間として生きることができる社会」を実現することです。
人は「学ぶ」ことで、人間として高まり、喜びを感じます。
「学び合う」ことで、その喜びは倍加し、主体性をもつ人の連帯が広がります。
その中で民主主義は健やかに育ち、「賢い財政」を実現していくことができるのです。
「学びの社会」を創るために欠かせないのは「誰でも、いつでも、どこでも、ただで」の原則です。
特に大切なのは「ただで」ということ。
経済的な貧富の差によって、「学びの機会」が奪われることがあってはなりません。
誰でも、いちでも、何度でも学び直せる社会を創る。
そのためには「無償」が必須要件なのです。
社会の一員として自分の役割を問い直す「学び直しの場」が必要です。
「リカレント教育(学校教育を終えた後も生涯にわたって学び続け、必要に応じて就労と学習を繰り返すこと)」を地域・社会にどう広げていくかが、重要な課題となるでしょう。
その点において、宗教は、地域ごとに人と人を結び、学びや語らいの場を提供し、共により良い社会を模索していくための土壌になってきた歴史があります。
日本
 </picture>
</picture>









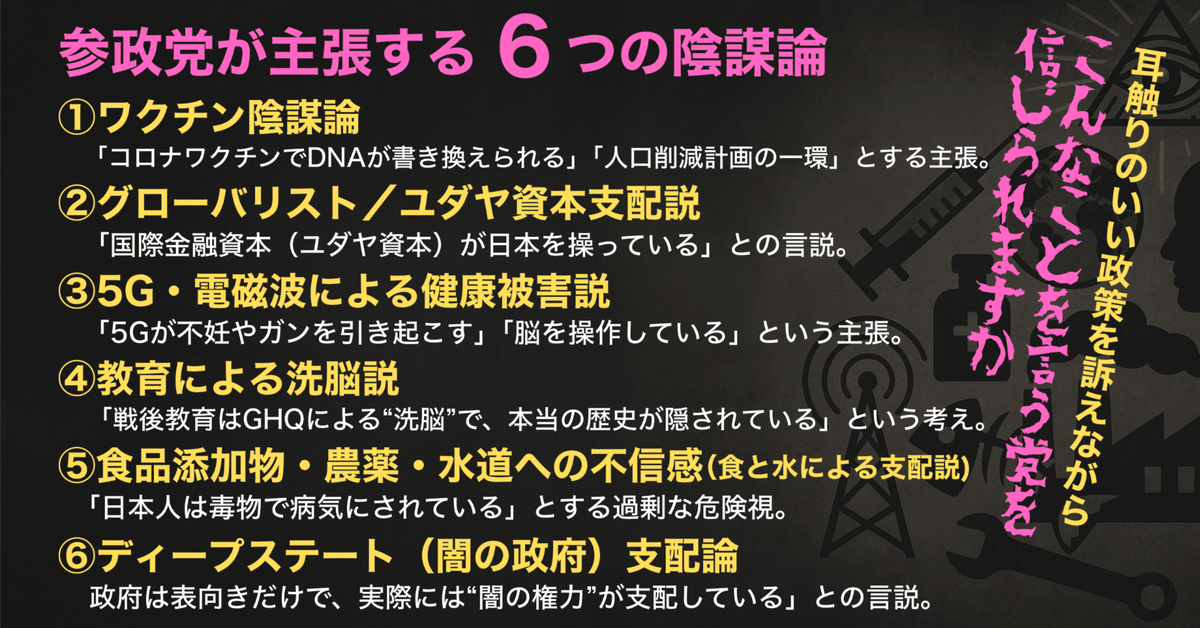


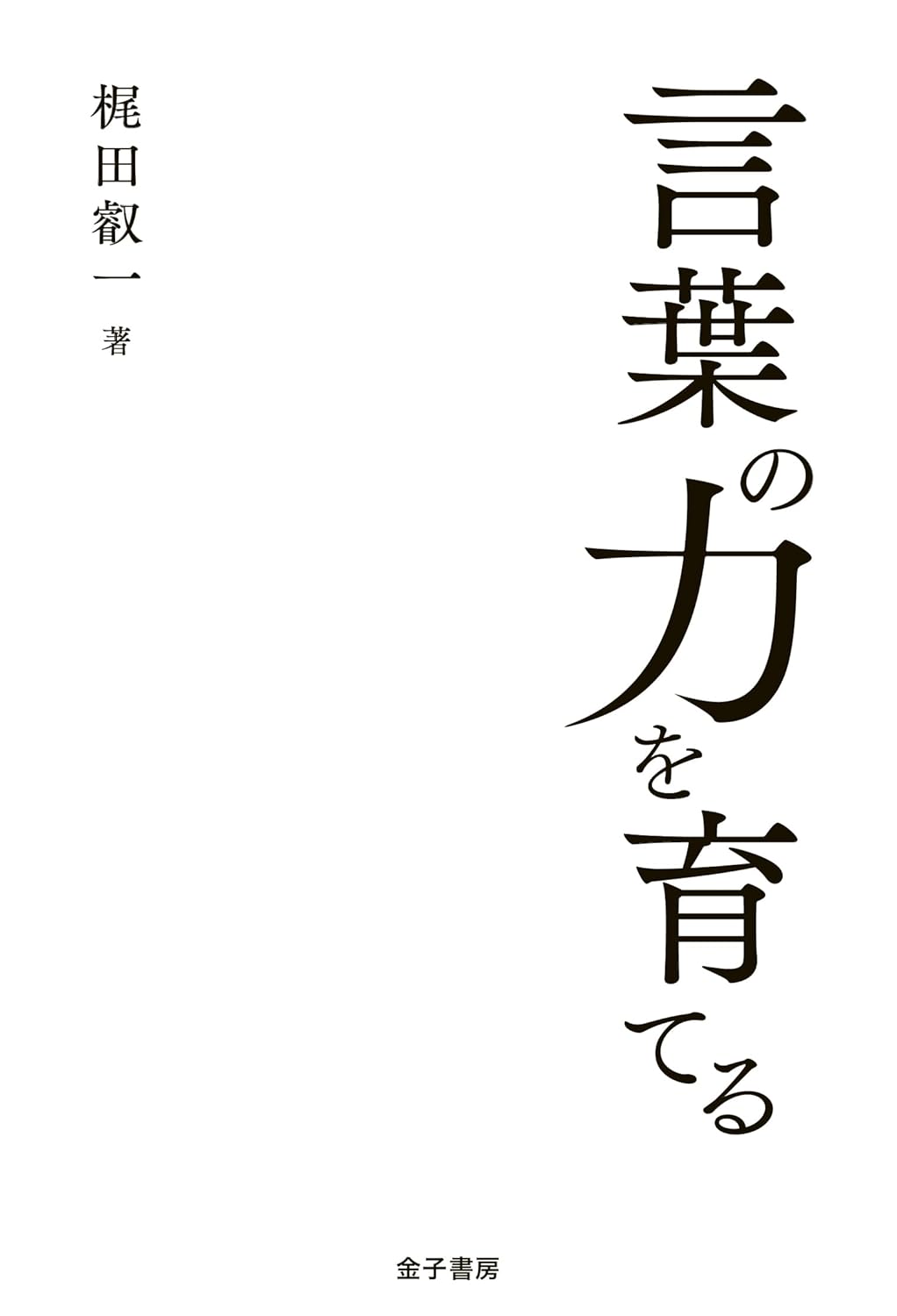











 </picture>
</picture>