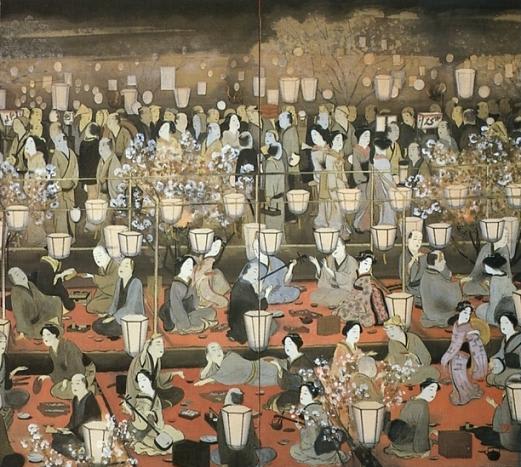野口謙蔵『五月の風景』

何と思い切った、大胆な風景画だろう。絵のほぼ中央を、一直線に地平線が横切る。前景には青々とした麦畑が、爽やかな微風に波打ちながら広がっている。快晴の空にはひと筋の雲が流れ、恵みの光がさんさんと降ってくるかのようだ。
そして天と地の間には、ぽつんと取り残されたように家々が描かれ、屋根の上には鯉のぼりがそよいでいる。日本のどこかの農村の、おおらかな五月の情景・・・。
***
それにしても、不思議な絵だ。使われている色の数は、非常に少ないように見える。描き方も、それほど細やかというわけではない。しかし画面からは広大な自然の豊かさ、思わず息を吸い込みたくなる豊饒な初夏の薫りが伝わってくる。
とはいうものの、ここには人間の手がまったく入っていない天然の大自然は、いっさい描かれていないのだ。整然と植えられた麦畑は、まるで緑色の壁のようにも見え、一種人工的なおもむきがする。この畑はもちろん村の人たちによって栽培され、きたるべき収穫を期して大切に育てられているのだろう。
現代の人は自然のかけらもない都会生活に飽きると、生まれたままの地球の姿を求め、アウトドアと称してわざわざ山に登ったり、小川のせせらぎの横でテントを張ったり、船に乗って沖へ出たりする。しかし昔の日本人は、自然とうまく共生することを知っていて、家を一歩出れば田畑がまわりに広がっていた。かつてはぼくも田舎に暮らしていたので、このような風景は少し歩けばいくらでも転がっていたものだが、そんな生活から遠く離れた今となっては、この絵に一抹の郷愁をそそられるほどになってしまった。
***
ここに描かれているのは、滋賀県の蒲生野と呼ばれるあたりの風景らしい。洋画家・野口謙蔵はその地に生まれ、東京で黒田清輝らに学ぶが卒業後は故郷に戻り、死ぬまで滋賀の風景や人々を描きつづけた。
全国的にはそれほど知られている画家ではないかもしれないが、郷里の美術館には作品がいくつも収蔵され、復元された生前のアトリエも公開されているそうだ。ぼくは7年ほど前に、彼の代表作を網羅した大きな展覧会を観たことがあるのだが、いずれも日本洋画の常識から大きく逸脱した、個性的な作品ばかりなので驚いた。
謙蔵の伯母は野口小蘋(しょうひん)という南画家で、謙蔵自身も一時は日本画を学んだことがあるというから、黒田清輝らのいわゆる外光派の影響を正当に受け継いでいるとはいいがたい。留学経験もない彼は、日本ならではの農村風景や、村で暮らす人々の生きざまを描くための手段を、誰の助けも借りないでひとりで追求したかに見える。
しかし、病魔が謙蔵を襲った。「新文展」(現在の「日展」の前身)の審査員に任命された翌年、道半ばで彼は倒れる。43歳の若さだった。
野口謙蔵がもう少し長生きしていたら、必ずや日本を代表する洋画家のひとりになっていたにちがいないと、ぼくは信じる。
(滋賀県立近代美術館蔵)
五十点美術館 No.17を読む

何と思い切った、大胆な風景画だろう。絵のほぼ中央を、一直線に地平線が横切る。前景には青々とした麦畑が、爽やかな微風に波打ちながら広がっている。快晴の空にはひと筋の雲が流れ、恵みの光がさんさんと降ってくるかのようだ。
そして天と地の間には、ぽつんと取り残されたように家々が描かれ、屋根の上には鯉のぼりがそよいでいる。日本のどこかの農村の、おおらかな五月の情景・・・。
***
それにしても、不思議な絵だ。使われている色の数は、非常に少ないように見える。描き方も、それほど細やかというわけではない。しかし画面からは広大な自然の豊かさ、思わず息を吸い込みたくなる豊饒な初夏の薫りが伝わってくる。
とはいうものの、ここには人間の手がまったく入っていない天然の大自然は、いっさい描かれていないのだ。整然と植えられた麦畑は、まるで緑色の壁のようにも見え、一種人工的なおもむきがする。この畑はもちろん村の人たちによって栽培され、きたるべき収穫を期して大切に育てられているのだろう。
現代の人は自然のかけらもない都会生活に飽きると、生まれたままの地球の姿を求め、アウトドアと称してわざわざ山に登ったり、小川のせせらぎの横でテントを張ったり、船に乗って沖へ出たりする。しかし昔の日本人は、自然とうまく共生することを知っていて、家を一歩出れば田畑がまわりに広がっていた。かつてはぼくも田舎に暮らしていたので、このような風景は少し歩けばいくらでも転がっていたものだが、そんな生活から遠く離れた今となっては、この絵に一抹の郷愁をそそられるほどになってしまった。
***
ここに描かれているのは、滋賀県の蒲生野と呼ばれるあたりの風景らしい。洋画家・野口謙蔵はその地に生まれ、東京で黒田清輝らに学ぶが卒業後は故郷に戻り、死ぬまで滋賀の風景や人々を描きつづけた。
全国的にはそれほど知られている画家ではないかもしれないが、郷里の美術館には作品がいくつも収蔵され、復元された生前のアトリエも公開されているそうだ。ぼくは7年ほど前に、彼の代表作を網羅した大きな展覧会を観たことがあるのだが、いずれも日本洋画の常識から大きく逸脱した、個性的な作品ばかりなので驚いた。
謙蔵の伯母は野口小蘋(しょうひん)という南画家で、謙蔵自身も一時は日本画を学んだことがあるというから、黒田清輝らのいわゆる外光派の影響を正当に受け継いでいるとはいいがたい。留学経験もない彼は、日本ならではの農村風景や、村で暮らす人々の生きざまを描くための手段を、誰の助けも借りないでひとりで追求したかに見える。
しかし、病魔が謙蔵を襲った。「新文展」(現在の「日展」の前身)の審査員に任命された翌年、道半ばで彼は倒れる。43歳の若さだった。
野口謙蔵がもう少し長生きしていたら、必ずや日本を代表する洋画家のひとりになっていたにちがいないと、ぼくは信じる。
(滋賀県立近代美術館蔵)
五十点美術館 No.17を読む