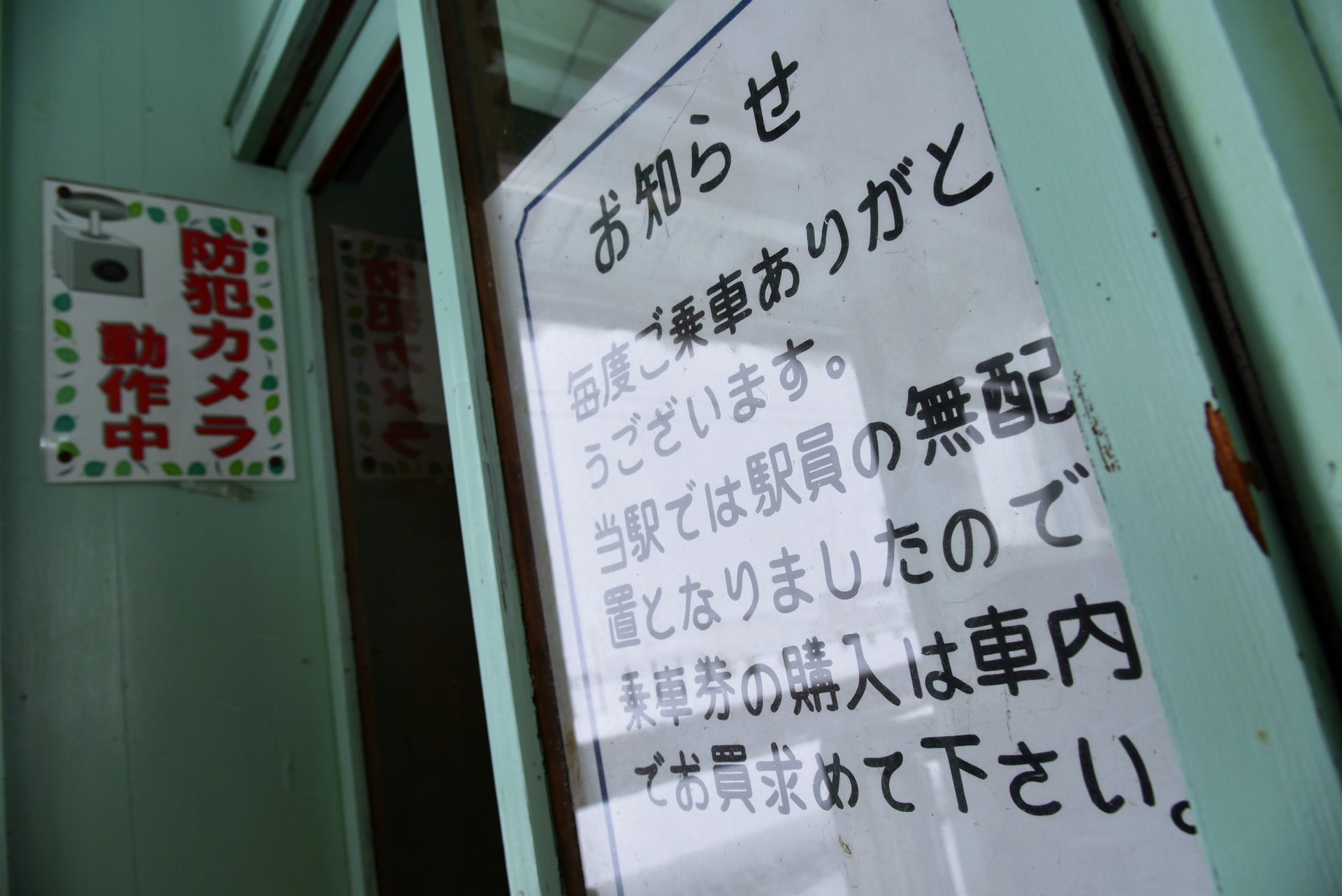(束の間の青空@釜ヶ淵~沢中山間)
大雪の黒部平野から大きく場面転換して、常願寺川が作り出す富山平野へ。この日の午後は立山線を狙いに行きました。お馴染みの鋳物師沢の陸橋。このポイント、陸橋の下にクルマを置けるスペースがあるのだが、そこには農家さんの農機具が置かれていた。冬の間、陸橋の下は農機具を雪から守るための車庫代わりになっているらしい。駐車スペースまで入る細道が除雪されてなかったらどうしようかなと思ったのだが、何とか道は通じていて一安心。もう何度となく立った陸橋のお立ち台は、遠く富山湾を見晴るかす眺望が売り。春の田植えと早苗の頃、夏の青々とした田園風景、初秋の黄金の稔りと季節ごとの顔がありますけども、この時期は一面の雪野原で、またひときわ美しいですねえ・・・。この雪が表土を守り、土壌を潤し、低温下で雑菌を消毒して清浄化し、秋の豊かな実りに繋がって行く訳だ。雪の中の二条のレール、遠くから微かに踏切の音。赤い矢が一矢、山へ向かって上って行きました。

そうそう、最近のコメの高騰ね。近所のスーパーでの売価が5kgで税込み4,000円を超えていて、巷では投機的な動きの中でブローカーが買い占めているのだとか、外国人が儲かるからと農家から直接コメを買い付けているのだとか、本当なのかどうなのか真偽不明の流言飛語が飛び交っております。そういった話も全くの嘘ではないんでしょうが、そもそもが昨年来コメが足りていなかったのではないか・・・?というのが通説になりつつあります。去年の秋の「新米が出てくれば価格は徐々に安定する」という農水大臣の談話も今となっては虚しく、今回の令和の米騒動、何のことはない「政策の失敗とそもそもの需要の見誤り」ということなんでしょうね。それもこれも半世紀に近づこうかという期間続けられた政府の減反政策は、作らなくても儲かるといういびつな状況を生み出し、補助金漬けで自立するチカラのなくなってしまったコメ農家と、就労世代がどんどん高齢化し、新規参入の起こらない構造を生み出してしまいました。コメ農家の衰退ってのが、結局現代日本の抱える「地方の衰退と過疎化」の元凶のひとつ。今になって「食糧安全保障!」とか言い始めた経済右派の方々には、ぜひともここに強力なテコ入れと人員の投入を図っていただきたいものである。
そう言えば、大正時代に米騒動が起こったのはこの富山県の魚津の街でしたね。魚津に行くと、「米騒動発祥の地」なんて看板が掲げられているらしいのだが、そんなもんの発祥の地はなくてもいいんであって(笑)。政府もコメ高騰対策に対して遅きに失した感のある備蓄米の放出などを始めましたが、あんまり国民を飢えさせるとそれこそ農林水産省の打ちこわしが起こっちゃうかもしれませんよ。