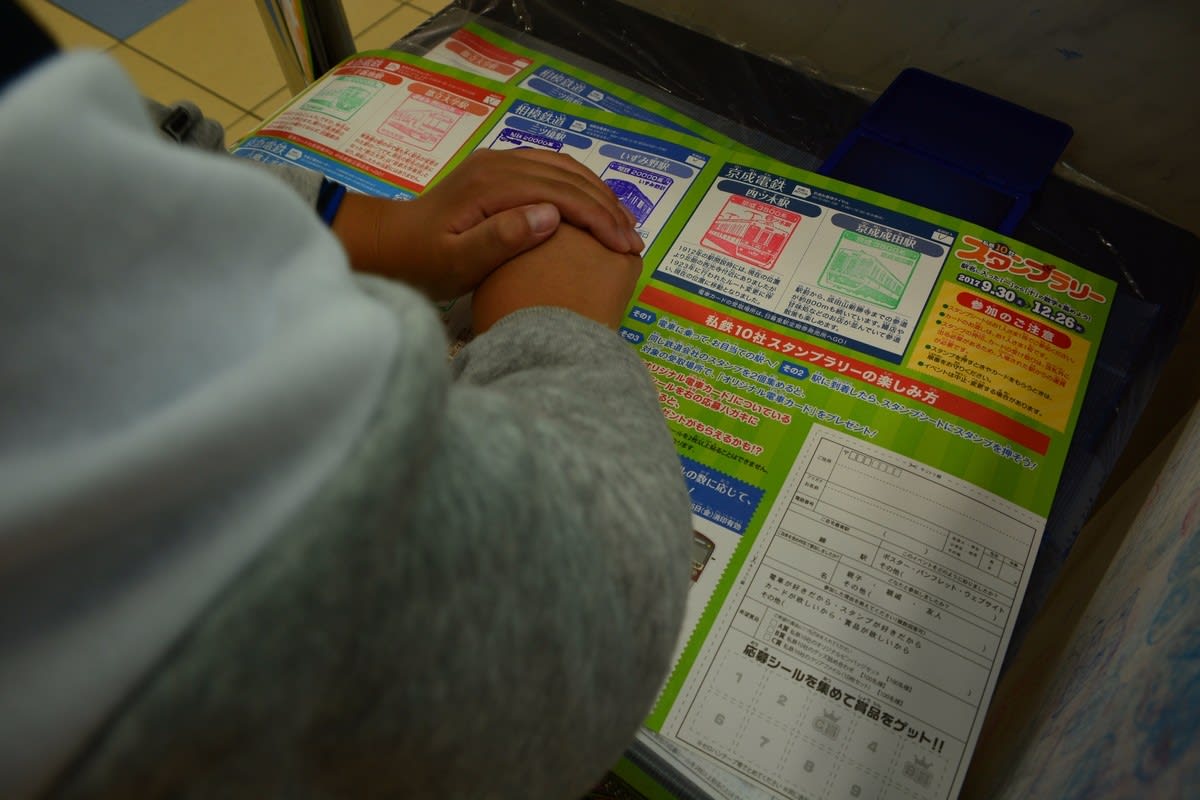(今日も元気だご飯が美味い@湯野上温泉某民宿)
湯野上温泉の朝。旅先の朝は、どうしてこうもメシが進むのだろうか。普段会社に行ってる時なんか置いてあるパンかじったりコーヒー飲んだりするくらいで、まともにメシなんか食ってないもんなあ。塩サバとか目玉焼きとかのありふれたおかずだけど、新米の会津コシヒカリとキノコたっぷりの味噌汁がめっぽう美味い。今日もしっかりメシを食って、元気に乗り鉄に勤しむ一日になりそうです。
湯野上温泉は、阿賀川(大川)沿いの渓谷に開かれた温泉郷ですがその歴史は古く、奈良時代から阿賀川の河原に湧き出る湯が使われていたそうです。駅から歩いて15分程度の場所にある温泉街は歓楽要素のない田舎のひなびた温泉場、という感じですが、渓谷に面した場所には新しめの立派なホテルもあったりします。以前は阿賀川の河原に無料の露天風呂があって「湯野上温泉露天風呂」の名前で親しまれていたのですが、訪問客のマナーが悪くて閉鎖されちゃったんだそうな。今は河原にその残骸が残るのみ。
宿の裏手にある阿賀川の渓谷にかかる吊り橋の上から温泉街と会津鉄道の線路を望みます。さすがに会津の朝は寒く、吊り橋の踏み板と欄干が白く凍っている。朝一番の下り列車は鬼怒川温泉行きAIZUマウントエクスプレス2号、まだ日の差し込まない暗い湯野上の温泉街を行く。始発列車が7時半とはずいぶんと遅い始発列車だが、会津田島方面への通学需要とかないのかしら。
ちょっと早めに宿を出て、ご主人にクルマで駅まで送っていただく。クルマの温度計は氷点下3度を示しており、結構冷え込んだようだ。朝の湯野上温泉駅では、茅葺きの駅舎内で囲炉裏に火が入っていたんですが、火を焚いても寒い。駅舎の中でお土産物なんかを眺めながら列車を待っていると、底冷えする朝の待合室に飛び込んで来たおばちゃんが旅行姿の我々を見付けて「この時期の寒いのはやぁ~ねぇ~!雪でも降ってくれたほうがよっぽどマシだわ!」と話しかけて来た。そんなもんなのかね。
茅葺き屋根にも霜が降りた南会津の白い朝。湯野上温泉を8時半に出るAIZUマウントエクスプレス4号で本日のスタート。昨日鬼怒川温泉から中三依まで乗った編成かな。会津若松を8時前に出て、東武日光に11時ちょうどに着くダイヤ。「快速」と銘打たれていても通過するのは会津田島~会津高原尾瀬口間の各駅と男鹿高原のみなので、あまり速達性はありません。
さて、東武日光行きの快速に乗ってどこまで行くのか…と思わせておいて次の駅であっさり降りてしまうテスト。暖房の効いた車内から再びしばれる寒さのアウトドアに逆戻りだ。子供がブーブー言っている。下車したのは湯野上温泉のお隣・塔のへつり駅。阿賀川が刻む渓谷の奇勝と言う事で、名前だけは知ってたんだけど行った事はなかったのでね。まあご存知かとは思いますがアタクシ割と地形マニアっぽいトコロがあるのでこの手の観光地には目がないのだ。
そもそも「塔のへつり」とは何ぞやと言う事なんですけど、なんか語感だけで言えば椎名へきるの親戚みたいな感じも致しますが漢字で書けば「塔」の「岪(へつり・山かんむりにドル)」。この「へつり」とは、「断崖・がけ」を意味する会津方言なのだとか。ちなみに自分は子供の頃「塔のへ」「つり」だと思ってました。なんか釣り場とか吊り橋のイメージがあったもんで(笑)。「塔のへつり」のアクセントは「正司敏江」と同じと思っていただけると分かりやすいかと(笑)。

紅葉の時期にはかなりの観光客が訪れる名所との事で、駐車場と観光客目当ての土産物屋が立ち並ぶ様はいかにも日本的なザ・観光地といった趣き。駅から歩いて5分くらいだったけど、果たしてハイシーズンでも鉄道に乗って来る人がどれだけいるのだろうか。まあそれにしても紅葉の時期もとっくに終わって山は冬枯れだし、雪景色でもないし、朝早いし、寒いし、だーれもいないよ(笑)。まあ観光客でゴミゴミしているよりはよっぽどいいけどね。