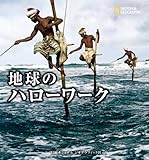| 太平洋戦争 最後の証言 第一部 零戦・特攻編 |
| 門田隆将 | |
| 小学館 |
暖かくなってきました。
春になり、桜が咲くと、不思議と戦争のことを思い出します。靖国の桜がそうさせるのかもしれません。
今年は2012年。1945年の終戦から67年目を迎えました。
私はもちろん戦後世代。ただ、子供の頃は間違いなく回りに「戦争」が残っていました。
親類には戦争に行って来た方もたくさんおり、戦争に起因する遺族も周りにたくさんいました。
父の2人の兄は二人とも従軍し、一人は戦死、もう一人は特攻の生き残りでした。
その叔父さんもずいぶん前に他界。
勤務先にも取引先にも軍隊上がりの方が必ず居ました。
そういえば高校の英語の老先生が我々のあまりの授業態度の悪さに激怒され豹変。
「元帝国軍人・鬼軍曹」と、一言だけいい、授業を再開されたことがありました。
つい先日、何気なくテレビをつけると、私が子供の頃にのめりこんだ数少ないアニメ「宇宙戦艦ヤマト」の2作目を放送していました。
一作目で死んでいった仲間たちを、生き残った仲間たちが「今の地球はあまりにも物質社会化している。こんな地球にするために命を賭けて戦ったのか? 死んだ仲間に申し訳ない」というようなシーンがありました。
果たしで今生き残っている太平洋戦争経験者たちは、一体なにを思っているのでしょうか・・。
この本は、まさに時間的にもそろそろ限界が近づいた、「戦争体験者」を取材し、あのころ現場では何がおき、若者はどう思い、行動したのか、ということを取材から掘り起こしています。
同様の本は今までもたくさん出されているでしょう。ただ、語り部が減り、特に太平洋戦争時代の幹部連中がこの世を去り、現場・第一線で戦っていた方々が話しやすくなったという環境・もう時間が無い、という中で今まで話しを拒んでいた方々が口を開き易くなった状況などから、より現場の真実が聞ける内容になっているのではないかな、と、思いました。
3部作のうちの一作目のこの本は、航空部隊・特攻に焦点を当てています。
不思議と子供の頃から特攻のことが気になります。そして、年齢とともに、その思いもずいぶんと変わってきました。
いつのまにかこの年齢になり、使われる立場から抜け、そして色々と見えてきたことがあります。
当初はもちろん違ったでしょうが、効果が見込まれない、ほとんどが敵艦に到着するまえに打ち落とされるという中で、それでも「練習機」でも飛び立たせたことは、少なからず、「現場はここまで必死にやっとります」という幹部連中の「言い訳」があったのではないか、と思います。
終戦後飛び立ち、自決された幹部の方もいらっしゃいます。美談として伝えられることもあるようですが、当然幹部の方は操縦できず、この自決に付き合わされて無意味に死なされた方々もいることを忘れるわけにはいきません。
言い訳のために逝かされた方々は今の日本をどう見ているのでしょうか? 或いは、「変わらない国だな・・」と思っているかもしれません。
戦争がどんどん遠くなってきました。そしていずれは、戦争体験者が居なくなってしまうのです。
「侵略戦争」だとか、「謝罪」だとか、そんな言葉だけが残っていくのはあまりにも情けなく、悲しいことです。
若いころは戦争に駆り出され、「若者は国のために死ね」といわれ、この歳になると「高齢者は死ね」といわれるような扱いを受け、なんなんでしょうかね・・という元軍人さんの言葉が、今の日本を象徴しています。