 さまざまある神社の約束(1)
さまざまある神社の約束(1) 神社の境内
神社の境内☆鎮守の森は、神があつまる場所
☆境内の基本的なつくり
*神社の入り口には鳥居がある
*鳥居をくぐると拝殿があり、拝殿の奥に神殿(本殿・正殿)がある
 神社にある神殿
神社にある神殿☆神社には、「本社」とよばれる主祭神をまつる社殿がある
☆他に「境内社」と称する小さな社「摂社」「末社」「分社」がある
*摂社や末社は、主祭神とゆかりの深い神をまつる
*分社は、本社の祭神を分霊してつくられた神社
☆稲倉のデザインが神殿のデザイン
*神社の建物は、弥生時代以来、稲を納める倉に似たものがつくられた
*今日の神社の神殿も、稲倉神殿形式を受け継いごでいる
☆神社には、神殿や拝殿がない神社もある
*大和朝廷の発祥の地にある大神神社は、神殿をもたない
*大神神社は、背後の三輪山を拝むための拝殿だけが設けられている
 神社と神職の格付け
神社と神職の格付け☆神社、神宮、大社がある
*「神社」といわれる普通のほか「神宮」「宮」「大社」「社」がある
*「神宮(神の宮殿)」で尊い神社をさす(伊勢神宮、明治神宮、石上神宮等)
*「大社」は、国津神をまつる中で、もっとも有力な神社
*八幡(「八幡宮」>「八幡神社」>「八幡社」の順で格付けが高い)
☆神職の名称 (関東「神主さん」、関西「禰宜さま」)
 神社建築の原型・神明造と大社造
神社建築の原型・神明造と大社造☆神殿の形式には、さまざまなものがある
☆日本を代表する伊勢神官(神明造)と出雲大社(大社造)
 神域と人間界を分ける鳥居と注連縄
神域と人間界を分ける鳥居と注連縄☆鳥居は神域と人間世界の境界
*鳥居は、神が降りてくる神域と人間が住む世界とを区画する
☆注連縄を張る理由
*神社の入り口の注連縄は、従来神域のまわり全体に張られていた
*人びとに「ここにむやみに近づいてはならない」と告げるもの
 鳥居の形式
鳥居の形式☆古くは、神域の入り口に鳥居を一つだけおかれていた
*今日は、有力神社の多くは、参道に複数の鳥居がみられる
☆鳥居の原形・神明鳥居
*神明鳥居、明神鳥居などの多くの形式がある
*伊勢神宮の内宮では、最も古いと形式の神明鳥居
 知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
 私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『神道』
出典、『神道』

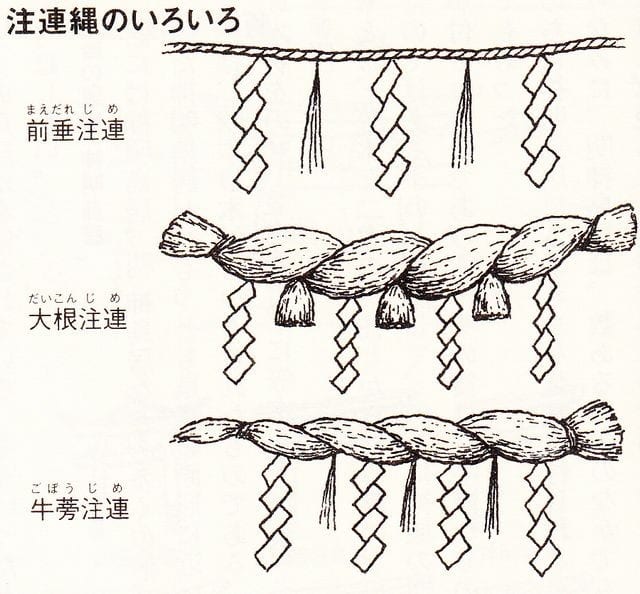
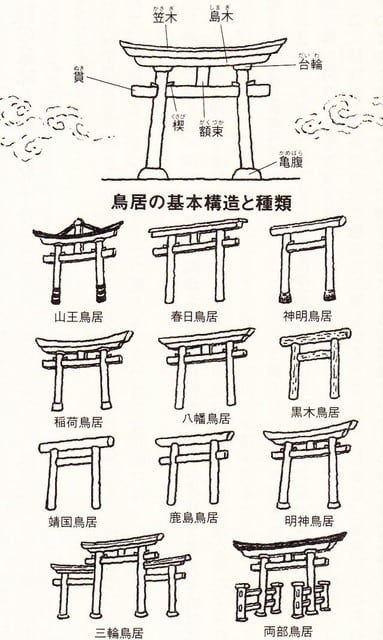
さまざまある神社の約束(1)(『神道』記事より画像引用)












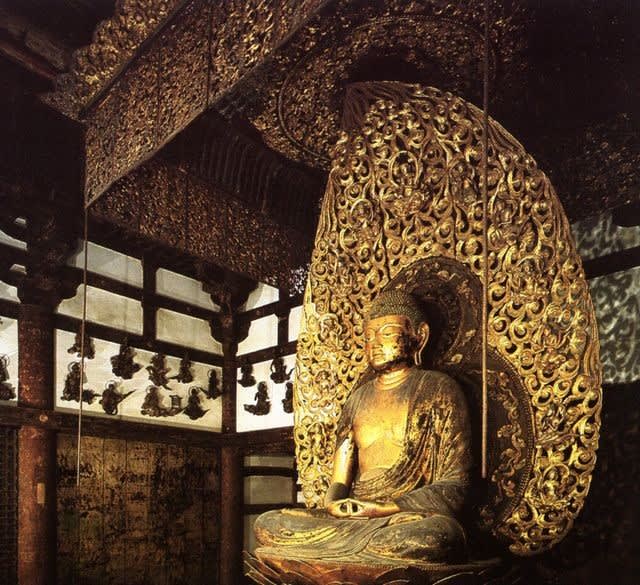

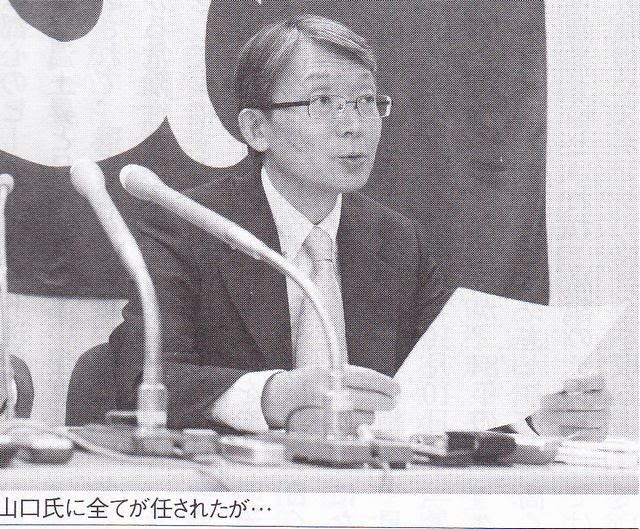
 What I want to do is to enjoy scuba.
What I want to do is to enjoy scuba. 復習
復習



