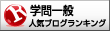■先夜、NHKのBS放送を見ていたら、超人的な記憶力の達成に挑戦する人たちを追うドキュメント番組があった。それは一種の競技として、記憶力の限界に挑むというもので、脳の機能の向上と、膨大な情報をいかに処理するかが、超人的な記憶力の達成のために不可欠であるということが「達人たち」の共通した認識のようであった。競技のひとつは、任意にまぜたトランプの順序、配列を、所定の時間内に、どれだけたくさん記憶することができるかというものだった。また、プリントで配られる未知の人々の顔写真とその名前を、所定の時間内にどれだけたくさん記憶することができるかというものだったりした。それらいくつかの競技の得点を総合して、参加者の中から「勝者」が決定されるのである。
印象に残ったのは、記憶力を増強するための訓練や、その記録の壁に挑むことの意義を問われて、多くの達人たちがその達成感について口にしたことだった。この番組の内容は、まあそういうものであり、それ以外の何か抽象的な話題を言外に匂わせているわけでもさなそうだった。
たまたまその直後、私は以前パソコンの中に収納しておいたフランセス・A・イエイツの『記憶術』なる書物を再読した。この本にはジョルダーノ・ブルーノについての言及がかなり多く、つねづね気になっていたのだ。以前この本を読んだ動機も、ブルーノの半生をたどることを目的にしていたのだが、さて今回再読して驚いたことは、以前読んだ内容を、私はまったく覚えていないことである。いや、まったくというのは言い過ぎかもしれない。たとえば、以前読んだとき、ヴェネツィアの行政顧問を務めたことのあるジョヴァンニ・モチェニゴなる人物とブルーノとの関係を、ローマの有力者デル・モンテ枢機卿とカラヴァッジオの関係と対比させると面白い、と考えたことがあるのを明確に記憶している。――そもそも私には、ハリー・ポッターなる架空の人物などよりも、ジョルダーノ・ブルーノのほうがはるかに「魔術的」な人物で、しかも実在した独創的な人物として、きわめて興味深いのである。
モチェニゴは、ブルーノから記憶術を学びたいという理由で、ブルーノをヴェネツィアに招いている。だが結局、ブルーノはイタリアヘ帰国することとなり、モチェニゴはヴェネツィアの異端審問所にブルーノを告訴するのである。こうした経緯で、やがてブルーノの投獄、そして1600年の焚刑へと連関してゆくのである。他方、教皇庁におけるトスカーナ公の大使だったデル・モンテ枢機卿は、数奇な運命をたどった呪われた画家のこのうえない理解者であり、庇護者でもあった。錬金術の研究者であり、新プラトン主義の信奉者でもあった枢機卿は、彫刻家や画家に寛大であり、カラヴァッジオを貧民街から救い出して自邸に住まわせてさえいる。この枢機卿とめぐりあうことがなければ、カラヴァッジオの画業はもっと違ったものになっていたことだろう。
――いずれにしても、最初に私がイエイツの著書を読んだときに記憶していたのは、せいぜいが以上のごときものだった。
スルバランやベルニーニが誕生した翌年にベラスケスが生まれ、さらにその翌年の1600年、ブルーノはローマのカンポ・ディ・フィオーリ広場で火刑にされた。彼の最期の言葉は「宣告を受けているわたくしよりも、わたくしに宣告を下しているあなた方のほうが、真理の前に恐れおののいているのではないか――」というものだった。
しかし『斬首された聖ヨハネ同信会』の古文書には次のような記録があるそうである。
《頭と心を数々の誤りと空しい自惚れに釘づけにしたまま、裁判所の役人たちにカンポ・デイ・フィオーリに引かれて行く時も、彼は依然として頑固だった。カンポでは裸にされ、火あぶり台に縛りつけられた後、生きながら焼かれた。その間中、われわれの兄弟たちが連祷を唱え、彼が頑固さを克服するよう最後の最後まで求め続けた。かくして彼の苦しみと惨めな人生は終わりを告げた》(デズモンド・スアード『カラヴァッジョ 灼熱の生涯』 石鍋真澄+石鍋真理子訳/白水社・2000)
ブルーノの火刑について、カラヴァッジオが何らかの関心を示したという記録はない。この年はカラヴァッジオにとっては最初の成功を収めた年であり、間違いなく彼の転換点だった。
――古典的な記憶術、つまりシモニデスやキケロの時代から、それを習得するための重要なファクターのひとつは、間違いなくイメージ処理能力についての質的問題だった。この事情は現代にいたってもさほど変わってはいない。
さて、ブルーノの記憶術は、たんに記憶力の向上という目的を達成するためのものではなく、新プラトン主義やヘルメス主義、コペルニクス主義とわかちがたく結びついている。
イエイツはブルーノの処女作『イデアの影について』 (De umbris idearun,1582) をめぐる考察のなかで、次のように述べている。
《ヘルメスが記憶に関する書物を提供するという『影』の冒頭は、昇りくる太陽の如きエジプトの啓示が衒学者によって反発を受けるという設定で書かれているが、これはブルーノが『聖灰日の晩餐』(Cena de le ceneri)で、コペルニクスの地動説を衒学者に対抗して弁護するくだりと酷似している。『影』でブルーノが到達した内なる太陽は、彼の「コペルニクス主義」、すなわち「エジプト的」理想とヘルメス的宗教ともどもの復権の、いわば前触れとして彼が地動説を採用したこと、の内的表現なのである。》 (フランセス・A・イエイツ『記憶術』玉泉八州男監訳/水声社・1966)
ブルーノはまた『原因について』 (De la causa, principio e uno) の中で、「〈一者〉における〈万物〉の統合」は、《自然の真理と秘儀にとって、堅固なる基盤である。というのも、自然が被造物へと下リ、知性が被造物に関する知識へと昇るのは、同じ一つの階梯を伝ってのことだからである。すなわち、一方はそれを伝って統一体から出発し、他方は中間にある多くの事物を通過しながら、それへと帰っていくからである》と述べている。
イエイツはいう。《記憶術の狙いは、重要なイメージを組織することによって、内面で、霊魂のなかで、統一体への知性の回帰を生じさせることだったのである。》
『験れる獣の追放』 (Spaccio della bestia tronfante) において、ブルーノは述べている。《魔術的かつ神聖な儀式によって[それらは]……同一の自然の階位を伝って神性の高みへと昇っていき、神性は階位自体の伝達によって、最も小さいものにまで下降していくのである。》 (フランセス・A・イエイツ『記憶術』)
以上のようなイエイツの指摘の意味に気づいてみれば、それにつづく以下の記述は、ごく当然の補足説明にすぎないように感じられる。
《記憶術の狙いは星の魔術的イメージに基づいた記憶によって、この魔術的な上昇を内面に生じさせるところにあるのである。
『英雄的狂気』 (De gli eroici furori) において、神性の痕跡を追い求める熱狂者は、自然界の美しい調和を瞑想する能力を獲得する。そして彼はすべての数の源である〈アンピトリテ〉、すなわち単子を見る。たとえその本質である絶対的光という形で単子を見るのではないにしろ、絶対的光の象徴のなかにそれを見ているのである。というのも、神性である単子から、世界であるその単子が生じるからだ。記憶術の狙いは、内面でしかなされることかできない統一化の理想を、まさにその内面で成し遂げることにある。なぜなら、内面における事物のイメージは外界にある事物そのものよりも実在により近く、光をよりよく反映するものだからだ。
このように、古典的記憶術は、『影』における記憶の手法にわれわれがみてきたような、非常に特異なルネサンス的、ヘルメス主義的変容を遂げながら、ヘルメス主義的神秘主義者にして〈魔術師〉の、霊魂を組織化する手段となっていった。内面に宇宙を反映させるという、宗教的経験としてのヘルメス主義的原理は、重要なイメージを配列することにより、現象界を把握し、統合する魔術=宗教的技術へと、記憶術を通して体系化されていったのである。記憶術のこういったヘルメス主義的変容がカミッロの〈劇場)において、より素朴な形で体現されていることは前にみたが、ブルーノの場合、この変容ははるかに複雑かつ過激であり、はるかに魔術的、かつ非常に宗教的だ。》
ところで、最近ふとしたことから、テッド・チャンの短篇小説『理解』を、やはり再読してみた。(ここでも私は、以前に読んだ内容の多くを忘れていることに愕然とさせられた。思うに、読書という行為は、やがて忘れることを必須の前提条件としなければ成立しないのではないのだろうか。)
『理解』では知覚強化が超人的なレベルに達した主人公グレコの活動が描かれ、さらには彼に敵対するもうひとりの超人レイノルズとの知的格闘のさまが描かれている。
知覚強化の初期段階で、グレコの知性がどのようなものかについては、以下の部分で象徴させることができる。(蛇足ながら、これは私がかつて体験したアカシック・イベントと酷似している。)
《なにを学習しても、わたしにはそのパターンがみてとれる。数学でも科学でも、美術でも音楽でも、心理学でも社会学でも、あらゆるもののなかに、その統一的全体像が、音符の織りなすメロディがみえるのだ。テキスト類を読んでいると、その著者たちはみえない連関を手さぐりしながら、ある点からつぎの点へたどたどしくたどっているとしか思えなくなる。バッハのソナタの譜面をにらんで、ある音符がつぎの音符につづく理由を知ろうとあがいている、音楽を理解できないその他おおぜいのひとびとと似たようなものだ。》 (テッド・チャン『あなたの人生の物語』所収 公手成幸訳/早川書房・2003)
そして彼は日をおかずして次のようなレベルに達する。
《わたしは実験的に、長大な詩の一部をなすものを書いている。ひとつの篇を仕上げれば、あらゆる芸術が内包するパターンを統一するためのアプローチを選択できるようになるだろう。用いている言語は、現代のものが六種で、古代のものが四種。これだけあれば、人類文明の重要な世界観は大半が包含される。それぞれが異なった意味あいと詩内効果を与え、並置によって輝きを放つ場合もある。この詩は各行に、別の言語の語形変化による成形で生みだされた新造語を含んでいる。全篇が完成すれぽ、パウンドの『詩篇』によって多重化された『フィネガンズ・ウェイク』とみなされるものになるかもしれない。》
そもそもグレコは、ある事故にみまわれ、それに起因する脳の損傷を治療するために、ホルモンKなる新薬を投与されたのである。脳卒中やアルツハイマー病の患者たちに対してのホルモンK療法では、重大な損傷をこうむった脳ほど大きな知能の向上がみられたが、グレコはだれよりも多くの追加注入を受けていた。
やがてこのホルモンK療法をめぐって、CIAの影がちらつきはじめる。そしてホルモンK療法の継続を拒否して所在をくらましたグレコに対して、CIAは水面下で画策する。
グレコはホルモンKの残存アンプルを巧妙に盗みとり、潜伏先で投薬をつづけている。
《切断手術を施された切り口に思いがけず時計職人の手が移植された感じというか、自分の肉体が一新されたのがわかる。随意筋のコントロールなどはとるにたりないこと。わたしには超人的な筋肉調整能力があるのだ。ふつうなら習熟に数千回の反復を必要とする技術でも、二、三度で身についてしまう。演奏中のピアニストの手を映したヴィデオをみれば、さほどもなく、自分のまえにキーボードをおくこともなく、その指の動きを模倣できるようになる。選択的な筋肉の収縮弛緩運動によって、わたしの筋力と柔軟性は向上している。筋肉の反応時間は、意識的運動か反射的運動かを問わず、三十五ミリセカンド。ろくにトレーニングをしなくても、アクロバットやマーシャルアーツのわざを身につけることができるだろう。》
このような状態で外界に目を転じてみると――。
《周囲にはよろこばしくもすさまじい、目もくらむばかりの対称性。数多のシンメトリーがさまざまなパターンの内部に編みこまれて、全宇宙がみずから像をなそうとしている。わたしは究極のゲシュタルトに、そのなかではすべての知が調和して光を与えられるコンテクストに、マンダラに、天球の音楽に、コスモスに、迫りつつある。
わたしの求める悟りは、霊的なものではなく理性的なものだ。それにいたるにはまださきへ進まねばならないが、こんどはそのゴールがたえずわたしの指さきからしりぞいていくことにはならない。わが心の言語をもってすれば、おのれと悟りをへだてる距離は正確に計測できる。最終目的地が視野にはいったのだ。》
そんなグレコに先行すること十五日間、臨界超越者となったレイノルズの存在があきらかとなる。
グレコはレイノルズにおびき寄せられるようにして、彼のアパートメントに足を運ぶ。
《居間には、背中をこちらにむけた大きな回転椅子がひとつ。レイノルズの姿はみえず、体性放射物は昏睡状態のレベルに抑制されている。わたしは自分の存在を、さらには相手を認識していることを伝達する。
〔レイノルズ〕
認知。〔グレコ〕
椅子がなめらかに、ゆっくりとまわる。彼がわたしにほほえみかけ、そばにあるシンセサイザのスウィッチを切る。満足感。〔きみに会えてうれしい〕
われわれがコミュニケイトのためにつかっているのは、ことばの短縮ヴァージョンである、通常の体性言語の断片的やりとりだ。ひとつの句の伝達に要する時間は十分の一秒。遺憾の念を暗示する。〔敵対しなくてはならないとは残念〕
もの悲しげな同意と、それにつづく提議。〔しかり。われわれが協調して行動すればいかに世界を変えうるかを想像せよ。ふたつの強化された心。このような機会が失われるとは〕
協調して行動すれば、個々になしうるよりはるかに大きなことが達成できるだろうことはたしかだ。あらゆる交流が、とほうもない成果をもたらすだろう。わたしに匹敵する思考速度をもち、わたしには目新しいアイデアを提示でき、わたしと同じメロディをききとれる相手となら、たんに討論をするだけでどれほど大きな満足が得られることか。彼の思いも同じだ。どちらかひとりは生きてこの部屋を出られないことを思って、われわれはともに胸を痛めている。
提案。〔われわれが過去半年のあいだに学んだことを共有する意志は?〕
彼はこちらの答えを知っている。》
レイノルズの伝達言語「われわれが協調して行動すればいかに世界を変えうるかを想像せよ」に対して、グレコもまた「あらゆる交流が、とほうもない成果をもたらすだろう」と認識している。だが彼はそれに賛同しない。
――ここで私が感じるのは、レイノルズは超人的に強化された二人が「融合」することでブルーノ的な意味での〈一者〉をめざそうとしているのに対して、グレコのほうは対立抗争のすえに淘汰された〈一者〉をめざそうとしているらしい、ということである。
しかし物語は、闘争的なグレコが敗北する結果となる。
表面はおだやかなレイノルズとのこの会談で、グレコに敗北をもたらすものの正体を、レイノルズがあきらかにする。
《レイノルズが笑みをかえす。〔きみは考察したことがあるか――〕とうとつに、投射物は沈黙のみとなる。彼は口でいおうとしているのだが、それがなにかをわたしは予測できない。すぐにそれは、ささやきとなって到来する。
「――自己破壊コマンドのことを。グレコ?」
彼がそういうなり、わたしのなかにある彼の再構成像の脱落は満たされ、オーヴァーフロウして、その含意が彼に関する知識のすべてに彩りを与える。彼がいわんとしているのはあの“ことば”、それが発せられると聞き手の心を破壊するだろうという、あのセンテンスのことだ。レイノルズは、あの神話は真実だと、すべての心にそのようなひきがねがビルトインされているのだと主張している。ひとにはそれぞれ、その人間の能力を減退させて白痴に、狂気に、緊張型統合失調症に追いやるセンテンスがあるのだと。そして彼は、わたしにとってのそのセンテンスはなにかを知っているのだと主張している。》
自己破壊コマンドをビルトインして、任意のときにそのトリガーを作動させる、というガジェットは、きわめて魔術的な発想である。
《レイノルズが芝居じみた身ぶりで片手をあげ、なにかを強調するかのように人さし指をのばす。こちらは彼の破壊コマンドを生成しようにも、それができるほどの情報をもたないから、この瞬間にやれるのは防御に専念することのみ。もしこの攻撃を生きて切りぬけられれば、また別の自分の武器を投射するゆとりができるかもしれない。
人さし指を上方にあげて、彼がいう。
「理解」
最初は、なにも感じない。やがて、恐怖が襲ってくる。
彼は、口に出すものとしてコマンドを設計してはいなかった。感覚的トリガーでもなかった。それは記憶のトリガー、個々には無害な知覚物のつらなりからなるコマンドで、時限爆弾のようにわたしの脳内に植えこまれていたのだ。記憶のひとつの結果として形成されていたそれらの心的構造物が、いまはわたしの崩壊を規定するゲシュタルトを形成しつつある。わたしはみずから、その“ことば”を直感している。》
結局は「理解」という“ことば”がグレコに対する自己破壊コマンドだったのだ。グレコは才覚においてレイノルズがうわまわっていることを認識し、知覚能力の急激な減退の先に待ち受けている破滅に直面する。
――以上のようなことを長々と書いてきたのは、記憶術や知覚強化などというかたちで課せられる知的行為について、大まかな構造を理解(再確認)しておきたかったからである。神的な〈一者〉に対置されるのは、イメージ的に効率よく――あるいは魅力的に――整理された膨大な情報である。そして強大な記憶力にとって、もっとも切実な問題は、おそらく、忘却という破綻だろうと思われる。どれだけ熱心に読書しても、いずれ忘れ去ることがわかっているのなら、その努力を経ずして読書的成熟を得ることはできないものだろうか。――当然できない。ただ読む前と読んだ後で何も変化がないのなら、読書にはまったく意味がないことになる。それでも読書は楽しいから厄介である。しかしこれは、人は覚えるよりも忘れるほうが多いと私が勝手に思い込んでいるだけなのかもしれない。また、自分は忘れたつもりでも、こっそり側頭葉に隠れ住んでいる場合もあるだろう。ごくまれに、超人的な記憶力を誇るものの、長期間記憶した内容を忘れることができず、それが苦痛で、生活にも支障をきたす場合があるという。心理学者ルリヤによれば、ある記憶力の達人は、あらゆることをイメージに変換できる特殊能力を持っていたため、ごく普通の文章を理解することが困難だったという。個々の単語が一つ一つ、互いに独立したイメージとして浮かんでくるので、文章全体の理解が不可能になるというのである。
■ジョルダーノ・ブルーノ
■記憶と能力
印象に残ったのは、記憶力を増強するための訓練や、その記録の壁に挑むことの意義を問われて、多くの達人たちがその達成感について口にしたことだった。この番組の内容は、まあそういうものであり、それ以外の何か抽象的な話題を言外に匂わせているわけでもさなそうだった。
たまたまその直後、私は以前パソコンの中に収納しておいたフランセス・A・イエイツの『記憶術』なる書物を再読した。この本にはジョルダーノ・ブルーノについての言及がかなり多く、つねづね気になっていたのだ。以前この本を読んだ動機も、ブルーノの半生をたどることを目的にしていたのだが、さて今回再読して驚いたことは、以前読んだ内容を、私はまったく覚えていないことである。いや、まったくというのは言い過ぎかもしれない。たとえば、以前読んだとき、ヴェネツィアの行政顧問を務めたことのあるジョヴァンニ・モチェニゴなる人物とブルーノとの関係を、ローマの有力者デル・モンテ枢機卿とカラヴァッジオの関係と対比させると面白い、と考えたことがあるのを明確に記憶している。――そもそも私には、ハリー・ポッターなる架空の人物などよりも、ジョルダーノ・ブルーノのほうがはるかに「魔術的」な人物で、しかも実在した独創的な人物として、きわめて興味深いのである。
モチェニゴは、ブルーノから記憶術を学びたいという理由で、ブルーノをヴェネツィアに招いている。だが結局、ブルーノはイタリアヘ帰国することとなり、モチェニゴはヴェネツィアの異端審問所にブルーノを告訴するのである。こうした経緯で、やがてブルーノの投獄、そして1600年の焚刑へと連関してゆくのである。他方、教皇庁におけるトスカーナ公の大使だったデル・モンテ枢機卿は、数奇な運命をたどった呪われた画家のこのうえない理解者であり、庇護者でもあった。錬金術の研究者であり、新プラトン主義の信奉者でもあった枢機卿は、彫刻家や画家に寛大であり、カラヴァッジオを貧民街から救い出して自邸に住まわせてさえいる。この枢機卿とめぐりあうことがなければ、カラヴァッジオの画業はもっと違ったものになっていたことだろう。
――いずれにしても、最初に私がイエイツの著書を読んだときに記憶していたのは、せいぜいが以上のごときものだった。
スルバランやベルニーニが誕生した翌年にベラスケスが生まれ、さらにその翌年の1600年、ブルーノはローマのカンポ・ディ・フィオーリ広場で火刑にされた。彼の最期の言葉は「宣告を受けているわたくしよりも、わたくしに宣告を下しているあなた方のほうが、真理の前に恐れおののいているのではないか――」というものだった。
しかし『斬首された聖ヨハネ同信会』の古文書には次のような記録があるそうである。
《頭と心を数々の誤りと空しい自惚れに釘づけにしたまま、裁判所の役人たちにカンポ・デイ・フィオーリに引かれて行く時も、彼は依然として頑固だった。カンポでは裸にされ、火あぶり台に縛りつけられた後、生きながら焼かれた。その間中、われわれの兄弟たちが連祷を唱え、彼が頑固さを克服するよう最後の最後まで求め続けた。かくして彼の苦しみと惨めな人生は終わりを告げた》(デズモンド・スアード『カラヴァッジョ 灼熱の生涯』 石鍋真澄+石鍋真理子訳/白水社・2000)
ブルーノの火刑について、カラヴァッジオが何らかの関心を示したという記録はない。この年はカラヴァッジオにとっては最初の成功を収めた年であり、間違いなく彼の転換点だった。
――古典的な記憶術、つまりシモニデスやキケロの時代から、それを習得するための重要なファクターのひとつは、間違いなくイメージ処理能力についての質的問題だった。この事情は現代にいたってもさほど変わってはいない。
さて、ブルーノの記憶術は、たんに記憶力の向上という目的を達成するためのものではなく、新プラトン主義やヘルメス主義、コペルニクス主義とわかちがたく結びついている。
イエイツはブルーノの処女作『イデアの影について』 (De umbris idearun,1582) をめぐる考察のなかで、次のように述べている。
《ヘルメスが記憶に関する書物を提供するという『影』の冒頭は、昇りくる太陽の如きエジプトの啓示が衒学者によって反発を受けるという設定で書かれているが、これはブルーノが『聖灰日の晩餐』(Cena de le ceneri)で、コペルニクスの地動説を衒学者に対抗して弁護するくだりと酷似している。『影』でブルーノが到達した内なる太陽は、彼の「コペルニクス主義」、すなわち「エジプト的」理想とヘルメス的宗教ともどもの復権の、いわば前触れとして彼が地動説を採用したこと、の内的表現なのである。》 (フランセス・A・イエイツ『記憶術』玉泉八州男監訳/水声社・1966)
ブルーノはまた『原因について』 (De la causa, principio e uno) の中で、「〈一者〉における〈万物〉の統合」は、《自然の真理と秘儀にとって、堅固なる基盤である。というのも、自然が被造物へと下リ、知性が被造物に関する知識へと昇るのは、同じ一つの階梯を伝ってのことだからである。すなわち、一方はそれを伝って統一体から出発し、他方は中間にある多くの事物を通過しながら、それへと帰っていくからである》と述べている。
イエイツはいう。《記憶術の狙いは、重要なイメージを組織することによって、内面で、霊魂のなかで、統一体への知性の回帰を生じさせることだったのである。》
『験れる獣の追放』 (Spaccio della bestia tronfante) において、ブルーノは述べている。《魔術的かつ神聖な儀式によって[それらは]……同一の自然の階位を伝って神性の高みへと昇っていき、神性は階位自体の伝達によって、最も小さいものにまで下降していくのである。》 (フランセス・A・イエイツ『記憶術』)
以上のようなイエイツの指摘の意味に気づいてみれば、それにつづく以下の記述は、ごく当然の補足説明にすぎないように感じられる。
《記憶術の狙いは星の魔術的イメージに基づいた記憶によって、この魔術的な上昇を内面に生じさせるところにあるのである。
『英雄的狂気』 (De gli eroici furori) において、神性の痕跡を追い求める熱狂者は、自然界の美しい調和を瞑想する能力を獲得する。そして彼はすべての数の源である〈アンピトリテ〉、すなわち単子を見る。たとえその本質である絶対的光という形で単子を見るのではないにしろ、絶対的光の象徴のなかにそれを見ているのである。というのも、神性である単子から、世界であるその単子が生じるからだ。記憶術の狙いは、内面でしかなされることかできない統一化の理想を、まさにその内面で成し遂げることにある。なぜなら、内面における事物のイメージは外界にある事物そのものよりも実在により近く、光をよりよく反映するものだからだ。
このように、古典的記憶術は、『影』における記憶の手法にわれわれがみてきたような、非常に特異なルネサンス的、ヘルメス主義的変容を遂げながら、ヘルメス主義的神秘主義者にして〈魔術師〉の、霊魂を組織化する手段となっていった。内面に宇宙を反映させるという、宗教的経験としてのヘルメス主義的原理は、重要なイメージを配列することにより、現象界を把握し、統合する魔術=宗教的技術へと、記憶術を通して体系化されていったのである。記憶術のこういったヘルメス主義的変容がカミッロの〈劇場)において、より素朴な形で体現されていることは前にみたが、ブルーノの場合、この変容ははるかに複雑かつ過激であり、はるかに魔術的、かつ非常に宗教的だ。》
ところで、最近ふとしたことから、テッド・チャンの短篇小説『理解』を、やはり再読してみた。(ここでも私は、以前に読んだ内容の多くを忘れていることに愕然とさせられた。思うに、読書という行為は、やがて忘れることを必須の前提条件としなければ成立しないのではないのだろうか。)
『理解』では知覚強化が超人的なレベルに達した主人公グレコの活動が描かれ、さらには彼に敵対するもうひとりの超人レイノルズとの知的格闘のさまが描かれている。
知覚強化の初期段階で、グレコの知性がどのようなものかについては、以下の部分で象徴させることができる。(蛇足ながら、これは私がかつて体験したアカシック・イベントと酷似している。)
《なにを学習しても、わたしにはそのパターンがみてとれる。数学でも科学でも、美術でも音楽でも、心理学でも社会学でも、あらゆるもののなかに、その統一的全体像が、音符の織りなすメロディがみえるのだ。テキスト類を読んでいると、その著者たちはみえない連関を手さぐりしながら、ある点からつぎの点へたどたどしくたどっているとしか思えなくなる。バッハのソナタの譜面をにらんで、ある音符がつぎの音符につづく理由を知ろうとあがいている、音楽を理解できないその他おおぜいのひとびとと似たようなものだ。》 (テッド・チャン『あなたの人生の物語』所収 公手成幸訳/早川書房・2003)
そして彼は日をおかずして次のようなレベルに達する。
《わたしは実験的に、長大な詩の一部をなすものを書いている。ひとつの篇を仕上げれば、あらゆる芸術が内包するパターンを統一するためのアプローチを選択できるようになるだろう。用いている言語は、現代のものが六種で、古代のものが四種。これだけあれば、人類文明の重要な世界観は大半が包含される。それぞれが異なった意味あいと詩内効果を与え、並置によって輝きを放つ場合もある。この詩は各行に、別の言語の語形変化による成形で生みだされた新造語を含んでいる。全篇が完成すれぽ、パウンドの『詩篇』によって多重化された『フィネガンズ・ウェイク』とみなされるものになるかもしれない。》
そもそもグレコは、ある事故にみまわれ、それに起因する脳の損傷を治療するために、ホルモンKなる新薬を投与されたのである。脳卒中やアルツハイマー病の患者たちに対してのホルモンK療法では、重大な損傷をこうむった脳ほど大きな知能の向上がみられたが、グレコはだれよりも多くの追加注入を受けていた。
やがてこのホルモンK療法をめぐって、CIAの影がちらつきはじめる。そしてホルモンK療法の継続を拒否して所在をくらましたグレコに対して、CIAは水面下で画策する。
グレコはホルモンKの残存アンプルを巧妙に盗みとり、潜伏先で投薬をつづけている。
《切断手術を施された切り口に思いがけず時計職人の手が移植された感じというか、自分の肉体が一新されたのがわかる。随意筋のコントロールなどはとるにたりないこと。わたしには超人的な筋肉調整能力があるのだ。ふつうなら習熟に数千回の反復を必要とする技術でも、二、三度で身についてしまう。演奏中のピアニストの手を映したヴィデオをみれば、さほどもなく、自分のまえにキーボードをおくこともなく、その指の動きを模倣できるようになる。選択的な筋肉の収縮弛緩運動によって、わたしの筋力と柔軟性は向上している。筋肉の反応時間は、意識的運動か反射的運動かを問わず、三十五ミリセカンド。ろくにトレーニングをしなくても、アクロバットやマーシャルアーツのわざを身につけることができるだろう。》
このような状態で外界に目を転じてみると――。
《周囲にはよろこばしくもすさまじい、目もくらむばかりの対称性。数多のシンメトリーがさまざまなパターンの内部に編みこまれて、全宇宙がみずから像をなそうとしている。わたしは究極のゲシュタルトに、そのなかではすべての知が調和して光を与えられるコンテクストに、マンダラに、天球の音楽に、コスモスに、迫りつつある。
わたしの求める悟りは、霊的なものではなく理性的なものだ。それにいたるにはまださきへ進まねばならないが、こんどはそのゴールがたえずわたしの指さきからしりぞいていくことにはならない。わが心の言語をもってすれば、おのれと悟りをへだてる距離は正確に計測できる。最終目的地が視野にはいったのだ。》
そんなグレコに先行すること十五日間、臨界超越者となったレイノルズの存在があきらかとなる。
グレコはレイノルズにおびき寄せられるようにして、彼のアパートメントに足を運ぶ。
《居間には、背中をこちらにむけた大きな回転椅子がひとつ。レイノルズの姿はみえず、体性放射物は昏睡状態のレベルに抑制されている。わたしは自分の存在を、さらには相手を認識していることを伝達する。
〔レイノルズ〕
認知。〔グレコ〕
椅子がなめらかに、ゆっくりとまわる。彼がわたしにほほえみかけ、そばにあるシンセサイザのスウィッチを切る。満足感。〔きみに会えてうれしい〕
われわれがコミュニケイトのためにつかっているのは、ことばの短縮ヴァージョンである、通常の体性言語の断片的やりとりだ。ひとつの句の伝達に要する時間は十分の一秒。遺憾の念を暗示する。〔敵対しなくてはならないとは残念〕
もの悲しげな同意と、それにつづく提議。〔しかり。われわれが協調して行動すればいかに世界を変えうるかを想像せよ。ふたつの強化された心。このような機会が失われるとは〕
協調して行動すれば、個々になしうるよりはるかに大きなことが達成できるだろうことはたしかだ。あらゆる交流が、とほうもない成果をもたらすだろう。わたしに匹敵する思考速度をもち、わたしには目新しいアイデアを提示でき、わたしと同じメロディをききとれる相手となら、たんに討論をするだけでどれほど大きな満足が得られることか。彼の思いも同じだ。どちらかひとりは生きてこの部屋を出られないことを思って、われわれはともに胸を痛めている。
提案。〔われわれが過去半年のあいだに学んだことを共有する意志は?〕
彼はこちらの答えを知っている。》
レイノルズの伝達言語「われわれが協調して行動すればいかに世界を変えうるかを想像せよ」に対して、グレコもまた「あらゆる交流が、とほうもない成果をもたらすだろう」と認識している。だが彼はそれに賛同しない。
――ここで私が感じるのは、レイノルズは超人的に強化された二人が「融合」することでブルーノ的な意味での〈一者〉をめざそうとしているのに対して、グレコのほうは対立抗争のすえに淘汰された〈一者〉をめざそうとしているらしい、ということである。
しかし物語は、闘争的なグレコが敗北する結果となる。
表面はおだやかなレイノルズとのこの会談で、グレコに敗北をもたらすものの正体を、レイノルズがあきらかにする。
《レイノルズが笑みをかえす。〔きみは考察したことがあるか――〕とうとつに、投射物は沈黙のみとなる。彼は口でいおうとしているのだが、それがなにかをわたしは予測できない。すぐにそれは、ささやきとなって到来する。
「――自己破壊コマンドのことを。グレコ?」
彼がそういうなり、わたしのなかにある彼の再構成像の脱落は満たされ、オーヴァーフロウして、その含意が彼に関する知識のすべてに彩りを与える。彼がいわんとしているのはあの“ことば”、それが発せられると聞き手の心を破壊するだろうという、あのセンテンスのことだ。レイノルズは、あの神話は真実だと、すべての心にそのようなひきがねがビルトインされているのだと主張している。ひとにはそれぞれ、その人間の能力を減退させて白痴に、狂気に、緊張型統合失調症に追いやるセンテンスがあるのだと。そして彼は、わたしにとってのそのセンテンスはなにかを知っているのだと主張している。》
自己破壊コマンドをビルトインして、任意のときにそのトリガーを作動させる、というガジェットは、きわめて魔術的な発想である。
《レイノルズが芝居じみた身ぶりで片手をあげ、なにかを強調するかのように人さし指をのばす。こちらは彼の破壊コマンドを生成しようにも、それができるほどの情報をもたないから、この瞬間にやれるのは防御に専念することのみ。もしこの攻撃を生きて切りぬけられれば、また別の自分の武器を投射するゆとりができるかもしれない。
人さし指を上方にあげて、彼がいう。
「理解」
最初は、なにも感じない。やがて、恐怖が襲ってくる。
彼は、口に出すものとしてコマンドを設計してはいなかった。感覚的トリガーでもなかった。それは記憶のトリガー、個々には無害な知覚物のつらなりからなるコマンドで、時限爆弾のようにわたしの脳内に植えこまれていたのだ。記憶のひとつの結果として形成されていたそれらの心的構造物が、いまはわたしの崩壊を規定するゲシュタルトを形成しつつある。わたしはみずから、その“ことば”を直感している。》
結局は「理解」という“ことば”がグレコに対する自己破壊コマンドだったのだ。グレコは才覚においてレイノルズがうわまわっていることを認識し、知覚能力の急激な減退の先に待ち受けている破滅に直面する。
――以上のようなことを長々と書いてきたのは、記憶術や知覚強化などというかたちで課せられる知的行為について、大まかな構造を理解(再確認)しておきたかったからである。神的な〈一者〉に対置されるのは、イメージ的に効率よく――あるいは魅力的に――整理された膨大な情報である。そして強大な記憶力にとって、もっとも切実な問題は、おそらく、忘却という破綻だろうと思われる。どれだけ熱心に読書しても、いずれ忘れ去ることがわかっているのなら、その努力を経ずして読書的成熟を得ることはできないものだろうか。――当然できない。ただ読む前と読んだ後で何も変化がないのなら、読書にはまったく意味がないことになる。それでも読書は楽しいから厄介である。しかしこれは、人は覚えるよりも忘れるほうが多いと私が勝手に思い込んでいるだけなのかもしれない。また、自分は忘れたつもりでも、こっそり側頭葉に隠れ住んでいる場合もあるだろう。ごくまれに、超人的な記憶力を誇るものの、長期間記憶した内容を忘れることができず、それが苦痛で、生活にも支障をきたす場合があるという。心理学者ルリヤによれば、ある記憶力の達人は、あらゆることをイメージに変換できる特殊能力を持っていたため、ごく普通の文章を理解することが困難だったという。個々の単語が一つ一つ、互いに独立したイメージとして浮かんでくるので、文章全体の理解が不可能になるというのである。
■ジョルダーノ・ブルーノ
■記憶と能力