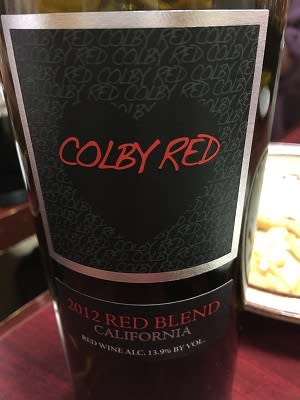「お寺」では、独自のいろいろなイベントが企画され、実施されています。しかし、予定や企画の内容などを広報したり、告知したりする取り組みはあまり積極的には行われていないようです。
洞泉院では、来る10/25(日)18:00~「観月讃仏会と落語会」が予定されています。お寺の本堂で座布団に座り(座ることが苦手な人のために椅子も用意されています)、数メートルの距離で落語家の生声で噺を愉しむことができます。滅多にない、貴重な体験ができます。それも「無料」で。誰でも参加できます。皆さん、お誘い合わせの上、ぜひお見逃しのないように!!

松戸仏教会(松戸市)が、市内の寺院六十四カ所を紹介するガイドブック「松戸のお寺」を初めて作成した。寺ごとに歴史や境内の見どころなどを記載していて、所在地が分かる地図もついている。仏教や寺の基礎知識が分かる「Q&A」コーナーもあり、入門書としても活用できる。無料。転入転出の多い同市では、長年住み、檀家(だんか)でもある市民のほかは、地元の寺と縁を持つ機会は少ない。同協会は身近な寺を知ってもらい、安らぎや願いごとなどで気軽に訪れてもらおうと企画し、二年余りかけ完成させた。サイズはA5判で、オールカラーの百ページ。寺の紹介は、それぞれの住職らが執筆し、由緒やご本尊、名木などを紹介。例えば、本福(ほんぷく)寺(上本郷)は幕末に長州を脱藩した吉田松陰が一夜の宿を求めた歴史を、西蓮(さいれん)寺(下矢切)は近くの矢切の渡しを舞台にした伊藤左千夫の名作「野菊の墓」の文学碑が境内にあることを記している。各寺の取り組みが一目で分かるように、座禅会、写経会、御朱印などをアイコン(絵文字)で示した。仏教行事、宗派、招福を願って巡る松戸七福神についての説明もある。中学生も読みやすいように多くの漢字にルビをふってある。ジャズコンサートを開いたり、ヨガ教室に本堂を開放している寺もあり、徳蔵院(日暮)住職の高味良信会長(68)は「高いとよく言われる敷居を取り払うために取り組んだ。市民のみなさんにお寺に親しんでもらいたい」と話している。一万部を発行。市内の市立小中学校などに寄贈するほか、市民向け五千八百部を、市観光協会などに置いてある。問い合わせは徳蔵院=電047(387)2989=へ。