
手紙/東野圭吾/文春文庫
キーワード/兄弟、合同殺人、サクラ印、バイト、音楽、通信、大学、田園調布、就職、結婚
…キーワード、きりがないから強制終了。
今月封切られた映画の原作。実はこれ見ようか涙そうそうにしようか悩んだんだけど(悩んでそっちかよ!というツッコミはおいといて)、丁度本を読んでるところだったので涙そうそうにした、といういわくつき。
で。
一回目は、読みながら途中からがんがん飛ばして読んでました。なんでだろう、あまりの不幸ぶりに目を覆いたくなったのもあるし、早く結論まで辿り着きたかったのもあるし、ともかく、救われたかった。主人公が何らかの形で僅かでも救われるなら、読んでるおいらも救われるような気がしてな。
でも、走り読んでしまったら、え!終わり?!え?!て感じで、救われるも何も、こんなとこで?これで?って疑問しかわいてこなくて、何一つ納得していなかった。
ので、折り返し二回目に突入。走り読み始めたあたり、第三章くらいから読みました。で、ようやく色んなことが目に入ってきた。
映画は原作とは違います。それは監督(もしくは脚本家)がそう言ってます。おいらは新聞で読んだかな。ミュージシャンを目指してるところをお笑いにするとかね、なんかそういう風に、少しでも明るさを取り入れたかったんだとか。確かに、これを原作に忠実に映画化したら、すっごい重い話になると思った。(でも山田孝之の歌は聞きたかったなあ。似合いそうだよなあ)
映画は見てないけど、予告は見たことあるし、本屋で予告クリップが流れてる。あと、試写を見たのであろう人達、有名無名を問わず、の感想も読んだ。それによると、社長の言葉が泣けるんだそうだ。あーそうかも。本では後半のキーワードだ、多分。全編を通してのキーワードとも言える。これをすっ飛ばしたおいらは、失敗した。読み取れなかった。
重いよ。
ほんとに重いよ。
おいら、まだこの本は腑に落ちてない。
結果が見えにくいし、落としどころはどこにあるんだか、さっぱり見えない。いやそれこそが、この本の落としどころかもしれないけど、納得できない。おいらの中ではちっとも終わらない。なんだいこれ!
でも、多分そういう事なんだろう。
そんなね、何でもかんでも腑に落ちて、納得ずくで、良くも悪くも結果がきちんと出て、っていうふうには世の中回らない。理不尽な、或いはそれ以前の話で終わらされている(誰も望んではいないのに)話が多い、それしか無いかもしれない、生きるってことは。
それでも、生きる。
しかも、それは決して一人ではなく。
生きていればなんとかなる、なんてのは慰めにもならないけど、それでも生きる。
明日が、今日と同じかどうかは、明日が終わるまで分からない。
そして明日は、生きている限り絶対にやって来る。(勿論、地球が回っている限り、て前提で。)
だから、おいらは、生きるのだ。
今日、答えが出なくても、腑に落ちなくても、納得できなくても、救われなくても、
いい。
だから、明日に生きるのだ。
キーワード/兄弟、合同殺人、サクラ印、バイト、音楽、通信、大学、田園調布、就職、結婚
…キーワード、きりがないから強制終了。
今月封切られた映画の原作。実はこれ見ようか涙そうそうにしようか悩んだんだけど(悩んでそっちかよ!というツッコミはおいといて)、丁度本を読んでるところだったので涙そうそうにした、といういわくつき。
で。
一回目は、読みながら途中からがんがん飛ばして読んでました。なんでだろう、あまりの不幸ぶりに目を覆いたくなったのもあるし、早く結論まで辿り着きたかったのもあるし、ともかく、救われたかった。主人公が何らかの形で僅かでも救われるなら、読んでるおいらも救われるような気がしてな。
でも、走り読んでしまったら、え!終わり?!え?!て感じで、救われるも何も、こんなとこで?これで?って疑問しかわいてこなくて、何一つ納得していなかった。
ので、折り返し二回目に突入。走り読み始めたあたり、第三章くらいから読みました。で、ようやく色んなことが目に入ってきた。
映画は原作とは違います。それは監督(もしくは脚本家)がそう言ってます。おいらは新聞で読んだかな。ミュージシャンを目指してるところをお笑いにするとかね、なんかそういう風に、少しでも明るさを取り入れたかったんだとか。確かに、これを原作に忠実に映画化したら、すっごい重い話になると思った。(でも山田孝之の歌は聞きたかったなあ。似合いそうだよなあ)
映画は見てないけど、予告は見たことあるし、本屋で予告クリップが流れてる。あと、試写を見たのであろう人達、有名無名を問わず、の感想も読んだ。それによると、社長の言葉が泣けるんだそうだ。あーそうかも。本では後半のキーワードだ、多分。全編を通してのキーワードとも言える。これをすっ飛ばしたおいらは、失敗した。読み取れなかった。
重いよ。
ほんとに重いよ。
おいら、まだこの本は腑に落ちてない。
結果が見えにくいし、落としどころはどこにあるんだか、さっぱり見えない。いやそれこそが、この本の落としどころかもしれないけど、納得できない。おいらの中ではちっとも終わらない。なんだいこれ!
でも、多分そういう事なんだろう。
そんなね、何でもかんでも腑に落ちて、納得ずくで、良くも悪くも結果がきちんと出て、っていうふうには世の中回らない。理不尽な、或いはそれ以前の話で終わらされている(誰も望んではいないのに)話が多い、それしか無いかもしれない、生きるってことは。
それでも、生きる。
しかも、それは決して一人ではなく。
生きていればなんとかなる、なんてのは慰めにもならないけど、それでも生きる。
明日が、今日と同じかどうかは、明日が終わるまで分からない。
そして明日は、生きている限り絶対にやって来る。(勿論、地球が回っている限り、て前提で。)
だから、おいらは、生きるのだ。
今日、答えが出なくても、腑に落ちなくても、納得できなくても、救われなくても、
いい。
だから、明日に生きるのだ。










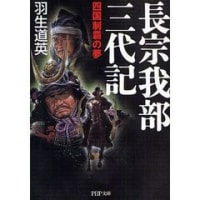
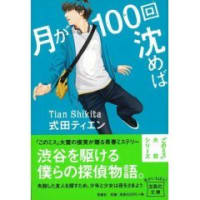
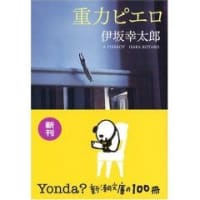
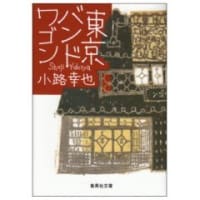

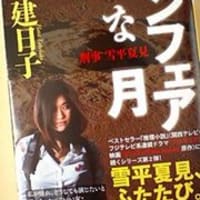




私、やはり映画の予告の社長さんの言葉に、
あと、玉山鉄二さんの美しい坊主頭(小太吉的弱点)に、グッときまして。
がんばって読んだら、トラックバックさせていただきます。
あと、もひとつググッときました。
すぎむらさん、生きるってそういうことですよね。
小太吉も同感です。
生きることに意味や対価を求めようとすると、たちまち浮世が息苦しくなる。
いのちあることそのもの、そのいのちで毎日を紡いでいくこと、それが大事。
意味なんかなくてもいい、日々を生き切る。
そのことが一番、潔く、価値あること。
そしたら、そのうちなんとかなるもんだ。
小太吉、常日頃そう思っております。
うへぇ。
おやすみなさい。
書評なんて恐れ多いもんじゃなくて、おいらの書いたものなんて、ただの書き散らし、書き逃げ、書きっぱなしですってー。文芸春秋社(だっけな)から売り上げに貢献してくれたご褒美、とかないかな(ねえよ!)。
というおバカな話は捨て置いて。
昨今、ほんとにもう、どっちを向いても自殺だのなんだのって。理由はどうあれさー、なんで自殺なんだよー。おいらのじいちゃんが生前口癖のように「死んだらしまい」と言っておりましたが、ほんとにそうざますよ。本人は「しまい」に出来るつもりだろうけど、世の中に存在するのはアンタだけじゃないって。「しまい」に出来ない人の方が絶対に多いんだから。頼むよほんとに。
曲がりなりにも、人の親となってみて、
改めて自殺ということに立ち向かっていかねばな、と思うわけです。
日々報道される「自殺」の、その子の母親の気持ちを思わずにはいられません。
小太吉の文章が固くて大袈裟なだけです、きっと。
もうちっとやわらかいものが書けるといいのですが。
で、「手紙」読了いたしました。
すぎむらさんのコメントでいちばん気になったのは、
「腑に落ちない」というところです。
そして、私もそこに思いっきり嵌ってしまいました。
はい、ずぼっと。
読書感想文はトラックバックしました。
でも、とーんでもなく長いし、とッ散らかってしまっています。
小太吉は長年、自分の文章を書く領域を封印していたので、ただ今十何年ぶりの放出モードなのです。
時間的にも、脳味噌的にも暇だということも災いして、ブログも狂ったように更新しています。
落ち着いたら、もう少しましになるとは思いますが・・・。
しばし、ご容赦ください。
自殺を繰り返す子供たちの話ですが。
亡くなった子供に腹を立てても、仕方ないのですが、
親として、何もできることがなかった結果をいきなり突き付けられるなんて、残酷すぎます。
昨今、「死んだらしまい」という感覚がない子供たちが、統計でも多いらしいですね。
生き返る、と本気で信じている子供もいるとか。
生きること、死ぬことってどういうこと、を伝えることがまず一歩なんでしょうね。
とても難しい、一歩ですね。