天下分け目の関ヶ原の合戦で、大勝利をおさめた東軍の大将「徳川家康」は、反旗を翻した石田三成の居城(佐和山城)を一掃し、同時に西国の豊臣恩顧の大名達に睨みを利かせるため、女城主直虎(NHK大河ドラマ)でお馴染みの徳川四天王のひとり「井伊直政公」に彦根城築城を命じた。18万石をもって彦根城築城(1604年より約20年の歳月をかけて完成)の許可を与えられた井伊公は、その後の勢力情勢の推移にも上手に立ち回り、当時の建造物である天守閣を現存させて今に残す。



金亀山に聳え立つお城であることから別名「金亀城(こんきじょう)」とも呼ばれている「彦根城天守閣(国宝)」は、姫路城・犬山城・松本城・松江城と並んで、日本の現存天守閣12城のなかでも国宝五城のひとつに指定されている。地元ということもあって、ワシはそこらのボランティアガイドよりも詳しい知識を持っているので、チラチラご紹介しつつ進めていきたい。



いろは松が立ち並ぶ「佐和山口」から、井伊直弼大老の銅像を右に見て「佐和口多聞櫓(さわぐちたもんやぐら・国宝)」横から表門橋を渡るルートで、敵兵になったつもりで侵入する。佐和山城から移築された防御に秀でている多聞櫓は、周囲のジグザグ通路を侵入する際、無数に開けられた矢狭間・鉄砲狭間などから、敵兵を後ろから狙い撃てる仕掛けが施されている。外壁は完全修復されているが、櫓内の創りは極太の梁など当時を偲ぶ面影が残る。

▲▼いろは松は藩士の名前を松につけ責任もって世話をさせたので大きく育った

▼佐和口多聞櫓(国宝)奈良多聞城の松永久秀が作った4階櫓が素晴らしく各お城は真似て「多聞櫓」を作った


▲佐和口多聞櫓の梁も国宝だけあって素晴らしく立派

▼この場所で敵兵は後姿を見せるので佐和口多聞櫓から狙い打ち


もうひとつの城への経路に、京橋口から大手門橋を渡って侵入してくる兵と、鉢合せする恰好になるのが、「天秤櫓(てんびんやぐら)」の真下で、長浜城の大手門が移築された天秤櫓には、下の通路こそ大掛りな堀切(敵兵の侵入を防ぐ人為的な堀)になっている。上にかかる「廊下橋」は、天秤櫓・本丸へと敵兵が攻めこもうとすると、橋そのものを崩して落とす仕掛けもあるので、この天秤櫓が彦根城の守りの要となっている。この周辺が時代劇に数多く出てくる場所だ。

▲いざとなれば廊下橋は落とされる

▲左右対称なことから天秤櫓と名がついている。ワシの目には左の方が重そうだ

▲もちろん廊下橋を渡ってくる敵兵は格好の的になる

天秤櫓の下の石垣は、時代によって積み方が違った「野面積み」と、古い時代の「牛蒡積み」にクッキリと分かれている部分があり、表面積は小さい石でもゴボウのように細長く奥深く積んでいる「牛蒡積み」の方が頑丈な積み方だと言われている。櫓の左右がほぼ対象で、つり合いが取れそうな天秤のような姿から、天秤櫓の名がついたようだが、敵兵がこの難関を通過できないと本丸への道は閉ざされる。

▲廊下橋の真下は牛蒡積みの石垣で、左側は時代が新しく野面積みの石垣だが

▲左側の野面積みより、牛蒡積みの方が頑丈だと言われている

▲天秤櫓の右横から石田三成の佐和山城跡が覗いているのは何かの因縁?

▲天秤櫓から本丸方向を見上げる ▼天秤櫓には井伊家の「井」のマークが

順序に逆らって、搦め手(裏口からの攻撃兵)が侵入する場合には、びわ湖側の見張り塔の役割も果たしている「西の丸三重櫓」がある。この建造物は、一説では小谷城の浅井長政が生活していた本丸だったと云いつたえがあるが、それを一旦長浜城へ移築されたのちに、再び彦根城へ移築された経歴を持つ。


▼▲西の丸三重櫓まで辿りつくには幾重にも石垣が


▼▲西の丸三重櫓の下には天秤櫓の下より深い堀切がある

西の丸三重櫓の前には、天秤櫓のものより深い堀切が侵入を阻み、道なき道を攻めあがろうとすると、日本でも現存が珍しい「登り石垣」が、重装備の鎧兜をつけた武者を阻む険しいものとなるよう仕掛けが設計されている。

▼西の丸三重櫓の梁は、浅井長政が眺めていたものだろうか

▼西の丸へ続く山には、全国的に珍しい「上り石垣」がまともな形で残る。案外ガイドさんも触れないスポットだ

▼この「上り石垣」が攻めるお城の山中にあると、約30キロの甲冑を装着している武将はたまらない

▼上り石垣を数か所探すだけでも苦労したので、乗り越えて行けと言われると更に大変そう

さて天秤櫓側に戻って、攻め進むと長浜城もしくわ佐和山城から移築された「太鼓門櫓(たいこもんやぐら)」があり、城下側の壁を作っておらず、中で太鼓をたたくとメガホン効果で、城下の隅々まで音が鳴り響く仕掛けだったとある。今は壁も作られ、単なる櫓としての役割をする建造物のような趣だが。



更に石段をあがると、本丸跡と当時の「現存天守閣(国宝)」が聳え、寄り添うように「附櫓(つけやぐら・国宝)」が建造されている。京極高次が城主を務めた「大津城」の4重5階の上3重部分を移築した天守閣は、通し柱を使わず各階ごとに積み上げられ、3層3階地下1階の複合式で各重なりに千鳥破風・切妻破風・唐破風・入母屋破風を詰め込んだように、天守閣品評会のように配置しており、色々な表情を見せるので風格がある。



さて、お得意の石垣を解説する。基礎は「牛蒡積み(ごぼうづみ)」なる石垣で支えられていると推測されていたが、近代(H17年)になってNHKのセンサーカメラが石垣内部へ入ったところ、牛蒡済積みだと思われていた石垣は僅か数十センチの薄っぺらな石であることが確認され、石垣フェチの歴史ロマンを打ち消した。牛蒡積みとは、ゴボウのような細長い大小の自然石を、縦横に組み合わせた組み木のようで、表面に出る石面は小さくとも、奥まで長く続いているんで、非常に堅固で頑丈な石垣と言われていた。


▼恒例の石垣補強を施してきた

天守閣の中へとはいると、地下一階からクネクネ曲がった極太の梁が、縦横無尽に組み上げられており、各階をつなぐ階段は急こう配で、敵兵が登ってきても蹴落とせるし、階段自体も蹴り崩せる仕掛けとなっているようだ。最上階からは竹生島も見え、びわ湖からの水軍による攻撃も監視できるような眺望であった。各地の現存天守閣を見ていて一度も戦闘が行われていない彦根城ほど、保存状態というか奇麗な状態で残っている天守閣は珍しい。是非訪れ見学されることをお薦めする。








★ご紹介しきれなかった画像は、アルバムでご覧頂けます。興味のある方は是非!



金亀山に聳え立つお城であることから別名「金亀城(こんきじょう)」とも呼ばれている「彦根城天守閣(国宝)」は、姫路城・犬山城・松本城・松江城と並んで、日本の現存天守閣12城のなかでも国宝五城のひとつに指定されている。地元ということもあって、ワシはそこらのボランティアガイドよりも詳しい知識を持っているので、チラチラご紹介しつつ進めていきたい。



いろは松が立ち並ぶ「佐和山口」から、井伊直弼大老の銅像を右に見て「佐和口多聞櫓(さわぐちたもんやぐら・国宝)」横から表門橋を渡るルートで、敵兵になったつもりで侵入する。佐和山城から移築された防御に秀でている多聞櫓は、周囲のジグザグ通路を侵入する際、無数に開けられた矢狭間・鉄砲狭間などから、敵兵を後ろから狙い撃てる仕掛けが施されている。外壁は完全修復されているが、櫓内の創りは極太の梁など当時を偲ぶ面影が残る。

▲▼いろは松は藩士の名前を松につけ責任もって世話をさせたので大きく育った

▼佐和口多聞櫓(国宝)奈良多聞城の松永久秀が作った4階櫓が素晴らしく各お城は真似て「多聞櫓」を作った


▲佐和口多聞櫓の梁も国宝だけあって素晴らしく立派

▼この場所で敵兵は後姿を見せるので佐和口多聞櫓から狙い打ち


もうひとつの城への経路に、京橋口から大手門橋を渡って侵入してくる兵と、鉢合せする恰好になるのが、「天秤櫓(てんびんやぐら)」の真下で、長浜城の大手門が移築された天秤櫓には、下の通路こそ大掛りな堀切(敵兵の侵入を防ぐ人為的な堀)になっている。上にかかる「廊下橋」は、天秤櫓・本丸へと敵兵が攻めこもうとすると、橋そのものを崩して落とす仕掛けもあるので、この天秤櫓が彦根城の守りの要となっている。この周辺が時代劇に数多く出てくる場所だ。

▲いざとなれば廊下橋は落とされる

▲左右対称なことから天秤櫓と名がついている。ワシの目には左の方が重そうだ

▲もちろん廊下橋を渡ってくる敵兵は格好の的になる

天秤櫓の下の石垣は、時代によって積み方が違った「野面積み」と、古い時代の「牛蒡積み」にクッキリと分かれている部分があり、表面積は小さい石でもゴボウのように細長く奥深く積んでいる「牛蒡積み」の方が頑丈な積み方だと言われている。櫓の左右がほぼ対象で、つり合いが取れそうな天秤のような姿から、天秤櫓の名がついたようだが、敵兵がこの難関を通過できないと本丸への道は閉ざされる。

▲廊下橋の真下は牛蒡積みの石垣で、左側は時代が新しく野面積みの石垣だが

▲左側の野面積みより、牛蒡積みの方が頑丈だと言われている

▲天秤櫓の右横から石田三成の佐和山城跡が覗いているのは何かの因縁?

▲天秤櫓から本丸方向を見上げる ▼天秤櫓には井伊家の「井」のマークが

順序に逆らって、搦め手(裏口からの攻撃兵)が侵入する場合には、びわ湖側の見張り塔の役割も果たしている「西の丸三重櫓」がある。この建造物は、一説では小谷城の浅井長政が生活していた本丸だったと云いつたえがあるが、それを一旦長浜城へ移築されたのちに、再び彦根城へ移築された経歴を持つ。


▼▲西の丸三重櫓まで辿りつくには幾重にも石垣が


▼▲西の丸三重櫓の下には天秤櫓の下より深い堀切がある

西の丸三重櫓の前には、天秤櫓のものより深い堀切が侵入を阻み、道なき道を攻めあがろうとすると、日本でも現存が珍しい「登り石垣」が、重装備の鎧兜をつけた武者を阻む険しいものとなるよう仕掛けが設計されている。

▼西の丸三重櫓の梁は、浅井長政が眺めていたものだろうか

▼西の丸へ続く山には、全国的に珍しい「上り石垣」がまともな形で残る。案外ガイドさんも触れないスポットだ

▼この「上り石垣」が攻めるお城の山中にあると、約30キロの甲冑を装着している武将はたまらない

▼上り石垣を数か所探すだけでも苦労したので、乗り越えて行けと言われると更に大変そう

さて天秤櫓側に戻って、攻め進むと長浜城もしくわ佐和山城から移築された「太鼓門櫓(たいこもんやぐら)」があり、城下側の壁を作っておらず、中で太鼓をたたくとメガホン効果で、城下の隅々まで音が鳴り響く仕掛けだったとある。今は壁も作られ、単なる櫓としての役割をする建造物のような趣だが。



更に石段をあがると、本丸跡と当時の「現存天守閣(国宝)」が聳え、寄り添うように「附櫓(つけやぐら・国宝)」が建造されている。京極高次が城主を務めた「大津城」の4重5階の上3重部分を移築した天守閣は、通し柱を使わず各階ごとに積み上げられ、3層3階地下1階の複合式で各重なりに千鳥破風・切妻破風・唐破風・入母屋破風を詰め込んだように、天守閣品評会のように配置しており、色々な表情を見せるので風格がある。



さて、お得意の石垣を解説する。基礎は「牛蒡積み(ごぼうづみ)」なる石垣で支えられていると推測されていたが、近代(H17年)になってNHKのセンサーカメラが石垣内部へ入ったところ、牛蒡済積みだと思われていた石垣は僅か数十センチの薄っぺらな石であることが確認され、石垣フェチの歴史ロマンを打ち消した。牛蒡積みとは、ゴボウのような細長い大小の自然石を、縦横に組み合わせた組み木のようで、表面に出る石面は小さくとも、奥まで長く続いているんで、非常に堅固で頑丈な石垣と言われていた。


▼恒例の石垣補強を施してきた

天守閣の中へとはいると、地下一階からクネクネ曲がった極太の梁が、縦横無尽に組み上げられており、各階をつなぐ階段は急こう配で、敵兵が登ってきても蹴落とせるし、階段自体も蹴り崩せる仕掛けとなっているようだ。最上階からは竹生島も見え、びわ湖からの水軍による攻撃も監視できるような眺望であった。各地の現存天守閣を見ていて一度も戦闘が行われていない彦根城ほど、保存状態というか奇麗な状態で残っている天守閣は珍しい。是非訪れ見学されることをお薦めする。








★ご紹介しきれなかった画像は、アルバムでご覧頂けます。興味のある方は是非!
……………<切り取り線>……………
ご訪問してくださってありがとうです。
どなたさまでも、お気軽にコメント戴けると嬉しいです。
酔っ払っていても写る「CANON Power Shot G7XⅡ」と「iPhone」での撮影です。
日本ブログ村 こだわり料理部門、写真ブログ部門に参戦しております。
下のバナーをポチ(クリック)して頂くと励みになります。
どなたさまでも、お気軽にコメント戴けると嬉しいです。
酔っ払っていても写る「CANON Power Shot G7XⅡ」と「iPhone」での撮影です。
日本ブログ村 こだわり料理部門、写真ブログ部門に参戦しております。
下のバナーをポチ(クリック)して頂くと励みになります。























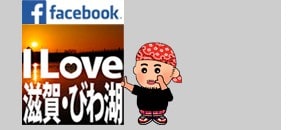









彦根城って素敵だすよね
しじみが社会人になったとき、商社に
勤めただすが、そこの上司が彦根の出で
何百回となく素敵なお城だと聞かされただすが💦
なんせ上司はおっさんだすし当時は
セクハラとは言われない時代で(笑)
きっといいお城のお話だったのかもだすが(笑)
覚えてないだす でもこうやって今
炎クリさんのブログでこうやっていろいろ
説明とお写真みせていただき
やっぱり素敵なお城なんだと納得だす
梁すごいだすよね まっすぐじゃないのも
素敵 門のところの石の配置の仕方も
魅力的だす
いっこ、いっこの写真で1つのブログできちゃう
ほどかっこいいだす
ぷっちんだす
炎クリさん♪
琵琶湖と共に。国宝彦根城の勇姿は
今もって、歴史とこの風景の中に雄大に聳えてるんですね。
石垣、櫓、橋、門、お堀や天守閣
あらゆる各所に施された仕掛けや創りは、戦国時代の多くの合戦の拠点として、名実ともに大きな役割を担ってきたんでしょうね。
当時は
戦うためが、全てだったんでしょうが、
今に残る現在は
この勇姿や当時を偲ばせる魅力。是非とも訪れたいと足を運ぶ。名城なんですね。
炎クリさんのお話は凄くためになり、
綺麗で各所のスポット写真と共に一気に読み進めてしまいました。いやぁ~先人の知恵といいそれに準じて作り上げていった人達。尊敬あるのみです。
今朝もありがとうございます。炎クリさん♪井伊直弼、まさか、ひこにゃんが城主の如く、人気博してるなんて思ってもみなかったでしょうね(笑
さすが素晴らしい^^
35万石・・・そういう名前の和菓子も売っていますね.
いつも見ている彦根城でもこういう風にみるとまさに立派なんですね.
今まで渡井の取り方が悪かった笑
また行きたくなります.
ひこにゃんにも会いたいわ.
また桜の花がよく似合う!
>ワシはそこらのボランティアガイドよりも詳しい知識を持っている
いくら地元であっても、なかなか分からないものです。
すごいですね。
ついて歩きたいわ。
松が立派!
>いろは松は藩士の名前を松につけ責任もって世話をさせたので大きく育った
策士ですね。
佐和口多聞櫓の梁は今なお、むかしのまま保っているのはすごいです。
そして天秤櫓には井伊家の「井」のマーク。
細かい所も凝っているんですね。
見所たくさんの彦根城。。いつかいってみたいです。
すばらしい、ガイドをありがとうございました。
しじみちゃん
お城のお話を聞かされても、セクハラにはならないと?どちらかと言うと「モラルハラスメント?」かな。彦根城は、白鷺城の姫路には一目置きますが、他の国宝級天守閣持ちの城郭と比べると、地元贔屓は抜きにしても秀でていると思います。梁の力強さも、魅力の一つなんですよ。写真にお褒めのお言葉ありがとうです。
くにちゃん
本編の写真では、少し離れた所に琵琶湖岸がありますが、お城の建造当時はびわ湖が際まであって、その後「干拓」されてこのような形になったようです。こんな戦闘モードを兼ね備えたお城なのに、一度の戦闘経験もないくらい、代々の城主の気遣いっていうか、当時の権力者への根回しが凄かったようです。そこらが好感度があがらない戦国武将たる理由なんでしょうけど、そのお陰でお城が無傷で残ったとも言えるでしょうね。「ひこにゃん」の住民票は彦根城天守閣にあるんですよ。(笑)
Satokoさん
これは4回に渡って行った写真を混ぜ合わせていますが、例えば木の葉が生い茂っていると、全景が見えない「天秤櫓」などがありますからね。わざわざ木が枯れて見えるようになってから行くんですよ。「ひこにゃん」って、土日に行かないと出張しているんでしたっけ?(笑)
Brosaさん
一度、ワシの知識の総仕上げとして、ボランティアガイドさんに案内してもらったんですが「これは言ってほしいなぁ~」って、場面が何回かありましたし、古いデータを説明されていたところもありました。佐和口多聞櫓は、石田三成の佐和山城から移築さ、今も姿を残しているのは「三成」の因縁ですね。Brosaさんが彦根城見物に来られましたら、ぜひご案内したいと思います。
皆さんの応援に感謝します。
いつも(^_-)-☆ありがとうです!
いっぱいポチしときます(^^)
全国に残っているとこみると、感激よ~
上から下まで、見ごたえあるお城だね~
やすさん
国宝の彦根城は、カメラアングルを考えたら、キリがないくらい色んなパターンがありますからね。自然とカット数も増えます。
チーママさん
滋賀県もキチンとしたお城は「彦根城」だけで、ここは見ごたえ充分なんですよ。あとは鉄筋コンクリート建ての「長浜城」と、その他は城跡ばかりで、同じような感じですよ。
皆さんの応援に感謝します。
いつも(^_-)-☆ありがとうです!