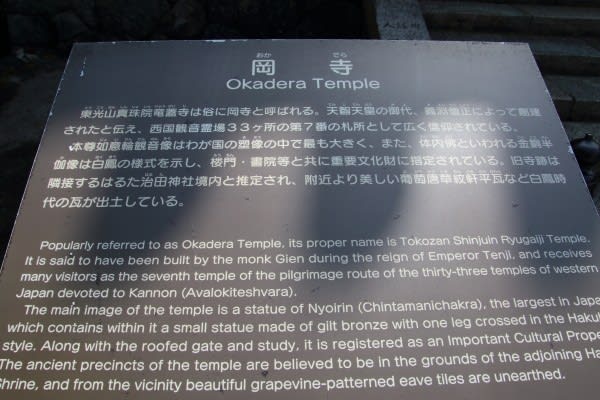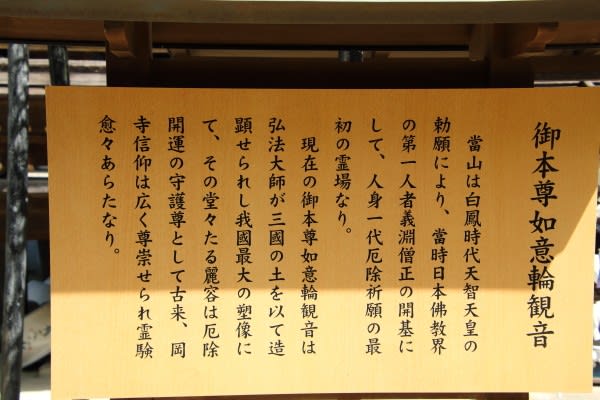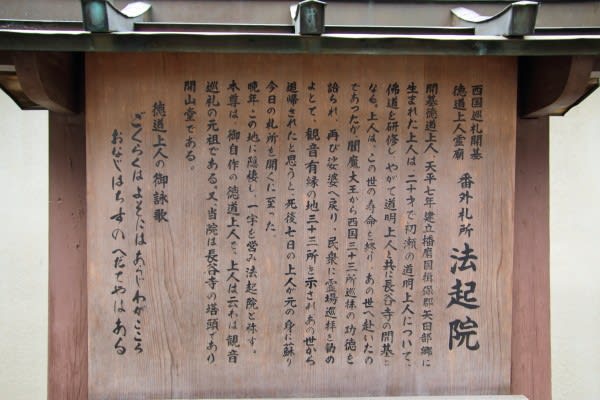6月5日「西国第十番札所 三室戸寺」(みむろとじ)」に行ってきました。 京都府
宇治市莵道滋賀谷(とどう しがたに)京阪電車宇治線「三室戸(みむろど)駅」より
歩いて15分です。
駅名は「と」に濁点つくのね。 (^^♪
ここ真っすぐ。
JR宇治線の踏切を渡り。
線路は続くよどこまでも ♬♫
車は右 徒歩は左ね。 車、遠回りやね。
沿道にもアジサイ咲いています。 (^^♪
08:32 拝観受付に来ました。拝観開始2分後。すごく並んでる。(^^♪
受付を通り、山門に向かいます。アジサイきれい。 おねえさんきれい。 (^^♪
雨上がりのアジサイです。 濡れてます。 (^^♪
葉も濡れてます。
「あぢさゐの 色をあつめて 虚空(こくう)とす」 岡井 省二
なんか哲学 (^^♪
本日より開催予定のライトアップの紙灯籠並んでいます。
源氏物語 四十七帖「総角(あげまき)」
「総角に 長き契りを 結びこめ おなじ所に よりもあはなん」薫中納言
なんかせつない (^^♪
庭園見えてきました。 見頃です。 !(^^)!
5年ぶりです。 前回はツツジ咲いてました。 (^^♪
あじさい一万株 毎年恒例 今月1日に開園したアジサイ園です。!(^^)!
今日はアジサイを見に来ました。(^^♪
先に本堂にお参りしてきます。 石段に「紫陽花昇龍図」 !(^^)!
コロナ終息を祈願し、60段の石段に赤60、白270,青270のあじさいポッド。 上部の
赤は宝珠を、それを護持せんと青いアジサイで表現した天空を昇っていく龍を白で表
したものだとか。 !(^^)!


上から。
「耳をさわれば福がくる 髭を撫でると健康長寿 しっぽをさすれば金運がつく」
人頭蛇身 「宇賀神(うがしん)像」 全部さわってきました。 !(^^)!
本堂。手前は蓮の鉢です。
「明星山(みじょうざん)三室戸寺」 宝亀(ほうき)元年(770年)光仁(こうにん)
天皇の勅願により最澄の師である行表(ぎょうひょう)が創建した本山修験宗の別格
本山です。ご本尊は千手観音像 写真も公表されていない秘仏とか。(^^)/
本堂左「福徳兎」
本堂右「勝運の牛」
お賽銭をと。(^^♪
参拝のみなさんいっぱい。 (^^♪

ですな。 (^^♪
「三重塔」へ。
「三重塔」元禄17年(1704年」建立 前高16m。 兵庫県佐用町の「高蔵寺」より、
明治43年に当寺が買い取り移設しました。
下りてきました。庭園を観に行きます。
「与楽苑(よらくえん)」名前ついてるのね。平成元年「中根 金作 氏」作。
足立美術館の庭園を作庭した人ですな。
5000坪の池泉回遊式の庭園です。(^^♪
先ほどの山門見えます。 色とりどり。 (^^♪
近くへ。
「花の茶屋」休憩処 。メニューいっぱい書いてる。 余計なことですけど傘破けてますよ。 (^^♪
お茶屋さんの前の水路です。水きれい。 (^^♪

お庭を散策。
後方の緑はツツジを刈り込みした処です。 (^^♪

撮影スポットなのかな 渋滞してる。 回れ右 (^^♪


左は「石庭」 枯山水です。
緑のなかへ。

お元気ですか。(^^♪


お土産処。飴ちゃん買って帰ろう。 (^^♪
紫陽花きれいです。 (^^)/~~~