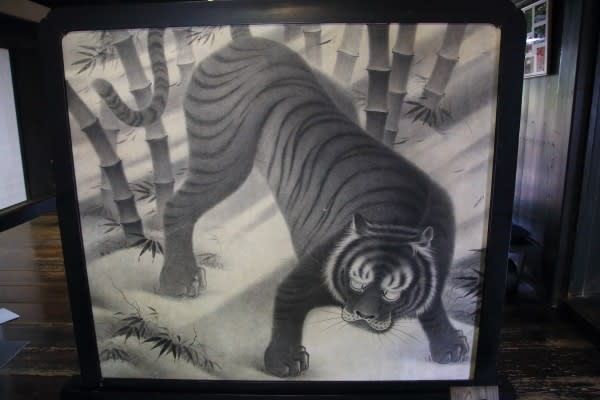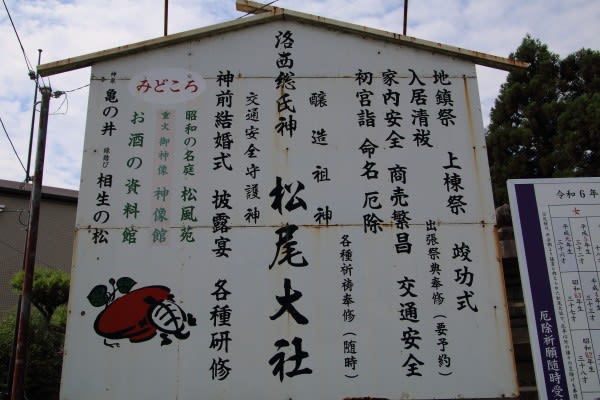8月10日「神泉苑(しんせんえん)」に行ってきました。 京都市中京区御池通(おい
けどおり)神泉苑町 京都市営地下鉄東西線「二条城前駅」より歩いて5分です。
09:00 駅に着きました。
一番出口より上がってきました。すぐ前が「二条城」です。押小路(おしこうじ)通
の信号を渡ります。「神泉苑」には信号を渡らずそのまま左へなんですがちょっとお
城の門を観ていきます。 (^^♪
朝早くから観光客いっぱいです。ほとんどインバウンドの方みたい。
お濠 いい感じです。 (^^♪
「東南隅櫓(とうなんすみやぐら)」往時は見張り台であり武器庫だったとか。

お昼にこの「東大手門」を見るの初めてです。夜はイルミネーションの催しをしてる
時にこの門から城内に入りました。
徳川家康が慶長8年(1603年)に築き、十五代慶喜が「大政奉還」を決意した場所です。
明るい時に行ってみよう
堀川通(府道38号線)の信号を渡りました。戦後の下水道整備で水流が消滅しました
が平成の水流復活事業で復活した「堀川」の開渠部です。御池通でまた暗渠、近鉄京
都線「上鳥羽口(かみとばぐち)駅」の西で再び開渠となり「鴨川」と合流していま
す。いい感じのリバーサイドね。 (^^♪
「橋本左内(さない)寓居跡」安政の大獄で26歳で獄死した福井藩士、幕末の志士で
す。ここに住んでらっしゃったのね。
「HOTEL THE MITSUI KYOTO」の外塀です。いいね。 (^^♪
おいでやす。 (^^♪
御池通りに来ました。「麻の館 麻小路」京都麻業(まぎょう)株式会社さんの支店
です。創業1952年 麻の専門店。いいね。いい感じやね。 (^^♪
なんのお店かな。二階の格子いいね。 (^^♪
「神泉苑」に着きました。
バス停のすぐそばなのね。
「神泉苑」延暦13年(794年) 桓武天皇が平安京の天皇御座所に南東に接して造営し
た天皇が御遊するための庭「禁苑(きんえん)」です。現在は「東寺(とうじ)真言
宗」の寺院となっています。
読めんけど、「神泉苑」と書いてあります。維新時に明治天皇のブレーンと云われた
山階宮晃(やましなのみや あきら)親王が明治16年に揮毫した書を元にしたとか。
それでは境内へ。 ガイドブックに掲載されているのね。ここも殆どインバウンドの
方です。 (^^♪
「法成就池(ほうじょうじゅいけ)」天長元年(824年)日照りが続き民が苦しんだ
淳和(じゅんわ)天皇の命により空海が雨乞いの祈祷を行ないました。その時、空海
が呼び寄せた「善女龍神」が棲むと云われるお池です。法力によって雨が降ったため
「法成就池」と呼ぶようになりました。 (^^♪
「恵方社(えほうしゃ)」 恵方におられる「歳徳神(さいとくじん)」をお祀りし
ています。毎年大晦日に新年の恵方の方角に社殿の向きを変える「恵方廻し」が行わ
れ円形の基壇の上に置かれた祠の向きが変わります。
「善女龍王社」 こちらは「拝殿」後方が「御本殿」です。
きれいなお守り。
「法成橋(ほうじょうばし)」を渡ります。
何匹いるのかな。どちらさんも元気でよろしい。 (^^♪
往時は二条通から三条通まで南北500m、東西240mに及ぶ大きな庭苑だったとか。
「本殿 利生殿(りしょうでん)」 お賽銭をと。
鎌倉時代以降、荒廃が徐々に進みさらに二条城築城の影響で境内が城内に取り込まれ
るなど著しく規模が縮小しました。現状を憂いた当時「東寺」と関わりのあった「快
我(かいが)上人」が朝廷に許しを得て、慶長12年(1607年)から20年余に渡り池や
堂塔を整え再興し以来東寺の管理する寺院となりました。ごくろうさんです。(^^♪
亀さん見なかったね。 (^^♪
名月や 神泉苑の 魚おとる 与謝 蕪村
元気な鯉を見て詠んだんですな。魚おとる(躍る) ね。 (^^♪
寺紋は「雨に龍」です。龍の顔はどこかいな。 (^^♪
天皇行幸の場であった神泉苑がこの「空海祈雨」が成功して以来、霊場として喧伝
されるようになりました。貞観11年(869年)疫病や地震などの災いが続き、災いを
成す怨霊を鎮めるために、歌舞の奉納、相撲、騎射などを行い八坂神社から神輿を送
り天下泰平を祈りました。それが「祇園祭」の起源とされています。
「祇園祭」発祥の地であります。 !(^^)!
「矢剱(やつるぎ)稲荷社」 鎮守のお稲荷さんみたいですな。
「弁天堂」増運弁財天(呼称不明)をお祀りしています。諸芸上達、福徳円満の御利
益があります。 (^^♪

「神泉苑 観月会」に「施餓鬼供養」 色々、行事あるのね。 (^^♪

油照り 神泉苑の 亀いずこ (^^)/~~~