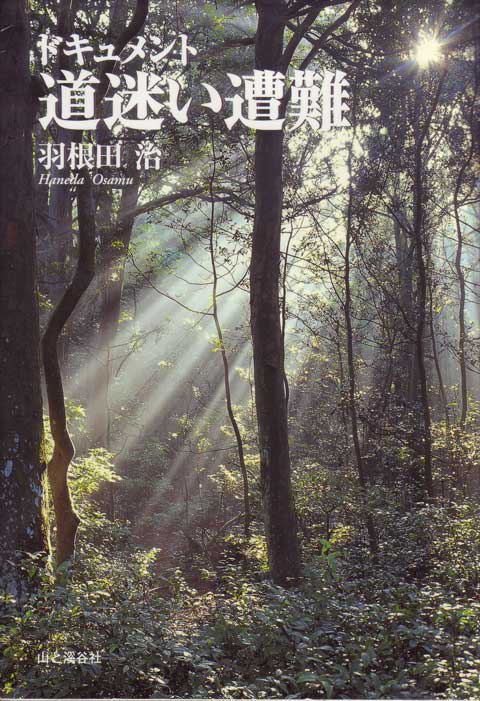増加する山岳遭難。
山岳遭難者数 態様別で一番 多いのは 道迷い。
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
7つの道迷い遭難を取り上げている。
道迷い「迷わぬ者に 悟りなし」
------------------------------------------------------------------------------
「だからほとんどの道迷い遭難は、ごく単純なことで防ぐことができる。なにしろ「おかしい」と思った時点で、引き返せばいいのだから。
ところが、この簡単なことが難しい。
それはたぶん、道迷い遭難が人の本能と願望の葛藤に起因するものだからだと思う。
「今たどっているルートが正しいものであってほしい。」とする願望と、本能が発する「そっちは違うぞ」という危険信号とのせめぎ合い。
その結果、人はどうしても楽なほう、安易なほうに流されがちであるから、が願望が勝ってしまう。かくして道迷い遭難が起きる。」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
------------------------------------------------------------------------------
■1 南アルプス 荒川三山 1999年8月
「このとき、「あれ?おかしいな」という疑念が一瞬頭に浮かんだという。だが、次の瞬間には「ルートはこっちだな」と思いこんでいた。
------------(中略)------------
さすがに「あ、これは道を間違ったな」と気がついた。
「でも『いいや、広河原小屋までもうすぐだろうから、このままおりちゃえ』と。」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
--------------------------------------
遭難者は 小屋のすぐ近くにいながら 8月14日から 救出される22日まで 9日間 苦闘することになる。
------------------------------------------------------------------------------
■2 北アルプス・常念岳 2001年1月
「焦る気持ちを落ち着かせようと、小休止して地形図を取り出して眺めてみた。しかし、現在地がわからず、視界がきかない以上、なんの問題の解決にもならなかった。「やばい これが遭難なのか」嫌な思いが頭をよぎった。」
「自分なら下りきれると自信過剰も手伝って、自ら遭難してでも最短ルートで下りようという甘い考えが支配していたと思う」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
--------------------------------------
冷静な判断が出来なくなっていった結果、最悪の選択をしてしまう。
------------------------------------------------------------------------------
■3 南アルプス 北岳 2001年9月
「今だったら、「このとき引き返すべきだった」と言うことは出来る。だが、このときは前日からろくに食事もとっていなかったし、疲れも溜まっていた。1時間 近く下がってきた道を登り返してもどることなど、とても考えられなかった。」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
--------------------------------------
1時間の引き返しを 惜しんだために、結局 道迷い 遭難、4日間の彷徨の末 救出となった。
------------------------------------------------------------------------------
■4 群馬・上州 武尊山 2002年5月
「武尊山の山頂には午後1時過ぎごろ着いた。------休憩時間は30分ほど、ひとりだったので長居することもなく、山頂をあとにした。その下山途中で道に迷った。だが、迷ったと気づいたときには、コースを外れてまだそれほど時間が時間が経っていなかった。-----「-----ええ、道を間違えていることはわかっていました、自分でも、「あ、これ、はまっている」って思っていましたから。でも 引き返せなかったんです。」-----なんとか 下っていけるのではないかと思いこんでしまった。」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
--------------------------------------
5日間 山中を彷徨し 林道に辿り着く。
------------------------------------------------------------------------------
■5 北信・高沢山 2003年5月
「山頂から雪の上を2,30メートル歩いていったところで、木に結びつけられている赤いリボンが目に入った。リボンはその先の木の枝にも結びつけられていた。」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
--------------------------------------
自分のとるべきコースでないのに ナビゲーション能力が不足していたので、全く違う目的で 他人が全く違うルートにつけた 赤いリボンに引き込まれ これが 引き金となり 5日間彷徨、救出。
------------------------------------------------------------------------------
■6 房総・麻綿原高原 2003年11月
「結局、小1時間をかけて どうにか林道に出たときには午後4時を回っていて、あたりも薄暗くなっていた。
最終的には、ここでの判断がその後の明暗を分けることになった。
まず、林道に出たいいが、この林道が清澄山に続いている林道なのかどうかの確信がもてなかった。」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
--------------------------------------
「慣れから来る油断と自信過剰」
つい甘く見てしまう 低山。だが 枝道など数多くあり 道に迷い易い。
------------------------------------------------------------------------------
■7 奥秩父・和名倉山 2005年5月
「この和名倉沢は沢登りの人気ルートとなっていて、沢を遡行してきた登山者が一般ルートに出るための目印として、枝沢に思い思いにテープを付けていた。一方、正規のルートにも、ルートを示すテープが付けられている。つまりこのあたりには、沢を遡行する登山者のためのテープと、縦走する登山者のためのテープが無秩序に入り乱れていたのであった。
それを知らない尾崎(仮名)は、いつしか正規のルートを外れ沢登りの人たちが付けたテープにずるずると引き込まれるようににして、和名倉沢の方に導かれていってしまう。」
『ドキュメント道迷い遭難』 羽根田 治 著 山と溪谷社 2006年1月
--------------------------------------
赤テープなど盲目的に信じずに 何の目的で付けているか 疑ってみるべきだ。
そして道迷い人を増やさないためにも 無闇に 残置テープを残さないようにしていかないといけない。
------------------------------------------------------------------------------

自分が行動不能になったとき
『山と溪谷 2010年1月号付録 山の便利帳』

仲間 が行動不能になったとき
『山と溪谷 2010年1月号付録 山の便利帳』
道迷い「迷わぬ者に 悟りなし」