 夜ちょびっと
夜ちょびっと 冬の抵抗続く?
冬の抵抗続く?これは旧ブログからの再録です。



みなさんご存知の『般若心経』は詳しくは『摩訶般若波羅蜜多心経』という。『西遊記』のモデルで有名な唐の三蔵法師玄奘の訳である。訳とはサンスクリット原典から漢訳したことである。お経と言うと漢文を連想する人が多いが、実はそれらはみな中国で翻訳されたものである。玄奘の訳を「新訳」といい、それ以前の訳を「旧訳(くやく)」という。

さて、タイトルの「般若波羅蜜多」であるが、これは悟りの智恵を意味する「般若」と悟りに向かう菩薩の修行を意味する「波羅蜜多」を合わせた言葉である。サンスクリット語では「パーラミター」といい、「波羅蜜多」はその音訳である。「到彼岸」という意訳もあるが、あえて原典の響きを残している。

この「パーラミター」は、旧訳では「波羅蜜」と訳されている。旧訳の代表的な訳者は鳩摩羅什(くまらじゅう=クマーラジーヴァ)である。鳩摩羅什(羅什と略すことあり)訳の『法華経』にも「波羅蜜」という言葉はよく出てくるが、決して「波羅蜜多」とは書かれていない。菩薩の六種の修行を「六波羅蜜」というが「六波羅蜜多」とはいわない。なぜ同じ「パーラミター」が「多」をつけたりつけなかったりするのか。

玄奘は唐初期の中国語の発音に忠実な音訳を試みた。現代中国語では「蜜」の音は「ミー」である。そこには「タ」行の音は含まれない。玄奘の時代やはり「蜜」は「ミー」であり、玄奘は「パーラミター」の最後の「ター」を表すために「多」の文字を加えたことが判っている。

玄奘より何百年も前の羅什の時代は「蜜」に「ミツ」という具合にタ行の音がついていた。そこで羅什はあえて「多」の字をつける必要がなかったわけである。

さて現在の日本語で「蜜」は「みつ」である。つまり唐代の中国ですでに失われていたタ行の音がついている。ということは日本語の「蜜」の発音はかなり古い時代に伝わった音であり、それがそのまま使われ続けたことになる。拙稿「呉音・漢音・宋音(唐音)」でも述べたが、このように日本の漢字の発音には、中国本土の発音の変遷を何気なく反映している場合がある。特にお経のように何百年間にわたり翻訳され続けたものには、その痕跡を見ることができる。ということを、今は亡き梶山雄一先生に習ったのであった。













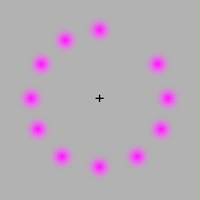







ところで鳩摩羅什はインド人ではありません。血筋的にはインドも入っていますが。東トルキスタン(西域)の亀茲(クチャ)国の人です。幼少の頃より仏教を学び、西域が中国(北朝)に占領され、捕虜として中国に連れてこられました。やがて長安に落ち着くまでの捕虜生活の間に中国語をマスターしたそうです。
鳩摩羅什をはじめ西域出身の訳経家は多いのですが、これらの訳経がどれだけ忠実にサンスクリット原典から翻訳されたのか、実は疑問視されています。いったん中央アジアの言語に翻訳されたものを漢訳(重訳)していると思われるケースが多いのです。玄奘もそのことを知っていたので、本当に信頼できる原典を求めてインドまで旅したわけです。