戦争責任最終回―4 太平洋戦争責任者を総括する
作家・司馬遼太郎は【大正生まれの「故老」】と言うエッセイの中で、東条英機を軍事の初歩も弁えない様な軍人であると痛烈に批判し【集団的政治発狂組合の事務局長】のような人物と断じている。
確かに東条は知識の詰め込み教育一辺倒の偏差値教育の中でペーパーテストには優秀であったが、内政・外交等の国家戦略、其の為の思想・哲学等には凡そ無縁な軍事官僚に過ぎなかった。従って善悪は別にして昭和陸軍の戦略構想を立てたのは陸大出身のエリート軍事官僚の中で統制派と言われた『一夕会』の中心メンバー、永田鉄山、石原莞爾、武藤章、田中新一の4人で、東条はその構想に乗っかって動いていたに過ぎない。そういった意味で【……事務局長】と言う命名は、成る程言い得て妙である。ある時は昭和天皇の意向に沿って避戦を唱え、そうかと思えばすぐさま田中新一の様な狂気の戦争推進者のお先棒を担いで徹底抗戦を唱えたりして多くの生命・財産を灰燼に帰した。
英米との衝突を避ける為【協調外交】を唱える荒木陸相や小畑敏四郎中将を中心とする皇道派は生ぬるいと主張する永田をリーダーとする統制派メンバーは、来るべき戦争に備えるべく【国家総力戦思想や満蒙領有論(中国への侵攻)】を主張し、皇道派排除に乗り出した。これが皇道派による【永田の暗殺、更には2.26事件】に繋がり、皇道派の衰退、軍上層部や政治家のクーデターへの恐怖心を煽って統制派のやりたい放題・暴走、太平洋戦争に繋がって行くことになる。
皇道派の中心人物、陸軍中将・小畑敏四郎は統制派・岡村寧次、永田鉄山と共に陸士同期で陸軍三羽烏の一人とされていたが「小畑と永田」の盟友二人の路線闘争が陸軍の派閥抗争に繋がり、小畑・永田の俊英を失ったことが、東条の様なバランス感覚の乏しい事務局長的な人間に太平洋戦争の舵取りをさせると言う悲劇を生むことになったのである。但し石原莞爾らが関東軍を使って惹き起こした満州事変を、永田を含めた一夕会は支持して居り、永田が関東軍の暴走を結果的に支持していたのは事実で、彼に対する評価は割れるところである。尚永田は東条が陸大試験に失敗した際、自宅に呼び、つききりで試験勉強を指導しており、永田が暗殺された時、東条に染み付いた皇道派憎しの感情が2・26事件の際に真っ先にクーデター討伐の声を上げさせることになった。この時同じ強硬意見を唱えた梅津美治郎が事件後、陸軍次官に登用され、その後梅津の推薦で東條はゴボウ抜きの様に陸軍次官に昇格し、陸軍の中枢を歩むことになった。又この無定見極まりない人事を反映し陸軍内では強硬意見を吐くことが出世に繋がると言うジンクスの様な悪弊が出来上がり、沈着冷静、俯瞰的視野で物事を判断する有能な人材が登用されなくなった。
一方小畑は皇道派の一掃を図る粛軍人事により、8月に予備役に編入され表舞台から姿を消した。尚終戦時1945年9月2日の太平洋戦争降伏文書調印式に、陸軍参謀総長であった梅津美治郎が出席を渋って居るのを見て、当時退役軍人として国務大臣に就任していた小畑は梅津を叱り飛ばし、梅津に降伏調印式に出席させたという逸話が残っている。
石原は関東軍赴任前から、20世紀後半期に日米間で戦争が行われるとする「世界最終戦争」という一種誇大妄想に近い世界観を持っていた。石原は将来的に、アジアの指導国家となった日本と、欧米を代表する米が世界最終戦争を戦うと予想し、その戦争に勝つためには鉄・石炭などの資源が必要で、その方策として全満州を領有し中国大陸の資源確保を確固たるものにする必要があると考えていたのである。太平洋戦争の根源はこの石原の妄想に端を発する。
当時の若槻礼次郎内閣は戦線の「不拡大」を決めたが、関東軍は政府や軍上層部の方針を無視して戦線を拡大した。陸軍省の軍事課長だった永田も、石原らの行動を支持した。満州事変は永田を中心とした一夕会の周到な準備によって遂行されたものだったのだ。石原らの謀略、越権行為に対し若槻はこれを罰する事はせず容認した為、以降出世欲に凝り固まった現地軍トップの暴走を、政治・軍首脳が抑止出来ず,逆に追認してしまうと言う大きな悪弊「石原モデル」が出来上がってしまった。
此処で纏めとして太平洋戦争の責任を負うべき者を総括しておきたい。
❂❂(1)⁂―太平洋戦争の引き金【満州事変】……関東軍参謀・石原莞爾、板垣征四郎、参謀本部・橋本欣五郎 林銑十郎(朝鮮軍司令官)
⁂―関東軍・朝鮮軍の現地軍暴走容認…若槻礼次郎首相、南次郎陸相
⁂―満州国の建設…土肥原賢二(奉天特務機関長)
❂❂(2) 【日中戦争の拡大】……近衛文麿(首相)、杉山元(陸相)、武藤章(参謀本部作戦課長)、田中新一(陸軍省軍事課長)……上司である石原(参謀本部作戦部長)の戦争不拡大方針を無視して、武藤、田中が戦線を拡大、杉山陸相もこれを後押しした。
広田弘毅外相は日中戦争に至る過程で外相・首相・外相を歴任し、外務省・文官として、中国進出の軍拡路線をとる軍に対して一貫して対峙していたにもかかわらず極東軍事裁判では軍国主義者ではないとされたが、南京事件での残虐行為を止めなかった不作為の責任を問われ死刑が言い渡された。田中新一始め、太平洋戦争のあらゆる局面で脅迫的に戦争拡大路線を主張した軍首脳が裁判を巧みにすり抜けたのに対し、周囲の助言にも拘らず一切弁明せず文官として唯一人死刑を受けたのである。作家城山三郎がこの悲劇の宰相の生涯を『落日燃ゆ』と言う小説に表し、テレビドラマ化されたりもしている。
❂❂(3)【三国同盟】……近衛文麿(首相)、松岡洋右(外相)、大島浩(駐独大使)、白鳥敏夫(駐伊大使)……親独・反米の二人の外交官の偏った情報で軍首脳に独・軍事力の優位を盲信させ同盟締結の空気を醸成した。この3国対英軍事同盟にソ連を加えて4国の対米軍事同盟化しアメリカを孤立させようとのドイツ礼賛者の松岡外相の動きにより同盟は対米軍事同盟化が明確となった。国際連盟脱退で派手なパフォーマンスを演じた松岡の構想倒れがもたらした禍である。海軍も独・留学経験者で長期に亙り軍令部総長を務め隠然たる勢力を誇った伏見宮博恭王が親独派で同盟賛成に回った。昭和天皇は同盟に強い危惧を示したが近衛が押し切り締結となった。独・ヒトラーを嫌悪する米国を一層硬化させる事となった。
❂❂(4)【日米開戦】……東条英機(首相・陸相)、杉山元(参謀総長)、田中新一(参謀本部作戦部長)、服部卓四郎(同・作戦課長)、辻政信(同・作戦班長)、佐藤賢了(陸軍省・軍務課長)、伏見宮博恭王(軍令部総長)、永野修身(軍令部総長)、岡敬純(海軍省軍務局長)、石川慎吾(軍務局2課長)
杉山が集めた参謀【田中・服部・辻】は日米開戦の最強硬派で最悪の人選であった。特に服部・辻は上層部や組織の命令を無視して軍事行動を起こし多大の損害をもたらした悪名高い【ノモハン事件】の首謀者である。こんな人物を登用した杉山(参謀総長)の責任は極めて重い。東条が昭和天皇の避戦要請に応えられなかったのは、これら強硬派に対し何等指導力を発揮できなかった為で【発狂組合の事務局長】と称される所以である。海軍では多くが米国には勝てないと考えていたが、伏見宮博恭王(軍令部総長)を筆頭に一部の対米主戦論者に引きずられ、或いは陸軍に対する対抗意識・面子から戦争に突入した。服部はおめおめと生き残り、あろうことか敗戦後もGHQ情報部ウィロビー将軍などと結びついて再軍備を画策した。
*―ノモンハンで惨敗し日本軍潰滅・敗走して来た中尉以下約40名が第一線は全滅したと報告した際、辻参謀はいきなり司令部壕から飛び出し、彼等を大喝した。 「何が全滅だ。お前達が生きてるじゃないか。旅団長、連隊長、軍旗を見捨てて、それでも日本の軍人か‼」、潰走してきた兵は辻参謀の命令に従い、背嚢を下し、手榴弾をポケットに入れて前線に戻って行って全滅した。ノモンハン惨敗の責任を隠すため、自決すべき理由の全くない3人の部隊長が辻の命令で自決させられた。戦後辻参謀(元陸軍大佐、辻政信)は、戦犯逃れの為、アジアに逃亡したが、逃亡生活が終わると国会議員となり、昭和36年ラオス視察中に行方不明となった。
❂❂(5)【連戦連敗・但し継戦気運衰えず】……小磯国昭(首相)、梅津美治郎(参謀総長)、杉山元(陸相)、及川古志郎(軍令部総長) 戦争指導班が出した厳しい現状認識を無視し勝算根拠無きまま戦争完遂を唱えた。戦争終結の時機を失して、硫黄島玉砕・沖縄戦併せて20万人強の戦死者を出した。サイパン・硫黄島陥落により本土大空襲が可能となり日本各地が焦土と化した。
⁂……特攻作戦 山本五十六少将(連合艦隊司令長官)は新聞記者に対し「僕が海軍にいる間は、飛行機の体当たり戦術を断行する」「艦長が艦と運命を共にするなら、飛行機も同じだ」と語っており、特攻作戦が意識され始めていた。マリアナ沖海戦の敗北を受け、伏見宮博恭王が「戦局困難回復の為、陸海軍ともになにか特殊な兵器を考える必要がある」と発言、参謀本部総長東條英機は「風船爆弾」と「対戦車挺身爆雷」他2〜3の新兵器を開発中と答え、軍令部総長嶋田繁太郎も2〜3考案中であると答えて、特攻戦略が本格化し、1944年6月元帥会議で承認される事となった。 海軍・ 大西滝治郎(中将)、同源田実(航空作戦参謀)達がこれを推進した。
草鹿龍之介(連合艦隊参謀長)は戦艦「大和」の司令官に特攻命令の説得を行った際、 「いずれ一億人・総特攻ということになるのであるから、 その模範となるよう立派に死んでもらいたい」と述べた。これに対し「大和」乗員の発言は「連合艦隊の作戦というのなら、なぜ参謀長は横浜・日吉の防空壕に隠れ潜んでおられるのか。防空壕を出て、自ら特攻の指揮をとる気はないのか」。戦艦大和の乗組員3332人のうち3063人が死亡した。
⁂……インパール作戦…日中戦争の発端となった盧溝橋事件の責任者・牟田口(当時連隊長)司令官が己の名誉挽回を図る目的で行った太平洋戦争の中で最も無策・無謀と言われるインド東北部インパールの占領作戦。大本営や南方郡司令官等から兵站に問題ありとして猛反対があったにも拘らず杉山(参謀総長)や東条(首相)のゴーサインを得て、食糧、医薬品は敵に求めるか現地自給を原則とし、ジャングルでは、雑草・蛇・野鼠等の小動物、昆虫が食料、これによりコレラ・チフス、マラリア、デング熱、栄養失調に陥る者が多く、病人は見捨てていく方針で、進撃を強行した。戦死者はおよそ3万人、傷病者は4万人、従軍兵士の口から作戦上の最大の敵は「①牟田口司令官、次いで②雨季とマラリア・疫病、③飢餓、最後に④敵兵・英国軍」であったとの記録が残されている。牟田口は3人の師団長に敵前逃亡等の責任を押し付け解任し、自らは第15軍司令官を罷免されて参謀本部附となり、12月に予備役編入されたが、翌1945年(昭和20年)1月に召集され、東条等の肝いりで応召の予備役中将として陸軍予科士官学校長に任命された。
❂❂(6)徹底抗戦・本土決戦、原爆、ソ連参戦……小磯国昭(首相)、及川古志郎(軍令部総長)、梅津美治郎(参謀総長)、豊田副武(軍令部総長)、阿南惟幾(陸相)、大西滝次郎(軍令部次長) *―45年2月東条が参謀総長兼務の天皇への上奏に際し「我が国知識階級の敗戦必死論は遺憾、アメリカは厭戦気運蔓延、本土空襲は近いうちに弱まる、ソ連参戦の可能性は薄い」と述べて居り、このような楽観論は軍上層部に共通していた。天皇の信頼を得ていた東条であるが部下には「天皇の命令といえども、国家に益なき場合は従う必要はない」と強硬意見を吐いている。東条は7月予備役となり重臣会議と陸軍大将の集会に出るだけとなったが、政府の和平工作に反し最後まで徹底抗戦を主張し続けていた。
*―45年8月ソ連参戦に対し、阿南陸相が布告を出した。「全軍将兵に告ぐ。 ソ聯遂に鋒を執つて皇国に寇す、名分如何に粉飾すと錐も、大東亜を侵略制覇せんとする野望 歴然たり、 事ここに至る又何をか言はん、断乎神洲護持の聖戦を戦ひ抜かんのみ 仮令(たとへ)草を喰み土を噛り野に伏するとも断じて戦ふところ、死中自ら活あるを信ず、 是即ち七生報国、「我れ一人生きてありせば」てふ(と言う)楠公救国の精神なると共に時宗の「莫煩悩」「驀直進前」以て敵を撃滅せる闘魂なり 全軍将兵宜しく一人も余さず楠公精神を具現すべし、而して又時宗の闘魂を再現して驕敵撃滅に驀直進前すべし。」 楠公(楠木正成)とか時宗(北条時宗)とか、一体全体将兵の誰が理解していると思うのか、「草を喰み土を噛り」等々、国家存亡の時に自己陶酔の極致、信じられない様な馬鹿丸出しの公文書、まさにこれを告げられた将兵や国民こそ「何をか言わんや」 である。
しかしこのような狂気に似た考え方は当時宮中、陸軍上層部に蔓延していた節がある。東京帝国大学の歴史学者・平泉澄が説いた皇国史観に基づく「平泉史観」が軍上層部にウイルスの如く蔓延し、東条や阿南の様な高官や中堅将校、更には近衛の様な政治家迄が一種マインドコントロールに陥ってかのような様相を呈した。
そもそも皇国史観とは古事記・日本書紀の神話部分も含め日本の国家統治は万世一系とする天皇によって連綿と行われて来たと考える歴史観で「明治憲法(第1条)や教育勅語」にもその旨明記されている。薩長土肥の下級武士と下級公家の討幕派によって行われた明治維新は、新政府の権威付けを行う為に、欧米のキリスト教に替わるものとして、天皇を超越的権威に仕立てあげ、新国家結集の旗印として利用する為に皇国史観を取り入れたのである。
昭和に入り軍国主義化と同時に万世一系の天皇をいただく日本の国家体制の優位性や永続性を強調する国粋主義が強まり、世界最終戦争を唱え満州事件を起こした石原莞爾も著書『戦争史大観・最終戦争論』で「現人神(あらひとがみ)たる天皇の御存在が世界統一の霊力である。」とし、「人類が心から現人神の信仰に悟入したところに、王道文明は初めてその真価を発揮する。最終戦争は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定する、人類歴史の中で空前絶後の大事件」と言う様な誇大妄想的な国体論を現している。
政府も国民の思想統一を図る為、文部省が「国体の本義」を発表し、これに迎合するように東大の学者の中には「天皇は神の子ではなく、神自身である(加藤玄智)、概念上神とすべきは唯一天皇(上杉慎吉)」と言った言説が相次ぎ、その集大成が平泉澄が説く独特の皇国史観であった。平泉史観とは南北朝時代、南朝公卿の北畠親房が著した歴史書「神皇正統記」の現代版に過ぎず学問的価値は甚だ乏しい。その要旨は日本は神武天皇以来、神勅により神孫が「正統」に君臨し,神の擁護が変わらず実現する「神国」であり、臣民の天皇への奉仕こそ「最高の道徳」であるとする考えである。又武将・楠木正成や北畠親房が活躍した南朝こそ正統だとする皇位継承論を展開している。平泉は満州事変以降、戦時体制が強化されていく中で、この歴史書の神話的言説を巧みに使って、ファッシズム、日本の領土拡張政策等の日本帝国主義のあらゆる行動を正当化する理論を展開し時代の尖兵となった。これに目を付けた軍上層部は陸海軍将校の教育に活用し、軍への講演活動の数は 1933 年の一年間だけで 43 か所、聴衆は1万4千人に昇ったと言われている。
平泉が特に強調したのは、小説「太平記」で描かれている世界、「後醍醐天皇への忠義の為に勝算の無い絶望的な戦いの中であっても,敢えて非業の死を遂げる」、これこそ「忠」であり「純正日本精神の美学の極致」であって、北畠親房、楠木正成らがこれを体現したと言う点であった。講義中には日本刀を振り回し「陸軍よ、願わくば精鋭にして豪壮なる事、この太刀の如くなれ………云々、但し武力は忠義の精神によって指導せられ、(天皇の)勅命によって発揮せられよ!!!」。何の事は無い三文講談師のアジ演説レベルであるが、この講義を参観し、惚れ込んだ東条が平泉邸をわざわざ訪問し、「士官学校の今迄の教育は間違っていた、これを立て直したいので平泉の弟子を士官学校の教師に出してほしい」と申し入れたのである。これ以降、平泉精神に凝り固まった多数の弟子達が士官学校教師に送り込まれ洗脳教育が行われる事になった。平泉教授は学外に私塾・(青々塾)を持ち、その出身者だけを東大の助手等にする公器私物化を行い、学内では(朱光会)と言う東大の右翼団体も組織していた。平泉は,「楠公精神」「皇国維持の道」「純正日本精神」等を主題に日本全国の陸海軍学校・基地を巡り公演を行った。講演会では太刀や短刀を抜き放ち、一朝有事には桜花の如く陛下の為に散らん……と言う様なセリフを時には和歌・短歌を交え朗々と芝居がかった口調で語り、若い将校の中には涙を流すものもいたと言う。オームの麻原彰晃顔負けのマインドコントロールである。
その教育の柱の一つは太平洋戦争は幕末、吉田松陰や橋本佐内が主張したように天皇親政を大日本帝国(朝鮮、台湾、千島・樺太、南洋諸島を含む)からアジア一帯に、更には世界全体に広げようとする、日本民族の神聖且つ正義の戦いであって、皇国無窮の発展の為にはこれを断行する以外にない。
更には太平洋戦争末期敗色濃厚となりつつある時には、「子や孫も含め一族郎党、天皇に忠義の限りを尽くして死ね、死んだら七度生き返って更に天皇に忠誠を尽くせ」と言う楠木正成の教えを日本人全員に求める事であった。
神孫である天皇を戴く我々に常に正義があるのだから、勝ち目は無くても先人に倣って天皇の為に命を捧げるのが最高の道徳である。この洗脳活動によって「玉砕」、「特攻」を命じる将校達から罪悪感が抜け去り、人間の死を前提とした人権無視の無茶苦茶な作戦がエスカレートして行くことになった。東条が作った「戦陣訓」もこの考えが下敷きにある。 海の特攻・人間魚雷「回転」の創案・開発者黒木少佐は熱烈な楠木正成の崇拝者で平泉教授の魂の分身と言われた人物である。又特攻隊は別名楠木正成ゆかりの寺の名前金剛にちなんで金剛隊又は楠木の家紋にちなんで菊水隊、更には楠木親子の別れの有名な地名・桜井にちなんで桜井隊とも呼ばれるなど一種異様なヒステリー状況を示していた。昭和20年6月に出された本土決戦基本大綱の一億玉砕の精神もこれがベースになって居り、鈴木首相もその席で「倒れるまで戦う所に日本人の本質があり、国民の信念は「七生尽忠」であります。」と決意を語っている。
東条以上に平泉教授に心酔していたのが阿南陸相である。阿南が近衛歩兵第二連隊長・大佐の頃、教授に紹介され、
足繁く「青々塾」を訪ねるようになり、終戦時、阿南陸相の廻りは塾生出身者の幕僚で固められるようになっていた。前述の「将兵に次ぐ」の告知文も塾生が代筆したものと推測される。
8月15日、この塾生出身の陸軍省・軍務局の竹下中佐、井田中佐、畑中少佐の3人が無条件降伏の天皇聖断による「ポッダム宣言受諾」は国体(天皇制)護持が保障されないとして日本の降伏を阻止する為、近衛第一師団長森赳中将を殺害、師団長命令を偽造し近衛歩兵第二連隊を用いて宮城(皇居)を占拠した。しかし陸軍首脳部の説得に失敗し首謀者の畑中少佐等の自刃によりクーデターは終息し天皇の玉音放送は無事行われる事になった。元々軍隊では聖徳太子の17条憲法3条の「承詔必謹」(天皇の命には必ず従え)が本分であったが、平泉は塾生たちに「純正日本人の臣道」として吉田松陰の「諫死論」を教えていた。諫死論は天皇の判断が間違っている時には一命を賭けて諫めなければならないと言う考え方で、畑中等の塾生達はこれを忠実に実行しようとしたものである。このクーデター計画は阿南陸相、梅津参謀総長も巻き込む大掛かりなものであったが、天皇の聖断が出て阿南等は腰が引け、畑中少佐等は事前に平泉にも相談を持ち掛けたが、手をぶるぶるふるわせるだけで終始無言を通し、畑中等は裏切られたとの思いで半ば自暴自棄の心理状態で皇居前の広場で自刃したものと思われる。この時刻平泉は教授会で終始無言、終わると辞表を提出し、さっさと福井の生家・白山神社に戻り、宮司に収まった。終戦直後、阿南陸相や特攻隊推進者大西中将が責任を感じて自刃したが、特攻・玉砕を煽りまくって多くの若者を死に至らしめた平泉には何の自責の念も無かった様である。そればかりか戦後も各地で、「狂信的な天皇崇拝思想と自分が日本陸軍を立て直した、日本を指導したとの自我自賛」の講演活動を続けていた。
思想家・大川周明がA級戦犯に指名されたが、平泉が国家・国民に与えた損失、被害の大きさから言えば遥かにこれを上回り、考えようによっては東条や阿南等と同等以上の罪科に値すると考えられる。
その後は皇学館大学学事顧問に就任し、「日本会議」の前身となる「日本を守る国民会議」発起人などで活動した。1956年文部省に教科書調査官制度が出来ると平泉のバックアップで皇国史観イデオロギーで凝り固まった朱光会出身の、村尾次郎、鳥巣通明、山口康助、平泉門下生が任官し、教育委員会にも進出、教育の国家統制に貢献危うい活動を行っている。
戦争責任最終回―5 続太平洋戦争責任者を総括する に続く
作家・司馬遼太郎は【大正生まれの「故老」】と言うエッセイの中で、東条英機を軍事の初歩も弁えない様な軍人であると痛烈に批判し【集団的政治発狂組合の事務局長】のような人物と断じている。
確かに東条は知識の詰め込み教育一辺倒の偏差値教育の中でペーパーテストには優秀であったが、内政・外交等の国家戦略、其の為の思想・哲学等には凡そ無縁な軍事官僚に過ぎなかった。従って善悪は別にして昭和陸軍の戦略構想を立てたのは陸大出身のエリート軍事官僚の中で統制派と言われた『一夕会』の中心メンバー、永田鉄山、石原莞爾、武藤章、田中新一の4人で、東条はその構想に乗っかって動いていたに過ぎない。そういった意味で【……事務局長】と言う命名は、成る程言い得て妙である。ある時は昭和天皇の意向に沿って避戦を唱え、そうかと思えばすぐさま田中新一の様な狂気の戦争推進者のお先棒を担いで徹底抗戦を唱えたりして多くの生命・財産を灰燼に帰した。
英米との衝突を避ける為【協調外交】を唱える荒木陸相や小畑敏四郎中将を中心とする皇道派は生ぬるいと主張する永田をリーダーとする統制派メンバーは、来るべき戦争に備えるべく【国家総力戦思想や満蒙領有論(中国への侵攻)】を主張し、皇道派排除に乗り出した。これが皇道派による【永田の暗殺、更には2.26事件】に繋がり、皇道派の衰退、軍上層部や政治家のクーデターへの恐怖心を煽って統制派のやりたい放題・暴走、太平洋戦争に繋がって行くことになる。
皇道派の中心人物、陸軍中将・小畑敏四郎は統制派・岡村寧次、永田鉄山と共に陸士同期で陸軍三羽烏の一人とされていたが「小畑と永田」の盟友二人の路線闘争が陸軍の派閥抗争に繋がり、小畑・永田の俊英を失ったことが、東条の様なバランス感覚の乏しい事務局長的な人間に太平洋戦争の舵取りをさせると言う悲劇を生むことになったのである。但し石原莞爾らが関東軍を使って惹き起こした満州事変を、永田を含めた一夕会は支持して居り、永田が関東軍の暴走を結果的に支持していたのは事実で、彼に対する評価は割れるところである。尚永田は東条が陸大試験に失敗した際、自宅に呼び、つききりで試験勉強を指導しており、永田が暗殺された時、東条に染み付いた皇道派憎しの感情が2・26事件の際に真っ先にクーデター討伐の声を上げさせることになった。この時同じ強硬意見を唱えた梅津美治郎が事件後、陸軍次官に登用され、その後梅津の推薦で東條はゴボウ抜きの様に陸軍次官に昇格し、陸軍の中枢を歩むことになった。又この無定見極まりない人事を反映し陸軍内では強硬意見を吐くことが出世に繋がると言うジンクスの様な悪弊が出来上がり、沈着冷静、俯瞰的視野で物事を判断する有能な人材が登用されなくなった。
一方小畑は皇道派の一掃を図る粛軍人事により、8月に予備役に編入され表舞台から姿を消した。尚終戦時1945年9月2日の太平洋戦争降伏文書調印式に、陸軍参謀総長であった梅津美治郎が出席を渋って居るのを見て、当時退役軍人として国務大臣に就任していた小畑は梅津を叱り飛ばし、梅津に降伏調印式に出席させたという逸話が残っている。
石原は関東軍赴任前から、20世紀後半期に日米間で戦争が行われるとする「世界最終戦争」という一種誇大妄想に近い世界観を持っていた。石原は将来的に、アジアの指導国家となった日本と、欧米を代表する米が世界最終戦争を戦うと予想し、その戦争に勝つためには鉄・石炭などの資源が必要で、その方策として全満州を領有し中国大陸の資源確保を確固たるものにする必要があると考えていたのである。太平洋戦争の根源はこの石原の妄想に端を発する。
当時の若槻礼次郎内閣は戦線の「不拡大」を決めたが、関東軍は政府や軍上層部の方針を無視して戦線を拡大した。陸軍省の軍事課長だった永田も、石原らの行動を支持した。満州事変は永田を中心とした一夕会の周到な準備によって遂行されたものだったのだ。石原らの謀略、越権行為に対し若槻はこれを罰する事はせず容認した為、以降出世欲に凝り固まった現地軍トップの暴走を、政治・軍首脳が抑止出来ず,逆に追認してしまうと言う大きな悪弊「石原モデル」が出来上がってしまった。
此処で纏めとして太平洋戦争の責任を負うべき者を総括しておきたい。
❂❂(1)⁂―太平洋戦争の引き金【満州事変】……関東軍参謀・石原莞爾、板垣征四郎、参謀本部・橋本欣五郎 林銑十郎(朝鮮軍司令官)
⁂―関東軍・朝鮮軍の現地軍暴走容認…若槻礼次郎首相、南次郎陸相
⁂―満州国の建設…土肥原賢二(奉天特務機関長)
❂❂(2) 【日中戦争の拡大】……近衛文麿(首相)、杉山元(陸相)、武藤章(参謀本部作戦課長)、田中新一(陸軍省軍事課長)……上司である石原(参謀本部作戦部長)の戦争不拡大方針を無視して、武藤、田中が戦線を拡大、杉山陸相もこれを後押しした。
広田弘毅外相は日中戦争に至る過程で外相・首相・外相を歴任し、外務省・文官として、中国進出の軍拡路線をとる軍に対して一貫して対峙していたにもかかわらず極東軍事裁判では軍国主義者ではないとされたが、南京事件での残虐行為を止めなかった不作為の責任を問われ死刑が言い渡された。田中新一始め、太平洋戦争のあらゆる局面で脅迫的に戦争拡大路線を主張した軍首脳が裁判を巧みにすり抜けたのに対し、周囲の助言にも拘らず一切弁明せず文官として唯一人死刑を受けたのである。作家城山三郎がこの悲劇の宰相の生涯を『落日燃ゆ』と言う小説に表し、テレビドラマ化されたりもしている。
❂❂(3)【三国同盟】……近衛文麿(首相)、松岡洋右(外相)、大島浩(駐独大使)、白鳥敏夫(駐伊大使)……親独・反米の二人の外交官の偏った情報で軍首脳に独・軍事力の優位を盲信させ同盟締結の空気を醸成した。この3国対英軍事同盟にソ連を加えて4国の対米軍事同盟化しアメリカを孤立させようとのドイツ礼賛者の松岡外相の動きにより同盟は対米軍事同盟化が明確となった。国際連盟脱退で派手なパフォーマンスを演じた松岡の構想倒れがもたらした禍である。海軍も独・留学経験者で長期に亙り軍令部総長を務め隠然たる勢力を誇った伏見宮博恭王が親独派で同盟賛成に回った。昭和天皇は同盟に強い危惧を示したが近衛が押し切り締結となった。独・ヒトラーを嫌悪する米国を一層硬化させる事となった。
❂❂(4)【日米開戦】……東条英機(首相・陸相)、杉山元(参謀総長)、田中新一(参謀本部作戦部長)、服部卓四郎(同・作戦課長)、辻政信(同・作戦班長)、佐藤賢了(陸軍省・軍務課長)、伏見宮博恭王(軍令部総長)、永野修身(軍令部総長)、岡敬純(海軍省軍務局長)、石川慎吾(軍務局2課長)
杉山が集めた参謀【田中・服部・辻】は日米開戦の最強硬派で最悪の人選であった。特に服部・辻は上層部や組織の命令を無視して軍事行動を起こし多大の損害をもたらした悪名高い【ノモハン事件】の首謀者である。こんな人物を登用した杉山(参謀総長)の責任は極めて重い。東条が昭和天皇の避戦要請に応えられなかったのは、これら強硬派に対し何等指導力を発揮できなかった為で【発狂組合の事務局長】と称される所以である。海軍では多くが米国には勝てないと考えていたが、伏見宮博恭王(軍令部総長)を筆頭に一部の対米主戦論者に引きずられ、或いは陸軍に対する対抗意識・面子から戦争に突入した。服部はおめおめと生き残り、あろうことか敗戦後もGHQ情報部ウィロビー将軍などと結びついて再軍備を画策した。
*―ノモンハンで惨敗し日本軍潰滅・敗走して来た中尉以下約40名が第一線は全滅したと報告した際、辻参謀はいきなり司令部壕から飛び出し、彼等を大喝した。 「何が全滅だ。お前達が生きてるじゃないか。旅団長、連隊長、軍旗を見捨てて、それでも日本の軍人か‼」、潰走してきた兵は辻参謀の命令に従い、背嚢を下し、手榴弾をポケットに入れて前線に戻って行って全滅した。ノモンハン惨敗の責任を隠すため、自決すべき理由の全くない3人の部隊長が辻の命令で自決させられた。戦後辻参謀(元陸軍大佐、辻政信)は、戦犯逃れの為、アジアに逃亡したが、逃亡生活が終わると国会議員となり、昭和36年ラオス視察中に行方不明となった。
❂❂(5)【連戦連敗・但し継戦気運衰えず】……小磯国昭(首相)、梅津美治郎(参謀総長)、杉山元(陸相)、及川古志郎(軍令部総長) 戦争指導班が出した厳しい現状認識を無視し勝算根拠無きまま戦争完遂を唱えた。戦争終結の時機を失して、硫黄島玉砕・沖縄戦併せて20万人強の戦死者を出した。サイパン・硫黄島陥落により本土大空襲が可能となり日本各地が焦土と化した。
⁂……特攻作戦 山本五十六少将(連合艦隊司令長官)は新聞記者に対し「僕が海軍にいる間は、飛行機の体当たり戦術を断行する」「艦長が艦と運命を共にするなら、飛行機も同じだ」と語っており、特攻作戦が意識され始めていた。マリアナ沖海戦の敗北を受け、伏見宮博恭王が「戦局困難回復の為、陸海軍ともになにか特殊な兵器を考える必要がある」と発言、参謀本部総長東條英機は「風船爆弾」と「対戦車挺身爆雷」他2〜3の新兵器を開発中と答え、軍令部総長嶋田繁太郎も2〜3考案中であると答えて、特攻戦略が本格化し、1944年6月元帥会議で承認される事となった。 海軍・ 大西滝治郎(中将)、同源田実(航空作戦参謀)達がこれを推進した。
草鹿龍之介(連合艦隊参謀長)は戦艦「大和」の司令官に特攻命令の説得を行った際、 「いずれ一億人・総特攻ということになるのであるから、 その模範となるよう立派に死んでもらいたい」と述べた。これに対し「大和」乗員の発言は「連合艦隊の作戦というのなら、なぜ参謀長は横浜・日吉の防空壕に隠れ潜んでおられるのか。防空壕を出て、自ら特攻の指揮をとる気はないのか」。戦艦大和の乗組員3332人のうち3063人が死亡した。
⁂……インパール作戦…日中戦争の発端となった盧溝橋事件の責任者・牟田口(当時連隊長)司令官が己の名誉挽回を図る目的で行った太平洋戦争の中で最も無策・無謀と言われるインド東北部インパールの占領作戦。大本営や南方郡司令官等から兵站に問題ありとして猛反対があったにも拘らず杉山(参謀総長)や東条(首相)のゴーサインを得て、食糧、医薬品は敵に求めるか現地自給を原則とし、ジャングルでは、雑草・蛇・野鼠等の小動物、昆虫が食料、これによりコレラ・チフス、マラリア、デング熱、栄養失調に陥る者が多く、病人は見捨てていく方針で、進撃を強行した。戦死者はおよそ3万人、傷病者は4万人、従軍兵士の口から作戦上の最大の敵は「①牟田口司令官、次いで②雨季とマラリア・疫病、③飢餓、最後に④敵兵・英国軍」であったとの記録が残されている。牟田口は3人の師団長に敵前逃亡等の責任を押し付け解任し、自らは第15軍司令官を罷免されて参謀本部附となり、12月に予備役編入されたが、翌1945年(昭和20年)1月に召集され、東条等の肝いりで応召の予備役中将として陸軍予科士官学校長に任命された。
❂❂(6)徹底抗戦・本土決戦、原爆、ソ連参戦……小磯国昭(首相)、及川古志郎(軍令部総長)、梅津美治郎(参謀総長)、豊田副武(軍令部総長)、阿南惟幾(陸相)、大西滝次郎(軍令部次長) *―45年2月東条が参謀総長兼務の天皇への上奏に際し「我が国知識階級の敗戦必死論は遺憾、アメリカは厭戦気運蔓延、本土空襲は近いうちに弱まる、ソ連参戦の可能性は薄い」と述べて居り、このような楽観論は軍上層部に共通していた。天皇の信頼を得ていた東条であるが部下には「天皇の命令といえども、国家に益なき場合は従う必要はない」と強硬意見を吐いている。東条は7月予備役となり重臣会議と陸軍大将の集会に出るだけとなったが、政府の和平工作に反し最後まで徹底抗戦を主張し続けていた。
*―45年8月ソ連参戦に対し、阿南陸相が布告を出した。「全軍将兵に告ぐ。 ソ聯遂に鋒を執つて皇国に寇す、名分如何に粉飾すと錐も、大東亜を侵略制覇せんとする野望 歴然たり、 事ここに至る又何をか言はん、断乎神洲護持の聖戦を戦ひ抜かんのみ 仮令(たとへ)草を喰み土を噛り野に伏するとも断じて戦ふところ、死中自ら活あるを信ず、 是即ち七生報国、「我れ一人生きてありせば」てふ(と言う)楠公救国の精神なると共に時宗の「莫煩悩」「驀直進前」以て敵を撃滅せる闘魂なり 全軍将兵宜しく一人も余さず楠公精神を具現すべし、而して又時宗の闘魂を再現して驕敵撃滅に驀直進前すべし。」 楠公(楠木正成)とか時宗(北条時宗)とか、一体全体将兵の誰が理解していると思うのか、「草を喰み土を噛り」等々、国家存亡の時に自己陶酔の極致、信じられない様な馬鹿丸出しの公文書、まさにこれを告げられた将兵や国民こそ「何をか言わんや」 である。
しかしこのような狂気に似た考え方は当時宮中、陸軍上層部に蔓延していた節がある。東京帝国大学の歴史学者・平泉澄が説いた皇国史観に基づく「平泉史観」が軍上層部にウイルスの如く蔓延し、東条や阿南の様な高官や中堅将校、更には近衛の様な政治家迄が一種マインドコントロールに陥ってかのような様相を呈した。
そもそも皇国史観とは古事記・日本書紀の神話部分も含め日本の国家統治は万世一系とする天皇によって連綿と行われて来たと考える歴史観で「明治憲法(第1条)や教育勅語」にもその旨明記されている。薩長土肥の下級武士と下級公家の討幕派によって行われた明治維新は、新政府の権威付けを行う為に、欧米のキリスト教に替わるものとして、天皇を超越的権威に仕立てあげ、新国家結集の旗印として利用する為に皇国史観を取り入れたのである。
昭和に入り軍国主義化と同時に万世一系の天皇をいただく日本の国家体制の優位性や永続性を強調する国粋主義が強まり、世界最終戦争を唱え満州事件を起こした石原莞爾も著書『戦争史大観・最終戦争論』で「現人神(あらひとがみ)たる天皇の御存在が世界統一の霊力である。」とし、「人類が心から現人神の信仰に悟入したところに、王道文明は初めてその真価を発揮する。最終戦争は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定する、人類歴史の中で空前絶後の大事件」と言う様な誇大妄想的な国体論を現している。
政府も国民の思想統一を図る為、文部省が「国体の本義」を発表し、これに迎合するように東大の学者の中には「天皇は神の子ではなく、神自身である(加藤玄智)、概念上神とすべきは唯一天皇(上杉慎吉)」と言った言説が相次ぎ、その集大成が平泉澄が説く独特の皇国史観であった。平泉史観とは南北朝時代、南朝公卿の北畠親房が著した歴史書「神皇正統記」の現代版に過ぎず学問的価値は甚だ乏しい。その要旨は日本は神武天皇以来、神勅により神孫が「正統」に君臨し,神の擁護が変わらず実現する「神国」であり、臣民の天皇への奉仕こそ「最高の道徳」であるとする考えである。又武将・楠木正成や北畠親房が活躍した南朝こそ正統だとする皇位継承論を展開している。平泉は満州事変以降、戦時体制が強化されていく中で、この歴史書の神話的言説を巧みに使って、ファッシズム、日本の領土拡張政策等の日本帝国主義のあらゆる行動を正当化する理論を展開し時代の尖兵となった。これに目を付けた軍上層部は陸海軍将校の教育に活用し、軍への講演活動の数は 1933 年の一年間だけで 43 か所、聴衆は1万4千人に昇ったと言われている。
平泉が特に強調したのは、小説「太平記」で描かれている世界、「後醍醐天皇への忠義の為に勝算の無い絶望的な戦いの中であっても,敢えて非業の死を遂げる」、これこそ「忠」であり「純正日本精神の美学の極致」であって、北畠親房、楠木正成らがこれを体現したと言う点であった。講義中には日本刀を振り回し「陸軍よ、願わくば精鋭にして豪壮なる事、この太刀の如くなれ………云々、但し武力は忠義の精神によって指導せられ、(天皇の)勅命によって発揮せられよ!!!」。何の事は無い三文講談師のアジ演説レベルであるが、この講義を参観し、惚れ込んだ東条が平泉邸をわざわざ訪問し、「士官学校の今迄の教育は間違っていた、これを立て直したいので平泉の弟子を士官学校の教師に出してほしい」と申し入れたのである。これ以降、平泉精神に凝り固まった多数の弟子達が士官学校教師に送り込まれ洗脳教育が行われる事になった。平泉教授は学外に私塾・(青々塾)を持ち、その出身者だけを東大の助手等にする公器私物化を行い、学内では(朱光会)と言う東大の右翼団体も組織していた。平泉は,「楠公精神」「皇国維持の道」「純正日本精神」等を主題に日本全国の陸海軍学校・基地を巡り公演を行った。講演会では太刀や短刀を抜き放ち、一朝有事には桜花の如く陛下の為に散らん……と言う様なセリフを時には和歌・短歌を交え朗々と芝居がかった口調で語り、若い将校の中には涙を流すものもいたと言う。オームの麻原彰晃顔負けのマインドコントロールである。
その教育の柱の一つは太平洋戦争は幕末、吉田松陰や橋本佐内が主張したように天皇親政を大日本帝国(朝鮮、台湾、千島・樺太、南洋諸島を含む)からアジア一帯に、更には世界全体に広げようとする、日本民族の神聖且つ正義の戦いであって、皇国無窮の発展の為にはこれを断行する以外にない。
更には太平洋戦争末期敗色濃厚となりつつある時には、「子や孫も含め一族郎党、天皇に忠義の限りを尽くして死ね、死んだら七度生き返って更に天皇に忠誠を尽くせ」と言う楠木正成の教えを日本人全員に求める事であった。
神孫である天皇を戴く我々に常に正義があるのだから、勝ち目は無くても先人に倣って天皇の為に命を捧げるのが最高の道徳である。この洗脳活動によって「玉砕」、「特攻」を命じる将校達から罪悪感が抜け去り、人間の死を前提とした人権無視の無茶苦茶な作戦がエスカレートして行くことになった。東条が作った「戦陣訓」もこの考えが下敷きにある。 海の特攻・人間魚雷「回転」の創案・開発者黒木少佐は熱烈な楠木正成の崇拝者で平泉教授の魂の分身と言われた人物である。又特攻隊は別名楠木正成ゆかりの寺の名前金剛にちなんで金剛隊又は楠木の家紋にちなんで菊水隊、更には楠木親子の別れの有名な地名・桜井にちなんで桜井隊とも呼ばれるなど一種異様なヒステリー状況を示していた。昭和20年6月に出された本土決戦基本大綱の一億玉砕の精神もこれがベースになって居り、鈴木首相もその席で「倒れるまで戦う所に日本人の本質があり、国民の信念は「七生尽忠」であります。」と決意を語っている。
東条以上に平泉教授に心酔していたのが阿南陸相である。阿南が近衛歩兵第二連隊長・大佐の頃、教授に紹介され、
足繁く「青々塾」を訪ねるようになり、終戦時、阿南陸相の廻りは塾生出身者の幕僚で固められるようになっていた。前述の「将兵に次ぐ」の告知文も塾生が代筆したものと推測される。
8月15日、この塾生出身の陸軍省・軍務局の竹下中佐、井田中佐、畑中少佐の3人が無条件降伏の天皇聖断による「ポッダム宣言受諾」は国体(天皇制)護持が保障されないとして日本の降伏を阻止する為、近衛第一師団長森赳中将を殺害、師団長命令を偽造し近衛歩兵第二連隊を用いて宮城(皇居)を占拠した。しかし陸軍首脳部の説得に失敗し首謀者の畑中少佐等の自刃によりクーデターは終息し天皇の玉音放送は無事行われる事になった。元々軍隊では聖徳太子の17条憲法3条の「承詔必謹」(天皇の命には必ず従え)が本分であったが、平泉は塾生たちに「純正日本人の臣道」として吉田松陰の「諫死論」を教えていた。諫死論は天皇の判断が間違っている時には一命を賭けて諫めなければならないと言う考え方で、畑中等の塾生達はこれを忠実に実行しようとしたものである。このクーデター計画は阿南陸相、梅津参謀総長も巻き込む大掛かりなものであったが、天皇の聖断が出て阿南等は腰が引け、畑中少佐等は事前に平泉にも相談を持ち掛けたが、手をぶるぶるふるわせるだけで終始無言を通し、畑中等は裏切られたとの思いで半ば自暴自棄の心理状態で皇居前の広場で自刃したものと思われる。この時刻平泉は教授会で終始無言、終わると辞表を提出し、さっさと福井の生家・白山神社に戻り、宮司に収まった。終戦直後、阿南陸相や特攻隊推進者大西中将が責任を感じて自刃したが、特攻・玉砕を煽りまくって多くの若者を死に至らしめた平泉には何の自責の念も無かった様である。そればかりか戦後も各地で、「狂信的な天皇崇拝思想と自分が日本陸軍を立て直した、日本を指導したとの自我自賛」の講演活動を続けていた。
思想家・大川周明がA級戦犯に指名されたが、平泉が国家・国民に与えた損失、被害の大きさから言えば遥かにこれを上回り、考えようによっては東条や阿南等と同等以上の罪科に値すると考えられる。
その後は皇学館大学学事顧問に就任し、「日本会議」の前身となる「日本を守る国民会議」発起人などで活動した。1956年文部省に教科書調査官制度が出来ると平泉のバックアップで皇国史観イデオロギーで凝り固まった朱光会出身の、村尾次郎、鳥巣通明、山口康助、平泉門下生が任官し、教育委員会にも進出、教育の国家統制に貢献危うい活動を行っている。
戦争責任最終回―5 続太平洋戦争責任者を総括する に続く










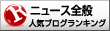















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます