このシキミ、四季を通じて葉が美しい為に仏前や墓前に供える事が多く、枝葉にはサフ
ロールを多く含み良い香りがするのでハナノキ・コウノキ等と呼ばれ、線香の材料にも
なるそうだ。
しかし、良い香りがする一方で、植物全体(特に果実)に有毒物質を含んでおり、種子が
近縁種のトウシキミ(乾燥した物は八角・八角茴香・大茴香と呼ばれる香辛料)やシイの
実に似ているので誤って食べて死亡した例もあり、その危険性のゆえにシキミの実は植
物としては唯一劇物に指定されているのだそうだ。
又、シキミは、死臭を和らげ悪霊や動物が土葬のお墓を荒らすのを防ぐ神聖な木とされ
ていたが、実に毒があるなど暗いイメージもあるせいか、縁起の悪い木として庭に植え
る事が少ないと言われている。
何だか全く逆の評価をされる不思議な木で、面白そうなので敢えて植えて見る事にした!
ロールを多く含み良い香りがするのでハナノキ・コウノキ等と呼ばれ、線香の材料にも
なるそうだ。
しかし、良い香りがする一方で、植物全体(特に果実)に有毒物質を含んでおり、種子が
近縁種のトウシキミ(乾燥した物は八角・八角茴香・大茴香と呼ばれる香辛料)やシイの
実に似ているので誤って食べて死亡した例もあり、その危険性のゆえにシキミの実は植
物としては唯一劇物に指定されているのだそうだ。
又、シキミは、死臭を和らげ悪霊や動物が土葬のお墓を荒らすのを防ぐ神聖な木とされ
ていたが、実に毒があるなど暗いイメージもあるせいか、縁起の悪い木として庭に植え
る事が少ないと言われている。
何だか全く逆の評価をされる不思議な木で、面白そうなので敢えて植えて見る事にした!
 |  |
| 花 | 花 |
 |  |
| 実 | 種 |











 >
>
 >
>








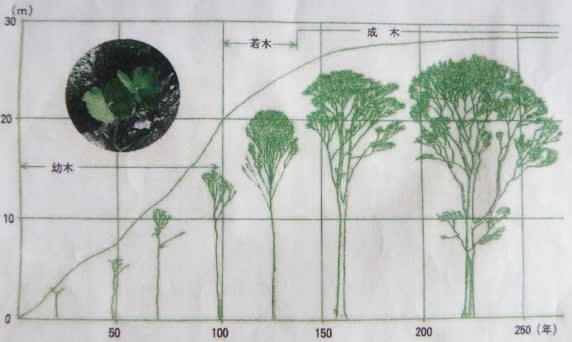



 >
> >
> >
>








 次はカンボクだが、これは簡単だ。
次はカンボクだが、これは簡単だ。