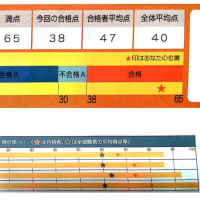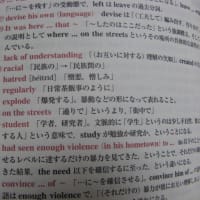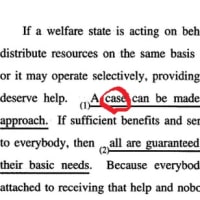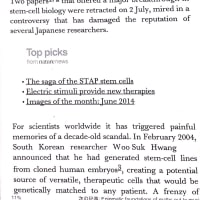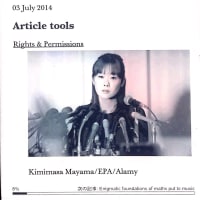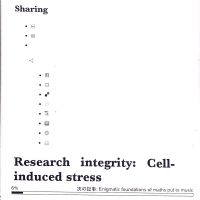先日、壺井栄原作の映画『二十四の瞳』をはじめて見てみた。いまではいくつかのバージョンがあるようだが、木下恵介監督、高峰秀子主演のオリジナルのほうだ。製作発表されたのは昭和29年(1954年)で、黒澤明の「七人の侍」等を抑えて『キネ旬』の一位に選ばれた。そんな日本映画の黄金時代の名作である。
「二十四の瞳」は昭和29年当時の観客にとって、間違いなく感涙物のはずだ。今の大人にとっては、批評的に見るならばたいそう興味深い作品と評価するだろう。ただし、塾のブログであるから書いておくのだが、平成生まれの子供たちに対して、そのまま鑑賞を勧められるような作品だとは言いにい。昭和の歴史を知らない子供たちには分りにくいし、退屈かもしれない作品である。いったい、どのような作品なのか?
私は初めてみるものだから、てっきり、戦争に翻弄される子供たちを描いた,反戦的な色彩根の強い映画かと思っていた。だが、予想は外れた。むしろ、昭和の20年間を、農村漁村の生活者の視点から、淡々と回顧する作品だったのである。それ故に、この映画作品が貴重なのである。が、同時に、現代の子供たちには少々わかりにくい。いや、もっとはっきりいってしまえば、私にも少々難しい作品だった。
映画は昭和3年(1928年)から始まっており、昭和25年くらいまでが描かれているという設定になっている。この年月を、1人の若い女性が結婚して子供がいる中年女性になるくらいの期間において、たっぷりと描いたものだ。当時の日本人の観客は、懐かしみながら、悲しみを思い起こしながら、鑑賞したことだろう。
外国の作品でいえば,ギリシャ映画の『旅芸人の記録』 と似たような雰囲気だ。調べてみると、日本人にはちょっと退屈なこのギリシャ映画は、1939年から1952年の歴史と政治史が旅芸人の視点から語られているものである。なるほど,年代的にも手法的にもかなり重なりあっていることが想像できる。
「旅芸人」よりも、さらに「二十四の瞳」と似ている映画も見たことがある。辺境の灯台守の夫婦の何十年かを描いた日本映画だ。調べてみたら、似ているの当たり前だ。該当する映画「喜びも悲しみも幾歳月」(昭和32年)は、木下惠介監督と高峰秀子という全く同じコンビだった。こちらは昭和7年(1932年)~昭和31年(1956年)の25年間を描いたものである。日本各地でロケーションしたという点では少々異なるが、辺境の地を舞台に、淡々と昭和史というと長い年月を描くという意味では、ほとんど同じテーマのバリエーションだと言ってもよい。
我々にとってこの映画が興味深いのは、次のような点だ。(1)都市インテリ・リベラルの視点ではなく、農村庶民の生活者の視点であること、(2)激動の昭和史というイメージから自由なこと、(3)ドラマは淡々と語られること、(4)昭和史20年間に社会変動がほとんど感じられないこと、(5)本当の主人公は12人の子供たちであり、ひとり一人の境遇が描き分けられようとしていること、(6)しかし、現代人にとっては12人の子供たちと、当時の状況が理解しにくくなっている。
(1)この作品は、リベラルでインテリ的な都会人や有識者の立場から昭和の歴史や戦争の時代を描いたりはしない。。舞台は小豆島であるが、おそらく日本のどの農村漁村でもよかったのだろう。東京でも地方都市でもない村を中心とした歴史回顧なのだ。そして、小学校の女先生である大石先生は、前任の先生とはちがって女子師範(香川県女子師範?)出身ではある。だが、大インテリだとか良家の子女ではないし、都会出身者でもない。普通に男と結婚し、子供を作るような庶民の女性である。そういうひとりの普通の女性の視点から、田舎にの子供たちの成長を描いた作品だということは、注目に値する。
(2)田舎の庶民の視点で昭和を描くというのは、ある意味では斬新だ。激動と苦難の昭和史というイメージはほとんど出てこないからである。特高に追い回されたり、米軍の空襲や爆撃に逃げまどう姿もなければ、戦後の食糧難も苦しみはここでは描かれない。「二十四の瞳」や「喜びも悲しみも幾歳月」(昭和32年)のような映画は、私たちがついつい親しんでしまう<都会リベラル>の昭和像とは異なる昭和が描かれているわけだ。
たとえば、大石先生はアカだと疑われそうになったり、軍国主義教育に辟易して小学校の先生をやめてしまう。しかしだからといって,厳しい言論とか軍人の横暴などが非常に強調して描かれているわけではないのである。あくまでも、等身大の辺境の庶民の生活にのしかかるものとして穏やかに描かれているわけである。
同様に、「はだしのゲン」や「ひめゆり学徒隊」のような戦争の悲劇からはいっさい無縁である。(余談であるが、私は5月の連休で沖縄に行きました。そのときにはじめて知ったのですが、「ひめゆり学徒隊」というのは、、沖縄師範学校の少女たちであり、普通の少女というよりは、むしろローカル・エリートの少女たちであることをはじめて知りました。)
また、終戦戦後の食糧難ですら、漁業や農業の盛んな田舎の島では、ほとんど存在しなかったように見える。「火垂るの墓」はあくまでも都会インテリの苦しい思い出なのであると再確認させられるのである。(映画「瀬戸内少年野球団」では、逆に戦後は羽振りが良かったように描かれる)。
(3)(2)のような特徴は、逆に言えば、ドラマの起伏が乏しいということになる。人は簡単にあっけなく死んでしまうが、大事件が起きるわけではない。 あくまでも淡々と人々が描かれている映画であり、小説なのだ。
(4)さらにいえば、社会変化のようなものもほとんど見られないのだ。20年間にわたって、島の風景や人々の暮らしはほとんど変化していないのだ。
島を走るシマバスは全く変化がない。昭和3年に登場する子供たちと、最後に登場する新しい世代の子供たちとでは、20年の年月が経ているはずなのに、ほとんど何の変化もないようにすら見える。もちろん、校舎はまったく変わっていない。唯一変化したのが大石先生である。高峰秀子演じる女先生が、若い女性から中年女性になったということだけなのだ。日本の辺境の村は、モダンも戦災も、あるいは戦後復興とも無縁なのだ。
我々大人の鑑賞者が「二十四の瞳」を見て、村の昭和史を想像するとき、ある種の感銘をおぼえることができるだろう。(続く)
「二十四の瞳」は昭和29年当時の観客にとって、間違いなく感涙物のはずだ。今の大人にとっては、批評的に見るならばたいそう興味深い作品と評価するだろう。ただし、塾のブログであるから書いておくのだが、平成生まれの子供たちに対して、そのまま鑑賞を勧められるような作品だとは言いにい。昭和の歴史を知らない子供たちには分りにくいし、退屈かもしれない作品である。いったい、どのような作品なのか?
私は初めてみるものだから、てっきり、戦争に翻弄される子供たちを描いた,反戦的な色彩根の強い映画かと思っていた。だが、予想は外れた。むしろ、昭和の20年間を、農村漁村の生活者の視点から、淡々と回顧する作品だったのである。それ故に、この映画作品が貴重なのである。が、同時に、現代の子供たちには少々わかりにくい。いや、もっとはっきりいってしまえば、私にも少々難しい作品だった。
映画は昭和3年(1928年)から始まっており、昭和25年くらいまでが描かれているという設定になっている。この年月を、1人の若い女性が結婚して子供がいる中年女性になるくらいの期間において、たっぷりと描いたものだ。当時の日本人の観客は、懐かしみながら、悲しみを思い起こしながら、鑑賞したことだろう。
外国の作品でいえば,ギリシャ映画の『旅芸人の記録』 と似たような雰囲気だ。調べてみると、日本人にはちょっと退屈なこのギリシャ映画は、1939年から1952年の歴史と政治史が旅芸人の視点から語られているものである。なるほど,年代的にも手法的にもかなり重なりあっていることが想像できる。
「旅芸人」よりも、さらに「二十四の瞳」と似ている映画も見たことがある。辺境の灯台守の夫婦の何十年かを描いた日本映画だ。調べてみたら、似ているの当たり前だ。該当する映画「喜びも悲しみも幾歳月」(昭和32年)は、木下惠介監督と高峰秀子という全く同じコンビだった。こちらは昭和7年(1932年)~昭和31年(1956年)の25年間を描いたものである。日本各地でロケーションしたという点では少々異なるが、辺境の地を舞台に、淡々と昭和史というと長い年月を描くという意味では、ほとんど同じテーマのバリエーションだと言ってもよい。
我々にとってこの映画が興味深いのは、次のような点だ。(1)都市インテリ・リベラルの視点ではなく、農村庶民の生活者の視点であること、(2)激動の昭和史というイメージから自由なこと、(3)ドラマは淡々と語られること、(4)昭和史20年間に社会変動がほとんど感じられないこと、(5)本当の主人公は12人の子供たちであり、ひとり一人の境遇が描き分けられようとしていること、(6)しかし、現代人にとっては12人の子供たちと、当時の状況が理解しにくくなっている。
(1)この作品は、リベラルでインテリ的な都会人や有識者の立場から昭和の歴史や戦争の時代を描いたりはしない。。舞台は小豆島であるが、おそらく日本のどの農村漁村でもよかったのだろう。東京でも地方都市でもない村を中心とした歴史回顧なのだ。そして、小学校の女先生である大石先生は、前任の先生とはちがって女子師範(香川県女子師範?)出身ではある。だが、大インテリだとか良家の子女ではないし、都会出身者でもない。普通に男と結婚し、子供を作るような庶民の女性である。そういうひとりの普通の女性の視点から、田舎にの子供たちの成長を描いた作品だということは、注目に値する。
(2)田舎の庶民の視点で昭和を描くというのは、ある意味では斬新だ。激動と苦難の昭和史というイメージはほとんど出てこないからである。特高に追い回されたり、米軍の空襲や爆撃に逃げまどう姿もなければ、戦後の食糧難も苦しみはここでは描かれない。「二十四の瞳」や「喜びも悲しみも幾歳月」(昭和32年)のような映画は、私たちがついつい親しんでしまう<都会リベラル>の昭和像とは異なる昭和が描かれているわけだ。
たとえば、大石先生はアカだと疑われそうになったり、軍国主義教育に辟易して小学校の先生をやめてしまう。しかしだからといって,厳しい言論とか軍人の横暴などが非常に強調して描かれているわけではないのである。あくまでも、等身大の辺境の庶民の生活にのしかかるものとして穏やかに描かれているわけである。
同様に、「はだしのゲン」や「ひめゆり学徒隊」のような戦争の悲劇からはいっさい無縁である。(余談であるが、私は5月の連休で沖縄に行きました。そのときにはじめて知ったのですが、「ひめゆり学徒隊」というのは、、沖縄師範学校の少女たちであり、普通の少女というよりは、むしろローカル・エリートの少女たちであることをはじめて知りました。)
また、終戦戦後の食糧難ですら、漁業や農業の盛んな田舎の島では、ほとんど存在しなかったように見える。「火垂るの墓」はあくまでも都会インテリの苦しい思い出なのであると再確認させられるのである。(映画「瀬戸内少年野球団」では、逆に戦後は羽振りが良かったように描かれる)。
(3)(2)のような特徴は、逆に言えば、ドラマの起伏が乏しいということになる。人は簡単にあっけなく死んでしまうが、大事件が起きるわけではない。 あくまでも淡々と人々が描かれている映画であり、小説なのだ。
(4)さらにいえば、社会変化のようなものもほとんど見られないのだ。20年間にわたって、島の風景や人々の暮らしはほとんど変化していないのだ。
島を走るシマバスは全く変化がない。昭和3年に登場する子供たちと、最後に登場する新しい世代の子供たちとでは、20年の年月が経ているはずなのに、ほとんど何の変化もないようにすら見える。もちろん、校舎はまったく変わっていない。唯一変化したのが大石先生である。高峰秀子演じる女先生が、若い女性から中年女性になったということだけなのだ。日本の辺境の村は、モダンも戦災も、あるいは戦後復興とも無縁なのだ。
我々大人の鑑賞者が「二十四の瞳」を見て、村の昭和史を想像するとき、ある種の感銘をおぼえることができるだろう。(続く)