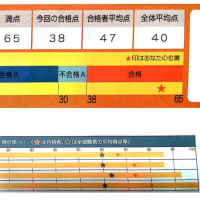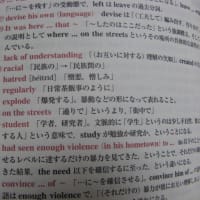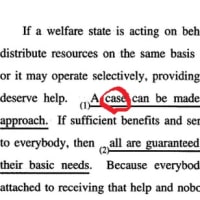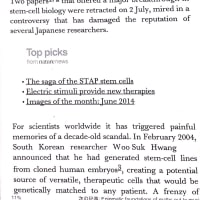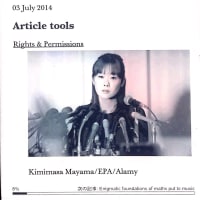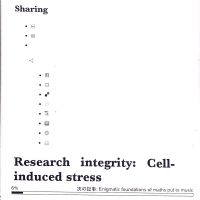(5)大石先生を演じるのは昭和の大女優高峰秀子である。だが、彼女も実は主人公の一人にすぎない。原作においてはもちろんのことだが、この映画においても公募で集められた子役たちが、本当の主人公になりえている。さすがだ。
田舎の子供たちを取り巻く諸問題とは、一言で言ってしまえば貧困問題といえてしまうかもしれない。しかし、ひとり一人の子供たちの境遇はそれぞれ微妙に異なり、それぞれ別の悩みを抱えていることが映画からも見て取れるのである。「貧困」という安易な要約を許さない点にこそ、「二十四の瞳」が群像ドラマとして効果を上げている点ではないかと思うのだ。
都会的意味で裕福な子供はいないかもしれないが、それなりに生活に余裕のある生徒もいるし、そうではない子もいることが分かる。生活の余裕がある子は、小学校高学年ともなると、様々な夢を抱ける。もちろん、それがかなうとは限らないことを我々は知っている。
進学できる子、できない子。裕福であっても、勉強嫌いで進学したくない子もいる。小学校卒業後も上の学校に進み、将来は兵隊になって下士官になろうという子。高等教育をうけて直ちに下士官になり、さらに出世しようという子。夢を語れない貧しい子、嫁として売られていくことを覚悟する女の子。歌手になりたいという夢がつよくて家出してしまう、裕福な家の子等々。もちろんその後には過酷な運命も待ち受けており、多くが後戦死したり、売られたりっするわけである。。。。
ところで「二十四の瞳」といえば、今回の記事に掲載した、汽車ごっこをしている村の貧しい子供たちのイメージであった。貧しい村の子供たちだけれども、ともに遊び、互いに助け合って成長していく例のイメージである。私も映画を見ている限りは、そういう風な受け取り方であった。しかし、原作を読むと、自尊心が強く、互いに張り合ったり、あるいは、恵まれない子を馬鹿にしたり、優越感にひたったりといった現実も、正確に描いているのだ。
たとえば、「将来は下士官になるぞ」という子がいるから、「僕は大学を卒業したら、即、下士官になるんだぞ」という趣旨の発言の子供がでてくる。だが、壺井栄は、その少年たちの言葉を黙って聴いているしかない、ずっとずっと貧しい子供が居ることを見逃さないのだ。
さらに残酷なこと、たとえば、「遊び女として売られた◎◎子に会ったぞ」とか、「めくらになるくらいなら死んでしまった方がよいのに」といった同級生の言葉さえも、この小説にはあるのだ。
映画にはもしかしたら十分に描写されていなかったかもしれない葛藤や対立が、実は原作にはあったということであろうか(続く)
田舎の子供たちを取り巻く諸問題とは、一言で言ってしまえば貧困問題といえてしまうかもしれない。しかし、ひとり一人の子供たちの境遇はそれぞれ微妙に異なり、それぞれ別の悩みを抱えていることが映画からも見て取れるのである。「貧困」という安易な要約を許さない点にこそ、「二十四の瞳」が群像ドラマとして効果を上げている点ではないかと思うのだ。
都会的意味で裕福な子供はいないかもしれないが、それなりに生活に余裕のある生徒もいるし、そうではない子もいることが分かる。生活の余裕がある子は、小学校高学年ともなると、様々な夢を抱ける。もちろん、それがかなうとは限らないことを我々は知っている。
進学できる子、できない子。裕福であっても、勉強嫌いで進学したくない子もいる。小学校卒業後も上の学校に進み、将来は兵隊になって下士官になろうという子。高等教育をうけて直ちに下士官になり、さらに出世しようという子。夢を語れない貧しい子、嫁として売られていくことを覚悟する女の子。歌手になりたいという夢がつよくて家出してしまう、裕福な家の子等々。もちろんその後には過酷な運命も待ち受けており、多くが後戦死したり、売られたりっするわけである。。。。
ところで「二十四の瞳」といえば、今回の記事に掲載した、汽車ごっこをしている村の貧しい子供たちのイメージであった。貧しい村の子供たちだけれども、ともに遊び、互いに助け合って成長していく例のイメージである。私も映画を見ている限りは、そういう風な受け取り方であった。しかし、原作を読むと、自尊心が強く、互いに張り合ったり、あるいは、恵まれない子を馬鹿にしたり、優越感にひたったりといった現実も、正確に描いているのだ。
たとえば、「将来は下士官になるぞ」という子がいるから、「僕は大学を卒業したら、即、下士官になるんだぞ」という趣旨の発言の子供がでてくる。だが、壺井栄は、その少年たちの言葉を黙って聴いているしかない、ずっとずっと貧しい子供が居ることを見逃さないのだ。
さらに残酷なこと、たとえば、「遊び女として売られた◎◎子に会ったぞ」とか、「めくらになるくらいなら死んでしまった方がよいのに」といった同級生の言葉さえも、この小説にはあるのだ。
映画にはもしかしたら十分に描写されていなかったかもしれない葛藤や対立が、実は原作にはあったということであろうか(続く)