特別史跡 多賀城跡を訪ねて

仙台駅から東北本線下り普通列車に乗って十数分ほど陸前山王駅を過ぎた左側の小高い丘陵が見てきます。これが多賀城跡です。
多賀城跡は江戸時代から注目され、大正年間に調査・研究がされていましたが、本格的には昭和三十八年の調査が最初でした。それ以来現在も発掘調査は行われています。

多賀城は、仙台平野の東北部に位置し、丘陵の高さは52メートルでこの丘陵から沖積地にわたっています。
丘陵は二本の谷によって東・西・中央の三つに分けられ丘陵上の平坦部に諸施設が設けられていました。

多賀城の全体の平面形は、丘陵に立地するため不整な四角形となっています。
規模は東辺1000メートル、南辺860メートル、西辺670メートル、北辺770メートルで、総面積が72ヘクタールとなっています。
これは、東北の古代城柵のなかでは、志和城(岩手県紫波町)と並ぶ規模となっています。

発掘調査と文献史料によれば、創建以降、多賀城は四期の変遷をたどっていることが明らかになっています。
第Ⅰ期(724年前後~762年) 創建期
第Ⅱ期(762年~780年) 多賀城碑にみられる天平宝字六年(762)藤原恵美朝臣朝猟による修造から、宝亀十一年(780)伊治公呰麻呂の乱によって焼亡するまで。
第Ⅲ期(780年~869年) 伊治公呰麻呂の乱の焼亡後の復興から、貞観十一年(869)の大地震により被害をうけるまで。
第Ⅳ期(869年~10世紀後半)地震後の復興から廃絶まで。
現在、復元整備されているのは第Ⅱ期を基にしています。
外郭の大部分が高さ5メートルの築地塀(土をつき固め、屋根をかけた土塀)で、東辺や西辺の低湿地では、材木を密接して立て並べた材木列の塀の部分もありました。
現在でも築地塀の跡が残っている部分もあります。

外郭の東辺築地塀は、当初のものが第Ⅲ期以降、内側(西側)へ40メートル移動して築き直されていることが明らかになりました。また、平安時代になると外郭築地塀の各所に櫓を設けるようになっていきます。
外郭には南門・東門・西門があり、いずれも正面三間、奥行き二間のいわゆる八脚門でした。
東門と西門は時期によって位置を変えて建造されています。

政庁に対する儀礼的な意味をもつ城の正面である外郭の南門を入ると、南北道路があり、300メートルほど北進すると政庁南門につきあたります。
外郭南門は丘陵上にあり南北道路はこの丘陵をいったん下ると、政庁南門まで上り坂になっています。
国内の郡司や蝦夷は政庁で行われる儀式に参列することがあったので、丘陵を利用して外郭南門から政庁への参上する人々へ威圧するように設計されていたのです。

【多賀城碑(壺の碑)】
多賀城碑は、碑文によれば天平宝字六年(762)に建てられ、他の文献史料によっては知ることのできない多賀城の創建と修造の年代を記しています。
この碑は多賀城の外郭南門跡のある丘陵上にあります。

県道根白石塩竈線の南側で、南門跡の内側にあり江戸時代に建てられた覆屋に収められています。
碑の高さは196センチメートル、幅92センチメートル、厚さ70センチメートルの大きさで砂岩の自然石の一面を平滑に加工して文字を刻み、刻文面を西にむけてほぼ垂直に立っています。
碑文の内容は、前半部分に、多賀城の位置を、京、蝦夷国界、常陸国界、下野国界、靺鞨(中国東北部松花江流域に居住した種族)国界からの距離で示し、後半部分に神亀元年(724)大野東人が建置し、天平宝字六年、藤原恵美朝獦が修造したことを記し、末尾に建碑した天平宝字六年十二月一日の日付を刻んでいます。
多賀城碑は、藤原恵美朝獦が多賀城を修造したことを記念し、かつ彼の造営事業を顕彰するために建てられた碑ということになります。
【多賀城廃寺跡】

多賀城廃寺跡は多賀城跡の東南約1キロメートルの多賀城市高崎の丘陵上にあります。

八世紀初頭に建立されたとされる寺院ですが確かな記録がなく古くは地名をとって高崎廃寺、現在では多賀城廃寺と呼んでいます。

昭和36年から41年まで5年にわたって発掘調査を行い、全貌が明らかになっています。
この寺は多賀城付属の官寺です。
多賀城創建時の瓦が廃寺跡から出土することから多賀城と同じ八世紀前半に創建され、十世紀中ごろまで存続し、多賀城と盛衰をともにしたとされています。

伽藍の配置は、三重塔と金堂を東西に配置する点に特徴が見られますが、この配置は筑前大宰府の観音寺と基本的に同じとなっています。
蝦夷に対する東の守りである多賀城の付属寺院の伽藍配置として、大陸・半島に対する西の守りである大宰府に付属する観音寺のそれを意識的に模倣したと云われています。

地形から見ると、規則正しい方形の寺域を占めることはなく、中門の南の南門と寺域を区画する施設もなかったとされています。

平安時代になると講堂が廃絶し、その基壇の上に小規模な堂、築地塀の西外側に二棟の堂が建造されてきます。
現在は松林のなか史跡公園として基壇・礎石等が復元整備されています。
(出典 宮城県の歴史 (県史) )
)
【多賀城跡MAP】
<iframe height="480" marginheight="0" src="https://maps.google.co.jp/maps?q=38.306789,140.988638&num=1&hl=ja&brcurrent=3,0x5f8985c0b16f2925:0x1c125a9c3661e1f9,0,0x5f8985b8bab807ed:0x961591ed7f0fe149&ie=UTF8&t=m&ll=38.306574,140.989609&spn=0.032329,0.054932&z=14&output=embed" frameborder="0" width="640" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe>
大きな地図で見る
【多賀城関連書籍】
<iframe style="width: 120px; height: 240px" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=FFFFFF&IS2=1&npa=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=takpon-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4787710362" frameborder="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=FFFFFF&IS2=1&npa=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=takpon-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4569771149" frameborder="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=FFFFFF&IS2=1&npa=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=takpon-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4886214525" frameborder="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=FFFFFF&IS2=1&npa=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=takpon-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4163693009" frameborder="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=FFFFFF&IS2=1&npa=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=takpon-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4642021965" frameborder="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe><iframe style="width: 120px; height: 240px" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=FFFFFF&IS2=1&npa=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=takpon-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4639008627" frameborder="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe>


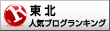




)












![岩手 前沢牛[奥州市前沢区]前沢牛サーロインステーキ(150g×2枚)](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fheimat%2fcabinet%2fikou_20100219%2fimg10591847933.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fheimat%2fcabinet%2fikou_20100219%2fimg10591847933.jpg%3f_ex%3d80x80)


























