
「恥の多い生涯を送って来ました。自分には、人間の生活というものが、見当つかないのです」―世の中の営みの不可解さに絶えず戸惑いと恐怖を抱き、生きる能力を喪失した主人公の告白する生涯。太宰が最後の力をふりしぼった長篇『人間失格』に、絶筆『グッド・バイ』、晩年の評論『如是我聞』を併せ収める。
出版社:岩波書店(岩波文庫)
太宰の代表作『人間失格』は、十代のときに2回、二十代のときに1回読んでいる。
十代で読んだときは、主人公に対していらいらし、二十代で読んだときも主人公に対していらいらし、そして三十代で読んだ今回も、主人公に対していらいらした。
どうやら僕はこの小説の主人公が嫌いであるらしい。
だが読み終えた後には、ふしぎと悲しみも覚えるのである。
それはこんな生き方しかできなかった、大庭葉蔵に対する憐みなのかもしれない。
大庭葉蔵はめんどくさい人である。
もちろん表面だけを見れば彼ほど印象のいい人はいないかもしれない。
周りにおべっかを使い、愛嬌は良く、おもしろいことを言う。見るからにネアカって感じだ。
だが彼は人間の営みというものが理解できない。
そしてそれゆえに自分が変わっているのかもしれない、と思いこみ、それをごまかそうとして道化を演じている。
彼がそんなことをするのは、基本的に人の目を気にするがためだろう。
人である以上、多かれ少なかれ、他人の目は多少は気にする。それはわかっているけれど、彼の場合は結構、自意識過剰の傾向は強いように思う。
そして同時に自己愛性が強い人とも感じた。
人目を気にして、嫌われないようにと願うあたり、人から愛されたいという願望が強いのではないだろうか。
ある意味、大庭葉蔵はパーソナリティ障害なのかもしれないと読んでいて感じた。
むかしはそんな便利な言葉もなかったから、それを抱えている人はしんどかったことは想像に難くない。
そんな彼の道化は時に人から見破られることもある。
たとえば竹一という同級生にはあっさり、そのことを見破られて、大いに戸惑っている。
別にいいじゃん、開き直れば、と僕は思うのだけど、彼はそういうことができない人らしい。
それゆえにいらいらするのだけど、見ていて悲しくもなる。
生きていくのは本当に大変だったんだろうな、と読んでいて感じてしまう。
だがそんな風に、他者に対する評価を気にする葉蔵が、他人のことに関心があるかと言ったらそうでもないのである。
たとえば銀座の女給が自分の身の上話をするときも、彼は興味を持てない。
彼が欲しているのは、侘びしい、と口にされて、ほかならぬ自分を求めてくれることなのではないか、とさえ思えてくる。
そういう観点からしても、やっぱりこの人は自己愛が強いのかもしれない。
だがそれをナルシストと嫌悪感をもって切り捨てるのも少し違う気がする。
彼は「友情」を感じたことがないとも言い、人間の生活がわからない、と言う。
そういう自分の感情の欠落を自覚しているからこそ、あるいは自己愛の中に逃れるしかなかったのかもしれない。
そしてその自己愛を守る(他人の自分に対する評価を守る)ためなら、自己保身よりも他者に対する献身をも厭わないのである。
いわく悲壮ですらある。本当に大変だったのだろう、とつくづく感じてならない。
そんな彼は最終的に、狂人という烙印を押されることで終わる。
しかしマダムは葉蔵のことを「神様みたいないい子」だったと語っている。
彼は他者から愛されるために、それこそ苦悶しながら戦った。
そしてその結果、彼と親しかった人は、彼にいつまでも良い印象を抱いてくれる。
そういう点、彼の努力は報われたのだろう。
それが美しいことかは別であり、皮肉にも見えなくはない。
葉蔵がその事実を知ったところで、別の場面で、彼はいろいろうだうだ考え悩むのだろう。
しかし世界の見方は主観でのみ、切り捨てることはできない。
そんなことを言っているようにも見え、なかなかおもしろい。
個人的に、『人間失格』は合わない作品ではある。
併録の『グッド・バイ』の方が、(自殺する直前に書いていたとは思えないほど)コメディタッチで、笑える箇所も多く好きだ。
『人間失格』よりもこちらを完結させてほしかったとすら思う。
それでも、太宰は自分の性癖をつぶさに観察し、描き、しかも客観的に捉え、物語としても上手く昇華していることは、伝わってくる。
何より内容について多くを語りたくなる。それだけでもすばらしい作品と言えるのだろう。
評価:★★★★(満点は★★★★★)
そのほかの太宰治作品感想
『ヴィヨンの妻』
『お伽草紙』
『斜陽』
『惜別』
『津軽』
『パンドラの匣』










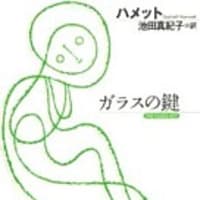

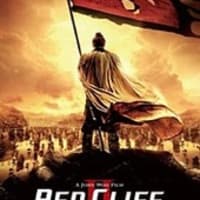
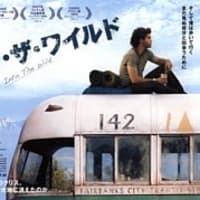
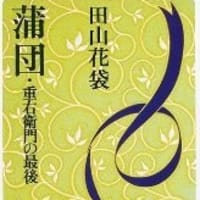
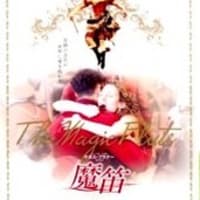
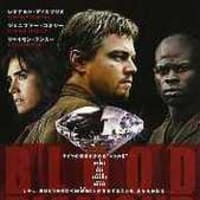
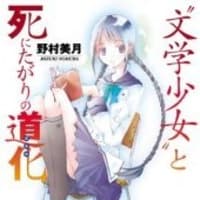
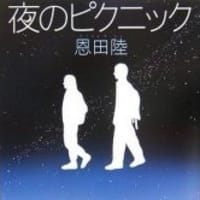










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます