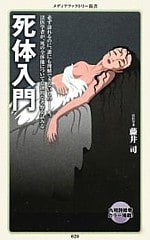生後まもないハイイロガンの雌のヒナは、こちらをじっとみつめていた。私のふと洩らした言葉に挨拶のひと鳴きを返した瞬間から、彼女は人間の私を母親と認め、よちよち歩きでどこへでもついてくるようになった…“刷り込み”などの理論で著名なノーベル賞受賞の動物行動学者ローレンツが、けものや鳥、魚たちの生態をユーモアとシンパシーあふれる筆致で描いた、永遠の名作。著者による「第2版へのまえがき」初収録。
出版社:早川書房(ハヤカワ文庫NF)
動物行動学者による科学エッセイである。
動物のことは言うほど好きでもないのだけど、対象の動物をしっかり観察し、それを愛情深く、ユーモラスに語る著者の筆致はともかくも達者。
知らない世界も多くて、非常に興味深かった。
たとえばコクマルガラスについて述べられた第五章。
刷り込みによって、コクマルガラスであるのに人間の仲間と思いこみ、人間を好きになることや、人間に恋し、口や耳に餌を入れようとするところは微笑ましい。
そしてそれによって、親から敵に対する恐怖を身につけることができなくなる点、本能的には敵を知らない点はおもしろく読んだ。
そしてコクマルガラスの求愛行動も、人間みたいで関心を引く。
ラストのロートゲルプとゲルプグリューンの話は、ちょっと感動的だった。
コクマルガラスというのはよく知らないけれど、鳥たちにもいろいろな行動原理があるのだなとつくづくと思い知らされる。
最後の章もおもしろい。
「敗北者」に対して、社会的抑制を持つ動物と、持たない動物がいるという事実は初めて知ることなので、ワクワクしながら読めた。
ジュズカケバトやバンビなど傷つける力が弱いからこそ、手加減というものを知らず、徹底的に相手を痛めつけることができるらしい。
しかし強力な武器を持っている動物は、相手が敗北し首筋を差し出すと、社会的抑制が働いて、かみたいけどかめなくなる。
この事実は本当にすてきだった。
そこには種の保全という遺伝子の因子もあるのだけど、人間のモラルにも通じるものがあって、心震わせる。
動物の世界は実に奥深い。
そのほかにも、ジャッカルとオオカミ系の犬の違いや、どの動物が飼うのにふさわしいかなど、興味を呼ぶ話題が多い。
僕は生物をまともには勉強しなかったし、動物をきちんと飼ったことすらない。
それでも非常に楽しく読め、知的好奇心を存分に満たしてくれる一冊であった。
評価:★★★(満点は★★★★★)