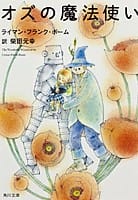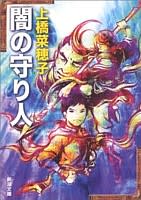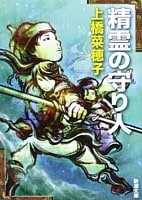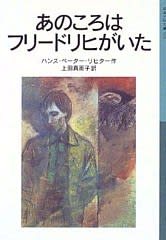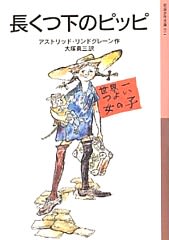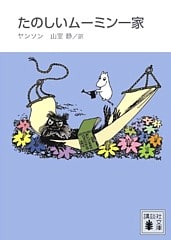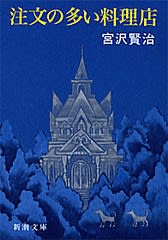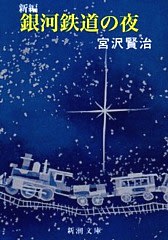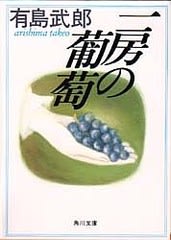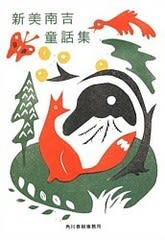サハラ砂漠に不時着した孤独な飛行士と,「ほんとうのこと」しか知りたがらない純粋な星の王子さまとのふれあいを描いた永遠の名作.
内藤濯 訳
出版社:岩波書店
『星の王子さま』を初めて読んだのは、岩波の内藤濯訳である。
この訳で久しぶりに読み返してみたが、新潮の河野訳と比べると、幾分言葉が古臭く、硬めであることは否めない。
しかし内容自体は当然ながらすばらしい。
この訳を通して、たくさんの人たちが感銘を受けたことも容易に納得できるのだ。
『星の王子さま』を端的に表現するならば、愛の物語ということになろう。
本書は、愛、というものが世界をいかに美しくするか、ということを象徴的に描いた作品であると読んでいると感じる。
王子さまは最初遠くの小さい星に住んでいたのだが、わがままな花にふりまわされて、その星を出ることとなる。
そうして王子さまはたくさんの星の住人に会っていくのだが、どの住人も基本的には自分のことしか考えていない。王さまやうぬぼれ男みたいに自尊心を肥大化させたり、実業家のように私欲に汲々とする者ばかり。
その中で唯一好感を持つのが、点灯夫だ。
それは彼が「じぶんのことではなく、ほかのことを考えているから」ということに尽きる。
そしてそんな点灯夫の姿こそ、本書の一つのテーマだろう。
なぜなら愛とは、自分以外の何ものかのことを考えることにあるからだ。
キツネとの会話はそういう意味で象徴的だ。
キツネなんてのは、この世にいくらでもいるが、キツネと仲良くなることで、「この世でたったひとりのひとになるし」「かけがえのないものになる」。
ありふれたキツネがその瞬間、特別な存在に変わっていくのだ。
そして特別な存在になるからこそ、その相手のことを思うと狂おしい気持ちにもなるのである。それはとても幸福なことだろう。
もちろんそうなると、その関係に責任が伴うし、守らなければいけない約束なども生まれる。
しかしそんな風に特別な存在ができるからこそ、世界は見方を変えるのだ。
「星があんなに美しいのも、目に見えない花が一つあるから」とも感じるし、「砂漠が美しいのは、どこかに井戸をかくしているから」と思えるような世界に変わっていく。
そしてそれは、「ぼく」にとっての「王子さま」に対する思いにも通じるものがある。
しかしそういった内面的なものは、物質主義や、自己愛の中からは決して見えない。
愛他的な観念を通してでしか到達できない世界なのだろう。
だからこそ、「かんじんなことは、目には見えない」。ということになるのかもしれない。
表層的なものからは見えざる世界なのだ。
そういう意味、この話はシンプルで平易な言葉で語っていながら、深い領域にまで到達している作品であるとつくづく感じる。
『星の王子さま』まさに名著である。
そう再認識する次第であった。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかのアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ作品感想
『人間の土地』
『星の王子さま』(河野万里子訳)