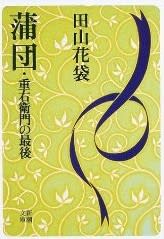
蒲団に残るあのひとの匂いが恋しい―赤裸々な内面生活を大胆に告白して、自然主義文学のさきがけとなった記念碑的作品『蒲団』と、歪曲した人間性をもった藤田重右衛門を公然と殺害し、不起訴のうちに葬り去ってしまった信州の閉鎖性の強い村落を描いた『重右衛門の最後』とを収録。
その新しい作風と旺盛な好奇心とナイーヴな感受性で若い明治日本の真率な精神の香気を伝える。
出版社:新潮社(新潮文庫)
「蒲団」は自然主義文学、言い換えるなら私小説の代表作として知らされる作品だ。
もっともそう書くと堅苦しく聞こえるけれど、読んでみると、そんな堅苦しい要素がなくて正直驚いてしまう。だがそれは読みやすいという意味ではない。堅苦しさを感じなかった理由は、この小説が本当にくだらない作品だったからである。
一言で説明するなら、そう、この小説の主人公がびっくりするくらいに、キモい、のだ。
この作品は小説家の中年男が、弟子となった女に惚れるという作品だ。
その中年の主人公が冒頭で、自身の趣味や主義や性癖をちょろりとこぼすシーンがある。たとえば浮気願望を語るシーン。
「出勤する途上に、毎朝邂逅う美しい女教師があった。渠はその頃この女に逢うのをその日その日の唯一の楽みとして、その女に就いていろいろな空想を逞うした。恋が成立って、神楽坂あたりの小待合に連れて行って、人目を忍んで楽しんだらどう……。細君に知れずに、二人近郊を散歩したらどう……。いや、それどころではない、その時、細君が懐妊しておったから、不図難産して死ぬ、その後にその女を入れるとしてどうであろう。……平気で後妻に入れることが出来るだろうかどうかなどと考えて歩いた。」
とか、小説のファンだと語る女性の手紙を読んで
「ある時などは写真を送れと言って遣ろうと思って、手紙の隅に小さく書いて、そしてまたこれを黒々と塗って了った。女性には容色と謂うものが是非必要である。容色のわるい女はいくら才があっても男が相手に為ない。時雄も内々胸の中で、どうせ文学を遣ろうというような女だから、不容色に相違ないと思った。けれどなるべくは見られる位の女であって欲しいと思った。」
というシーンには、苦笑7割、爆笑3割という比率で大いに笑ってしまった。
確かにこの程度の性欲めいた感情は男なら抱いても驚きはない。でもここまで大衆の面前で、赤裸々に語られると、読み手のこちらとしてはドン引きするほかにない。本当にキモい。
だがそのキモさこそがこの作品のおもしろいところであるのだ。
そんなキモさと作者の人間的な欠陥を描き上げることで、滑稽な中年男の姿が前面に出てくる。
特に好きになった女が恋人の男と関係を持っているかもしれないとやきもきするシーンはくだらなすぎておもしろい。
「こうしてはおかれぬ、こういう自由を精神の定まらぬ女に与えておくことは出来ん。監督せんければならん、保護せんけりゃならん。私共は熱情もあるが理性がある! 私共とは何だ! 何故私とは書かぬ、何故複数を用いた?」
と一人ツッコミをするシーンは最高だ。また
「その位なら、――あの男に身を任せていた位なら、何もその処女の節操を尊ぶには当らなかった。自分も大胆に手を出して、性慾の満足を買えば好かった。」
と露骨に語る処女願望の強さに苦い笑いをこみ上げまくりである。中年男性の性情が非常にはっきりと、いやになるくらいに読み手に伝わってくるのが印象的だ。
しかしこんな風に心情をあけすけに語るのも、どうかと思わずにはいられない。
確かにそれだけ全開タッチで自身の性欲を語られると、そこから人間の業のようなものが浮かび上がってくるのは確かだ。それを文学的というのも可能だろう。
しかしそれはあまりに露悪的すぎる。潔癖だった十代のころに読んだら、笑うことすらできなかったかもしれない。
作品自体はまったく嫌いではないのだけど、とても他人に勧められる作品ではないというのが正直なところだ。
併録の「重右衛門の最後」は単純に物語としておもしろい作品だ。特に殺人犯の重右衛門は現代の殺人鬼とも通じる部分があって印象深い。
重右衛門を殺した村の閉鎖性は説教臭さが鼻についてうまく伝わってこなかったが、重右衛門のキャラのおかげで全体的に、すごみというべきものが漂っていたように思う。
評価:★★★★(満点は★★★★★)



















