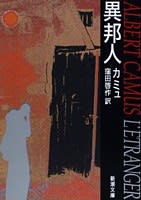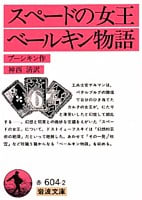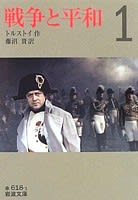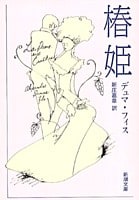一八〇五年夏、ペテルブルグ。上流社会のパーティに外国帰りの奇妙な青年ピエールが現れる。モスクワでは伯爵家の少女ナターシャが名の日の祝いに平和を満喫。一方従軍するアンドレイ、ニコライらに戦火は迫り―対ナポレオン戦争を描いて世界文学史に輝く不滅の名作。
藤沼貴 訳
出版社:岩波書店(岩波文庫)
岩波文庫バージョンで計6冊と、さすがに長大な作品である。
しかし一度読んでみて良かったなと素直に思えた。
訳文はこなれているし、ところどころに差しはさまれるコラムや、各巻末にある年表のおかげで、筋が追えなくなったり、わからなくなったりすることも少ない。
何より物語として単純におもしろいのである。
だから少々の不満はあっても(エピローグの締め方、さすがに長すぎるストーリー)、退屈で投げ出すことはなかった。
最後までおもしろく読める作品である。
この作品にはたくさんの人物が登場するが、どの人物もキャラが立っていておもしろい。
とは言え、主要キャラはピエールとアンドレイの二人だろう。
主人公的立ち位置のピエールは、基本的に善人である。
そしてそれゆえに深く考えず、周りに流されるきらいがある。
若いときには無軌道なことをしたが、それだって悪友に流されたからのように見えるし、結婚だって周囲の期待にこたえようとして不幸な選択をしたところもある。
だが善人だからフリーメーソンになって社会の変革を夢見るし、ナポレオンを殺す運命にあると思いこみ、実際に行動している。
しかし何がしたいのか、わからないところもあり、ボロジノでは見学者よろしく戦場視察しているし、ナポレオンを暗殺するはずがフランス軍将校を助け、知らない少女を救出したりする。
基本的に波乱万丈の割に、右往左往しているような人だ。
そしてそれが素直で善人で理想化肌の彼らしいと思え、好ましく見えるのである。
一方のアンドレイは幾分屈折した男だ。
俗っぽい世間を嫌う彼は英雄を夢見るものの、アウステルリッツで命を落としかけて、人生の無意味を悟る。
その後は、人生の希望と絶望と失望を行ったり来たりしている感じだ。
ピエールと違い、やや考えすぎるところが彼の虚無的な性向に拍車をかけているのかもしれない。この性格もおもしろく読んだ。
それ以外の人物もおもしろい。
ナターシャの子供じみていて、遠距離恋愛で心が折れかけて、アナトールみたいな男に口説かれてなびいてしまうところなんか、現代にもいそうでおもしろい。
マリアは暴君の父のせいで卑屈になっていて、哀れさを誘う。
ソーニャもニコライに惹かれながら、自分の立場上、結婚できないで苦しむところなどは目を引いた。
そして各人がしどろもどろと人生を生きる中で、ナポレオンが到来するのである。
ナポレオン戦争のシーンは臨場感に富んでいて大変楽しく読めた。
現場の指揮系統が混乱する様、
砲弾が飛び交っている命の危険が迫る中でも、どこか暢気さを感じさせる会話、
やくざ者の群れのように略奪をくり返す兵隊たち、
甘い見通しで作戦を立てる将校や、敵が迫っているのに派閥争いをくり返す身内同士、
ペーチャのように血気盛んで、英雄的行為に憧れ、死を急ぐ者、など、
現実の戦争でありそうなことばかりで生々しいのがすばらしい。
これもすべてトルストイが実際に戦場を経験しているからだろう。
見てきたものだからこそ、書ける説得力がある。
そうして運命の急転する中で、ピエールやアンドレイのたどりついたのは、ずばり愛だ。
絶望と希望と失望をくり返してきたアンドレイは、自分の死を前に、全人的な隣人愛を感じている。キリスト教的な感慨と言えよう。
また同じくピエールも死の間近まで接近した結果、頭でっかちな考えではなく、プラトン・カタラーエフのように虚心に、あるがままに世界を眺めることを知るようになる。
そしてその中で、汎神論めいた神の存在を意識するようになる。
「生がすべてなのだ。生が神なのだ。すべてが移り、動く。そして、その運動が神なのだ。そして、生あるうちは、神を自覚する喜びがある。生を愛すべきだ、神を愛すべきだ。この生を苦悩のなかで、罪なき苦悩のなかっで愛することが、何よりも難しく、何よりも幸せなことなのだ」
とピエールは独白しているが、そういうことなのだろう。
僕がイメージするトルストイらしい結論だ。
いろいろ書いたが、ともあれ読み終えた後には、深い感慨に浸ることができる作品ということはまちがいない。
ともあれ、世界を代表する大作。一読に足るとつくづく思う次第だ。
評価:★★★★(満点は★★★★★)
そのほかのレフ・トルストイ作品感想
『アンナ・カレーニナ』
『イワン・イリイチの死/クロイツェル・ソナタ』