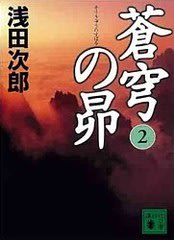英雄豪傑が各地に輩出し、互いに覇をきそいあった戦国の世、四国土佐の片田舎に野望に燃えた若者がいた。その名は長曽我部元親。わずか一郡の領主でしかなかった彼が、武力調略ないまぜて土佐一国を制するや、近隣諸国へなだれ込んだ。四国を征服し、あわよくば京へ…。が、そこでは織田信長が隆盛の時を迎えんとしていた。
出版社:文藝春秋(文春文庫)
名は知られているものの、長宗我部元親について、僕が知っていることはだいぶ少ない。
これは名古屋生まれで東北在住という、僕の出身の問題もあるが、やはり辺境の英雄はどうしても軽視されやすいという事実もあるのではないか。
歴史に詳しい人や、四国以外の一般の人も多分、僕と似たようなものと思う。
そのように人物を知らない分、本書を楽しく読むことができた。
そういう意味、価値あり一冊と言える。
司馬は元親を決して魅力的には書いていない。
気難しく悩みまくりで、それでいて典型的なマキアベリストでもある。
そういった性質は彼の臆病さから来ているという。それゆえに後ろ暗い手段も辞さない。
元親も初陣こそ、彼なりの才気を見せているが、本質的には謀略をもって事に当たることが性質にもあっているらしい。
戦国という時代を考えれば、それは美点かもしれない。
しかしその中には湿った腹黒さとでも形容したくなるような暗さがある。
後半は精彩をなくし、意固地の頑固者になっていくという点を見ても、あまり友だちにはしたくないタイプだ。
元親の妻の菜々は弟の弥九郎の方が男として好みだったと言うが、むべなるかなと思う。
人間的な魅力で言うなら、断トツで信親の方が抜きんでいている。
小説内の彼はとにかくすてきな男である。戸次川の戦いで家臣が共に死のうとしたのも納得の好人物だ。
しかし元親にはそんな爽やかさはない。そのためちょっと乗りきれなかった部分があるのは否定しない。
とは言え、元親が大きな仕事をしたことはまちがいない。
しかしそれも大きな勢力を前に屈しなくてはいけなくなる。
彼は田舎者で限界があり、器量も天下人の前では存外に小さい。元親自身もそのことを痛切に感じずにはいられなくなる。
それを目にした時点で、元親の心は折れていたのだろう。
それでも何とか気力を保てたのは、信親の存在が大きいと思う。
秀吉に屈したのも土佐一国を信親のために残したかったからだ。
実際信親に口出しする彼は、世の鬱陶しい父親を見るようだ。息子からすればうざいだろうが、少なくとも愛は見える。
しかしそんな息子も戦で亡くしてしまう。
それからの転落っぷりは見ていても悲しいくらいだ。
人は心が折れてしまった瞬間から、精彩を失くしていく生き物なのかもしれない。
その姿には哀切さが漂っていて、深く胸に響いたのである。
評価:★★★★(満点は★★★★★)
そのほかの司馬遼太郎作品感想
『国盗り物語』
『坂の上の雲』