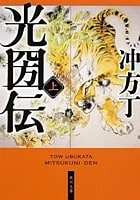ちくま文庫の『芥川龍之介全集』収録のすべての小説を読み終わったので、評価を記す。
やや辛めに点数をつけたかな。
★3つ以上が満足できるレベルである。
最高傑作は技術的には『歯車』。
ただ今の心情的には重すぎるので『トロッコ』にしておく。
★★★★★(満点は★★★★★)
鼻
芋粥
偸盗
地獄変
疑惑
トロッコ
雛
歯車
或阿呆の一生
★★★★(満点は★★★★★)
虱
手巾
煙管
戯作三昧
蜘蛛の糸
枯野抄
蜜柑
沼地
秋
藪の中
お富の貞操
おぎん
お時儀
あばばばば
点鬼簿
玄鶴山房
河童
★★★(満点は★★★★★)
ひょっとこ
羅生門
野呂松人形
煙草と悪魔
運
尾形了斎覚え書
忠義
二つの手紙
或日の大石内蔵助
黄粱夢
西郷隆盛
開化の殺人
奉教人の死
るしへる
邪宗門
あの頃の自分の事
開化の良人
きりしとほろ上人伝
竜
魔術
葱
鼠小僧次郎吉
舞踏会
黒衣聖母
或敵打の話
老いたる素戔嗚尊
南京の基督
杜子春
捨児
影
秋山図
奇怪な再会
妙な話
好色
俊寛
将軍
神神の微笑
報恩記
仙人(5巻収録)
一夕話
三つの宝
猿蟹合戦
二人小町
おしの
白
子供の病気
一塊の土
糸女覚え書
三右衛門の罪
文章
少年
桃太郎
尼提
春の夜
彼
彼第二
蜃気楼
誘惑
たね子の憂鬱
古千屋
三つの窓
★★(満点は★★★★★)
仙人(1巻収録)
孤独地獄
父
猿
MENSURA ZOILI
さまよえる猶太人
片恋
英雄の器
首が落ちた話
袈裟と盛遠
毛利先生
犬と笛
じゅりあの・吉助
妖婆
女
素戔嗚尊
お律と子等と
山鴫
アグニの神
奇遇
往生絵巻
母
庭
六の宮の姫君
保吉の手帳から
伝吉の敵打ち
或恋愛小説
寒さ
文放古
十円札
大導寺信輔の半生
馬の脚
春
温泉だより
死後
湖南の扇
年末の一日
カルメン
悠々荘
浅草公園
冬
手紙
闇中問答
夢
★(満点は★★★★★)
老年
青年と死
酒虫
道祖問答
貉
世之助の話
女体
路上
尾生の信
魚河岸
百合
不思議な島
金将軍
第四の夫から
早春
海のほとり
三つのなぜ
やや辛めに点数をつけたかな。
★3つ以上が満足できるレベルである。
最高傑作は技術的には『歯車』。
ただ今の心情的には重すぎるので『トロッコ』にしておく。
★★★★★(満点は★★★★★)
鼻
芋粥
偸盗
地獄変
疑惑
トロッコ
雛
歯車
或阿呆の一生
★★★★(満点は★★★★★)
虱
手巾
煙管
戯作三昧
蜘蛛の糸
枯野抄
蜜柑
沼地
秋
藪の中
お富の貞操
おぎん
お時儀
あばばばば
点鬼簿
玄鶴山房
河童
★★★(満点は★★★★★)
ひょっとこ
羅生門
野呂松人形
煙草と悪魔
運
尾形了斎覚え書
忠義
二つの手紙
或日の大石内蔵助
黄粱夢
西郷隆盛
開化の殺人
奉教人の死
るしへる
邪宗門
あの頃の自分の事
開化の良人
きりしとほろ上人伝
竜
魔術
葱
鼠小僧次郎吉
舞踏会
黒衣聖母
或敵打の話
老いたる素戔嗚尊
南京の基督
杜子春
捨児
影
秋山図
奇怪な再会
妙な話
好色
俊寛
将軍
神神の微笑
報恩記
仙人(5巻収録)
一夕話
三つの宝
猿蟹合戦
二人小町
おしの
白
子供の病気
一塊の土
糸女覚え書
三右衛門の罪
文章
少年
桃太郎
尼提
春の夜
彼
彼第二
蜃気楼
誘惑
たね子の憂鬱
古千屋
三つの窓
★★(満点は★★★★★)
仙人(1巻収録)
孤独地獄
父
猿
MENSURA ZOILI
さまよえる猶太人
片恋
英雄の器
首が落ちた話
袈裟と盛遠
毛利先生
犬と笛
じゅりあの・吉助
妖婆
女
素戔嗚尊
お律と子等と
山鴫
アグニの神
奇遇
往生絵巻
母
庭
六の宮の姫君
保吉の手帳から
伝吉の敵打ち
或恋愛小説
寒さ
文放古
十円札
大導寺信輔の半生
馬の脚
春
温泉だより
死後
湖南の扇
年末の一日
カルメン
悠々荘
浅草公園
冬
手紙
闇中問答
夢
★(満点は★★★★★)
老年
青年と死
酒虫
道祖問答
貉
世之助の話
女体
路上
尾生の信
魚河岸
百合
不思議な島
金将軍
第四の夫から
早春
海のほとり
三つのなぜ