城山シリーズです。
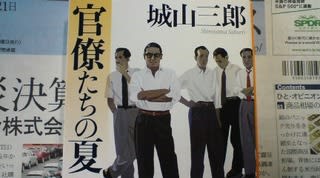
高度成長期の日本を支えてきた、官僚、キャリアと呼ばれる
男たちの仕事ぶり・哲学が描かれています。
ワシ的にいうと、官僚=「大蔵」「財務」「金融」と考えてしまいますが、
ここでの舞台は「通産省」です。そういまの経済産業省。
戦後からの奇跡的な復興を影で支えた通産官僚。
欧米からの自由主義圧力から国内産業を保護し、育成を優先させ日本を
世界トップクラスの工業国へ引き上げたのは、通産省の功績であることは
疑いのない事実。
「ノトーリアス・ミティ」と諸外国から酷評されていることがその証左。
この小説は「風越」という実力者を中心に、まさに国内産業保護と貿易自由化との
ぶつかり合いという激動の時代の中での、裏方である官僚の世界の話が進んでいきます。
「夏」というのは、ストーリーで随所にでてくる夏のシーンだけではなく、
まさに、通産官僚が幅広く活躍したこの時代を「盛夏」と看做してしるのでしょう。
事務次官まで上り詰めた「風越」であったが、部下の急逝や、政治・業界団体の反目等、ラストにかけて本人の想いとは違う方向へ、時代は流れていきます。
ラストシーンが「冬」の場面であるのは、まさに時代の流れ、通産官僚にとって活躍できた「夏」から、育成された国内産業が保護を必要としなくなり自由化へ突き進む時代をあらわしていることは印象的です。
男くさい、人間味あふれるストーリーで、官僚、政治家、業界団体等とのダイナミックな闘いが随所に出てきており、非常に興味を持って読めた一冊です。
ちなみに
ワシの属する業界、所管官庁は、このずっとずっと後に、このような時代を迎えます。
保護主義の代名詞みたいな業界さんですからね。
ちなみに、この主人公「風越」曰く、ウチの業界団体との交渉場面で、「背広を着た火星人にの群れにからかられている」だそうです。
当時はまったく自由化とは対極の位置にいたのでしょうね。
興味あるシーンでした。
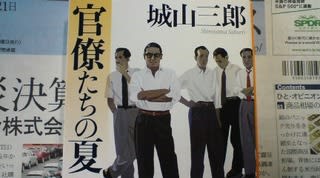
高度成長期の日本を支えてきた、官僚、キャリアと呼ばれる
男たちの仕事ぶり・哲学が描かれています。
ワシ的にいうと、官僚=「大蔵」「財務」「金融」と考えてしまいますが、
ここでの舞台は「通産省」です。そういまの経済産業省。
戦後からの奇跡的な復興を影で支えた通産官僚。
欧米からの自由主義圧力から国内産業を保護し、育成を優先させ日本を
世界トップクラスの工業国へ引き上げたのは、通産省の功績であることは
疑いのない事実。
「ノトーリアス・ミティ」と諸外国から酷評されていることがその証左。
この小説は「風越」という実力者を中心に、まさに国内産業保護と貿易自由化との
ぶつかり合いという激動の時代の中での、裏方である官僚の世界の話が進んでいきます。
「夏」というのは、ストーリーで随所にでてくる夏のシーンだけではなく、
まさに、通産官僚が幅広く活躍したこの時代を「盛夏」と看做してしるのでしょう。
事務次官まで上り詰めた「風越」であったが、部下の急逝や、政治・業界団体の反目等、ラストにかけて本人の想いとは違う方向へ、時代は流れていきます。
ラストシーンが「冬」の場面であるのは、まさに時代の流れ、通産官僚にとって活躍できた「夏」から、育成された国内産業が保護を必要としなくなり自由化へ突き進む時代をあらわしていることは印象的です。
男くさい、人間味あふれるストーリーで、官僚、政治家、業界団体等とのダイナミックな闘いが随所に出てきており、非常に興味を持って読めた一冊です。
ちなみに
ワシの属する業界、所管官庁は、このずっとずっと後に、このような時代を迎えます。
保護主義の代名詞みたいな業界さんですからね。
ちなみに、この主人公「風越」曰く、ウチの業界団体との交渉場面で、「背広を着た火星人にの群れにからかられている」だそうです。
当時はまったく自由化とは対極の位置にいたのでしょうね。
興味あるシーンでした。

















